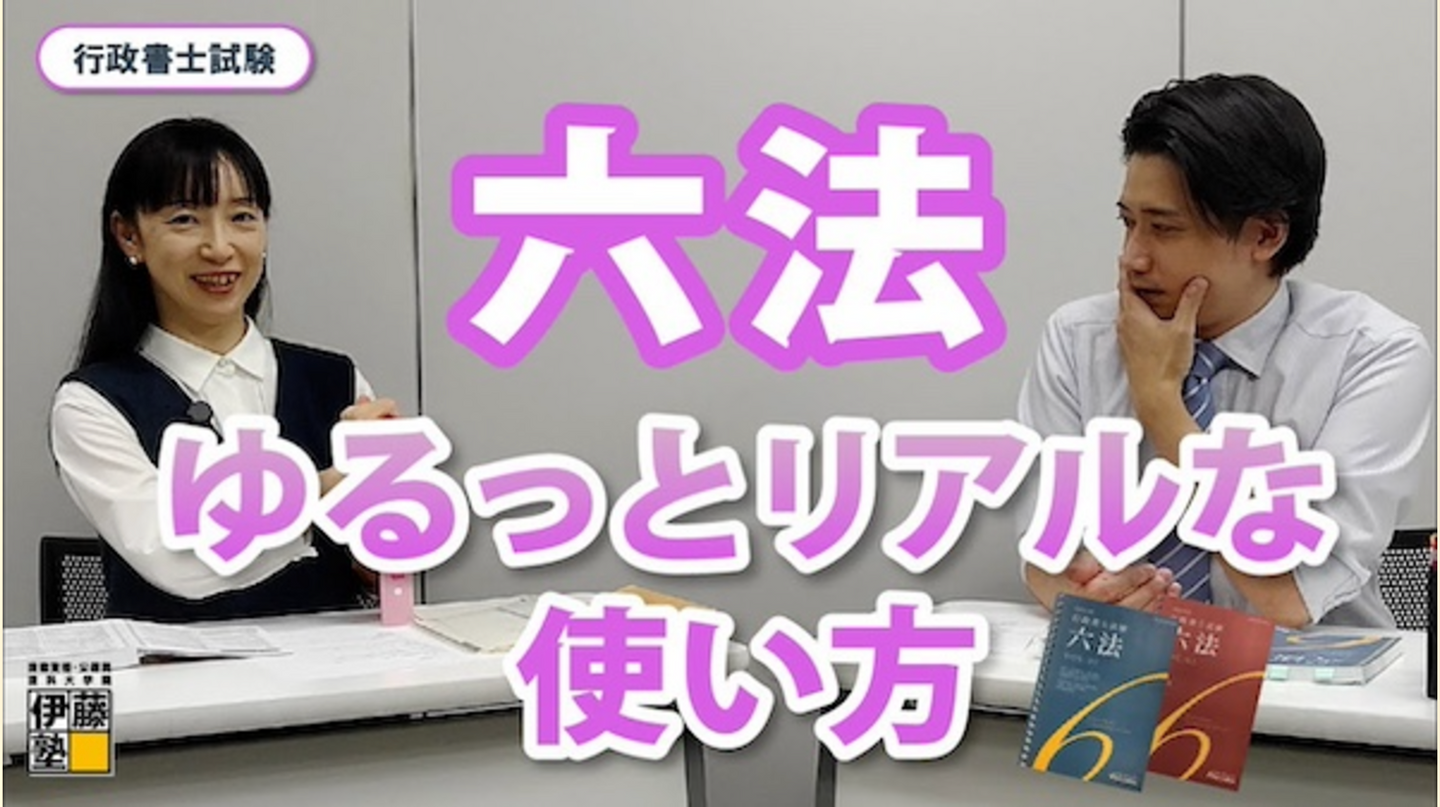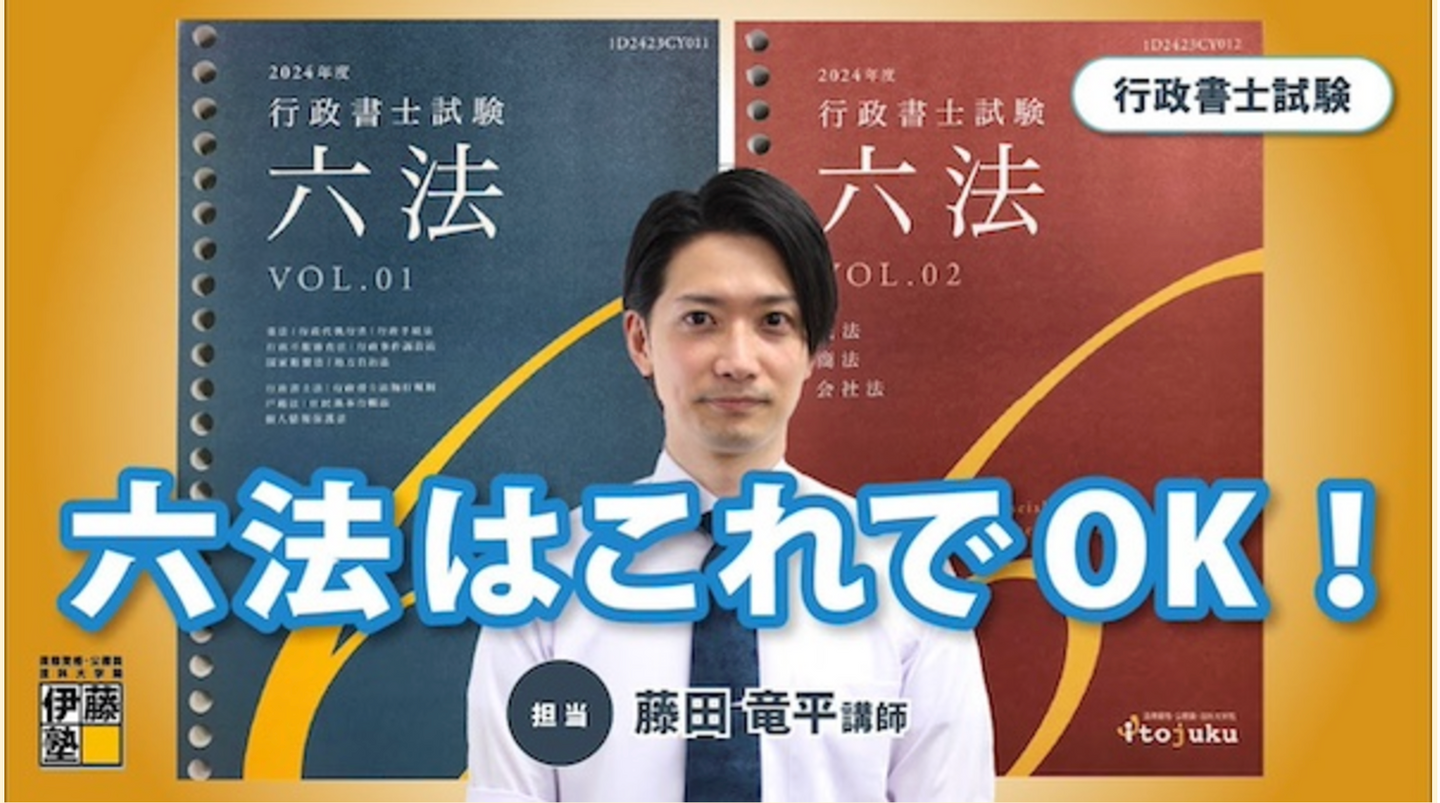行政書士試験に六法は必要?選び方と得点アップに向けた活用法をご紹介
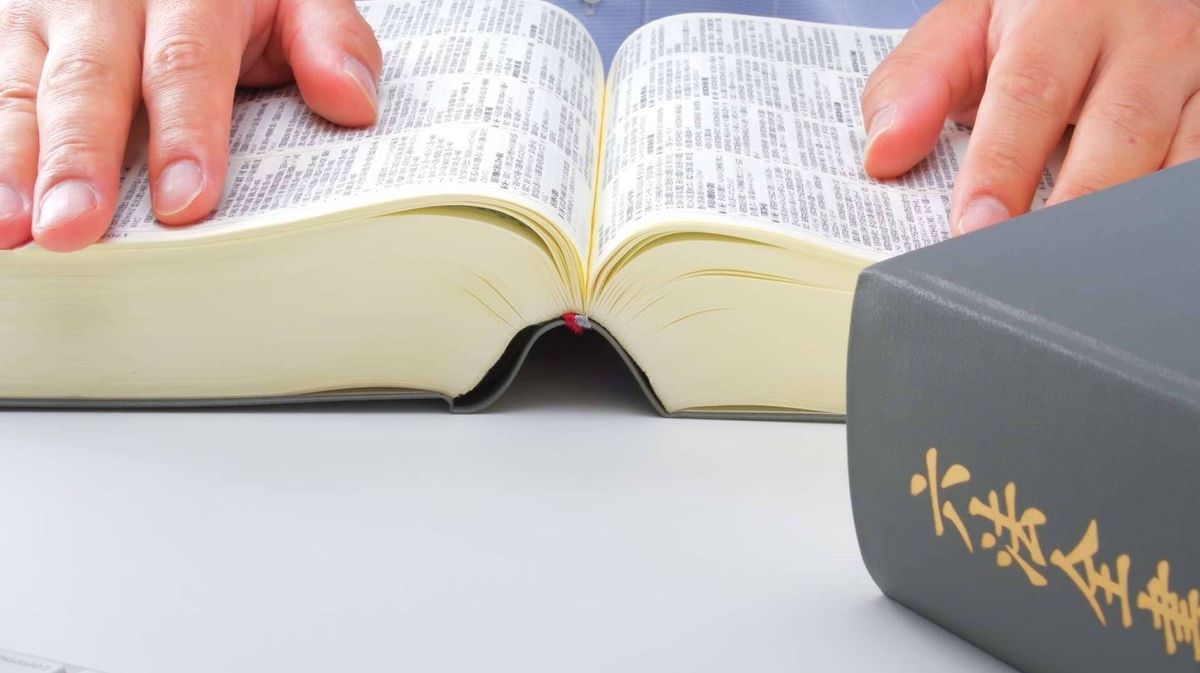
行政書士試験に「六法」は必要なのでしょうか?
様々な意見がありますが、六法を使った方が効率良く学習できるケースは多いです。
ただし、六法を全て読む必要はありません。テキストで学んだ条文を確認したり、過去問で頻出の条文を確認したりするだけでも、実力の伸び方は大きく変わってきます。
本記事では、行政書士試験の勉強における六法の必要性や、六法の効果的な活用法、選び方のポイントなどを詳しく解説します。
◉この記事を読んで分かること・合格するための実践的な六法の活用法
・六法を使いやすくするための工夫
・行政書士試験に特化した六法の選び方
行政書士試験で六法を使うべきか迷っている方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士試験で六法は必要?
2. 行政書士試験に合格するための六法の活用法
2-1.条文の素読に使う
2-2.論点を想起するために使う
2-3.具体的な場面をイメージする
3.六法を使うときの工夫は?|オススメ3選。
3-1.切り離して持ち歩いく
3-2.鉛筆で線を引いておく
3-3.色分けして、要件・効果をおさえる
4.行政書士試験の六法の選び方
4-1.必要な法令が全て収録されているか
4-2.条文だけで良いか、判例は必要か
4-3.自分が使いやすいと感じるか
5.試験対策なら伊藤塾の「行政書士試験六法」もおすすめ
6.まとめ
1.行政書士試験で六法は必要?
行政書士試験の勉強に六法は必須ではありません。
しかし、できる限り準備しておくことが望ましいです。なぜなら、六法を使うことで次のようなメリットが得られるからです。
・知識の正確性が上がる・条文が、体系的に整理できる
・記憶に定着しやすくなる
もちろん、六法を最初から最後まで全て読む必要はありません。
日々の勉強に六法を取り入れることから始めましょう。テキストを読んだ後に出てきた条文を引いてみたり、過去問に出てきた条文を確認してみるだけでも、実力の伸び方は大きく変わります。
「あれ?この条文どこにあるんだっけ?」
「これ、何条に書かれているんだろう?」
「準用されている条文が見つからない…」
このように、最初のうちは条文を調べるのに時間がかかり、面倒に感じるかもしれません。しかし、六法で条文を調べる作業自体が、実力を底上げしてくれます。
調べていく中で、自然と条文を覚えたり、関連する条文が頭に入ってきたり、法律全体の体系が分かってくるのです。
2. 行政書士試験に合格するための六法の活用法
それでは、具体的にどのように六法を活用すれば良いのでしょうか?
効果的な使い方を3つ紹介します。
・論点を想起するために使う
・具体的な場面をイメージする訓練をする
詳しく見ていきましょう
2-1.条文の素読に使う
六法の使い方でオススメなのが、条文を素読することです。条文を最初から最後まで、通しで読んでみましょう。
これによって、条文知識問題に強くなり、過去問で問われたことのない問題にも対応できるようになります。テキストや過去問だけでは埋められない「知識のスキマ」をカバーすることができるのです。
特に、憲法の統治や行政手続法、行政不服審査法などは、素読による得点力アップが大いに期待できる分野です。条文知識を問う問題が頻繁に出題される上、条文数が少ないので、費用対効果も悪くありません。
ただし、条文の素読はある程度学習が進んでから始める方が良いでしょう。全体を理解した上で読まなければ、せっかく読んでも頭に入らず、挫折してしまう可能性が高いです。
2-2.論点を想起するために使う
六法の条文から、論点を想起するのもオススメの活用法です。条文上、問題の所在となる箇所にマーカーなどを引いておき、どういった論点があったのかを思い出す訓練を積んでみましょう。
例えば、憲法であれば次のようなイメージです。
〔国会の地位〕第四十一条国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
「最高機関ってどういう意味だっけ?」
→「政治的美称説だったな。」
「唯一ってなんだっけ?」
→「確か『形式的意味の立法』と『実質的意味の立法』の2つがあったな…あと『国会中心立法の原則』と『国会単独立法の原則』も忘れないようにしないと。」
このように、条文から論点を想起し、学んだ内容を思い出してみるのです。
こういった作業を繰り返すことで、身につけた知識がより強固なものとなっていきます。
2-3.具体的な場面をイメージする
条文から具体的な場面をイメージすることも効果的な使い方です。法律の条文は、様々な事例に対応できるよう、あえて抽象的な文言によって書かれています。そのため、条文を見たときに具体的な場面をイメージできる力が必要です。
・条文を読んで、具体的な場面をイメージしてみる・逆に具体的な場面をイメージして、適用できる条文を探してみる など
これは択一式だけではなく、記述式対策としても有効です。ここ数年の記述式、特に民法では「どのような権利が行使できるか」について問われる問題が増えています。
例えば、令和6年の記述式(民法)では「動産売買の先取特権」に関する「事例問題」が出題されました。過去問であまり問われていないテーマだったので、苦しめられた受験生も多かったかもしれません。
このような問題についても、条文から典型的な場面をイメージする訓練を積んでおけば、対応することができます。日頃から、どの条文がどういった場面で使えるのか、あるいは具体的な場面別にどの条文で請求できるのか、イメージする訓練を積んでおきましょう。
3.六法を使うときの工夫は?|オススメ3選。
次に、六法を効果的に使うための工夫を3つご紹介します。
・切り離して持ち歩く・調べた判例・条文に鉛筆で線を引いておく
・色分けして、要件・効果をおさえる
それぞれ見ていきましょう。
3-1.切り離して持ち歩いく
六法を使い始めると、まず湧いてくる悩みが「六法が重い」という問題です。せっかく使いたくても、「六法が重すぎて持ち歩くことができない」と感じている受験生は多いでしょう。
この場合、六法を切り離して持ち歩くと解決できる場合があります。例えば、行政法や民法、諸法令など重点的に勉強する法令だけを切り離して持ち歩くのです。
ただし、切り取った箇所は製本テープで補強する必要があるなど、多少の手間は発生します。さらに、使い込んでいくうちに補強が弱くなってバラバラになってしまうこともあるので注意が必要です。
3-2.鉛筆で線を引いておく
六法で調べた条文や判例には、必ず鉛筆で線を引いておきましょう。
テキストで学んだ条文、過去問で出題された判例など、勉強で目にしたタイミングでその都度、鉛筆で薄くラインを引いていきます。これにより、どの条文が大切なのか一目瞭然になるのです。
・よく出題される条文・たまに出題される条文
・過去、一度も出題されたことのない条文 など
重要な条文ほど、ラインの色が濃くなっていくため、これらの情報が視覚的に判断できるようになります。
ポイントは、蛍光ペンやマーカーではなく、鉛筆で線を引くことです。マーカーだと、後から見返した時に色が気になったり裏写りしたりすることがありますが、鉛筆なら問題ありません。ラインを引くだけでなく、条文のポイントや注意点にも印をつけておくとさらに効果的です。
3-3.色分けして、要件・効果をおさえる
条文を色分けして、要件と効果をおさえることもオススメの工夫の1つです。
法律試験、特に民法では、各条文の要件と効果を押さえることが欠かせません。択一式はもちろん、記述式でも要件と効果を問われる問題が多いからです。
例えば、要件にはグリーン、効果にはイエローといったように色を分けて、六法の条文にマーカーを引いていきましょう。
※実際のイメージ
(即時取得)第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
こうすることで、各条文の構造が一目で分かるようになります。
条文上、どういった要件で、どういった効果が発生する構造となっているのかが、視覚的に判断できるのです。さらに、注意点などをメモ書きしておくと、条文を見るだけで間違えやすいポイントも思い出せるようになるでしょう。
これを徹底していくと、最終的には六法がテキストの役割を果たすようになります。直前期になるほど、大きな力を発揮してくれるはずです。
※こちらの動画もご覧ください。
【行政書士試験 六法】ゆるっとリアルな使い方を藤田講師、髙木講師双方がお伝えいたします。
4.行政書士試験の六法の選び方
ここまで、行政書士試験の勉強では六法を活用した方が良いことを説明してきました。
しかし、六法といっても様々な種類があります。どの六法を選べば良いのか、迷っている人も多いかもしれません。六法の選び方で迷ったら、次の3つのポイントを意識すると良いでしょう。
・必要な法令が全て掲載されているか・条文だけで良いか、判例は必要か
・自分が使いやすいと感じるか
それぞれ更に詳しく説明していきます。
4-1.必要な法令が全て収録されているか
1つ目のポイントは、行政書士試験に必要な法令が全て収録されているかどうかです。
・憲法・民法
・行政法
・商法、会社法
・個人情報保護法
・諸法令
(住民基本台帳法、戸籍法、行政書士法など)
これらの法令が全て収録されているかは、必ず確認しましょう。中でも、特に注意するべきなのは「個人情報保護法」と「諸法令」です。
「憲法、民法、行政法、商法」が収録されていない六法はほぼありませんが、「個人情報保護法」と「諸法令(住民基本台帳法、戸籍法、行政書士法など)」が漏れているケースは珍しくありません。
4-2.条文だけで良いか、判例は必要か
2つ目のポイントは、条文だけで良いのか、それとも判例も必要なのかという点です。
六法には、大きく次の2種類があります。
「条文+判例」が掲載されている六法
どちらを選ぶかで、特徴や使い方が変わってきます。
例えば、「条文+判例」の六法であれば、重要な判例も押さえられる反面、条文の素読には適していないなどの違いが出てくるのです。行政書士試験対策という面だけで考えれば、「条文」のみの六法で良いでしょう。
4-3.自分が使いやすいと感じるか
3つ目のポイントは、自分が読みやすい、使いやすいと感じるかどうかです。
六法には、前述した内容以外にも、「文字の大きさ・字体(フォント)、紙質、サイズ感、重さ」など様々な違いがあります。これらを確認した上で、自分が最も使いやすいと感じるものを探してみましょう。
結局、最も大切なポイントは、自分が「使い続けたい」と思えるかどうかです。最低限、必要な法令さえ収録されていれば、どの六法を選んでも、大きな問題は生じません。「どの六法を使うか」よりも、「六法をどうやって活用するか」を重視すると良いでしょう。
5.試験対策なら伊藤塾の「行政書士試験六法」もおすすめ
行政書士試験の六法選びで迷ったら、伊藤塾の「行政書士試験六法」もおすすめです。
「重くて持ち歩きたくない」「内容が足りない」あるいは「無駄な法令が多い」
「使い方がイマイチ分からない」
こういった受験生の悩みを解決した、まさに「行政書士試験受験生必携」の教材です。
【行政書士試験六法の3つの特徴】
・2024(令和6)年の新しい行政書士試験の法律科目に対応・藤田竜平講師による当六法のための「特別講義」
・六法をPDFデータでダウンロードできるから手軽に持ち運べる
プロの講師による特別講義で、「行政書士試験六法」を使用した学習のポイントや使い方もお伝えするため、さらに効率的に学習に取り組むことができます。
「行政書士試験六法」を活用し、行政書士試験合格を確実なものとしましょう。
→ 2025年合格目標 行政書士試験六法【Web講義付き】
※こちらの動画もご覧ください。
【行政書士試験】受験生必携!2024年(令和6年度)試験完全対応!!伊藤塾「行政書士試験六法」の全貌
6.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉行政書士試験の勉強は、六法を活用した方が良い
◉六法のオススメ活用法は3つ
・論点を想起するために使う
・具体的な場面をイメージする訓練をする
◉次のような工夫をすると使いやすくなる
・調べた判例、条文に鉛筆で線を引いておく
・条文を色分けして、要件・効果をおさえる
◉行政書士試験の六法の選び方のポイントは3つ
・条文だけで良いか、判例は必要か
・自分が使いやすいと感じる内容となっているか
以上です。
六法を使った勉強に、ハードルの高さを感じる受験生は珍しくありません。
しかし、六法を上手く活用すれば、あなたが行政書士試験に合格する可能性は確実にアップします。是非、六法を使った学習に取り組んでみてください。
伊藤塾では、行政書士試験で必要な内容を、初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」も開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。