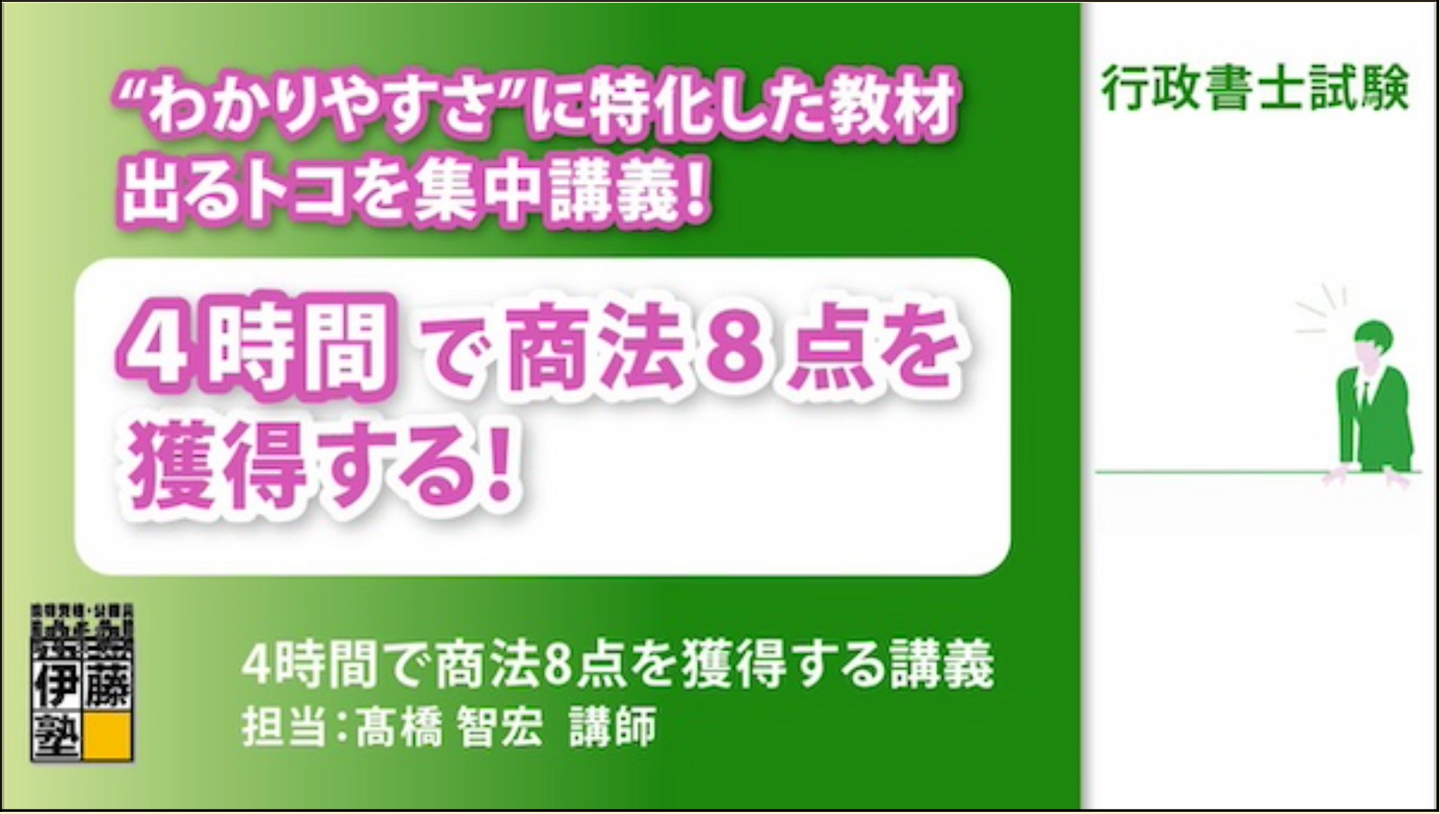商法・会社法は捨てないで!行政書士試験で差がつく効率的な学習法

「行政書士試験の商法・会社法が不安」
「時間がなければ捨ててもいい?」
「どうやって対策をすればいいの?」
こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
「商法・会社法」は、苦手意識を感じている受験生がとても多い科目です。合否に影響しないと考えて、はじめから捨て科目にしてしまっている人もいるでしょう。しかし、それは非常にもったいない選択かもしれません。
なぜなら、この記事を参考にして勉強すれば、短時間(4時間)の勉強でも、少なくとも2問(8点)の正解が目指せるからです。限られた時間を有効に使いたい受験生こそ、戦略的に対策して欲しい科目です。
本記事では、次の点を取り上げました。
◉この記事を読んで分かること・行政書士試験の商法・会社法の概要
・商法、会社法の対策のポイント
・勉強期間別の学習方法
行政書士試験の「商法・会社法」で悩んでいる方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士試験の商法・会社法とは?
2.行政書士試験【商法・会社法】の対策のポイント
2-1.出題範囲の広さに対して、配点が低い
2-2.頻出分野は限られている
2-3.民法との比較が大切
3.【勉強期間別】商法・会社法の学習法
3-1.半年〜1年程度かけて学習するケース
3-2.1年以上時間が取れるケース
3-3.超短期(3ヶ月〜)で合格する場合は?
4.時間がない方は「4時間で商法8点を獲得する講義」がおすすめ
5.まとめ
1.行政書士試験の商法・会社法とは?
商法・会社法は、商売のプロのための法律です。「商法」は民法の特別法として位置づけられており、その中でも特に会社を対象としているのが「会社法」です。
行政書士試験では、「商法・会社法」として5問が出題され、商法から1問、会社法から4問が出題されます。
【行政書士試験の配点】
| 配点 | 択一式 | 記述式 | 多肢 選択式 | ||
| 基礎知識 科目 | 基礎知識 科目 | 56点 | 14問 | ||
法令等 科目 | 基礎法学 | 8点 | 2問 | ||
| 憲法 | 28点 | 5問 | 1問 | ||
| 民法 | 76点 | 9問 | 2問 | ||
| 行政法 | 112点 | 19問 | 1問 | 2問 | |
| 商法 | 20点 | 5問 | |||
| 合計 | 300点 | ||||
中には、「商法・会社法」を完全に捨て科目にする人もいます。しかし、少ないとはいえ「20点」の配点があります。20点分を全く勉強しないというのも、非常にもったいない選択だと言えるでしょう。
商法・会社法対策では、いかに効率的に対策するかが、学習のポイントとなります。
2.行政書士試験【商法・会社法】の対策のポイント
それでは、具体的にどのように対策をすれば良いのでしょうか?
商法・会社法の対策で意識するべきポイントを3つ紹介します。
・頻出分野は限られていること
・常に民法との比較を忘れないこと
それぞれ見ていきましょう。
2-1.出題範囲の広さに対して、配点が低い
商法・会社法は、出題範囲の広さに対して、配点が非常に低い科目です。合計「2000条」近くある条文数に対して、試験全体における配点は「20点」しかありません。
例えば、出題範囲が広く、多くの受験生を苦しめている民法と比較してみましょう。
民法の条文数は、合計「1050条」です。範囲は膨大ですが、配点も高く「76点」もの配点が与えられており、行政書士試験全体の4分の1に相当します。間違いなく、合格のカギを握っている科目だと言えるでしょう。
一方、「商法・会社法」の条文数は、民法以上に膨大です。
商法が850条、会社法が979条、合計すると2000条近い条文数があります。しかし、その一方で、配点は決して高いとは言えず、全て正解しても20点しかありません。「条文数」は民法の2倍近い数がある一方で、「配点」は民法の4分の1しかないのです。
2-2.頻出分野は限られている
一方で、実は、毎年の頻出分野は限られています。全ての分野が同じ割合で出題されているわけではなく、一部の分野だけが、毎年のように出題されているのです。
そのため、出題される可能性が高い分野に絞って学習すれば、非常に効率よく対策をすることができます。まずは、次の表をご覧ください
商法・会社法の出題実績(会社設立・商行為)
| 株式会社の 設立 | 商行為 | |
| 平成18年 | ◯ | |
| 平成19年 | ◯ | ◯ |
| 平成20年 | ◯ | |
| 平成21年 | ◯ | |
| 平成22年 | ◯ | |
| 平成23年 | ◯ | |
| 平成24年 | ◯ | ◯ |
| 平成25年 | ◯ | |
| 平成26年 | ◯ | |
| 平成27年 | ◯ | ◯ |
| 平成28年 | ◯ | ◯ |
| 平成29年 | ◯ | ◯ |
| 平成30年 | ◯ | ◯ |
| 令和1年 | ◯ | ◯ |
| 令和2年 | ◯ | ◯ |
| 令和3年 | ◯ | ◯ |
| 令和4年 | ◯ | |
| 令和5年 | ◯ | ◯ |
上記は、商法・会社法で頻出とされている「株式会社の設立」「商行為」の出題実績です。特に平成23年以降、ほぼ毎年のように、2つの分野が出題されていることが分かります。
つまり、「株式会社の設立」「商行為」に絞って学習するだけでも、少なくとも5問中2問(20点中8点)はカバーすることができるのです。
商法・会社法の全ての範囲を勉強する時間がない受験生は、決して少なくありません。限られた時間で、行政書士試験に合格するには、上記のような頻出分野に絞った学習が非常に効果的です。
商法・会社法の対策をする場合、まずは上記の2分野から進めることをおすすめします。
2-3.民法との比較が大切
商法、会社法を学ぶうえで、常に意識して欲しいのが「民法との比較」です。特に商法は、民法の特別法として、商売のプロのために設けられている法律です。
そのため、民法と同じ法律行為でも、法律の趣旨が異なるため、多くの点で民法とは異なる結論となっています。
例えば、一例として「代理権の消滅原因」が挙げられます。任意代理人の代理権は、民法では「本人の死亡」によって消滅しますが、商法では本人が死亡しても消滅しません。
・この違いはどこから来ているのか・なぜ結論が異なるのか
上記のようなポイントを強く意識して、勉強を進めていきましょう。
大切なのは、相違点を暗記するのではなく、それぞれの法律の趣旨を理解することです。「民法」と「商法」のキャラクターの違いを意識して勉強すれば、違いが頭に残りやすくなります。
3.【勉強期間別】商法・会社法の学習法
ここまでの内容で、商法・会社法の対策のポイントを説明しました。ポイントを絞って対策を進めれば、決して「商法・会社法」の全てを捨てる必要はないことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
さらにここからは、それぞれの学習期間に応じた勉強の進め方を解説します。「半年〜1年程度かけて合格するケース」、「1年以上時間が取れるケース」、「超短期(3ヶ月〜)で合格するケース」に分けて説明します。
3-1.半年〜1年程度かけて学習するケース
半年〜1年程度かけて学習するケースでは、「商法・会社法」に十分な時間を費やす余裕はありません。必要以上に時間をかけるのではなく、配点の高い民法や行政法に時間を充てましょう。「商法・会社法」に時間をかけすぎて、他の科目が疎かになってしまうと、本末転倒です。
前述した「株式会社の設立」や「商行為」など、本試験での頻出分野や、出題が予想される分野を中心に学習していきましょう。「最短の学習時間」で「5問中2問程度の正解を目指す」ことが、基本的な学習スタンスです。
なお、環境によっては、そもそも「商法・会社法」の対策自体が必須ではありません。例えば、次のようなケースでは、捨てることも選択肢の1つです。
・カリキュラムの進捗が間に合っていない・仕事や家事・育児などで時間がない
・民法や行政法の対策が追いついていない
「商法・会社法」の優先順位は、「民法や行政法、基礎知識科目」などと比べると、決して高くはありません。学習内容を絞り込み、重要な部分だけを繰り返して勉強しましょう。
3-2.1年以上時間が取れるケース
1年以上時間が取れるケースでは、商法・会社法にも十分に時間をかけることができます。
早期スタートのメリットを活かして、余裕があるタイミングでしっかりと学習しておきましょう。「商法・会社法」は、民法や行政法と比べると少ないとはいえ、20点分の配点があります。
確実な合格を考えるなら、正答できるメリットは大きいです。
「あと数点あれば合格できたのに…」という受験生は決して少なくありません。
また、ここまで「商法・会社法」はコスパが悪いと説明しましたが、それはあくまでも試験対策上の話です。合格後、行政書士の実務で「商法・会社法」の知識が必要になる場面は多いでしょう。特に会社法は、法人関係の業務を行うのであれば必須の知識です。
試験対策として重要ではない「計算」「解散・清算」「持分会社」「組織再編」といったテーマについても、身につけておけば心強い武器となるはずです。さらに、商法・会社法の知識は、民法とも関連するので、民法力のアップにも役立ちます。
試験合格だけではなく、合格後のことを考えるなら、余裕があるタイミングでしっかりと学習しておくことをオススメします。
※試験対策から実務レベルまで会社法を完全マスターしたい方に!
「会社法集中講義」はこちら
3-3.超短期(3ヶ月〜)で合格する場合は?
超短期(3ヶ月〜)で合格する場合、基本的には「捨てる(全く手を付けない)」一択です。そもそも「行政法・民法」や「基礎知識科目」が手一杯で、「商法・会社法」に充てる時間は無いケースが大半でしょう。
ただし、他の法律資格試験の経験者や、勉強に集中できる方の場合、頻出分野だけでも学習した方が良いケースがあります。
・他の法律試験で、民法や行政法をしっかりと勉強したことがある・勉強に集中できる環境で、十分な時間が確保できる など
また、受験指導校で短期合格を目指す場合、そもそも短期合格に特化したカリキュラムが組まれています。
例えば、伊藤塾では「超短期での合格を目指す方」に向けて、学習時間に応じた2つの講座を設けています。「商法・会社法」も対策する「スピードマスター講座」と、「商法・会社法」には手を付けない「超スピードマスター講座」です。
| 学習時間の目安 | 特徴 | |
| スピードマスター 講座 (商法・会社法あり) | 300〜400時間 (1週間で18〜20時 間の学習が目安) | ・学習内容は絞り 込むものの、「商 法・会社法」など の配点が低い科目 も学習する |
| 超スピードマスター 講座 (商法・会社法なし) | 200〜300時間 (1週間で15〜18時 間の学習が目安) | ・学習内容を徹底 的に絞り込み、 「商法・会社法」 などの配点が低い 科目は捨てる |
超短期での合格を目指すなら、このような受験指導校の「短期合格講座」を活用することも一案です。
※行政書士試験に、超短期で合格するための考え方については、こちらの動画をご覧ください。
【行政書士試験】「スピードマスター講座」と「超スピードマスター講座」どちらを選択すべきか
4.時間がない方は「4時間で商法8点を獲得する講義」がおすすめ
商法・会社法に苦手意識を感じている方は、伊藤塾の「4時間で商法8点を獲得する講義」がおすすめです。
「働きながら、家事・育児に追われながらで、商法・会社法にあてる時間がない」「短時間の勉強で、商法・会社法の頻出ポイントだけでもおさえたい」
こんな方に向けて開講しているのが、「4時間で商法8点を獲得する講義」です。
この講義では「4時間の講義」で「商法2問(8点)を獲得する」ことを目標に、商法でほぼ毎年出題される「株式会社の設立」「商行為」に絞って対策をしていきます。
商法の学習経験ゼロの方から商法の対策に四苦八苦している方まで、商法の対策に不安を感じている方はぜひご受講ください。
【行政書士試験】商法を捨て科目にしない!4時間で商法8点を獲得する講義
※次の記事もあわせて読まれています。
→ 行政書士試験合格に必要な勉強時間とは?目安や平均・最短合格のポイントについて解説
5.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
・行政書士試験では、「商法・会社法」として5問が出題される
・商法から1問、会社法から4問が出題される年が多い
・試験範囲は民法の「2倍」近いが、配点は民法の「4分の1」しかない
・ただし、頻出分野は限られている
・中でも「株式会社の設立」と「商行為」はほぼ毎年出題される
・「株式会社の設立」と「商行為」を勉強するだけで、8点は目指せる
・ポイントを絞って学習すれば、効率的に対策できる
・勉強期間別の、学習法は次のとおり
→「株式会社の設立」と「商行為」に絞って勉強する。
【半年〜1年のケース】
→頻出分野に特化して勉強する。
学習内容を絞り込み、重要な部分だけを繰り返す。
【1年以上あるケース】
→余裕があるタイミングでしっかりと学習する。
合格後のことも考えて、行政書士の実務を意識した勉強を心がける。
以上です。
「商法・会社法」は苦手意識を持つ受験生がとても多い科目です。しかし、ここで点数が取れれば、行政書士試験の合格に大きく近づきます。
「商法・会社法に苦手意識があって不安」、「対策した方がいいだろうけど、後手に回っている」という方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。
伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。