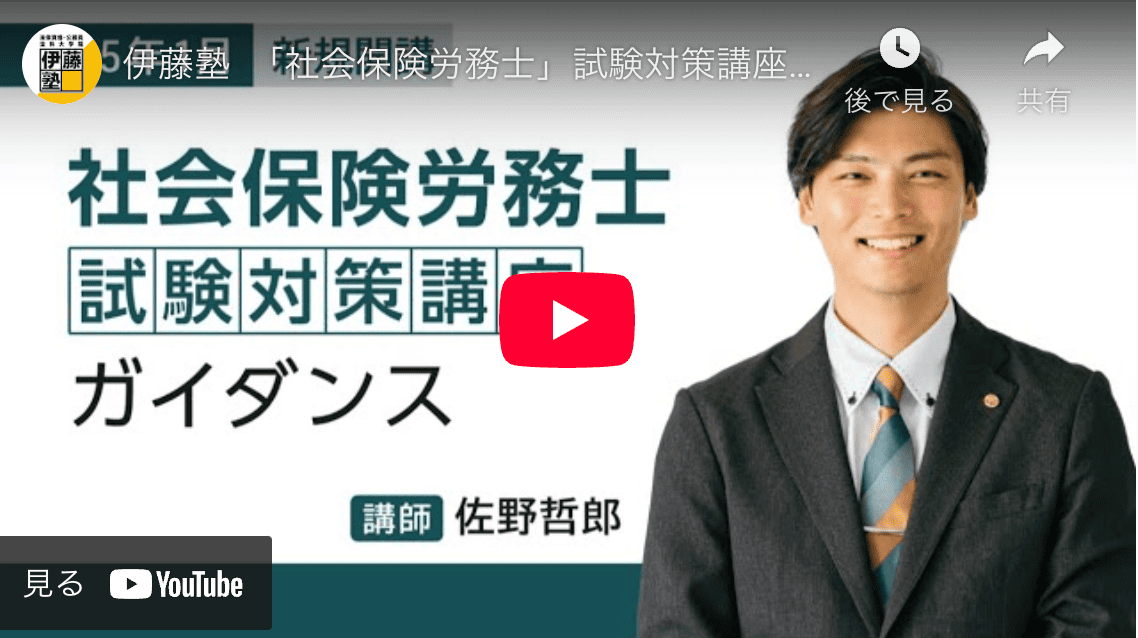社労士試験の勉強はつまらない?楽しく学んで合格を達成するコツを解説
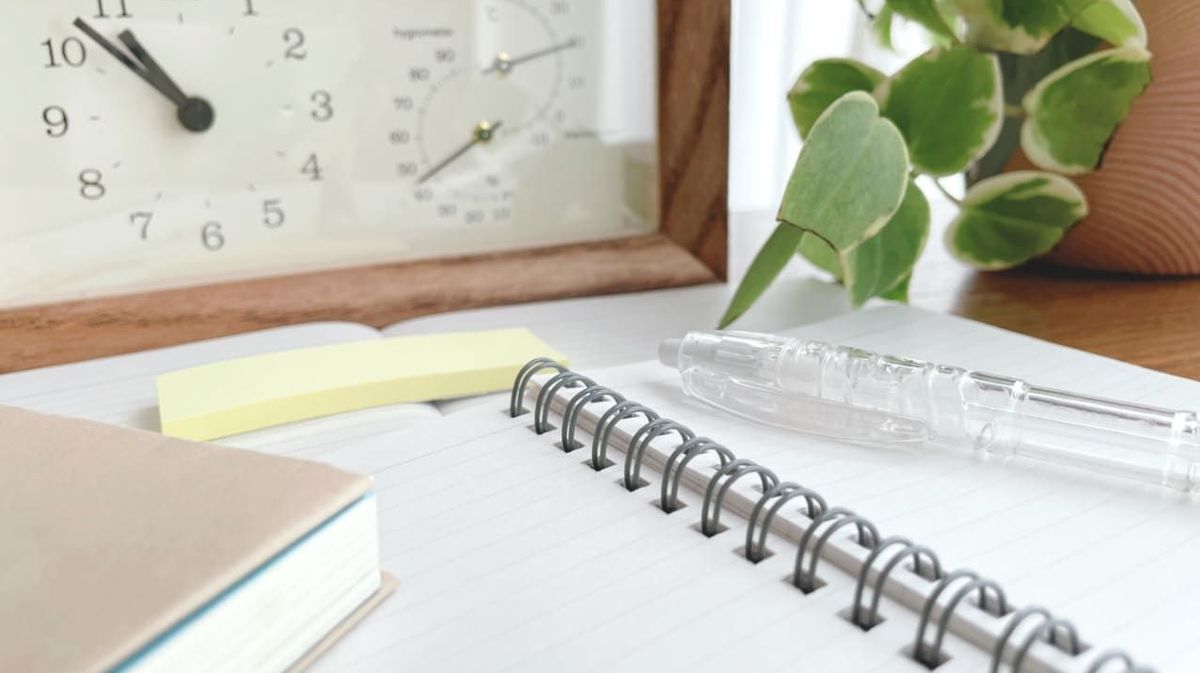
「社労士の資格を取りたいけど、勉強が大変そう」
「社労士試験の勉強を始めたけど、難しくてつまらない」
そんな不安や悩みを抱えていませんか? 確かに、膨大な法律の知識をインプットする必要があるため、楽な道のりではありません。
しかし、自分に合った学習スタイルを見つけて、勉強を「楽しい」と感じることができれば、合格の可能性は格段に上がります。なぜならば、興味を持って取り組む学習では、自然と集中力が増し、新しい知識の吸収も早くなるためです。
今回は、社労士試験を楽しく効率的に勉強するために、下記のポイントをお伝えしていきます。
| ・なぜ楽しく勉強することが大切なのか ・楽しく勉強を続ける4つの方法 ・勉強につまづきやすいポイントと対処法 |
今回の記事を読むことで、皆さまの試験勉強をより楽しく充実したものにするヒントとなれば幸いです。
【目次】
1. なぜ"楽しく"勉強することが大切なのか?
1-1. モチベーションが維持できる
1-2. 勉強に対する抵抗がなくなる
2. 社労士の勉強が「楽しい!」と感じる4つの方法
2-1. 成功体験を積み重ねて達成感を得る
2-1-1. 小さな目標を作る
2-1-2. 目に見える進捗管理をする
2-2. 孤独感を解消する
2-2-1. 質問できる相手を見つける
2-2-2. 資格勉強仲間を見つける
2-3. 勉強を習慣にする
2-3-1. 移動時間を活用する
2-3-2. 音声学習を取り入れる
2-3-3. スケジュールを決めすぎない
2-4. リフレッシュ方法を確立する
2-4-1. 適切な休息が大切な理由
2-4-2. 自分なりのリフレッシュ方法を見つける
3. つまずきやすいポイントとその対処法
3-1. モチベーションが低下した時
3-2. 範囲が広すぎて焦る時
3-3. 漠然とした不安に襲われる時
4. 社労士試験を受験するなら受験指導校がおすすめ
4-1. 法律資格専門の受験指導校としての実績がある
4-2. 質問システムやカウンセリングを受けられる
4-3. アプリによるアウトプットができる
5. おわりに
1. なぜ"楽しく"勉強することが大切なのか?
「勉強は我慢して頑張るもの」「苦しいのが当たり前」と考えている方が多いのではないでしょうか。
確かに社労士試験は、簡単に合格できる試験ではありません。
しかし、つまらないと思いながら勉強を続けるのと、楽しさを発見しながら勉強を進めるのとでは、勉強の成果や効率が格段に違ってきます。
なぜなら、勉強に対して「楽しい」という気持ちになることができれば、資格試験までのモチベーションを維持することができる上に、日々の勉強への抵抗が少なくなるからです。
そのため、「勉強が楽しい」という感覚を知ることは、効率的に合格に近づくための重要な要素なのです。
具体的に、楽しいと感じながら勉強をすることで資格試験の勉強にどのようなメリットがあるかを紹介していきます。
1-1. モチベーションが維持できる
勉強が楽しいと学習時間が苦痛ではなくなるため、資格試験に対するモチベーションを失わずに保つことができます。
社労士試験に合格するためには、長期間にわたる継続的な学習が必要です。
つまらないと感じながら勉強を続けると、途中で耐えきれなくなり勉強自体を投げ出してしまう可能性もあります。一方で、「好き」や「楽しい」という感情は、学習意欲を持続させることだけでなく、記憶力を高める効果があると言われています。
「もっと知りたい」という前向きな気持ちが生まれることで、自発的に学習時間が増え、より深い理解にもつながります。
つまり、楽しいと感じながら勉強をする方法を見つけることで、モチベーションを維持して学習を継続しやすくなる上に、効率的に知識を定着させることができるのです。
1-2. 勉強に対する抵抗がなくなる
勉強を楽しいと感じるようになれば、勉強そのものに対する抵抗感が薄れます。
「我慢してやる」「仕方なくやる」という義務感からではなく、「自分がやりたくてやる」という自然な行動に変えることができるのです。
そのため、自然と勉強時間が増え、勉強に向かった分だけ試験に必要な知識を蓄積することができます。
このように、勉強を義務的な作業ではなく、日々の生活の一部として取り入れるためにも「楽しい」という感覚で学ぶことが非常に重要です。
2. 社労士の勉強が「楽しい!」と感じる4つの方法
それでは、具体的にどのように楽しむ要素を取り入れればいいのでしょうか?ここでは、すぐにでも実践できる4つの方法をご紹介します。
2-1. 成功体験を積み重ねて達成感を得る
一つ目は、成功体験を重ねて達成感を得ていくことです。
人は何かを「できた」「わかった」と感じた時、その行為に対する楽しさを実感することができます。この達成感が、勉強を楽しんで継続する力となります。
特に、新しいことを学ぶ際には、この成功体験による達成感が自信に繋がり、さらなる学習意欲へと繋がっていきます。
具体的な、成功体験の例をご紹介します。
2-1-1. 小さな目標を作る
日々の学習で完了できるような、小さな目標を設定することで、日々の成功体験による達成感を得ることができます。
「資格試験合格」という大きな目標だけを見ていると、自分が目標に向かって進めているのかどうか不安になってしまいがちです。進んでいる道に自信がなくなると、勉強に対する意欲がなくなり、つまらないと感じる原因にもなります。
このようなモチベーションの低下を防ぐために、試験合格という大きな目標を達成するための道筋として、日々の学習で完結できるような小さな目標を立てることが大切です。
例えば「今日は労災保険法の保険給付の種類を覚える」「労働基準法に関する判例を3つ理解する」というような小さな目標を設定し、達成していくことで、自分の成長を実感することができます。
小さな目標をクリアしていく度に感じる達成感は、勉強を楽しいと感じる大切な要素です。この前向きな気持ちが、資格試験合格までの長い道のりを支える力となります。
2-1-2. 目に見える進捗管理をする
学習の進み具合を目に見える形で管理することでも、自分の成長を実感し、達成感を得ることができます。
例えば、1週間ごとのToDoリストを作って完了したものにチェックをつけていくことや、各科目の学習時間を記録して進捗の度合いを管理することにより、自分が達成したことを視覚的に確認して成長を感じることができます。
さらに、科目ごとの勉強時間を管理するのであれば、自分がどの科目にどの程度の時間を費やしているのかを確認することもできるため、その後の勉強のスケジュールを考える指針にもなります。
膨大な試験範囲を学習していると、進捗が掴めずに疲れてしまいがちです。しかし、自分の学習成果を目で確認できれば、達成感が生まれ、楽しく続けられるようになります。
2-2. 孤独感を解消する
二つ目の方法は、「一人きりで勉強している」という孤独感を解消することです。
一人で黙々と勉強していると、単調でつまらないと感じたり、勉強に対して不安を覚えて学習意欲が低下してしまいがちです。特に、忙しい社会人にとって、モチベーションを維持しながら勉強時間をしっかりと確保することは容易ではありません。
そのような時は、人とコミュニケーションをとることで、不安やストレスを軽減し、前向きな気持ちで学習に取り組めるようになることが多くあります。
孤独感を解消するための、具体的な方法を2つ紹介します。
2-2-1. 質問できる相手を見つける
勉強の内容について頼れる相手を見つけることは、理解が難しい知識の多い社労士試験で孤独感を解消するために非常に重要です。
テキストや過去問で理解ができない箇所があり、それが解消されないと「難しくてよくわからない」「勉強がつまらない」という感覚に陥ってしまいがちです。
そのような時に、不明な箇所について答えてくれる相手がいることで、立ち止まったり投げ出したりせずに、学習を続けていくことができます。
さらに、「不明点を質問して解決する」というプロセスを踏むことで、ただテキストを読むよりも知識を定着させることが可能になります。
人に質問をすることで孤独感が解消される上に、一人で不安を感じながら曖昧に知識をつけるよりも効率的に学習を進めることができるのです。
2-2-2. 資格勉強仲間を見つける
長期間の勉強を継続する中で、同じ目標を持つ仲間は孤独感を和らげる大きな支えとなります。
一人きりで勉強をしていると、やる気が起きない時などはそのまま勉強を投げ出してしまいがちです。しかし、一緒に勉強をしている仲間がいると、「自分も頑張ろう」という気持ちで勉強をスタートしやすくなります。
お互いの学習について進捗を共有したり、効果的な勉強方法について情報交換したり、一緒に気分転換をしたりなど、「一緒に頑張っている」「仲間がいる」という感覚があると勉強へ向き合う意欲は大きく変わるものです。
勉強仲間は、同じ社労士試験の受験生でなくても構いません。大切なのは、目標に向かう時間を共有できることです。成長や辛さを共有したり、一緒に作業をする時間を持ったりすることで、学習意欲が高まり、長期の学習を継続する力が生まれてきます。
共に頑張る仲間がいることで、モチベーションを高く維持しやすくなるだけでなく、孤独感を感じることなく、楽しく学習を進めることができます。
2-3. 勉強を習慣にする
三つ目の方法は、勉強を習慣化して楽しむことです。
生活の中には誰しも、趣味の読書や音楽鑑賞など、日々続けるうちに「楽しい」と感じて習慣化されたものがあるはずです。勉強も同じように、やらなければと気負うのではなく、自然に楽しめる日課として日常に組み込むことで、飽きずに続けやすくなります。
習慣化するためのポイントは、無理をせず、自分のペースを大切にすることです。日常のリズムに学習時間をうまく組み込んで、無理のない学習スタイルを作りましょう。
習慣化させるための具体的な例を3つ紹介します。
2-3-1. 移動時間を活用する
通勤などの移動時間を活用することは、勉強の習慣化に効果的です。
普段は何もしていない時間を有効に活用することで、無理なく一日の学習量を増やすことができます。
例えば、移動中に音声で学習をしたり、単語帳やアプリによるクイズ形式の学習方法があります。このような勉強法を取り入れることにより、家とは違う環境で楽しんで学ぶことも可能になります。
2-3-2. 音声学習を取り入れる
音声による学習は、疲れている時でも手軽に取り入れやすく、習慣化させやすい勉強法です。
音声学習には以下のようなメリットがあります。
| ・何かをしながらでもできる ・場所を選ばない ・聞くスピードを選べる |
例えば、目が疲れていてテキストを読むのが億劫な時でも、作業中で手が離せない時でも、日常生活で無理なく取り入れることができます。
さらに、聞くことによる学習は、耳から情報をインプットして脳に刺激を与えるため、記憶力の向上に効果的とされています。
このように、無理なく取り入れられ、効率的に学ぶことができる勉強法である音声学習は、勉強を習慣化させるために非常に有効です。
2-3-3. スケジュールを決めすぎない
長期間の勉強を楽しみながら習慣化させるためには、「必ずしなければ」と考え過ぎないことも大切です。
もちろん、試験日までに全ての範囲を学習し終えるためにスケジュールを組むことは重要です。しかし、全てを計画通りに進めようとして上手くいかないと、焦る気持ちが強くなり勉強が苦痛になってしまいます。
特に、仕事や家事と勉強とを両立している場合など、想定外のことが起こりやすい環境では、無理にスケジュール通り学習をしようとするよりも、その日の気分や時間に応じて勉強内容を調整する方が効率的です。
大まかなスケジュールを作りつつ、「勉強に取り組む」という姿勢を大切にしてある程度の自由を持つことが、勉強を楽しんで習慣化させる鍵となります。
2-4. リフレッシュ方法を確立する
四つ目の方法は、自分なりの最適なリフレッシュ方法を見つけておくことです。
勉強を続ける上で、適度な休息をとることは、楽しみながら勉強を継続するためにとても重要です。
休息が大切な理由と、オススメの休息の取り方を説明していきます。
2-4-1. 適切な休息が大切な理由
社労士試験の受験では、多くの方が長期間の学習に取り組むため、学習期間のモチベーションを維持するためには適度な休息が必要です。
「合格するためにずっと頑張り続けなければ」と考えてしまいがちですが、そのような気持ちが逆効果になる可能性があります。
疲れた状態で勉強を続けると、集中力や学習意欲が低下して勉強に対する前向きな気持ちがなくなり、つまらないと感じるようになるためです。
定期的な休憩時間や休息日を上手に取り入れることで、疲れた脳をリセットすることができるため、「また頑張ろう!」という前向きな気持ちで勉強に戻ることができます。
2-4-2. 自分なりのリフレッシュ方法を見つける
休息をとる時は、ただ漫然と休むのではなく、心身をリフレッシュできる効果的な休息方法を見つけることが大切です。
適切なリフレッシュの方法は人それぞれですが、一例としては以下の通りです。
| ・軽い運動やストレッチをする ・勉強環境を変えてみる ・仮眠をとる ・外に出かけてみる |
休息を取る際は、できるだけ時間を決めることが大切です。「午後3時まで」「今日1日だけ」など、明確な区切りを設けることで、メリハリを持って学習に戻りやすくなります。
このように計画的な休息を取り入れて気持ちをリフレッシュすることで、集中力と意欲を保ちながら継続的な学習に取り組むことができるのです。
3. つまずきやすいポイントとその対処法
長期間の勉強を進める中で、多くの人が共通して困難を感じる場面があります。学習につまずいてしまうと、モチベーションが下がり、資格試験までの道のりに楽しさを見出しにくくなってしまいます。
勉強が行き詰まった時は、そのまま頑張ろうとせずに適切な対処をすることが重要です。ここでは、受験生がつまずきやすいポイントと、その具体的な対処法をご紹介します。
3-1. モチベーションが低下した時
学習を長く続けていると、モチベーションが低下するタイミングが必ずあります。
特に、学習に成長を感じられず焦りを覚えたり、同じ作業を繰り返すことに疲れてしまった時などによく見られます。 結果として「やる気が出ない」「勉強がつまらない」と感じてしまい、学習効率が落ちてしまいます。
モチベーションが低下した時は、まずは休息を取ることが大切です。2-4.でご紹介したリフレッシュ方法などを実践して、勉強から少し距離を取りましょう。
さらに、「なぜモチベーションが下がったのか?」という原因を分析することも重要です。モチベーションが低下する時は、何らかの原因がある場合が多くあります。 例えば、テキストの内容が理解できずにモヤモヤしてしまう、毎日が同じことの繰り返しで疲れてしまうなどです。
原因がわかれば、それを取り除くことでモチベーションを回復できます。 具体的には、質問ができる相手を見つけたり、勉強方法や環境を変えてみるなどの対策が考えられます。
モチベーションが下がった時は、それでも無理やり学習を続けるのではなく、疲れた脳を休ませることと、原因を見つけて改善することで、モチベーションを持ち直して学習を進めるきっかけになります。
3-2. 範囲が広すぎて焦る時
社労士試験は、全10科目の幅広い知識が試験範囲となっています。細かい数字や知識を全て完璧に覚えることは、簡単にできるものではありません。
試験範囲だからといって、テキストに書いてあることを全て覚えようと考えていると、数字や単語が頭の中で混ざり合い、混乱し、勉強がつまらないと感じる原因になってしまいます。
資格試験で重要なのは、試験で問われるポイントを押さえることであって、全てを暗記する必要はありません。過去問を分析し、頻出分野や重要な論点を中心に学習を進めることで、効率的に合格点を目指すことができます。
範囲全てを暗記しようとせず、まずは合格に必要な知識を戦略的に身につけることを重視しましょう。
しかし、独学で学習を進めている場合、試験において重要となるポイントの判断や、効率的な学習範囲を選択していくことは簡単ではありません。
そのため、無駄なく学習を進めたいと感じる方は、資格試験対策の受験指導校の活用がオススメです。 資格試験に対する豊富な指導経験や実績を持つ講師が在籍しているため、効率的な学習サポートを受けることができます。
3-3. 漠然とした不安に襲われる時
勉強を続けていると、自分の進んでいる道が本当に正しいのか、この勉強方法を続けていて合格できるのかという不安が強くなる時があります。
試験日が近くなると、インターネットやSNSでも「今年の試験は例年より難しくなる」「この範囲は必ず出題される」「この教材では合格できない」といった、根拠の不確かな情報が数多く飛び交っています。
このような不確かな情報に触れすぎると、不安が大きくなってしまいがちです。
不安が強くなっていると感じた時に大切なのは、情報との適切な距離感を保つことです。「今の自分にとって本当に必要な情報なのか」と立ち止まって考えてみましょう。
学習は不安を持ちながら続けているとつまらなく感じてしまいがちですが、自信を持って取り組んでいると、前向きで楽しい気持ちで勉強を続けることができます。
4. 社労士試験を受験するなら受験指導校がおすすめ
社労士試験は独学での合格も不可能ではありませんが、より効率的に、楽しみながら学習を進めていくためには、受験指導校の活用をおすすめします。
今回は、伊藤塾の社労士講座の特徴を踏まえて、なぜ受験指導校による学習がおすすめなのかを紹介していきます。
4-1. 法律資格専門の受験指導校としての実績がある
伊藤塾は「法律資格専門の受験指導校」です。
文系最難関資格である司法試験の2024年度合格者のうち「9割以上が伊藤塾の受講生」という高い実績を誇り、法律分野の指導力については定評があります。
法律分野の知識は、馴染みにくく、苦手意識が強い方も多く、「理解できない。暗記だらけでつまらない。」と学習を断念する方が少なくありません。
伊藤塾では、「なぜこういう制度があるのか。この制度とこの制度とはどういう関係にあるのか。」といった「法律を趣旨から考える」講義を行っています。
「法律を趣旨から考える」ことによって、「なるほど、そういうことだったのか!」と腑に落ちる理解が可能となり、知識がつながり広がっていく喜びや楽しさを感じながら学習を進めていくことができます。
これは、丸暗記だらけの辛く苦しい受験勉強とは別世界の学習スタイルといってよいでしょう。
その結果、初学者であってもモチベーションを落とすことなく、楽しみながら合格まで学習を続けていくことができるほか、試験本番で初見の問題が出題された際にも、「趣旨」に立ち戻ることにより慌てることなく正解を導き出すことができるようになります。
学習範囲が広くて覚えきれないと感じている方や、重要な知識をメリハリをつけて学びたいと思う方、勉強に楽しさを見出して資格試験までのモチベーションを維持したい方にとっては、最適な学習方法となるでしょう。
長年の指導経験と高い実績に基づいた効果的な方法で確かな成果を出したい方はぜひ伊藤塾をご活用ください。
【社労士】伊藤真塾長×持田裕講師~伊藤塾で「社労士」を目指す意味とは~
4-2. 質問システムやカウンセリングを受けられる
伊藤塾では、学習内容に対する質問を受け付ける制度に加えて、学習方法や実務に関することなど、受験生活上での悩みや不安に対するカウンセリング制度が用意されています。
学習の中で疑問が発生した時、そのままにしたり、自分なりの曖昧なとした答えを見つけたりするだけでは、学習に対する不安がなくならず、学習意欲が低下していきがちです。
質問に対する適切な回答を得られることで、自分が成長をしたという実感が生まれ、勉強が楽しいという感覚を持つことができるようになります。
さらに、試験に関する知識以外の相談ができる相手がいることにより、「一人きりで勉強をしている」という孤独感が解消され、モチベーションの維持に繋げることができます。
4-3. アプリによるアウトプットができる
伊藤塾では、テキストの構成に対応した「一問一答形式」のアプリが用意されています。
アプリによる学習は、隙間時間や移動時間を利用して効率的に学びを深めることができますが、独学でアプリによる学習を取り入れることは簡単ではありません。
伊藤塾のアプリでは、カテゴリーや重要度ごとの絞り込みもできるため、自分にとって必要な箇所の出題を選択することができます。アプリを活用した学習は、ゲーム感覚で気軽に取り組むことができ、日々の学習をより楽しく、継続しやすいものにしてくれます。
さらに、隙間時間に効率よくアウトプット学習をすることにより、テキストなどでインプットした知識をより一層定着させることができます。
5. おわりに
社労士試験は、長期間の学習が必要であり、決して楽な道のりではありません。
しかし、勉強に対して「楽しい」という感覚を持つことで、試験合格への道のりがより確かなものとなります。
社労士試験の勉強を楽しく続けるためには、次の要素が重要です。
| ◉小さな成功体験を積み重ねること ◉孤独感を解消すること ◉勉強を習慣にすること ◉リフレッシュ方法を確立すること |
ただし、これらを独学ですべて達成することは決して簡単なことではありません。
合格までの学習を楽しみながら効率よく確実に進めていきたい方は、伊藤塾をご活用ください。
伊藤塾では、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講中です。
社労士試験に合格してキャリアアップに挑みたい方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。
この記事でご紹介した内容を参考に、「楽しい」と思える勉強法を見つけて、社労士合格を勝ち取りましょう!

著者:伊藤塾 社労士試験科
伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。