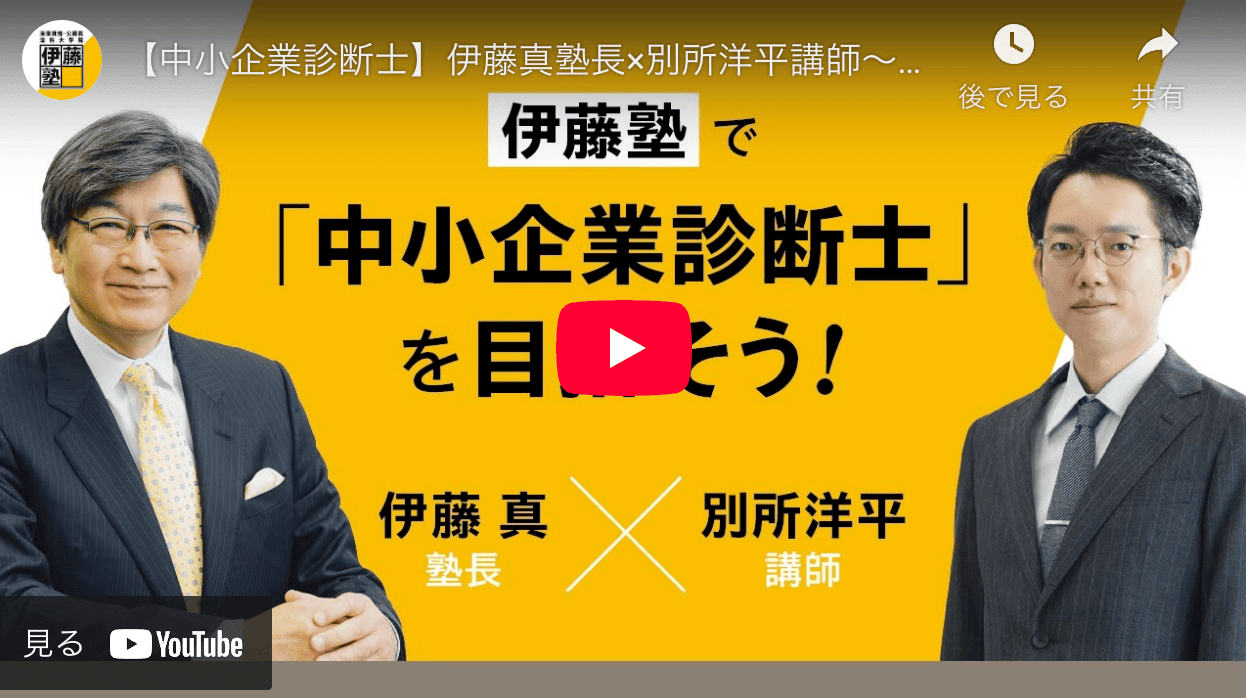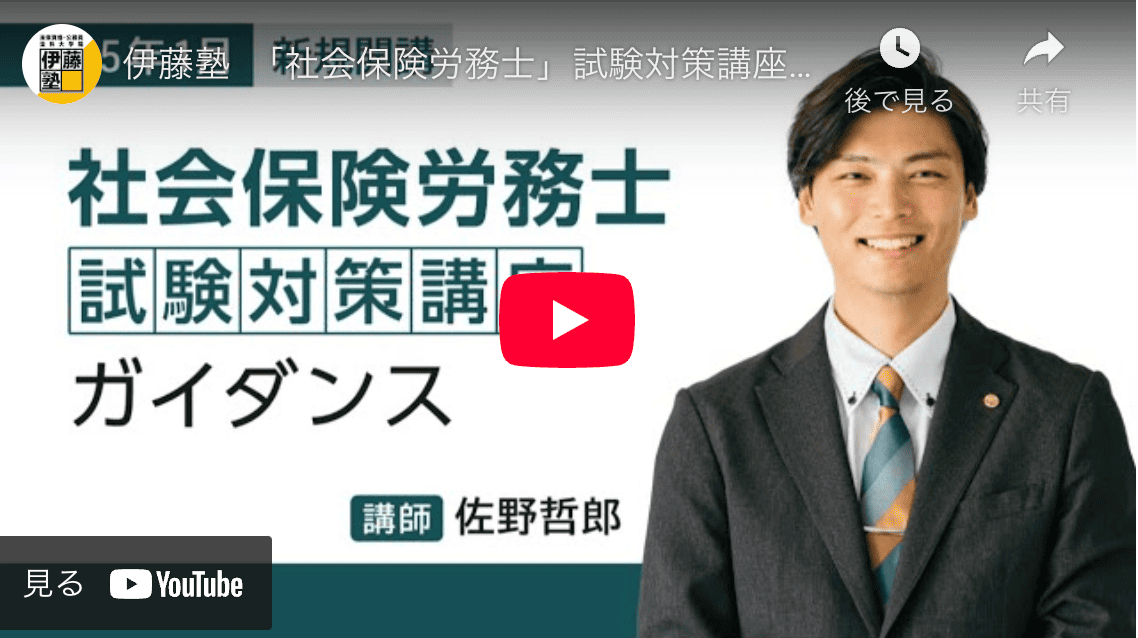社労士試験の申込みはいつからいつまで?インターネットと郵送の手順・必要書類についても解説
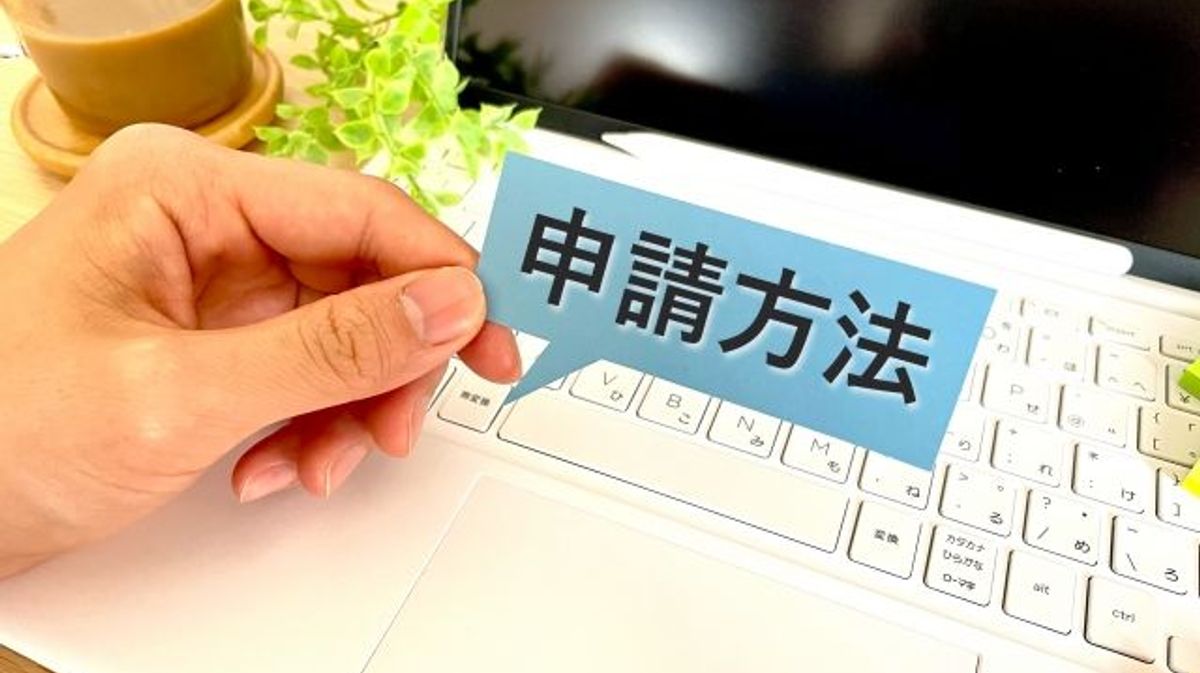
「人事のプロフェッショナルになりたい」
「独立して企業の労務サポートをしたい」
「自分のキャリアに確かな専門性を加えたい」
社会保険労務士(以下、社労士)は、このような思いを抱く人に注目されている資格です。
近年、働き方の多様化やワークライフバランスを重視する傾向が進み、職場環境の改善や人事労務の専門的な知識を持つ社労士という存在が重要視されています。
そのため、自身のキャリアの1つとして「社労士試験合格」を目指す人が多くなっているのです。
しかし、国家資格である社労士の試験においては、申込み手続きにも厳格な要件や手順が設けられています。家庭や仕事との両立を図りながら資格取得を目指す人にとって、こうした申込み方法を調べる作業は、資格試験に挑戦するハードルを上げる要因となってしまいがちです。
そこで今回は、社労士試験の申込み方法である「インターネット」と「郵送」について、事前準備、申請方法、必要書類などの、一連の流れをわかりやすく説明していきます。
今回の記事を参考に、社労士試験の申込みを終えて試験までの段取りを整えましょう。
【目次】
1.社労士試験の概要
1-1.試験日と試験時間
1-2.受験資格
1-3.申込みの方法
1-4.申込み期限
2. インターネット申込みの手順
2-1.事前準備
2-1-1.用意しておくもの
2-1-2.顔写真の形式
2-2.申込み完了までの流れ
2-2-1.マイページの登録
2-2-2.必要書類のアップロード
2-2-3.受験料の払込
2-2-4.申込み完了
2-4.申込み後の変更ができない点に注意
3. 郵送申込みの手順
3-1.事前準備
3-2.受験案内の請求
3-3.申込み方法
3-3-1.受験申込み書の記入方法
3-3-2.受験料の払込方法
3-3-3.受験申込み書の送付
3-4.郵送申込みの注意点
4.申込みはインターネット申込みがオススメ
5. 申込み後の流れ
5-1.受験票の発行時期
5-2.申込み内容の変更手続き
5-3.受験会場の決定方法
6.おわりに
1.社労士試験の概要
まずは、社労士試験を申し込むにあたって前提となる「社労士試験の概要」を解説します。
1-1.試験日と試験時間
社労士試験は毎年8月の第4日曜日に行われます。2025年の試験日はまだ公示されていませんが、例年通りであれば8月24日(日)に実施されます。
全国の会場で一斉に実施され、試験時間は午前(9:30~12:00)と午後(13:30~15:30)の2部制です。
(参考:全国社会保険労務士会連合会試験センター 社会保険労務士試験オフィシャルサイト)
1-2.受験資格
社労士試験を受験するためには、必要となる資格要件があります。
受験資格には「学歴」「実務経験」「国家試験合格」「過去受験」の4つの区分があり、それぞれの区分で要件が定められています。
いずれかの要件を1つでも満たしていれば、受験が可能です。
受験申込みの際は、要件を満たしていることを証明する受験資格証明書を提出する必要があります。証明するための書類は、該当する要件により異なり、原本又は写しの提出が必要です。
区分ごとの主な資格要件と、必要となる書類は以下の通りです。
| 区分 | 必要な資格 | 受験申込書とともに 提出すべき書類 |
| 学歴 | ①大学、短期大学専門職大学、 専門職短期大学又は5年制高等 専門学校を卒業した | 次のいずれか ・卒業証明書、修了証明書 ・卒業証書の写し ・学位記の写し |
| ②短期大学を除く上記の大学で 62単位以上の単位を修得した | 大学の成績証明書 | |
| ③修業年限が2年以上で修了に 必要な単位が62単位以上の専門 学校を修了した | 次のいずれか ・専門士、高度専門士の 称号が付与されていること を証明する書面 ・専修学校修了者受験資格 証明書 | |
| 実務経験 | 以下のいずれかの従事期間が3年 以上となる ①社労士事務所・社労士法人に 所属して行う補助業務 ②弁護士事務所・弁護士法人に 所属して行う補助業務 ②公務員としての行政事務 ③健康保険組合・年金事務所に 所属して行う社会保険法令に関 する業務 ④労働組合の役員としての労働 組合に関する業務 ⑤企業の役員としての労務担当 業務 ⑥労働組合や企業の職員として 行う労務関係事務 | 実務経験証明書 |
| 試験合格 | ①厚生労働大臣が認めた国家試験 に合格 | 次のいずれか ・合格証明書 ・合格証書の写し |
| ②司法試験予備試験の第一次試験 に合格 | 次のいずれか ・合格証明書 ・合格証書の写し | |
| ③行政書士試験に合格 | 次のいずれか ・合格証明書 ・合格証書若しくは証票 | |
| 過去受験 | ①直近3年間に実施された社労士 試験の受験票又は成績(結果) 通知書を所持している | 次のいずれか ・直近3年間に実施された 社労士試験の受験票 ・成績(結果)通知書 |
| ②社労士試験科目の一部免除決定 通知書を所持している | 社労士試験科目の 一部免除決定通知書の写し |
参照:受験資格について|社会保険労務士試験オフィシャルサイト
※社労士試験の受験資格については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。
→ 社労士試験の受験資格とは?高卒・実務経験なしでも受験可能?などわかりやすく解説
1-3.申込みの方法
試験の申込み方法は、インターネットと郵送の2種類です。ただし、社労士試験オフィシャルサイトではインターネット申込みを原則としており、こちらが推奨されています。
2つの方法の詳細な申込み手順については、後ほど詳しく説明していきます。
1-4.申込み期限
社労士試験の申込み期間は、例年4月中旬から5月下旬となっています。参考までに、2024年の場合は4月15日(月)から5月31日(金)でした。
郵送の場合は消印が期日までにされている必要があり、インターネットの場合は期日の23時59分までに手続きが完了している必要があります。
わずかでも遅れてしまうとその年の受験ができないため、申込み期間がいつからいつまでなのかを把握し、できるだけ早く手続きを済ますことが重要です。
2. インターネット申込みの手順
次に、インターネット申込みの手順を説明していきます。
2-1.事前準備
インターネット申込みを行うためには、パソコンやスマートフォンなどのインターネット環境とメールアドレスが必要です。ネットカフェなどでも申込みは可能ですが、セキュリティ面を考慮すると、自宅など信頼できる環境での利用が望ましいでしょう。
2-1-1.用意しておくもの
試験申込みには以下の書類をPDF、JPG又はJPEG形式で用意する必要があります。
| ①受験生全員が必要となる書類 ■顔写真 ■受験資格証明書 |
②必要に応じて用意する書類
■免除資格証明書
試験科目の一部免除を受ける場合に必要
実務経験を受験資格とする場合は受験資格証明の実務経験証明書と兼用が可能
■特別措置申請書
障害を持っていることにより試験において特別な措置を申請する場合に必要
障害の種類や程度により、別途で添付書類が必要
■戸籍個人事項証明書や住民票
改姓又は通称使用などで氏名変更をしている場合、それを証明するために必要
■外字届
合格証書に外字を使用したい場合に必要な書類
2-1-2.顔写真の形式
用意する顔写真は、以下の要件を満たしている必要があります。
・6か月以内に撮影したカラー写真である・受験者本人のみが写っている
・無背景、無帽、正面向きで撮影されている
・受験時に眼鏡を着用する場合は、眼鏡を着用して撮影されている
・明るさやコントラストが適切であり、鮮明である
また、アップロードするために必要なデータの条件は以下のとおりです。
・形式:JPG又はJPEG形式
・容量:3MBまで
サイズや縦横比は、アップロードをする際に切り取りや変更が可能です。
写真が上記の要件を満たしていない場合には、申込み後に再提出を求められる場合があります。要件を満たしているかを確認してからアップロードを行いましょう。
2-2.申込み完了までの流れ
申込みは以下の手順で進めます。
2-2-1.マイページの登録
①社労士試験の申込み専用サイトにアクセスし、メールアドレスを登録します。申込みサイトのマイページは毎年の試験終了後に情報が削除されるため、受験する年ごとに登録が必要です。
②登録後に受信したURLから、マイページのログインIDとパスワードを入力し、設定を完了させます。
2-2-2.必要書類のアップロード
①マイページにログインし、案内に従い必須事項を入力します。
②顔写真や証明書類を必要な形式でアップロードします。
2-2-3.受験料の払込
申込み画面から、受験料の払込方法を選択して払込を行います。
選択できる払込方法は、クレジットカード決済、又はコンビニ・銀行ATMでの振込のいずれかです。
コンビニ・銀行ATM振込の場合には、指定期日までに受験料を支払わなければ申込みは無効となるため、申込み後は速やかに振込を行いましょう。
2-2-4.申込み完了
上記の手順が終了すると申込みが完了となり、登録したメールアドレス宛に申込み完了メールが届きます。
申込み完了後は、マイページから申込み内容の確認や領収書のダウンロードをすることもできます。
2-4.申込み後の変更ができない点に注意
インターネットから申込みを行った場合でも、 申込み後に「住所・氏名・希望試験地」の変更をマイページ上で行うことができません。マイページ上で変更をすることができるのは、メールアドレスのみとなっています。
住所・氏名・希望試験地の変更をする場合には、指定の様式により郵送等で申請をする必要があります。変更の申請方法については、後ほど詳しくご説明をいたします。
3. 郵送申込みの手順
次に、郵送申込みの手順を説明していきます。
3-1.事前準備
郵送申込みの場合も、準備する書類はインターネット申込みと同様です。
ただし、書類一式を郵送するため、申込み時点で手元に書類が揃っていなければなりません。顔写真に必要な要件もインターネット申込みと同様ですが、申込み書に貼り付けるため、データではなく実際の写真を用意しておく必要があります。
3-2.受験案内の請求
郵送申込みでは、まずは申込みに必要な受験案内等を試験センターに請求して入手する必要があります。受験案内の取り寄せ方法は、以下のとおりです。
【準備するもの】
①往信用封筒(長形3号:縦 235 ㎜×横 120 ㎜)
②返信用封筒(角形2号:縦 332 ㎜×横 240 ㎜ ※A4判が折らずに入る大きさ)
③切手(往信用:110 円、返信用:180 円)
試験センターから速達での返信を希望する場合には、速達料金分の切手を加算し、返信用封筒に赤字で「速達」と記載します。書留対応はすることができません。
【請求の手順】
①「往信用封筒」に 110円分の切手を貼付して、試験センター、並びに請求者の郵便番号、住所、氏名を記入
②表面に「受験案内請求」と赤い文字で記入
③「返信用封筒」に 180円分の切手を貼付して、請求者の郵便番号、住所、氏名を記入
④手順③で用意した返信用封筒を折りたたみ、手順①で用意した往信用封筒に入れて、以下の住所へ送付
東京都中央区日本橋本石町 3-2-12
社会保険労務士会館 5階 全国社会保険労務士会連合会 試験センター
【請求受付期間】
2025年3月3日から5月30日まで
【受験案内等発送時期 】
2025年4月中旬(官報公示日)から2025年5月30日
・公示前に届いた請求分は、公示の翌営業日に発送されます。
・公示後に届いた請求分は、試験センターに到着した2営業日後を目安に発送されます。
【同封物 】
試験センターからは、下記の書類が送付されてきます。手元に届いたら、必ず中身に不足がないかを確認しましょう。
| ①受験案内 ②受験申込み書 ③受験手数料払込用紙 ④実務経験証明書用紙 ⑤受験申込み用封筒 |
3-3.申込み方法
試験案内が届いた後は、必要な手順を踏んで申込みを完了させる必要があります。
3-3-1.受験申込み書の記入方法
申込み書の記載要領に従って、受験申込み書に以下の事項についてボールペンで記入をします。
・受験者の基本情報(氏名・住所・生年月日・年齢等)・希望試験地
・免除等(科目免除がある人のみ)
受験申込み書には顔写真を貼付します。貼り付ける際は、顔写真の裏側に氏名を記載する必要があります。
3-3-2.受験料の払込方法
受験案内に同封されている「受験手数料払込用紙」により、コンビニ、郵便局又はゆうちょ銀行で支払いをします。インターネット申込みと支払いの選択肢が異なり、払込の選択肢は払込用紙による振込み以外を選択することはできません。
3-3-3.受験申込み書の送付
記入をした受験申込み書を専用の封筒に入れて試験センターに郵送します。郵送をする際は、必ず簡易書留で行う必要があります。
ここまで完了すると、申込み手続きが完了となります。
3-4.郵送申込みの注意点
郵送申込みは、インターネット申込みと比較して工程が多く、注意すべき点もいくつかあります。手続きを行う際は、主に以下の点などに注意をしましょう。
■書類の送付方法
書類の送付手段は「簡易書留」と決められています。そのため、郵便局の営業時間内に手続きを行うことが必要です
土日に営業している郵便局は限られているため、できるだけ申込み期間内の平日に手続きができるよう準備を進める必要があります。
■郵送期限と受付の手段
書類の提出は郵送のみで受け付けており、試験センターに持ち込むことはできません。申込み期日までの消印が必ずもらえるよう、余裕をもって郵送手続きをする必要があります。
■スケジュール管理
郵送申込みでは、書類の取り寄せに時間がかかることを考慮する必要があります。思い立ったらすぐに手続きができるわけではないので、余裕をもって早めに準備を始めましょう。必要な書類を取り寄せ、準備して郵送するまでの日数を逆算し、申込み期限に間に合うようスケジュール管理が必要です。
4.申込みはインターネット申込みがオススメ
ご説明をしたように、現在は2種類の申込み方法が用意されていますが、社労士試験オフィシャルサイトでは、原則はインターネット申込みであることが記載されており、受験生にとってもインターネット申込みは多くのメリットが挙げられます。
| 【インターネット申込みのメリット】 ・郵送費用の節約 ・手続きが最短1日で完結 ・写真はデータのみで手続き可能 ・マイページによる申込み内容の確認 ・申込み期日の23:59まで手続き可能 |
5. 申込み後の流れ
申込み手続きが完了した後は、受験生が受験日までにすべきことは基本的に2つだけです。それが「受験票到着後の記載事項確認」と「必要に応じた申込み内容変更の手続き」です。
次に、この2つのポイントについて、受験票の発行時期と申込み内容の変更方法を説明していきます。
5-1.受験票の発行時期
試験の受験票は、申込みの際に登録した住所宛に、8月の上旬に発送されます。
郵便の確認漏れがないように、その時期は郵送物に注意をしましょう。住所が変わっている場合、届かない可能性があるため、次に説明をする変更手続きを必ず行ってください。
5-2.申込み内容の変更手続き
申込み後に、住所・電話番号・氏名・希望試験地のいずれかに変更があった場合には、変更の申請が必要となります。
インターネット申込みをした人であっても、マイページから変更を行うことができるのはメールアドレスのみで、その他の変更には書類の提出が必要です。手続きの流れは、以下の通りです。
【変更手続きの流れ】①変更内容に応じた様式をダウンロード 社会保険労務士試験オフィシャルサイトから、変更内容に合った様式をダウンロードします。
②必要書類の準備 様式に必要書類を記入し、必要に応じて添付書類を準備します。
③提出期限までに提出
FAX又は簡易書留にて提出します。様式により書類の提出方法が異なるため、注意が必要です。
※書類の提出時期によっては、変更が反映されない可能性もあります。
5-3.受験会場の決定方法
試験申込み書には希望試験地を記載しますが、必ずしも希望の会場になるとは限りません。受験会場の希望人数が収容可能な人数をオーバーしている場合には、近くの別会場が試験会場として登録されます。
実際に決定された受験会場は、受験票に記載されています。受験票が手元に届いたら、記載されている受験会場を確認し、当日の行き先に間違いがないよう注意しましょう。
6.おわりに
今回は、社労士試験のインターネット申込みと郵送申込みについて、具体的な手順を解説しました。どちらの方法でも、余裕を持って準備を行い、必ず期限内に手続きをすることが大切です。
「まだ時間がある」と考えていると、気がつくと期日を過ぎてしまっていたり、インターネットの不具合で手続きができなかったりと、最悪の場合には申込みが遅れて受験できない危険性もあります。
このようなリスクを回避するためにも、申込みはできるだけ早めに済ませてしまいましょう。申込みを終えたら、あとは試験当日に向けて勉強に集中するだけです。
力を尽くして学習に取り組み、試験合格を掴み取りましょう。
「学習の進め方が分からない」「一人で勉強するのが不安」という人は、ぜひ受験指導校である伊藤塾の講座受講を検討してください。
伊藤塾では、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講中です。
資格試験に精通した講師による体系的な講義や、効率的な学習方法のアドバイスを受けることで、最短距離での合格を目指すことができます。
社労士としてのキャリアを目指したいと考えている方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。
【社労士】伊藤真塾長×持田裕講師~伊藤塾で「社労士」を目指す意味とは~

著者:伊藤塾 社労士試験科
伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。