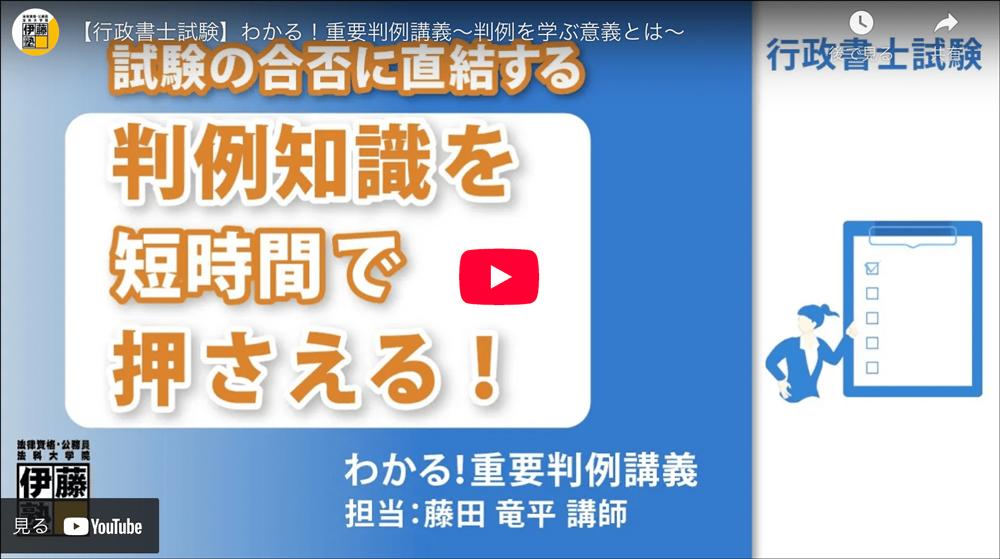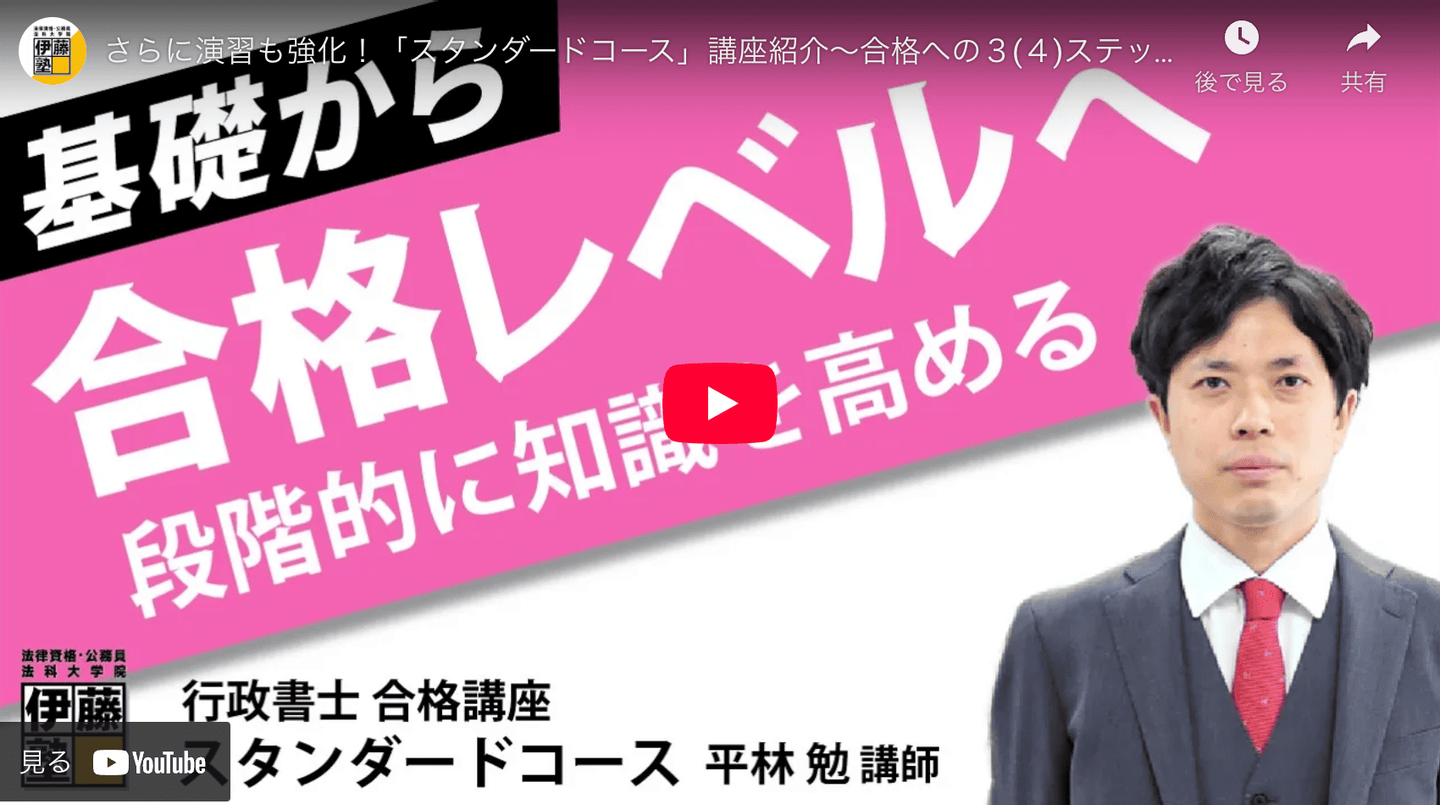行政書士試験に「判例集」はいらない?本当に必要な判例の覚え方
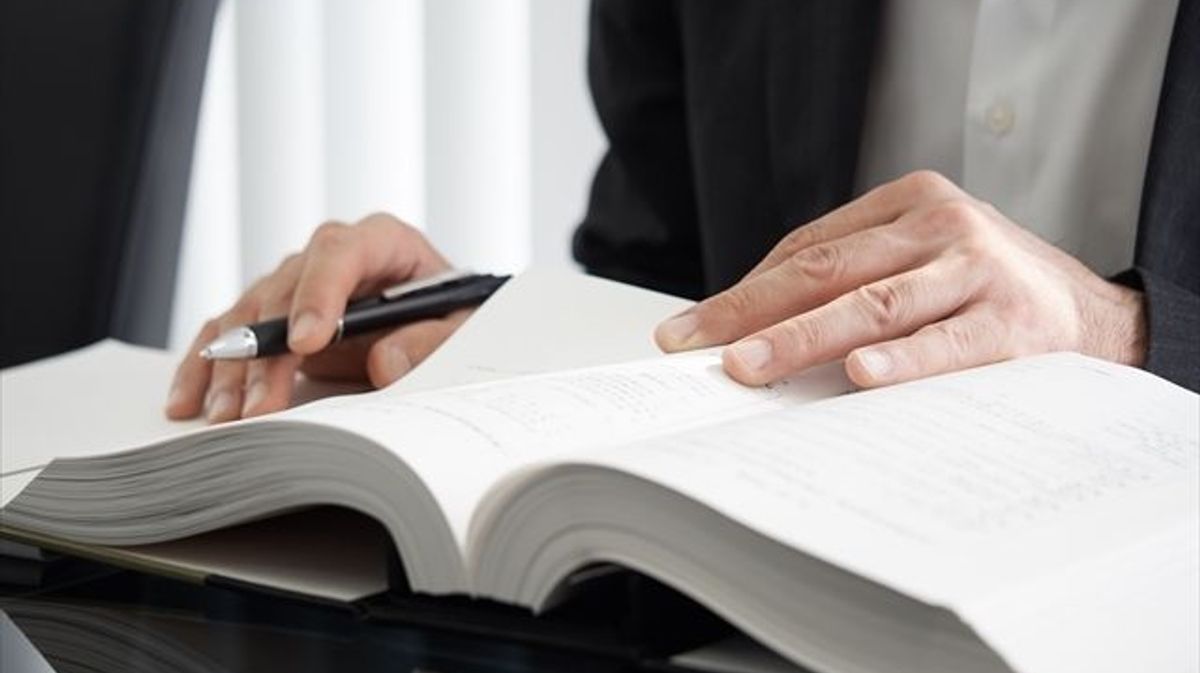
行政書士試験に合格するために「判例集」は必要なのでしょうか?
「判例集はいらない」
「いや、判例を覚えることが点数に直結する」
人によって様々な意見があるでしょう。
結論として、判例集は必須ではありませんが、判例を学ぶことは非常に大切です。
本試験でも、多くの問題が判例から出題されるため、判例の考え方を学ぶことが合否に大きく影響するからです。
では、もし判例集を使うならどう活用すればよいのでしょうか?また、効果的な判例の覚え方はあるのでしょうか?
本記事では、「判例集を使うべきか」「どのように判例を覚えればよいか」といった、判例学習のポイントを解説します。
【目次】
1.行政書士試験で判例集はいらない?
1-1.「判例集」は必須ではないが、「判例学習」は必要
1-2.判例集を全て暗記するのはNG
2.行政書士試験で判例集を使うメリット・デメリット
2-1.判例集を使うメリット
2-2.判例集を使うデメリット
3.行政書士試験の判例の覚え方
3-1.問題点と結論をおさえる
3-2.類似点と相違点をおさえる
3-3.思い出すきっかけを作る
4.判例集を使うべきか迷っている方へ
4-1.判例集の理想的な使い方
5.【藤田講師の動画解説】わかる!重要判例講義~判例を学ぶ意義とは~
6.まとめ
1.行政書士試験で判例集はいらない?
行政書士試験に合格するために判例集は必要なのでしょうか?
1-1.「判例集」は必須ではないが、「判例学習」は必要
行政書士試験において「判例集」は必ずしも必要ではありません。
重要な判例のほとんどは基本テキストに掲載されているからです。特に、基本的な判例や合否に直接関わってくる判例は、大半が講義やテキストでカバーされています。あえて「判例集」を使わなくても、合格レベルに達することはできるでしょう。
しかし、その一方で「判例学習」自体はとても大切です。本試験の問題は判例がベースになっているので、判例を押さえることで、より効果的に得点をアップできるからです。
例えば、過去5年間の本試験(憲法)を見ると、択一式では少なくとも3問、多肢選択式では毎年、判例が根拠となった問題が出題されています。判例をカバーすることで、得点力を飛躍的にアップできることが分かります。
【判例が根拠となった憲法の問題数】
| 5肢択一式 | 多肢選択式 | |
| 令和4年 | 4問 | ◯ |
| 令和3年 | 3問 | ◯ |
| 令和2年 | 4問 | ◯ |
| 令和元年 | 5問 | ◯ |
| 平成30年 | 4問 | ◯ |
1-2.判例集を全て暗記するのはNG
判例集を使うとき、くれぐれも注意したいのは「判例を全て暗記しようとしない」ことです。確かに、判例がベースとなっている問題は多いのですが、合否を左右するような判例知識はそれほど多くありません。あくまでも「重要な判例・出題が予想される判例」に絞って学習することが大切なのです。
「模試や過去問で知らない判例に出会うと、ついつい暗記しなければと思ってしまう…」
このような気持ちは分かりますが、判例集を精読したり、目についた判例をすべて覚えようとすると学習方針がブレてしまい、かえって合格から遠ざかります。
判例学習で最も大切なのは、「知らない判例を覚える」ことではなく、「既存の知識だけで正答できないか」を考える思考力を養うことです。見たことがない判例を見かけたら、次のような点を考えてみましょう。
・基本判例の趣旨から、結論を予想してみる・法律の定義から推測してみる
・なぜその判例が出題されたのかを考えてみる など
このような「現場思考」を身につけることで、知らない判例問題でも正解できる可能性は高まります。判例集は、判例を覚える教材ではなく、あくまでも理解を深めるための辞書代わりとして活用しましょう。
2.行政書士試験で判例集を使うメリット・デメリット
ここまでの内容で、「判例集」は必須ではないが「判例学習」は大切なことをお伝えしました。では、実際に判例集を使うべきでしょうか?
判例集を使うかどうか判断するために、そのメリットとデメリットを見ていきましょう。
2-1.判例集を使うメリット
判例集を使う最大のメリットは、多くの判例を短時間でまとめて確認できることです。
似ている判例や、異なった判例、特殊な判例を比較しながら学ぶことで、知識が体系的に整理され、より深い理解につながるでしょう。読み進めていくうちに、「なぜこの事例ではこのような判断になったのか」という法的思考力も自然と身につきます。
さらに、多くの判例をカバーしているので、テキストに載っていない新しい判例にも触れることができます。判例がどのような論理構成で書かれているかを学ぶことで、法的な文章の書き方が身につくという効果もあるでしょう。重要な判例だけに絞って学習できれば、非常に効率の良い試験対策になります。
◉判例集を活用するメリット
・短時間で判例をまとめて効率的に学習できる・似た判例や異なる判例を比較して体系的に知識を整理できる
・最新判例も含めて幅広く学べるため応用力がつく
・法的思考力が身につくので、記述式対策としても有効 など
2-2.判例集を使うデメリット
一方で、判例集を使う最大のデメリットは、膨大な時間を消費する危険性があることです。
判例集にはたくさんの判例が掲載されていますが、合否を分ける判例は、その中のごく一部にすぎません。そのため、やりすぎると負担が大きくなって他の勉強にも支障が生じます。
判例集を使うなら、試験の合否に直結する判例知識「のみ」に絞ることが重要です。
さらに、判例集で読んだ判例だからといって、必ずしも得点につながるとは限りません。
そもそも、試験で最新の判例が出題される場合、単に「知っているか」をチェックしているのではなく、「基本判例をきちんと理解できているか」を聞いていることが多いです。そのため、判例集を読んで知っていたからといって、丸暗記しているだけでは解けません。反対に、判例集を使っていなくても、基本判例の「考え方」さえ理解できていれば、正解できることもあります。
◉判例集を活用するデメリット・使い方を誤ると膨大な時間を浪費してしまう
・試験に直結しない判例まで手を広げると、非常に効率が悪い
・過去問演習など、他の勉強にあてる時間が圧迫される
・判例集で読んでいても、必ずしも正解できるとは限らない など
※こちらの記事もあわせて読まれています。
→ 行政書士試験に六法は必要?選び方と得点アップに向けた活用法をご紹介
3.行政書士試験の判例の覚え方
判例集を使うにせよ使わないにせよ、判例学習は必要です。
では、判例を学ぶときは、具体的にどのような方法で学習すれば良いのでしょうか?
判例の効果的な覚え方について、「問題点と結論をおさえる」「類似点と相違点をおさえる」「思い出すきっかけを作る」という3つの観点から説明します。
3-1.問題点と結論をおさえる
判例を覚える第一歩は、問題点と結論をしっかりおさえることです。
例えば、憲法の判例では必ず何らかの憲法問題が発生して、違憲訴訟が提起されています。
そのため、まずは「何が争われているのか」と「どのような結論になったのか」を理解することが重要です。具体的には次のようなポイントに着目しましょう。
① なぜ問題となっているのか② どういった人権が制約されているのか
③ 裁判所はどう判断したのか
【(例)憲法 マクリーン事件の場合】
→憲法第三章が、「国民の」権利及び義務となっているため、「外国人」にも権利が認められるかが問題となった②どういった人権が制約されている?
→外国人の基本的人権③裁判所はどう判断した?
→権利の性質上、日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも人権が認められる(性質説)
このように、判例を体系の中に落とし込んで理解することで、単なる暗記ではなく、実際に「考える力」が身につくのです。考え方が理解できれば、似たような判例が出題されても、現場思考で正解肢にたどり着くことができます。
3-2.類似点と相違点をおさえる
法律の勉強を進めていくと、似たような事案なのに結論が異なる判例に出会うことがあります。これらの判例は、本試験でも狙われやすいポイントです。
(例)憲法の場合
・薬事法の「距離制限」事件と小売市場の「距離制限」事件・「南九州税理士会」事件と「群馬司法書士会」事件 など
このような判例を覚えるときは、次の点を意識しましょう。
・どこが違うのか(相違点)
・なぜ違う結論になったのか(理由付け)
「合憲・違憲」といった結論だけでなく、「理由付け」をおさえることが大切です。裁判所がどのようなプロセスで結論に至ったのか、判例の考え方を理解しましょう。
似ている判例を「対比」する視点を持って勉強を進めると、思考が整理され、試験本番でもハッキリと思い出せるようになります。
※こちらの記事もあわせて読まれています。
→ 行政書士試験の憲法・基礎法学を攻略!捨てても良いのか?についても詳細解説
3-3.思い出すきっかけを作る
判例の中には、特殊なケースで体系的に理解しづらい判例もあります。
そこで重要なのが「思い出すきっかけ」を作ることです。きっかけは何でも構いません。
| ・具体的なエピソード ・語呂合わせ ・替え歌 ・絵などでイメージ化する など |
もちろん、全てを暗記することは避けるべきです。しかし中には、力技で覚える方がかえって効率的になるケースもあるでしょう。最初は語呂合わせなどで覚えていても、繰り返すうちに徐々に理解も深まっていくはずです。
また、憲法の違憲判決のように数が限られている場合は、先に「何個あるのか・どの判例があるか」を覚えてしまい、全体像を掴んだ方が良いケースもあります。「まずは覚える」と割り切ってしまい、知識を思い出すためのきっかけを作ることも戦略の一つです。
4.判例集を使うべきか迷っている方へ
「判例集も使うべきか迷っています…」
こういった質問をいただくことは珍しくありません。もちろん、余裕があるなら使用するに越したことはないでしょう。判例集によって、知識が広がることは間違いないからです。
ただし、ここで本当に考えるべきなのは「判例集を使った方がいいか」ではありません。大切なのは、今の状況で「実際に活用できるのか」です。
行政書士試験の勉強で、何より優先すべきなのは基本テキストと問題集です。
手を広げすぎるのではなく、一つのテキストと問題集を徹底的に繰り返して、基本的な内容を理解することが最優先です。これができていない状態で判例集まで手を広げると、逆効果になってしまいます。
4-1.判例集の理想的な使い方
一方で、テキストを読んでいて「何かしっくりこない」と感じる箇所があれば、そこだけ判例集で調べてみるのは非常に効果的でしょう。思考がクリアになって、判例に対する理解がさらに深まるはずです。
結局のところ、基本的な内容をしっかりと理解した上で、分からないところだけを深掘りするような使い方が理想的なのです。判例集は、あくまでも「辞書」のような位置付けで使用しましょう。迷ったときは立ち止まって考えてみてください。
今のあなたに必要なのは判例集なのか、それとも基本テキストの理解を深めることなのか…。そして、もし判例集を使うと決めたなら、試験の合否に直結する判例だけに絞り、短時間で集中的に学習することをおすすめします。すべての判例を学ぶのではなく、限られた時間を、いかに効率的に活用するかを意識しましょう。
5.【藤田講師の動画解説】わかる!重要判例講義~判例を学ぶ意義とは~
ここまでの内容で、「判例集を使うべきか」「どうやって判例を覚えるべきか」など、多くの受験生が悩むポイントを解説してきました。
では、実際に判例を理解して得点につなげるには、どのような勉強法が効果的なのでしょうか?
伊藤塾の人気講師、藤田講師が「判例学習の本当の意義」について具体的に説明します。
類似判例のポイントや、暗記に頼らない学習法など、合格に必要な判例学習のコツを紹介しますので、是非ご覧ください。
6.まとめ
記事のポイントをまとめます。
◉「判例集」は必須ではないが「判例学習」は必要
◉判例集を全て暗記するのはNG
・重要判例・出題予想判例に絞って学習するべき
・知っている知識だけで正答できないか、「現場思考」を養うことが大切
◉判例集を使うメリット・デメリット
・デメリットは、膨大な時間を浪費する危険性があること
◉判例の効果的な覚え方
・類似点と相違点をおさえる
・思い出すきっかけを作る(語呂合わせなど)
以上です。
判例学習では、やり方を間違えないことが大切です。特に「判例集」を使う場合は、時間をかけすぎないように注意しましょう。限られた判例を重点的に学び、本試験で「使える」知識を身に付けることが合格のカギを握っています。
独学で行政書士試験の勉強をしているけれど、なかなか成果が出ない方、これから行政書士試験に挑戦したいと考えている方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。
伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。
さらに演習を強化!「2025年合格目標 行政書士合格講座 スタンダードコース」のご紹介

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。