行政書士試験に落ちてもあきらめないで!再挑戦を勝ち抜くための合格戦略

「行政書士試験に落ちてしまった...」
「これだけ努力したのに、なぜダメだったのだろう...」
「また挑戦しようか…それとも諦めるべきか…」
行政書士試験に落ちてしまうと、こんな思いで胸がいっぱいになるかもしれません。
後悔の気持ちが押し寄せてしまい、自己嫌悪に陥っている人もいるでしょう。しかし、決して「自分はダメだ…」と感じる必要はありません。
試験に落ちたからといって、あなたの努力が否定されたわけではないのです。
さらに言えば、実は合格者の大半が、一度は不合格を経験しています。3回、4回と諦めずに挑戦して見事合格を勝ち取った方も大勢いるのです。
まずは気持ちを落ち着かせて、来年どうするべきか考えましょう。そして、再挑戦を決意されたなら、今年の結果をしっかりと分析して、早めに動き出すことが必要です。
本記事では、以下の内容を取り上げました。
・落ちてしまった方へ伝えたいこと・行政書士試験に落ちる主な原因
・来年に向けてするべきこと
・合格者は、何を変えたことで合格できたのか
行政書士試験に落ちてしまった方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士試験に落ちた方へ伝えたいこと
2.行政書士試験に落ちる主な原因
2-1.苦手な科目(民法)から逃げていた
2-2.過去問(問題演習)の取り組み方が誤っていた
2-3.勉強した量が足りていなかった
3.ギリギリで行政書士試験に落ちた方へ|原因は本当に「知識不足」?
4.行政書士試験に落ちた…来年に向けてすべきことは?
4-1.まずは「受かる」という覚悟を決める
4-2.勉強方法を見直してみる
4-3.ゴールから逆算してスケジューリングする
5.何を変えたら合格できた?何度も落ちた合格者の声を徹底分析
6.令和6年試験に落ちた方へ「平林講師の動画メッセージ」
7.まとめ
1.行政書士試験に落ちた方へ伝えたいこと
試験に落ちた直後は、様々な感情が湧き上がってくるものです。
「なぜ合格できなかったのだろう」「もっと努力すれば良かった」
「もう諦めたほうが良いのかも」
こうした後悔の気持ちでいっぱいになるかもしれません。しかし、無理に気持ちを奮い立たせる必要はありません。まずは少し時間を置いて、自分の気持ちと向き合ってみましょう。
行政書士になりたいという気持ちは本当に変わっていないでしょうか?
それとも、別の道を考えたいと思っているのでしょうか?
この時期に大切なのは、自分の気持ちに正直になることです。無理に前を向こうとしたり、自分を責め立てたりする必要はありません。十分に休息をとって、気持ちを整理する時間を持ちましょう。その上で、改めて「行政書士になりたい」という気持ちが残っているかどうかを、自分に問いかけてみてください。
2.行政書士試験に落ちる主な原因
再チャレンジを決めたら、自分が落ちた原因を考えてみましょう。
行政書士試験は決して簡単な試験ではありません。合格率は13%と非常に低く、大半の受験生が不合格となる試験です。
次の試験で合格したいなら、「なぜ落ちたのか」を徹底的に分析することが欠かせません。行政書士試験に落ちる主な原因は、次の3つです。
・苦手な科目から逃げていた・問題演習の取り組み方が誤っていた
・勉強量が足りていなかった
それぞれ見ていきましょう。
2-1.苦手な科目(民法)から逃げていた
あなたは、苦手科目から逃げていなかったでしょうか?
典型例は「民法」です。「難しい…」「分からない…」という苦手意識から、ついつい後回しにしてしまい、本番でも得点できなかった人は多いのではないでしょうか?
どれだけ苦手でも、民法を捨ててしまうと、行政書士試験に合格することは難しくなります。
「行政法などの得意科目だけで合格点を目指そう…」と考えるのではなく、しっかりと対策をすることが必要です。
苦手科目は、後回しにするのではなく「1日2問、3問」と決めて、強制的に毎日触れ続けましょう。継続することで、苦手意識は少しづつ薄れていきます。また、「できる・できない」の判断基準を厳しくすることも重要です。
ありがちなのが、過去問の正誤が分かっただけで「できた」と判断して、本番で失敗するケースです。過去問が解けても、「なぜその解答が正しいのか」を説明できなければ、本当は「できていない」と考えるべきでしょう。
中には、社会人としてのプライドや経験が邪魔をして、「できない・分からない」と認めることが苦手な人もいますが、素直に自分の弱点と向き合いましょう。
※「民法」への苦手意識を解消するためのアプローチ法について、伊藤塾の藤田講師がミニ講義を交えつつ解説しています。
2024年度試験において悔しい思いをした方、その中でも特に民法で大きな失敗をし、2025年度試験こそは民法も克服し、得点源にしていきたい方は是非ともご視聴ください
【受験経験者向け】合格発表後からの民法へのアプローチ ~今年は絶対に!民法は取りこぼさない!~
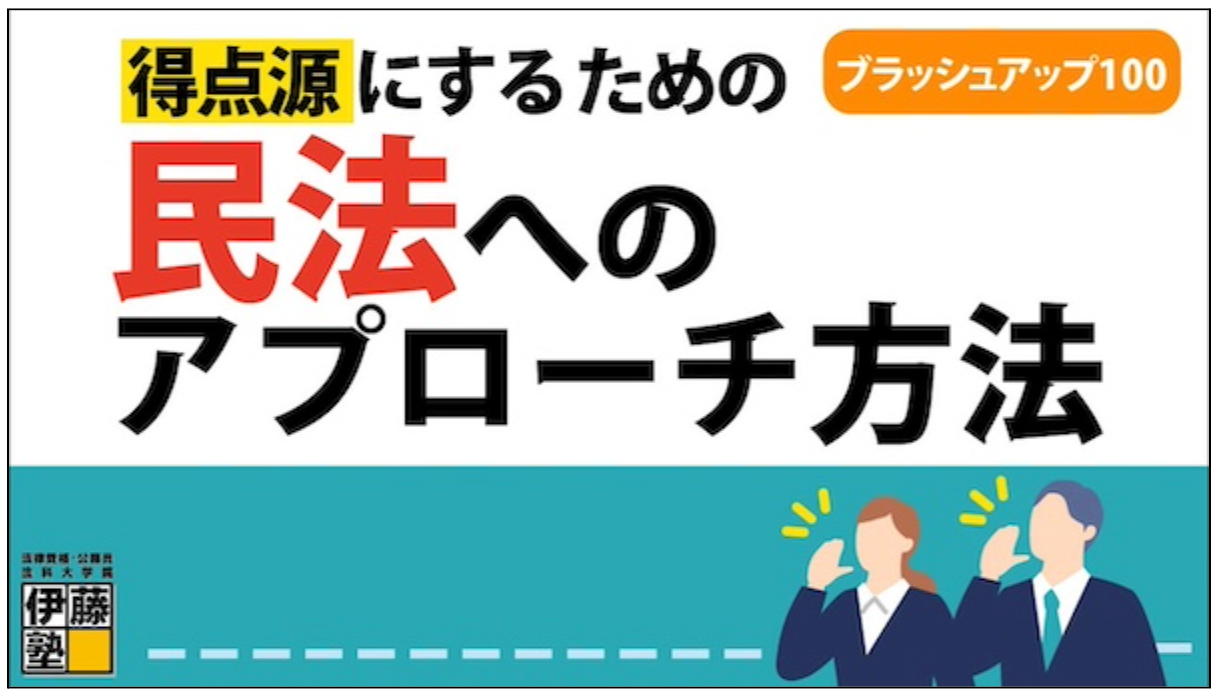
※さらに、民法の勉強法については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→ なぜ行政書士試験の民法は覚えられないのか?難しいと悩む前に試してほしい思考法
2-2.過去問(問題演習)の取り組み方が誤っていた
大量の過去問を解いても合格できなかった場合、問題への取り組み方が誤っていた可能性があります。多くの受験生が「過去問を解いた」と言いますが、合格者と不合格者では、その「解き方」に大きな違いがあるのです。
例えば、次のような勉強方法に心当たりは無いでしょうか?
・毎日、大量(30問以上)の過去問をこなしていた・過去問で正解することだけを目標に勉強していた
もし、思い当たる節があれば、過去問への取り組み方に問題がある可能性が高いです。
過去問演習で必要なのは、単に問題を解くことでなく、「なぜその解答になるのか」、「どういう思考プロセスで解くべきなのか」を理解することです。
これができていれば、1日に解ける過去問の数には自ずから限界が訪れます。少なくとも、毎日何十問も解くような勉強はできないはずです。
間違えた問題はもちろん、正解した問題も「どういった理由で正解となるのか」を振り返ってみましょう。
「正誤の結果」ではなく、「理由付け」を大切にして勉強に取り組んでみてください。これを徹底することで、正しい思考法が身につき、初見の問題にも対応できる力が養われます。
2-3.勉強した量が足りていなかった
人によっては、単に勉強量が足りていなかっただけの可能性もあります。そもそも、行政書士試験では「600〜1000時間」程度の勉強が必要だと言われています。
中には、3ヶ月などの超短期で合格する人もいますが、これは学習範囲を徹底的に絞り込み、絞り込んだ内容だけをひたむきに繰り返した結果です。よっぽど効率的に勉強を進めていかなければ、勉強量の不足をカバーすることは難しいです。
また、どれだけ効率的な学習法を実践しても、最低限必要な勉強時間は存在します。どれだけ忙しくても、一定の勉強時間を確保することは必要なのです。
大切なのは、勉強時間を「見つける」のではなく「作り出す」という意識です。
時間が足りない場合は、「朝1時間だけ早く起きる」、「通勤時間を活用する」、「昼休みに1問でも解く」などの工夫をしてみましょう。スキマ時間を上手く活用することで、最低限の勉強時間は確保できるはずです。
※行政書士の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 行政書士試験の勉強が「きつい」と感じたら?今すぐ試せる乗り越え方
3.ギリギリで行政書士試験に落ちてしまった方へ|原因は本当に「知識不足」?
試験に落ちた後、「知識が足りていなかった…」「もっと過去問を解けばよかった…」と考える方は多いです。しかし、本当に「知識不足」が原因なのでしょうか?
特に「ギリギリで落ちた」という方は、本試験の問題をもう一度振り返ってみてください。間違えた問題は、本当に「知らなかった」から解けなかったのでしょうか?
実は、すでに持っている知識を上手く活用するだけでも、正解にたどり着けたケースが多いのではないでしょうか?
合格に必要なのは、新しい知識をどんどん増やすことではなく、基本的な事項を確実に身につけて、様々な問題に応用する思考力を養うことです。そのためには、学習範囲を「絞り込み」、その内容を徹底的に「繰り返す」ことが不可欠です。
やみくもに手を広げるのではなく、必要な内容だけに集中して、盤石な基礎を身につけましょう。そうすれば、次回の試験では必ず合格の喜びを味わえるはずです。
4.行政書士試験に落ちた…来年に向けてすべきことは?
来年こそ行政書士試験に合格するために、何からスタートすれば良いのでしょうか?
再挑戦に向けて具体的に取り組むべきことを紹介します。
4-1.まずは「受かる」という覚悟を決める
まず必要なのは「絶対に受かってやる」という強い覚悟を決めることです。
行政書士試験は決して甘くなく、適当に勉強して合格できるものではありません。合格率13%の難関資格であることを、落ちた方は身をもって感じているでしょう。だからこそ、来年合格するためには、それなりの覚悟が必要なのです。
「来年こそは、絶対に合格してやるんだ」「行政書士になって、人生を変えてやる」
「そのためには、今頑張るしかない!」
このような強い決意をもって勉強に臨むと、学習の質と密度は格段に高まります。どれだけ強く決意できたかで、次回の結果が大きく変わってくるでしょう。
せっかく再チャレンジするのであれば、「絶対に来年受かってやる」と自分に約束しましょう。その覚悟が、これからの勉強を支える強固な土台となるはずです。
4-2.勉強方法を見直してみる
次に必要なのは、勉強方法の見直しです。
自分には何が足りなかったのか、どういった原因で不合格となったのかを冷静に分析し、その原因を克服する方法を考えることが重要です。例えば、以下のように原因と対策を考えてみましょう。
| 原因 | 勉強法 |
| 民法など特定の科目の 得点が低かった | その科目を集中的に強化する |
| 基本的な問題で間違え ていた | 苦手な分野だけ講義を再受講 するなどして、基礎から学び 直す |
| 知らない用語が多かった | ・インプットの比率を高める ・テキストや一問一答を活用 する など |
| 過去問は解けるのに本 番で得点できなかった | 「なぜそれが正解なのか」と いう理由付けを意識して過去 問に取り組む |
| 択一は合格圏内でも、 記述式ができなかった | ・記述式の解法を学び直す ・40文字で書くトレーニング をする |
落ちた原因をしっかりと分析して、対策を練り、合格までの道のりを描きましょう。
自信がない場合は、受験指導校のカウンセリングを利用することも一案です。プロ講師のアドバイスが、新たな気づきをもたらすかもしれません。
4-3.ゴールから逆算してスケジューリングする
現状分析が終わったら、ゴールから逆算して学習計画を立てましょう。
本試験までの残り日数、確保できる勉強時間、自分に足りないことを踏まえて、どのように勉強していくべきかを考えましょう。
例えば、本試験まで残り半年あるなら、その限られた時間の中で何を優先すべきかを明確にすることが必要です。
・苦手分野の克服に何ヶ月かける必要があるのか・インプットとアウトプットのどちらを重視するべきか
・過去問演習はいつ頃から始めるべきか
・記述対策はどの程度の時間が必要なのか など
ゴールまでのイメージが湧かない場合、合格者の話を参考にするのも効果的です。
身近に合格者がいれば話を聞いてみる、いなければ受験指導校の合格体験記を読むなどして、具体的なイメージを掴みましょう。
合格までの道筋をしっかりとイメージして、正しい方向に進んでいけるかが、合格のカギとなるのです。
※伊藤塾の行政書士試験合格体験記はこちらをご覧ください。
→ 2023年行政書士試験合格者が語る「合格を掴んだ学習法」
※行政書士の勉強スケジュールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 行政書士試験の勉強スケジュールは?いつ始める?合格者の勉強法も公開
5.何を変えたら合格できた?何度も落ちた合格者の声を徹底分析
行政書士試験に落ちた方が最も知りたいのは「一体、何を変えれば合格できるのか?」という点ではないでしょうか?
勉強法を見直すヒントは、実際に苦労して合格を勝ち取った先輩たちの体験談にあります。「何を変えれば合格できるのか」…実際に、不合格を経験して合格を勝ち取った方々の声から、合格した年の学習方法の変化を紹介します。
【伊藤塾 2023年行政書士試験 合格者の声】
TRAN THI TAMさん(5回目で合格)「過去問を何周しても試験本番では点数が伸び悩んでいましたが、なぜそのような結論になるのかを強く意識して勉強するようにしたところ、5回目の試験では記述で50点を取得し、合格することができました。」
竹内 あかりさん(3回目で合格)
「今まではただ記憶だけに頼り、何故そうなるのか?という理由までは考えて記憶していなかったため別の方向から問われると答えられないという状況でした。ゼミを取ったおかげで坂本講師から様々な角度から問われて鍛えられたのが大きな変化でした。それによりひとつの問いに対して幅広く思考を巡らせる癖が付いたと感じております。」
H.Sさん(4回目で合格)
「受験回数は4回ですが、体感では、2回目以降の知識は正確さを除けば、さほど変わらないと思っています。原因は、初見の問題が解けないことと、時間内に解ききれないことでした。過去問は解けるのに模試や本試験では点数が伸びない。とても悩みました。3回目の失敗を機に、根本の勉強方法が間違えているのでは?と考え、4回目の受講に、今までの受験指導校と伊藤塾をダブルで受講しました。気づいたこと。。。平林講師の講義で、解答までのプロセス・手順を踏んでいないことに気が付きました。目からウロコでした。知らない問題が、知らない問題に見えているだけのことでした。」
上記の声から、合格した年の変化をまとめると、次のようになります。
| 不合格だった年 | 合格した年 |
| ・過去問を何周もしていた ・試験本番では点数が伸び悩 んでいた | 「なぜそのような結論になる のか」を強く意識して勉強す るようにした |
| ・ただ記憶だけに頼っていた ・何故そうなるのか?という 理由を考えていなかった | 「ひとつの問いに対して幅広 く思考を巡らせる癖」 が付いた |
| ・初見の問題が解けなかった ・時間内に解ききれなかった ・過去問は解けるのに、模試 や本試験では点数が伸びなか った | ・(正確さを除けば)知識は さほど変わらなかった ・平林講師の講義で、「解答 までのプロセス・手順を踏ん でいないこと」に気が付いた ・知らない問題が「知らない 問題に見えていた」だけだと 分かった |
これらの合格者に共通しているのは、単なる「暗記」から「思考プロセス(理解)」を重視した勉強へ変えたことです。暗記に頼るのではなく、理由を考え、様々な角度から問題を捉える力を養うことが合格の鍵となっていることが分かります。
次回の挑戦では、ぜひ先輩たちの経験を参考に、学習方法を見直してみてください。
6.令和6年試験に落ちた方へ「平林講師の動画メッセージ」
行政書士試験に落ちてしまった方の中には、これからどのように学習を進めていくべきか、迷いや不安を抱えている人もいるでしょう。そんな方々へ向けて、伊藤塾の人気講師である平林講師から、動画メッセージをお届けします。
次回の試験に合格するための「逆算思考」という考え方に焦点を当てて、これからの学習計画の立て方や効果的な勉強法について解説します。ゴールから逆算して効率的に学習する方法や、合格者に共通する学習方法を知ることで、合格への道筋が見えてくるはずです。ぜひご視聴ください。
合格発表を受けて、再受験生のための合格戦略~本試験当日までの逆算思考で、これからの過ごし方、学習計画を考える~
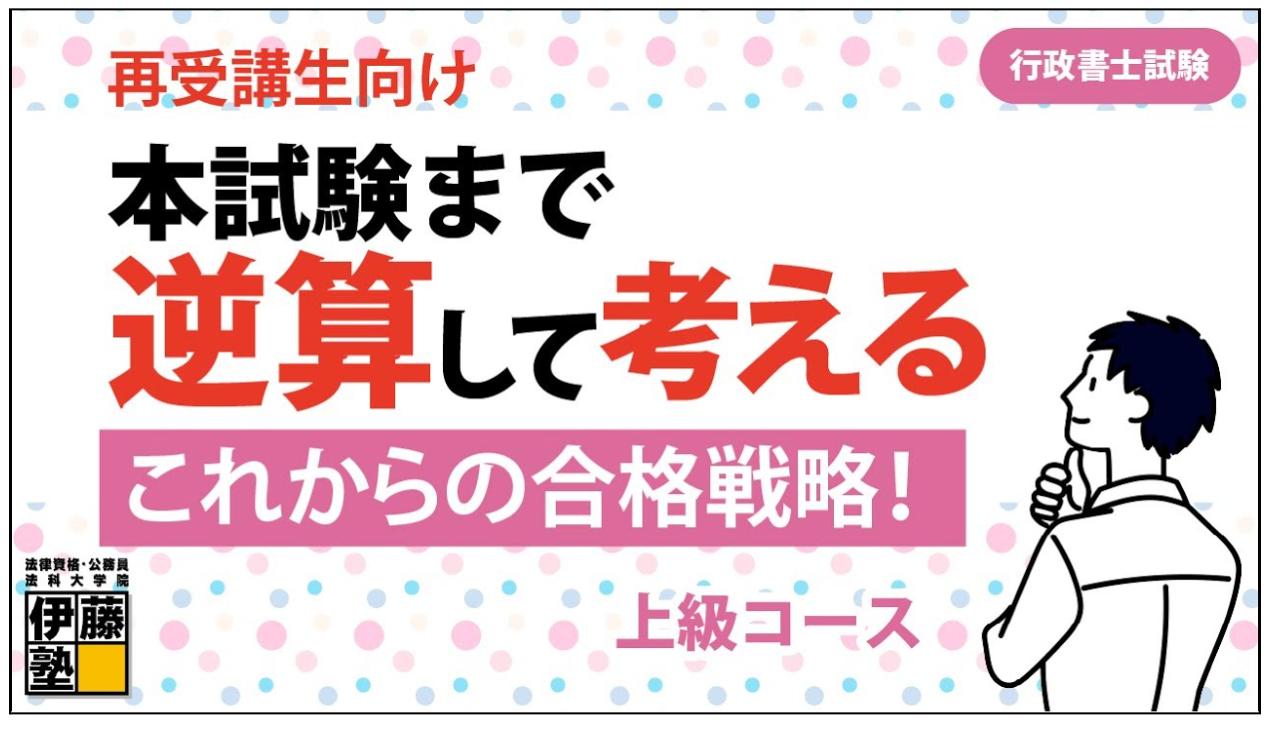
7.まとめ
記事のポイントをまとめます。
◉行政書士試験に落ちる主な原因は3つ
・苦手な科目(特に民法)から逃げていた・問題演習の取り組み方が誤っていた
・勉強量が足りていなかった
◉ギリギリで落ちた人の多くは「知識不足」ではなく「思考力不足」が原因
◉来年に向けて取り組むべきことは3つ
・勉強方法を見直して、原因と対策を分析する
・ゴールから逆算して学習計画を立てる
◉単なる「暗記」から「思考プロセス(理解)」を重視した勉強へ変えて合格する人が多い
以上です。
行政書士試験は、正しい方向で勉強すれば必ず合格できる試験です。
あなたが行政書士になりたいと思っているのなら、挑戦を諦める必要はありません。自分に何が足りなかったのかを分析して、来年こそ合格を勝ち取りましょう。
行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

















