行政書士試験の2つの足切り(基準点落ち)とは?科目別の対策を徹底解説
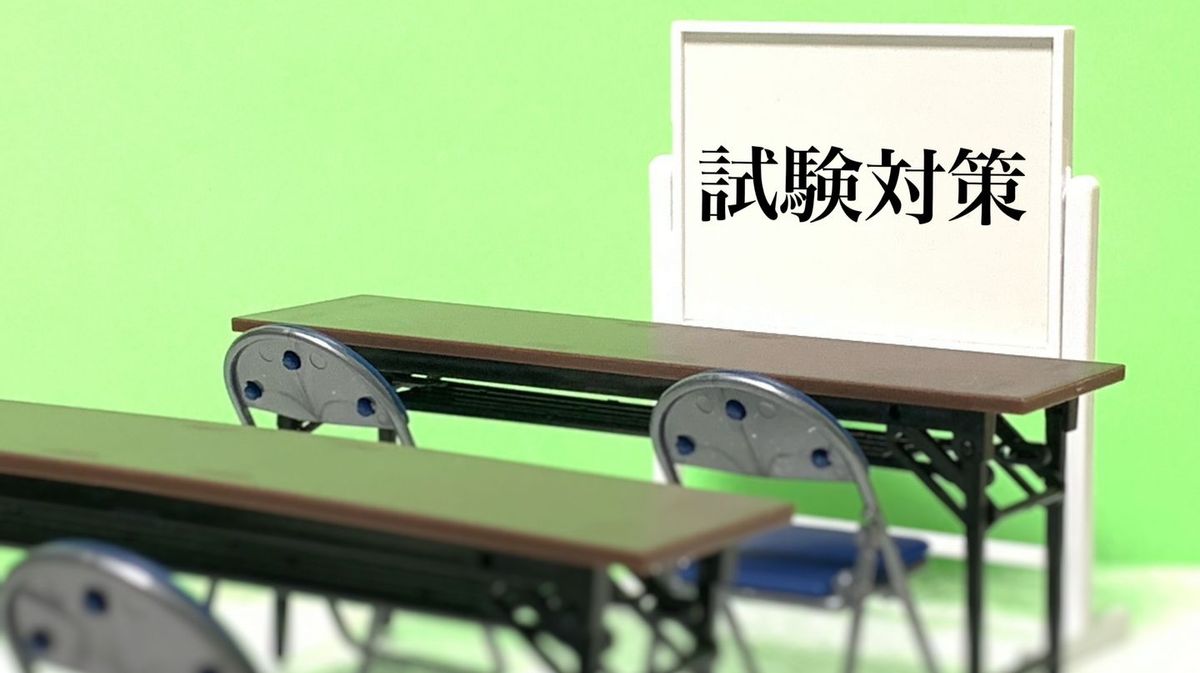
「行政書士試験の足切りが不安」
「足切りにならないためには、どうすればいい?」
こんな不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
行政書士試験では、次の2つの足切り(基準点落ち)が設定されています。
① 法令等科目で「122点」以上の得点があるか② 基礎知識科目で「24点」以上の得点があるか
特に「②基礎知識科目の足切り(基準点落ち)」は多くの受験生を苦しめています。
しかし、しっかりと得点戦略を考えて対策すれば、過剰に不安を感じる必要はありません。ポイントさえ理解できれば、基本的な内容を押さえるだけでも、十分に合格点に達するはずです。
本記事では、次の点を取り上げました。
◉この記事を読んで分かること・行政書士試験の足切り(基準点落ち)の概要
・「基礎知識科目」で足切り(基準点落ち)にならないための対策ポイント
・「法令等科目」の対策ポイント
行政書士試験の足切りが不安な方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士試験の「足切り(基準点落ち)」は2種類ある
1-1.①法令等科目の足切り(基準点落ち)は122点(50%)
1-2.②基礎知識科目の足切り(基準点落ち)は24点(40%)
1-3.記述式に足切り(基準点落ち)はある?
2.「基礎知識科目」の足切り対策
2-1.「諸法令」「情報通信・個人情報保護」を重点的に勉強する
2-1-1.「諸法令」の対策
2-1-2.「情報通信・個人情報保護」の対策
2-2.「一般知識(政治・経済・社会)」は力を入れすぎない
2-3.「文章理解」は満点を狙う
3.「法令等科目」の足切り対策
3-1.「民法」と「行政法」に力を入れる
3-2.基本的な問題を確実に正答する
4.【Q&A】行政書士試験の足切りに関するよくある質問
4-1.Q.行政書士試験では全科目に足切りがありますか?
4-2.Q.足切り点(基準点)を突破すれば合格できますか?
4-3.Q.合格するには、足切り点(基準点)+何点が必要ですか?
4-4.Q.法令等科目の足切りは、記述抜きで122点ですか?
4-5.Q.記述式が採点されない場合はありますか?
4-6.Q.基礎知識科目で足切り(基準点落ち)になったら、どうすればいいですか?
5.まとめ
1.行政書士試験の「足切り(基準点落ち)」は2種類ある
行政書士試験には「足切り」と呼ばれる制度があります。これは、科目ごとに設定された基準点を下回った場合、無条件で不合格となるものです。
具体的には、次の2つの基準が設定されています。
① 法令等科目で「122点」以上の得点があるか② 基礎知識科目で「24点」以上の得点があるか
足切り(基準点落ち)をクリアしても、それだけで合格できるわけではありません。しかし、逆に足切り(基準点落ち)をクリアできなければ、いくら高得点をとっても不合格になってしまいます。
行政書士試験に合格するには、法令等科目、基礎知識科目それぞれで、足切り(基準点落ち)を確実にクリアすることが必要です。
【(参考)令和6年度行政書士試験のご案内】次の要件のいずれも満たした者を合格とします。
① 行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者
② 行政書士の業務に関し必要な基礎知識科目の得点が、満点の40パーセント以上である者
③ 試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者
(注) 合格基準については、試験問題の難易度を評価し、補正的措置を加えることがあります。
(出典|(一財)行政書士試験研究センター)
1-1.①法令等科目の足切り(基準点落ち)は122点(50%)
法令等科目の足切り点(基準点落ち)は122点です。満点は244点なので、得点率にすると50%以上が必要です。
法令等科目では、基礎法学、憲法、民法、行政法、商法が出題されますが、各科目ごとや択一式・記述式といった出題形式別の足切り(基準点落ち)は設けられていません。つまり、科目・出題形式を問わず、合計122点以上あれば足切り(基準点落ち)はクリアできるのです。
ただし、実際のところは、法令等科目の点数がギリギリ足切り(基準点落ち)を突破する程度だと、合格は難しいでしょう。最低でも150点〜160点以上は目指したいところです。
【(参考)法令等科目で出題される科目】
| 択一式 | 多肢 選択式 | 記述式 | 科目別 の配点 | ||
| 法令等 科目 | 基礎法学 | 8点(2問) | 8点 | ||
| 憲法 | 20点(5問) | 8点(1問) | 28点 | ||
| 民法 | 36点(9問) | 40点(2問) | 76点 | ||
| 行政法 | 76点(14問) | 16点(2問) | 20点(1問) | 112点 | |
| 商法 | 20点(5問) | 20点 | |||
| 合計点 | 160点 | 24点(3問) | 244点 |
1-2.②基礎知識科目の足切り(基準点落ち)は24点(40%)
一方、基礎知識科目の足切り点(基準点)は24点です。満点は56点なので、得点率にすると40%以上が必要です。
40%と聞くと、一見、法令等科目よりも簡単そうだと感じる人が多いかもしれません。しかし、実は行政書士試験の足切り(基準点落ち)で涙を飲む人の大半は、基礎知識科目でつまずくケースだと言われています。
「法令等科目はトップクラスの成績だったのに、基礎知識科目で20点しか取れなかった」というのもよく聞く話です。したがって、行政書士試験の足切り(基準点落ち)をクリアするには、「基礎知識科目」の得点戦略が何より重要だと言えるでしょう。
「基礎知識科目」で足切り(基準点落ち)にならないための対策は後述します。
1-3.記述式に足切り(基準点落ち)はある?
記述式に、足切り(基準点落ち)は設定されていません。そのため、極端な話をすると、記述式がゼロ点でも択一式・多肢選択式で180点を超えれば合格できることになります。
とはいえ、実際に記述式を捨てることは全くオススメできません。苦手意識を持つ人も多いかもしれませんが、きちんと対策は行うべきです。
・日頃から理解に重点をおいて勉強する・部分点を積極的に狙っていく
・記述式から逃げずに、問題数をこなしていく
上記のようなポイントを意識すれば、択一式以上に効率よく得点を伸ばすことができます。
※記述式の対策については、次の記事で詳しく解説しています。
→「記述対策」を制するものは行政書士試験を制する?得点アップの秘訣を解説」
2.「基礎知識科目」の足切り対策
それでは、「基礎知識科目」で足切り(基準点落ち)にならないためには、どのように勉強していけば良いのでしょうか。ポイントになるのは次の3つです。
・「諸法令」「情報通信・個人情報保護」を重点的に勉強すること・「一般知識(政治・経済・社会)」は力を入れすぎないこと
・「文章理解」は満点を狙うこと
それぞれ詳しく説明します。
2-1.「諸法令」「情報通信・個人情報保護」を重点的に勉強する
基礎知識科目では、「諸法令」「情報通信・個人情報保護」を重点的に勉強しましょう。これらの科目は「基礎知識科目」とは言いつつ、実質的には法令科目に近いからです。したがって、しっかりと勉強をすれば確実に得点源にできます。
問題の難易度も「民法・行政法」などと比べると、決して高いとは言えません。細かな知識や、応用的な内容が問われるケースは少なく、基本的な知識だけで回答できる問題が大半を占めています。
2-1-1.「諸法令」の対策
諸法令は、2024年試験から加わった新しい科目です。主に「行政書士法」「住民基本台帳法」「戸籍法」などから、計4問程度の出題が予想されています。過去問が無いため、勉強の進めにくさを感じている人も多いかもしれません。
しかし、実は平成17年以前の行政書士試験でも、これらの問題は出題されていました。改正点に注意は必要ですが、平成17年以前の過去問を参考にすると勉強が進めやすくなるでしょう。
諸法令で出題される科目の内訳も、まだはっきりとはしていません。ただし、平成17年以前の試験制度では、行政書士法が少し多めに出題されていました。
そうすると、「行政書士法」から2問、「住民基本台帳法」から1問、「戸籍法」から1問となる可能性が高いと言われています。
※行政書士試験の「基礎知識科目」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【2024年】行政書士試験科目「一般知識等」から「基礎知識」への改正と対策について解説
2-1-2.「情報通信・個人情報保護」の対策
「情報通信・個人情報保護」からは、3問の出題が予想されています。このうち、「情報通信」は範囲が広く、予測がしづらい科目です。ウェブ上の用語から生成AIまで、情報通信に関する幅広い問題が出題されるからです。
ただし、ここ数年の問題を見る限り、過去問の内容が繰り返し出題される傾向があります。そのため、過去問を中心に勉強しておけば、十分に対応できるはずです。
一方、「個人情報保護」では、個人情報に関する法令の知識が問われます。問題の難易度も高くないため、得点源にするべき科目の1つです。なお、個人情報に関する法令はいくつもありますが、出題の中心は「個人情報保護法」です。時間がない場合は、「個人情報保護法」だけでもしっかりと勉強しておきましょう。
2-2.「一般知識(政治・経済・社会)」は力を入れすぎない
一般知識(政治・経済・社会)は、従来、8問が出題されていました。ただし、2024年以降は、問題数が半分程度まで削減されて、諸法令に充てられる可能性が高いです。
一般知識(政治・経済・社会)で大切なのは、勉強に力を入れすぎないことです。なぜなら、行政書士試験の中でも特に範囲が広く、ポイントを絞った対策が難しいからです。
勉強したからといって、確実に正答できるわけではなく、テキストや過去問に掲載されていない問題も珍しくありません。かと思えば、突然、正答率が9割を超えるような簡単な問題が出題される年もあります。つまり、費やした勉強時間に対するリターンが非常に小さいのです。
一般知識に費やす時間は最小限におさえましょう。最低限の対策だけ行い、浮いた時間は他の科目に時間を割くほうが賢明な選択です。短期間での合格を目指す場合は、全く手を付けないことも1つの方法です。
2-3.「文章理解」は満点を狙う
文章理解では、例年、3問が出題されます。目標とする正答率は、最低でも「3問中2問」、できれば満点を狙いたい科目です。
文章理解で満点(3点)を取れれば、基礎知識科目で足切りになる可能性は格段に低くなります。問題の難易度も、決して高いとは言えません。特に、令和元年以降は、正答率が9割を超える問題が大半を占めています。
すぐに得点力が伸びる科目ではありませんが、地道に訓練していけば、得点力は確実に伸びていきます。「諸法令」「情報通信・個人情報保護」と並び、得点源とするべき科目です。
※文章理解の対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 行政書士試験の文章理解で失敗しないポイントは?出題形式別の攻略法
3.「法令等科目」の足切り対策
次に、「法令等科目」の足切り対策について見ていきましょう。前述のとおり、法令等科目の基準点(足切り点)は122点です。出題形式、科目を問わず、122点以上あれば、足切り(基準点落ち)をクリアできます。
ただし、そもそも論として、「法令等科目」は足切り(基準点落ち)を気にするような科目ではありません。なぜなら、基礎知識科目の足切り(基準点落ち)を回避しつつ、法令等科目で点数を稼いでいくことが、行政書士試験に合格する基本戦略だからです。
法令等科目で、足切り(基準点落ち)ギリギリの点数しか取れないようであれば、合格はかなり難しいでしょう。「試験に合格する」という観点で考えると、最低でも「150点〜160点以上」は必要です。
そこでここからは、足切り(基準点落ち)を回避するだけでなく、「合格に必要な点数」をとることを踏まえた対策を説明します。ポイントとなるのは次の2つです。
・「民法」と「行政法」に力を入れること・基本的な問題を確実に正答すること
それぞれ詳しく説明します。
3-1.「民法」と「行政法」に力を入れる
「法令等科目」で最も力を入れるべき科目は、民法と行政法です。
なぜなら、民法と行政法だけで、行政書士試験全体の60%以上の得点を占めているからです。極論をいえば、「基礎知識科目」は基準点をクリアすることだけに専念しても、民法・行政法で8割正解できれば、試験には合格できてしまいます。
したがって、まずは「民法・行政法」に力を入れることが大切です。「民法・行政法」で安定して得点できれば、足切り回避はもちろん、行政書士の合格にも大きく近づけるでしょう。
※民法と行政法の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【行政書士の受験生必見】民法の勉強法を各分野・出題形式に分けて解説
→ 行政書士試験合格の鍵!行政法の効率的な勉強法を徹底解説
3-2.基本的な問題を確実に正答する
最も大切なポイントは、「基本的な問題を確実に正答すること」です。これさえできれば、法令等科目の足切り回避はもちろん、試験にも必ず合格することができます。
実際、多くの合格者は、本試験を受験した後で次のように話しています。
「なんだよ、結局、基本的な問題さえ取れていれば、合格できたんじゃないか…」受験生の多くが、勉強が進むほど、応用的な論点に目がいってしまいます。特に、直前期が近づいたり、模試の結果が悪かったりすると、その傾向が強く出てくるでしょう。見たことのない問題を目にすると、不安になる気持ちはよく分かります。
しかし、結局のところ、基本的な問題に確実に正答できれば、合格点に達することができるのです。
応用的な問題や、10年に一度しか問われないような細かな知識に、必要以上に目を奪われるのではなく、基本的な内容を着実に身につけましょう。最後までこの原則を忘れないことが、行政書士試験に合格するための最短ルートです。
4.【Q&A】行政書士試験の足切りに関するよくある質問
4-1.Q.行政書士試験では全科目に足切りがありますか?
いいえ。全科目に足切り(基準点落ち)があるわけではありません。
「法令等科目」全体で122点、「基礎知識科目」全体で24点が足切り点(基準点)として設けられています。
4-2.Q.足切り点(基準点)を突破すれば合格できますか?
いいえ。足切り点(基準点)を突破するだけでは合格できません。
合格には、試験全体で「180点」以上とることが必要です。
4-3.Q.合格するには、足切り点(基準点)+何点が必要ですか?
合格には、足切り点(基準点)+34点が必要です。
(34点=180点−122点(法令等科目の基準点)−24点(基礎知識科目の基準点))
4-4.Q.法令等科目の足切りは、記述抜きで122点ですか?
いいえ。法令等科目の足切り点(基準点)122点は、記述式も含めた点数です。
4-5.Q.記述式が採点されない場合はありますか?
はい。記述式以外の点数が「120点未満」の場合、記述式は採点されません。
択一式・多肢選択式の合計点が120点を下回ると、記述式で満点(60点)を取っても、合格できないからだと言われています。
4-6.Q.基礎知識科目で足切り(基準点落ち)になったら、どうすればいいですか?
次年度に向けて、「諸法令」や「情報通信・個人情報保護」などを中心に勉強を進めていきましょう。文章理解が苦手な場合は、毎日少しずつ、訓練を積むことが必要です。
「基礎知識科目」は独学では学習しづらいケースも多いです。苦手意識が抜けないようであれば、受験指導校の利用も検討してみましょう。
5.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉ 行政書士試験の足切り点(基準点)は次の2つ
・法令等科目で122点以上・基礎知識科目で24点以上
◉ 足切り(基準点落ち)で不合格になるケースの大半は、基礎知識科目が原因
◉ 基礎知識科目の足切り(基準点落ち)を回避するには、次の3つのポイントを意識する
・「一般知識(政治・経済・社会)」には時間をかけすぎない
・文章理解は満点を狙う
◉ 法令等科目では、足切り回避ではなく「150点〜160点以上」の得点を目指す
◉ ポイントは次の2つ
・基本的な問題に確実に正答できるようになること
以上です。
行政書士試験の足切り(基準点落ち)に苦しめられている受験生は珍しくありません。特に「基礎知識科目」の足切りが不安で、どう対策すれば良いか分からないという人は多いでしょう。
「基礎知識科目に苦手意識があって足切り(基準点落ち)が不安」、「法令等科目の得点がイマイチ伸びずに悩んでいる」という方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。
伊藤塾では、行政書士試験で必要な内容を、初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

















