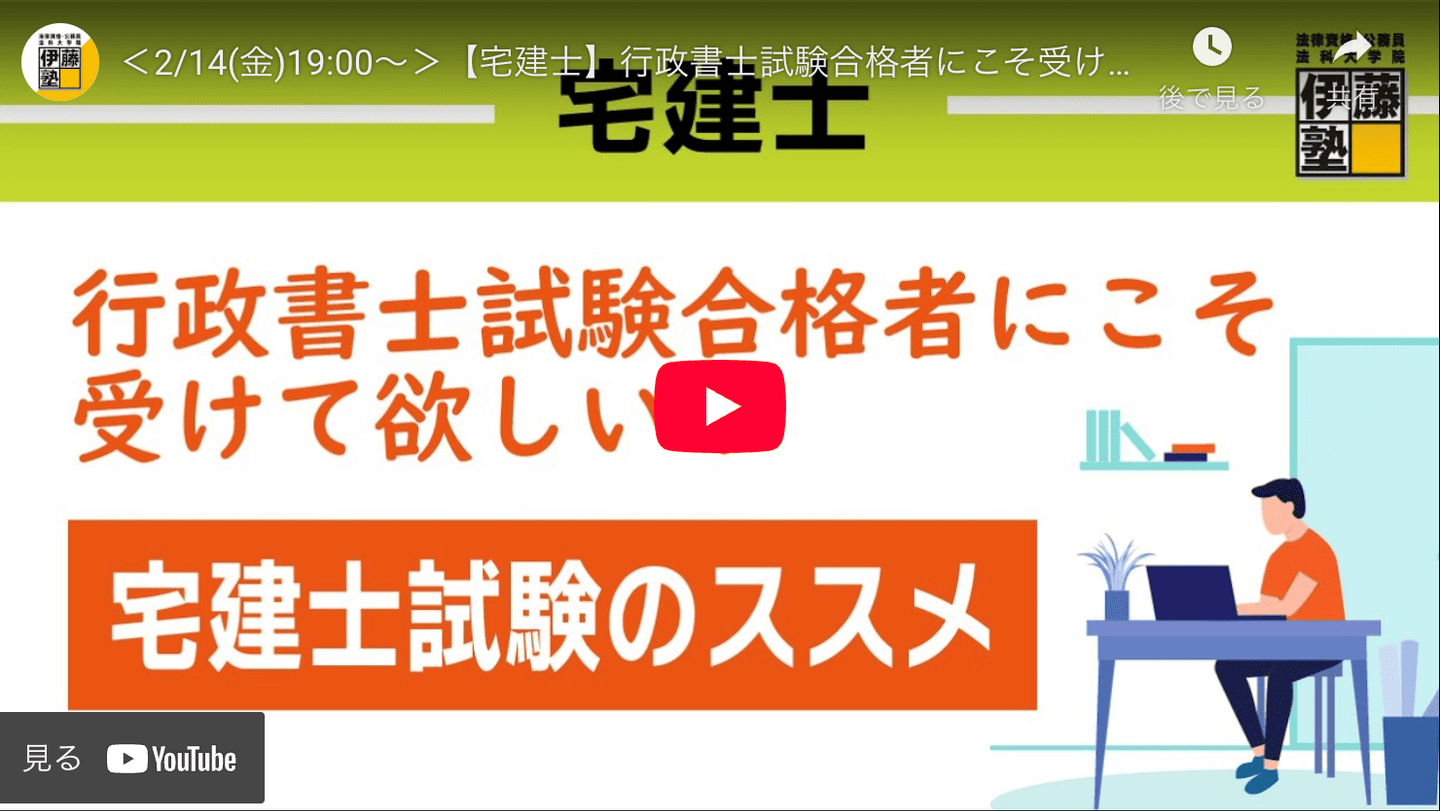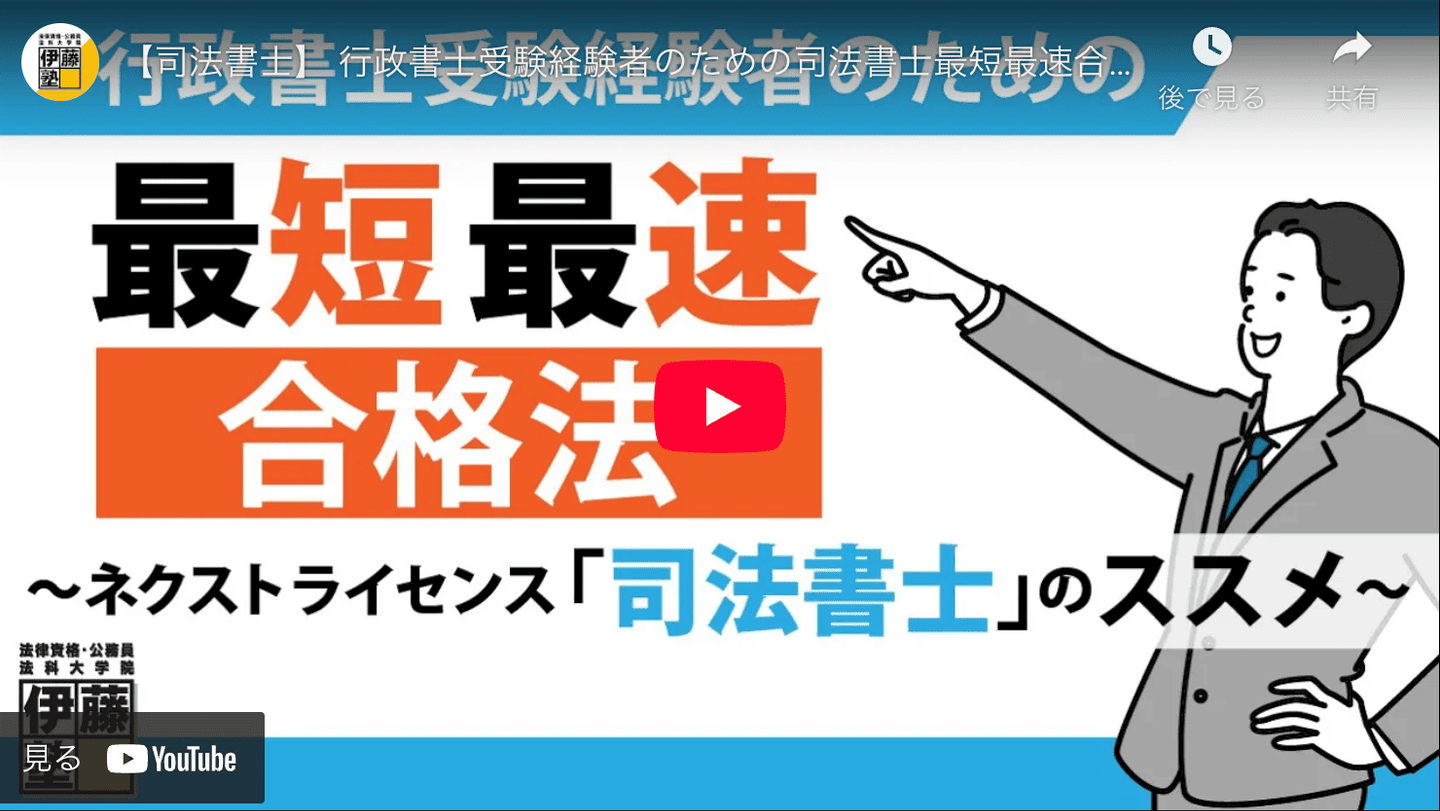行政書士が不動産業で活躍する方法!稼げる仕事4選と注意点も紹介

「行政書士と不動産業は関係ないのでは?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
一見すると接点が少ないように思えますが、実は行政書士の業務と不動産分野には深いつながりがあります。許認可申請から不動産仲介まで仕事の幅を広げたり、相続・農地転用から土地売買までサポートしたりと、様々な可能性があるのです。
本記事では、行政書士が不動産分野で活躍する方法と注意点を解説します。
【目次】
1.行政書士資格は不動産業でも活かせる
1-1.行政書士と不動産取引の関係
1-2.行政書士が不動産業で活躍できる理由
1-3.宅建業免許が必要なケースもある
2.行政書士が活躍しやすい不動産業務4選
2-1.不動産を含む相続(換価分割)
2-2.許認可申請からの不動産仲介
2-3.農地転用許可からの土地売買
2-4.建築物の用途変更
3.行政書士にできない不動産業務もあるので注意
3-1.不動産の登記はNG
3-2.不動産売買トラブルも介入してはダメ
4.行政書士として不動産業を扱うならダブルライセンスがおすすめ!
4-1.宅建士(宅地建物取引士)
4-2.司法書士
5.まとめ
1.行政書士資格は不動産業でも活かせる
「行政書士と不動産業は関係ないのでは?」と思われる方もいるでしょう。
一見すると接点が少ないように感じられますが、実は行政書士と不動産業には深いつながりがあります。特に「許認可申請」と「物件探し」はセットで依頼されることが多く、売上アップにつながります。
1-1.行政書士と不動産取引の関係
まずは、行政書士と不動産の関係を整理しておきましょう。
前提として、行政書士資格だけで「不動産取引」を進めることはできません。不動産取引で行政書士が行えるのは、「売買契約書」の作成だけだからです。
前後の売買交渉を代理で行ったり、売買契約後の不動産登記を行政書士が行うと、法律違反になってしまいます。
1-2.行政書士が不動産業で活躍できる理由
では、なぜ不動産売買ができないのに、行政書士が不動産業で活躍できるのでしょうか。答えは、行政書士の仕事の周辺に、不動産業が深く関わっているからです。
行政書士が最も得意としているのは、官公署への許認可申請です。飲食店の開業許可、リサイクルショップの古物商許可、民泊の許可申請などが典型例でしょう。そして、許認可申請の前後には、「店舗探し・物件探し」といった不動産業の仕事が存在しています。つまり、「せっかくなら開業用の物件も一緒に探して欲しい」といったニーズがあるのです。
行政書士としてこのようなニーズを拾っていけば、仕事の幅が広がります。仲介手数料などももらえるため、売上アップに直結するでしょう。
1-3.宅建業免許が必要なケースもある
ただし、上記のような不動産業では、宅建業免許が必要となるケースがあります。
特に、お金を受け取って物件の紹介や仲介をする場合は、宅地建物取引業者としての登録が法律で義務付けられています。行政書士資格だけでは、これらの仲介業務を行うことはできません。
宅地建物取引業者として登録するには、専任の宅建士を採用するか、あるいは自分で宅建士資格を取得する(ダブルライセンス)などの方法があります。免許要件は自治体によって異なるので、事前に確認が必要です。
※宅建士とのダブルライセンスについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士と行政書士を徹底比較!仕事・難易度・ダブルライセンスなど
2.行政書士が活躍しやすい不動産業務4選
行政書士が活躍しやすい不動産分野の仕事を4つ紹介します。
| ・不動産を含む相続(換価分割) ・許認可申請からの不動産仲介 ・農地転用許可から土地売買 ・建築物の用途変更 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2-1.不動産を含む相続(換価分割)
行政書士が行う相続サポートは、不動産仲介と深く関係しています。
相続財産に不動産が含まれる案件は多いですが、必ずしも相続人が譲り受けるとは限りません。
なかには不動産を売却し、現金化して分割する「換価分割」が取られるケースがあります。たとえば、複数の相続人がいて不動産の共有を望まなかったり、相続人が遠くに住んでいて物件管理が難しかったりする場合です。高齢化によって相続が急増する中で、「受け継ぐ」のではなく「売却したい」というニーズが高まっているのです。
不動産業を扱っている行政書士なら、相続手続きから売却まで一貫してサポートできます。売上につながるだけではなく、相続人にとっても大きな助けとなるはずです。
※行政書士の相続業務はこちらの記事で詳しく解説しています。
→ 「相続で行政書士ができること|相続業務の魅力や報酬も解説!」
2-2.許認可申請からの不動産仲介
意外とあるのが、許認可申請を依頼されたあと、不動産物件の紹介まで依頼されるケースです。例えば、飲食店を開くために相談に来た方から、開業用の物件探しを依頼されることがあります。また、民泊の開業許可で相談を受けた方に、用途変更に適した物件を仲介するケースも珍しくはありません。
行政書士が不動産仲介まで行うと、クライアントにとっても良い結果につながります。「許認可申請の要件を満たすのか」という観点から物件探しをすることで、「せっかく物件を選んだのに開業できなかった」というトラブルを避けられるからです。
「許認可申請ができる不動産業者」、あるいは「物件探しもできる行政書士」といったブランディングで、ライバルと差別化できるでしょう。
2-3.農地転用許可からの土地売買
さらに、「農地転用許可」も不動産業と相性が良い仕事です。
農地転用とは、田んぼや畑などを、農地以外の用途で利用するための手続きです。
例えば、実家の田んぼを使わなくなったケースを考えてみましょう。田んぼは農地法の適用を受けるので、基本的に「農地」としてしか利用できません。売却を考えても、「農地」として売る必要があるため、買い手が見つかりにくいという問題があります。
そこで必要になる手続きが、農地転用の許可申請です。行政書士が農地転用許可申請をすることで、田んぼを農地以外として活用できるのです。
そして、農地転用の許可がおりると、次は「土地をどのように活用するか」あるいは「誰に売却するか」という問題が発生します。行政書士が不動産業を扱っていれば、その後の不動産仲介まで、まとめて引き受けられます。実務上も、かなりニーズの高い分野です。
2-4.建築物の用途変更
建物の用途を変更する手続きも、行政書士が担当できる不動産業務です。
たとえば住宅を店舗に変更したり、オフィスを旅館に変更したりする場合には、建築基準法に基づく用途変更が必要になります。
用途変更には建築基準法だけでなく、消防法や都市計画法など複数の法律が関係するため、不動産業に精通した行政書士でなければ、スムーズな申請は難しいでしょう。
特に近年は、古民家をカフェに改装したり、民泊として活用したりなど、昔の住宅を用途変更して活用するケースが増えています。
不動産業として築古物件を紹介し、その後の用途変更まで一貫して扱うことができれば、大きなビジネスチャンスが広がります。
3.行政書士にできない不動産業務もあるので注意
一方で、行政書士にできない不動産業務もあります。
特に「不動産登記」や「契約トラブル」は、不動産業を扱っていくと必ず直面しますが、行政書士は扱えないので注意してください。それぞれ詳しく説明します。
3-1.不動産の登記はNG
不動産売買をしたり、相続をしたりしたときは、必ず不動産登記が必要です。しかし、この不動産登記は司法書士の独占業務です。行政書士が行うことはできません。
たとえば、相続財産に不動産があるケースでは、遺産分割協議書の作成までは行政書士の業務範囲ですが、その後の不動産登記は司法書士への依頼が必要です。行政書士は、登記に至るまでの一連の流れを進めたうえで、提携した司法書士に紹介するケースが一般的です。
行政書士に限らず、「不動産業」と切っても切れない関係にあるのが「不動産登記」です。不動産業を扱うなら、日頃から司法書士と良好な関係を築いておくことも、重要なポイントといえるでしょう。
3-2.不動産売買トラブルも介入してはダメ
不動産売買でトラブルが発生した場合も、行政書士は介入できません。法律によって紛争を解決することは、弁護士の独占業務だからです。
行政書士としてできるのは、あくまでも当事者の意思を反映した「売買契約書」を作成することだけです。例えば、「物件に隠れた瑕疵があった」「契約内容と違う」などのトラブルに発展した場合、代理人として交渉することはできません。
売買契約書の作成ができるので、実務上の区分けが難しいですが、最もトラブルになりやすい分野だといわれています。不動産売買を扱うなら、職域トラブルにならないよう細心の注意が必要です。
4.行政書士として不動産業を扱うならダブルライセンスがおすすめ!
不動産業に強い行政書士を目指すなら、「ダブルライセンス」が強力な武器になります。
行政書士資格だけでは様々な制限がありますが、「宅建士」や「司法書士」などの資格を組み合わせることで活躍の場が広がります。
※司法書士、行政書士、宅建士の3つの資格取得については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 司法書士・行政書士・宅建士のトリプルライセンスが最強!難易度も解説
4-1.宅建士(宅地建物取引士)
行政書士と宅建士(宅地建物取引士)のダブルライセンスは、不動産業を扱うなら最も実用的な組み合わせです。
宅建士資格を持てば、不動産の仲介業務を扱えます。他の人を採用しなくても、2章で紹介したような「許認可申請」と「不動産仲介」を組み合わせたサービスを提供できるため、売上アップにつながるでしょう。
宅建士試験は、行政書士試験よりも合格率が高く、試験内容も一部重複しているため、比較的挑戦しやすい資格です。不動産に強い行政書士を目指すなら、まず狙いたいダブルライセンスだといえるでしょう。
※宅建士については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【完全版】宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!
※【宅建士】行政書士試験合格者にこそ受けて欲しい宅建士試験のススメ
4-2.司法書士
司法書士とのダブルライセンスも、不動産業務の幅を大きく広げる組み合わせです。
前述の通り、行政書士は不動産の売買契約書作成などはできても、最終的な登記申請はできません。しかし司法書士資格があれば、契約から登記まで一貫して自分で行えるようになります。
例えば「農地転用→土地売買→所有権移転登記」という一連の流れを、途中で他の専門家に依頼することなく自分1人で完結できるのです。クライアントにとっても、手続きがスムーズになるだけでなく、費用面でもメリットがあります。
司法書士試験は試験範囲が広く、長時間の勉強が必要ですが、取得すれば大幅な収入アップが期待できる資格です。不動産分野に力を入れたい行政書士にとって、強力な武器となるでしょう。
※司法書士については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【完全版】司法書士とは?仕事内容・年収・資格のメリットをわかりやすく解説
※【司法書士】 行政書士受験経験者のための司法書士最短最速合格法~ネクストライセンス「司法書士」のススメ~
5.まとめ
記事のポイントをまとめます。
1.行政書士と不動産業務には深いつながりがある
行政書士と不動産業務には深いつながりがあります。許認可申請業務の前後には「店舗探し・物件探し」などのニーズがあり、これらを組み合わせることが売上アップにも直結します。ただし、物件紹介や仲介をする場合は宅建業免許が必要です。
2.行政書士と相性が良い不動産分野の仕事
許認可申請、不動産を含む相続、農地転用許可申請、建築物の用途変更などは、不動産業との相性が抜群の仕事です。
3.行政書士にはできない不動産業務もある
不動産登記は司法書士の独占業務であり、行政書士はできません。
また不動産売買でトラブルが発生した場合も、紛争解決は弁護士の独占業務のため介入できません。
4.不動産業を扱うならダブルライセンスがおすすめ
不動産業を扱うならダブルライセンスを目指しましょう。
宅建士資格があれば、人を雇わなくても不動産仲介が可能になり、司法書士資格があれば登記まで一貫して対応できます。業務範囲が広がるだけでなく、収入アップにもつながります。
以上です。
行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。