行政書士試験の文章理解で失敗しないポイントは?出題形式別の攻略法
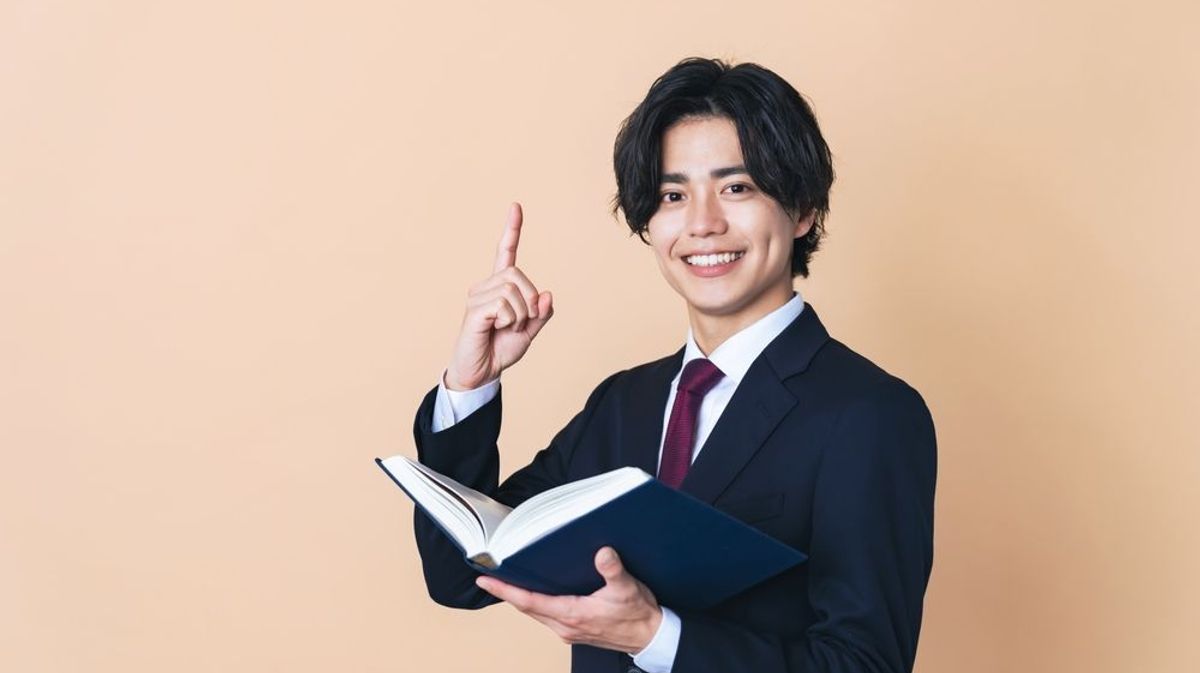
文章理解は、「基礎知識」科目で最も得点の取りやすい科目です。目標とする点数は、最低でも「3問中2問」、できれば満点を狙いたいところです。
「いつも、なんとなく正解できているから大丈夫」
「3問中1〜2問は取れるから、他の科目に勉強を時間を割きたい」
こういった方もいるかもしれませんが、できる限り満点を目指しましょう。
文章理解で満点を取ることができれば、基礎知識の足切り(基準点落ち)を回避できるだけでなく、法令科目にも良い影響が生じます。文章理解で満点を取ることは、あなたが考えているほど難しくはありません。
本記事では、次の点を取り上げました。
◉この記事を読んで分かること・文章理解で満点を目指すべき理由
・出題形式別の攻略法
・文章理解で失敗しないためのポイント
行政書士試験の合格を目指している方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士試験の文章理解は「満点」を目指そう
1-1.基礎知識の「足切り(基準点落ち)」を回避できるから
1-2.以前より簡単になっているから
1-3.多肢選択式・記述式でも役立つから
2.【出題形式別】文章理解の攻略法
2-1.「内容・趣旨型」問題のポイント
2-2.「空欄補充型」問題のポイント
2-3.「文章整序型」問題のポイント
3.行政書士試験の文章理解で失敗しないためのポイント
3-1.分かった「つもり」になるのが危険
3-2.得点力を上げるには時間がかかる
3-3.試験本番の時間配分に注意する
4.まとめ
1.行政書士試験の文章理解は「満点」を目指そう
「文章理解」は、行政書士試験の「基礎知識」科目の1つです。「14問」出題される基礎知識のうち、「3問」が文章理解として出題されます。
得点目標は「3問中3問」、つまり満点を目指すべき科目だと考えておきましょう。どれだけ調子が悪くても、3問中2問は必ず正解することが必要です。
【文章理解で、満点を目指すべき理由】
・基礎知識の「足切り(基準点落ち)」を回避できるから・令和元年以降、問題が簡単になっているから
・多肢選択式・記述式でも役立つから
それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。
1-1.基礎知識の「足切り(基準点落ち)」を回避できるから
文章理解で満点を取れば、「基礎知識」科目の足切り(基準点落ち)を回避できる可能性が格段に高くなります。文章理解で3問正解できれば、残りの11問中、3問以上正解するだけで基準点に到達できるからです。
基礎知識の基準点をクリアするには、14問中6問の正解、つまり約43%の正答率が必要です。一方、文章理解で3問正解した場合、残りの科目では11問中3問、つまり約27%の正答率で合格点に到達します。基礎知識が5肢択一であることを踏まえれば、決して難しい数字ではないでしょう。
毎年、「基礎知識」の基準点に苦しめられている受験生は少なくありません。「法令科目は十分だったのに、基礎知識で5問しか正答できず不合格になってしまった」という声は、多くの受験生から聞こえてきます。
とはいえ、基礎知識の出題範囲は広く、効率的な対策が難しいのが現状です。例えば「政治・経済・社会」では、過去問で見たことのない問題が出題される年もあります。安定的に高得点を狙うためには、膨大な量の勉強が必要でしょう。
限られた時間の中で、ここに時間を割くことは、決して効率的とは言えません。しかし、文章理解だけは、他の科目と異なります。文章理解で出題される問題は、本質的には日本語の問題だからです。
足切り(基準点落ち)を確実に突破するためにも、文章理解では「満点」を狙って勉強していきましょう。
1-2.以前より簡単になっているから
近年、文章理解の問題は「簡単になった」と言われています。特に「令和元年」以降は、非常に解きやすい問題が出題の中心となっています。
受験生の正答率を見ても、正答率90%以上の問題が大半を占めており、難しいといわれる問題でも、正答率は70%を超えているからです。
他の科目と比べても、非常に満点を狙いやすい科目であることは間違いないでしょう。もちろん個人差はありますが、きちんと勉強すれば、満点を取ることは決して難しくありません。
1-3.多肢選択式・記述式でも役立つから
文章理解で養われた読解力は、法令科目でも大いに活用できます。特に、法令科目の多肢選択式や記述式に正答するためには、読解力が欠かせません。
多肢選択式では、「前後の文脈から空欄の内容を読み取る力」が、記述式では、「設問を正しく読み取り、問いに対して正しく答える力」が求められるからです。例えば、次のような記述式の設問に対して、どう回答するべきかを考えてみましょう
(設問)「Xは、Yに対して、どのような義務を負うか?」
実際に、伊藤塾の模試で上記のような問題を出題したところ、次のような回答が散見されました。
(回答)「Yは、Xに対して、〇〇請求ができる」
しかし、これでは、設問に対して正しく回答しているとは言えません。「どのような義務を負うか?」という問いに対する回答になっていないからです。
「義務」が問われている以上、あくまでも「〇〇義務を負う」という形式で回答するべきなのです。このようなミスが生じる原因は、まさに読解力不足に他なりません。知識だけではなく、正しい読解力を身につけることが、法令科目の得点力アップにつながるのです。文章理解の学習を通して、これらの読解力を磨くことが重要です。
2.【出題形式別】文章理解の攻略法
行政書士試験の文章理解は、主に「内容・趣旨型」問題、「空欄補充型」問題、「文章整序型」問題の3つの形式で出題されます。それぞれの特徴や攻略のポイントを解説していきます。
2-1.「内容・趣旨型」問題のポイント
「内容・趣旨型」問題は、本文の内容を読み取り、趣旨に合った選択肢を回答する問題です。この問題を解くには、本文をしっかりと読み込んで、あくまでも本文に書かれている内容を前提に回答していくことが必要です。
内容・趣旨型の問題で最も多い失敗は、受験生自身の先入観に捉われてしまうことです。「思い込み」や「常識」に問われると、思わぬ失敗をしてしまうので注意しましょう。一見間違っていなさそうな選択肢でも、本文に書かれていなければ正解にはなりません。また、細かい文末の表現にも注意するべきです。
例えば、「少ない」と「いない」では、内容が大きく変わってくるからです。細かな表現に気を配るだけで、正誤判断できる場合も珍しくありません。
2-2.「空欄補充型」問題のポイント
「空欄補充型」問題は、本文の空欄に入れるべき語句を選択する問題です。
法令等科目の「多肢選択式」とほぼ同じ形式で出題されるため、「空欄補充型」問題で身につけた力は、そのまま多肢選択式に活用できます。
空欄補充型のポイントは、空欄となっている箇所の前後に注目することです。空欄より前の文章との論理関係、空欄に続く文章とのつながりなど、前後と照らしあわせて矛盾しない語句を選びましょう。
前後の文章を読んでいく際は、特に「接続詞」を意識しましょう。
「なぜなら(理由)」「また(並列)」
「つまり(言い換え)」
「しかし(逆説)」 など
接続詞に注目して、論理がどのように展開されているのかを見落とさなければ、正答の選択肢にたどり着けるケースが多いです。
2-3.「文章整序型」問題のポイント
「文章整序型」問題は、与えられた文章を正しく並び替える問題です。この問題を解くには、とにかく、論理の流れを正確に読み取ることが求められます。
ポイントとなるのは、やはり「指示語」や「接続詞」です。特に、並べ替える文章の先頭に「指示語」や「接続詞」があると、大きな手がかりになります。指示語が何を指しているのか、接続詞は順接なのか逆説なのかといったポイントに着目すれば、文章の前後関係が見えてくるからです。
いくつかの選択肢の前後関係が分かれば、それを起点にして選択肢を切っていくことができます。全ての順番が分からなくても、正答にたどり着ける場合は珍しくありません。
3.行政書士試験の文章理解で失敗しないためのポイント
最後に、文章理解で注意するべきポイントを3つ紹介します。
・分かった「つもり」になるのが危険・得点力を上げるのには時間がかかる
・試験本番の時間配分で失敗しやすい
いずれも、文章理解で失敗しないために、大切なポイントばかりです。しっかりと意識して、文章理解の対策を行いましょう。
3-1.分かった「つもり」になるのが危険
文章理解で最も危険なことは、分かった「つもり」になってしまうことです。
何度もお伝えしているとおり、文章理解は、本質的には日本語の問題です。そのため、正確に理解できていなくても、選択した根拠が曖昧でも、正解にたどり着けてしまいます。
しかし、文章理解で確実に満点を取るためには「なんとなく」では不十分です。
・なぜ回答した選択肢を選んだのか・どこが誤っているのか
・なぜ間違いだと言い切れるのか
これらについて丁寧に検討し、1問1問としっかり向き合いましょう。問題数をこなすことも大切ですが、いたずらに量をこなせば良いわけではありません。
3-2.得点力を上げるには時間がかかる
文章理解は、得点力を上げるのに時間がかかる科目です。なぜなら、文章理解で問われている「読解力」は、一朝一夕では身につかないからです。
最初から一定の得点が期待できる反面、時間をかけても得点が伸び辛いことが、文章理解の大きな特徴と言えるでしょう。
解法のテクニックを身につけたり、語彙力をアップさせたりすることで、得点アップは期待できますが、それでも一定の時間はかかります。
文章理解で満点を目指すには、勉強のスタート段階から、地道に訓練していくことが大切です。1日1問でも構いません。毎日コツコツと継続していくことこそが、文章理解の得点をアップさせる秘訣です。
3-3.試験本番の時間配分に注意する
行政書士試験の当日、文章理解は、最後の3問として出題されます。そのため、当日の時間配分には十分しましょう。
時間配分に失敗すると、時間があまり残されていない状況で、文章理解に取り組むケースも十分に考えられます。焦ってしまえば、解けるはずの問題も解けなくなってしまうでしょう。時間不足により、文章理解で失点してしまうことは、絶対に避けなければなりません。
対策としては、試験開始直後、まずは問題冊子を一読して、全体に目を通してみることをオススメします。もちろん、この段階では、時間がかかりそうな問題は飛ばしても構いません。こうすることで、時間に余裕がある状態で、文章理解に取り掛かることができます。
・解ける問題に時間をかけて、確実に正答する・難しい問題には、必要以上に時間をかけない
・分からない問題、時間がかかりそうな問題は後回しにする
これを徹底できれば、試験当日も、あなたの実力を最大限に発揮できるはずです。
※次の記事もあわせて読まれています。
→ 行政書士試験合格に必要な勉強時間とは?目安や平均・最短合格のポイントについて解説
4.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉文章理解では「満点」を目指すことが必要
◉その理由は次の3つ
・令和元年以降、問題が簡単になっているから
・身につけた読解力が「多肢選択式・記述式」でも役立つから
◉出題形式別の攻略ポイントは次のとおり
→先入観にとらわれず、あくまでも「本文にある内容だけを前提に」解答する
(空欄補充型)
→接続詞に注目して、論理がどのように展開されているのかを注視する
(文章整序型)
→並べ替える文章の先頭にある「指示語」や「接続詞」に注目。判明したものから、選択肢を切っていく
◉文章理解で失敗しないためのポイントは3つ
・勉強のスタート段階から、地道に訓練を続けること
・試験本番の時間配分に気をつけること
行政書士試験の「文章理解」は、基礎知識で最も点数の取りやすい科目です。
文章理解で満点を取ることができれば、基礎知識で足切り(基準点落ち)になる可能性は格段に低くなるでしょう。そして配点の高い「民法」や「行政法」でしっかりと点数を稼げれば、危なげなく、行政書士試験に合格できるはずです。
行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

















