行政書士試験の憲法・基礎法学を攻略!捨てても良いのか?についても詳細解説
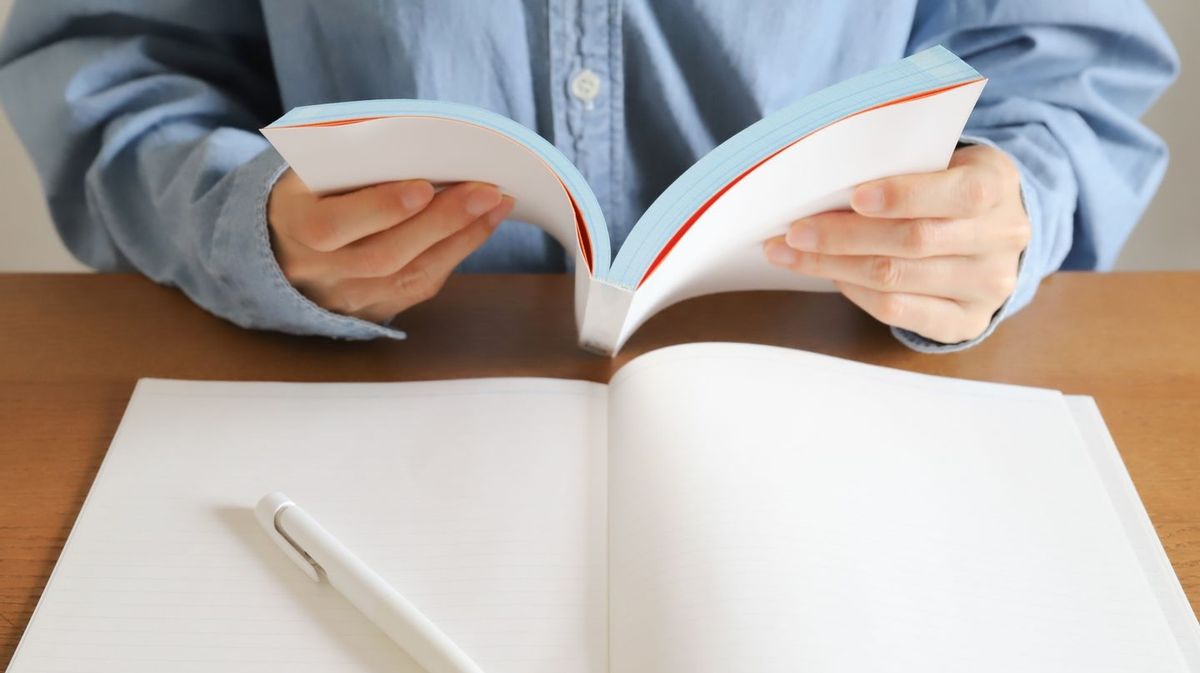
「行政書士試験の憲法が苦手」
「基礎法学の勉強法が分からない」
「余裕が無ければ、捨てても良い?」
こんな疑問をお持ちの受験生も多いかもしれません。
行政書士試験の「憲法」「基礎法学」は、いずれも対策が難しく、多くの受験生を悩ませている科目です。「民法」や「行政法」ほど時間を割くことはNGですが、全く勉強しないことも得策とは言えません。
「憲法」や「基礎法学」をいかに効率的に攻略できるかが、行政書士試験の合格に大きな影響を与えます。そこで、本記事では次の点を取り上げました。
・憲法の対策ポイント・「人権・統治」それぞれの効果的な勉強法
・基礎法学の対策ポイント
行政書士試験を目指している方は、是非ご一読ください。
※行政書士試験の科目ごとの勉強法については、以下の記事で詳しく解説しています。
民法→【行政書士の受験生必見】民法の勉強法を各分野・出題形式に分けて解説
行政法→ 行政書士試験合格の鍵!行政法の効率的な勉強法を徹底解説
会社法・商法→ 商法・会社法は捨てないで!行政書士試験で差がつく効率的な学習法
文章理解→ 行政書士試験の文章理解で失敗しないポイントは?出題形式別の攻略法
【目次】
1.行政書士試験の「憲法」とは?
1-1.憲法の目標点数は?
2.憲法の対策のポイント
2-1.過去問を攻略する
2-2.判例・条文のインプットに力を入れる
2-3.満点を狙わない
3.【分野別】憲法の勉強法
3-1.「人権」の勉強法
3-2.「統治」の勉強法
4.行政書士試験の「基礎法学」とは?
5.「基礎法学」の対策のポイント
5-1.「基礎法学」を捨てるのはあり?
6.【Q&A】行政書士試験のよくある質問
6-1.Q.「憲法」は何点を目標にすればよいですか?
6-2.Q.「憲法」の条文は暗記した方が良いですか?
6-3.Q.「基礎法学」は何点を目標にすればよいですか?
6-4.Q.「基礎法学」は過去問だけすればよいですか?
7.まとめ
1.行政書士試験の「憲法」とは?
憲法とは、国民の権利や自由を守るために定められた国の最高法規です。国民の権利を学ぶ「人権」と、国を統治する仕組みである「統治」の2つの分野に分けられます。
行政書士試験の憲法は、法令等科目の中でも特にとっつきやすい科目です。一方で、出題数は民法や行政法と比べると少なく、択一式で5問、多肢選択式で1問程度しか出題されません。
【憲法の配点】
| 問題数 | 配点 | |
| 択一式 | 5問 | 20点 |
| 多肢選択式 | 1問 | 8点 |
したがって、憲法の学習では「効率良く勉強すること」が何よりも大切です。じっくり時間をかけるのではなく、ポイントを絞った学習を心がけましょう。
重要なポイントに絞って効率よく勉強し、配点の大きい「民法・行政法」などに時間を割くことが、合格への最短ルートです。
1-1.憲法の目標点数は?
憲法の目標点数は、「5問中2問〜3問」程度の正解を目指すのが良いでしょう。ただし、この目標点数は、憲法の学習に充てられる時間によっても異なります。本当に時間が無いケースでは、憲法の得点力が低くても、民法や行政法の学習に時間を充てたほうが良い場合もあるでしょう。
とはいえ、憲法は配点自体は低いものの、行政法の理解に役立つ場面も多いです。そのため、よっぽど時間がないケースを除けば、一定の対策は行っておくべきです。
2.憲法の対策のポイント
憲法の対策で、大切なポイントは次の3つです。
・過去問を攻略する・インプットにも力を入れる
・満点を狙わない
それぞれ詳しく説明します。
2-1.過去問を攻略する
民法や行政法と同様に、憲法の対策でも、まずは過去問を攻略することが重要です。過去問に取り組むことで、次のようなポイントが理解できるからです。
・本試験では、どのような形式で出題されているのか・学習した内容の何が問われているのか
・どこを押さえておけば正答できたのか 等
ただし、過去問に取り組む回数は、民法・行政法などと比べると少なくても問題ありません。なぜなら、憲法は問題数が少なく、過去問では出題されたことの無い知識が出題されるケースも多いからです。
多くても3周程度取り組めば十分でしょう。ある程度過去問の傾向をつかんだら、後述する判例・条文のインプットに力を入れましょう。
2-2.判例・条文のインプットに力を入れる
憲法の出題では、大きく「判例」と「条文」の2つの知識が問われます。特に「判例」の知識を問う問題では、問題演習ではなく、インプットで固めたほうが対応しやすいケースが多いです。
なぜなら、本試験では、過去問と同じ判例が出題されたとしても、同じ知識で正答できるとは限らないからです。具体的には、次のようなケースが挙げられます。
・同じ判例でも、過去問とは異なる箇所が穴埋め式で出題される・過去問では結論だけ問われていたのに、本試験では「違憲審査基準」が問われている
・論点は同じでも、過去問では問われたことのない判例が出題される
過去問を繰り返し行っているだけでは、上記のような出題に対応できません。
本試験での対応力を上げるためには、過去問で出題されていない知識についても、しっかりとインプットしておきましょう。
2-3.満点を狙わない
満点を狙わないことも大切なポイントの一つです。前述のとおり、憲法の配点は決して高くは無いからです。さらに、近年の行政書士試験では、憲法は難化傾向にあります。
例えば、受験生の大半が正答できないような難しい問題や、現場で考えさせるタイプの問題が出題されるケースも珍しくありません。
そのため、長時間勉強したからといって、必ずしも満点が取れるとは限りません。確実に満点を狙おうとすると、膨大な勉強が必要となります。必要以上に時間をかけるのではなく、最小限の労力で対策し、浮いた時間は「民法・行政法」に充てるのが効果的です。
3.【分野別】憲法の勉強法
憲法の試験範囲は大きく「人権」と「統治」の2つに分かれます。
それぞれの分野に分けて、効果的な勉強法を解説します。
3-1.「人権」の勉強法
人権分野では、判例の知識が出題の中心となります。したがって、とにかく重要な判例を押さえていくことが大切です。
・過去問で出題されている判例
・違憲判決となった判例
・判例変更となった判例
など、出題されやすい判例を中心に学習していきましょう。判例を勉強する際のコツは、ただ漫然と読むのではなく、次のようなポイントを意識することです。
・誰と誰の、どの人権が衝突しているのか・問題の所在はどこにあるのか
・そもそも保障されている人権なのか
・制約の根拠は何なのか
・裁判所は、どういった要素を考慮しているのか
・どの違憲審査基準が使われたのか など
事案と結論だけ押さえるのではなく、背後にある判例の考え方を理解しましょう。考え方さえ理解できれば、未知の問題にも対応できるようになります。
過去問で出題されたことのない判例や、その場で考えさせるような問題が出題されても、正答を導けるようになるでしょう。
3-2.「統治」の勉強法
「統治」では、主に「国会・内閣・裁判所」の仕組みを学んでいきます。
統治分野の特徴は、人権と比べて「条文」の知識を問う問題が多く出題されることです。したがって、条文知識をしっかりと理解することが大切です。
条文の趣旨はもちろん、細かな知識についても押さえておく必要があるでしょう。「統治」のコツは、単に条文を暗記するのではなく、制度を設計する人の視点にたって考えることです。「どういった仕組みにすれば、制度がうまく回るのか」という視点を持って条文を読むと、全体像が頭に残りやすくなります。
例えば、「衆議院の優越」では「議決しない場合の日数」や「議決しない場合の効果」等が変えられて出題されます。
| (参議院が) 議決しない 場合の日数 | (参議院が) 議決しない 場合の効果 | |
| 内閣総理大臣 の指名 | 10日 | 衆議院の議決 を国会の議決 とする |
| 予算の議決 | 30日 | |
| 条約の承認 | 30日 | |
| 法律案の議決 | 60日 | 衆議院の 3分の2以上 で再議決 |
このうち「10日」「30日」「60日」といった数字を単に覚えようとすると、なかなか頭に残りません。せっかく覚えたつもりだったのに、本試験で思い出せなくなったというのも、よく聞く話です。
一方、制度設計者の視点に立って、「どれだけ急ぐ必要があるのか」という点を考慮すると、一気に頭に入りやすくなります。
「なぜ内閣総理大臣の指名だけ10日で短い?」→最も急ぐから(総理大臣が決まらないと、国政が停まってしまうから)
「なぜ、予算は30日?」
→総理大臣の指名ほどでは無いが、かなり急ぐから(予算が決まらないと、国の運営ができないから)
「なぜ条約も30日?」
→予算と同じくらい急ぐから(早く決めないと、相手の国に迷惑がかかるから)
「なぜ法律案の再議決は60日?」
→他の案件ほど急ぐ必要はないから(むしろ法改正では、慎重な議論が必要だから)
こういった視点で条文を見ていくと、単なる暗記ではなく、制度の理解にもつながります。
憲法の「統治」とは、要するに国をうまく運営するためのシステムに他なりません。暗記するべき点もゼロではありませんが、やみくもに条文を暗記する必要はないのです。
なぜそのような仕組みになっているのか、理由を考えて、理解を重視した勉強を行いましょう。記憶に残りやすくなることはもちろん、深い理解につながり、初見の問題でも正答率が格段に高くなります。
4.行政書士試験の「基礎法学」とは?
行政書士試験の「基礎法学」は、法学全般の基礎知識が問われる科目です。
試験範囲が広く、学習に膨大な時間がかかる一方で、問題は2問しか出題されません。そのため、行政書士試験の中でもトップクラスに学習効率が悪い科目です。
ただし、全く太刀打ちできないほど難易度が高いわけではなく、例年、2問中1問は正答率50%を超えています。そのため、完全に捨ててしまうことは得策ではありません。できれば、2問中1問は正解したいところです。難しい問題はスルーする、簡単な問題だけ確実に正答するといった心構えで取り組みましょう。
5.「基礎法学」の対策のポイント
前述のとおり、「基礎法学」は非常に対策が難しい科目です。
毎年2問しか出題されていないため、過去問も蓄積されていません。一方で、試験範囲は膨大で、試験当日に出題される問題の大半は、初見の問題です。したがって過去問演習だけで十分とは言えません。憲法以上に、ポイントを絞った効率的なインプットが必要となるでしょう。
とはいえ、全範囲を勉強するのも非常にタイムパフォーマンスが悪い方法です。受験指導校の講座や、過去問・模試などを活用し、出題が予想される分野に絞って学習すると良いでしょう。
なお、年によっては、超難問・奇問と呼ばれるような正答率の低い問題が出題されるケースもあります。ただし、その場合は誰も解けないので、気にせずスルーして構いません。正解できないことよりも、難問・奇問といった類の問題に時間をかけてしまい、全体の時間配分に失敗することに注意するべきです。
また、基礎法学は、行政書士試験の本番で1問目と2問目に出題されます。つまり、当日緊張している中で、最初に目にすることになるのです。ここで時間をかけてしまったり、いきなり難問を目にして調子を乱されると、試験全体の出来に影響してしまいます。
場合によっては、試験当日、1・2問目(基礎法学)は後回しにして、3問目から解き始めると決めておくことも選択肢の一つです。
5-1.「基礎法学」を捨てるのはあり?
「基礎法学」を捨てて合格する人は珍しくありません。特に、短期間での合格を目指していたり、働きながらで時間が取れない場合は、全く手を付けないのも一つの手段です。
ただし、確実に合格したいなら、やはり一定の対策はしておくことが望ましいです。配点が低いとはいえ、2問(8点分)は出題されるからです。
1問しか正答できなかったとしても、多くの受験生が苦手とする「基礎法学」で4点加算されるのは、非常に大きいです。
ただし、何度も繰り返しますが、深追いは厳禁です。他の科目が追いついていないのであれば、配点の高い科目から優先的に進めましょう。
6.【Q&A】行政書士試験のよくある質問
6-1.「憲法」は何点を目標にすればよいですか?
「5問中2問〜3問」程度の正解を目標にすると良いでしょう。
6-2.「憲法」の条文は暗記した方が良いですか?
全ての条文を暗記する必要はありませんが、基本的な内容は押さえておくことが必要です。特に「統治」では、細かな数字なども出題されるため、正確に記憶しておきましょう。
6-3.「基礎法学」は何点を目標にすればよいですか?
「2問中1問」は正答できるように勉強を進めていきましょう。
6-4.「基礎法学」は過去問だけすればよいですか?
基礎法学では、過去問で目にしたことの無い初見の問題も出題されます。過去問演習も必要ですが、過去問だけで十分とは言えません。受験指導校の模試や予想問題なども活用するとよいでしょう。
7.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉「憲法」のポイントは次のとおりです。
・まずは過去問を攻略して、傾向を押さえる・次に「判例」や「条文」のインプットに力を入れる
・満点ではなく「5問中2〜3問」程度の正答を目標にする
・「人権」では、とにかく重要な判例をおさえていく
・事案と結論だけではなく、背後にある考え方を理解する
・「統治」では、条文のインプットに力を入れる
・ただし、単に条文を暗記すると記憶に残りにくい
・「どういった仕組みにすれば、制度がうまく回るのか」という視点を持つ
◉「基礎法学」のポイントは次のとおりです。
・試験範囲が広い一方で、配点は少なく、例年2問しか出題されない
・行政書士試験でも、トップクラスに対策がしづらい
・ただし、2問中1問は正答率50%を超えるケースもある
・完全に捨てるのは得策ではない
・2問中1問は正解できることが望ましい
行政書士試験の「憲法・基礎法学」はいずれも効率的な対策が必要な科目です。
これらの科目を最小限の時間で攻略し、配点の高い「民法」や「行政法」に十分な時間を取ることができれば、限られた時間でも合格に大きく近づけるでしょう。
行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

















