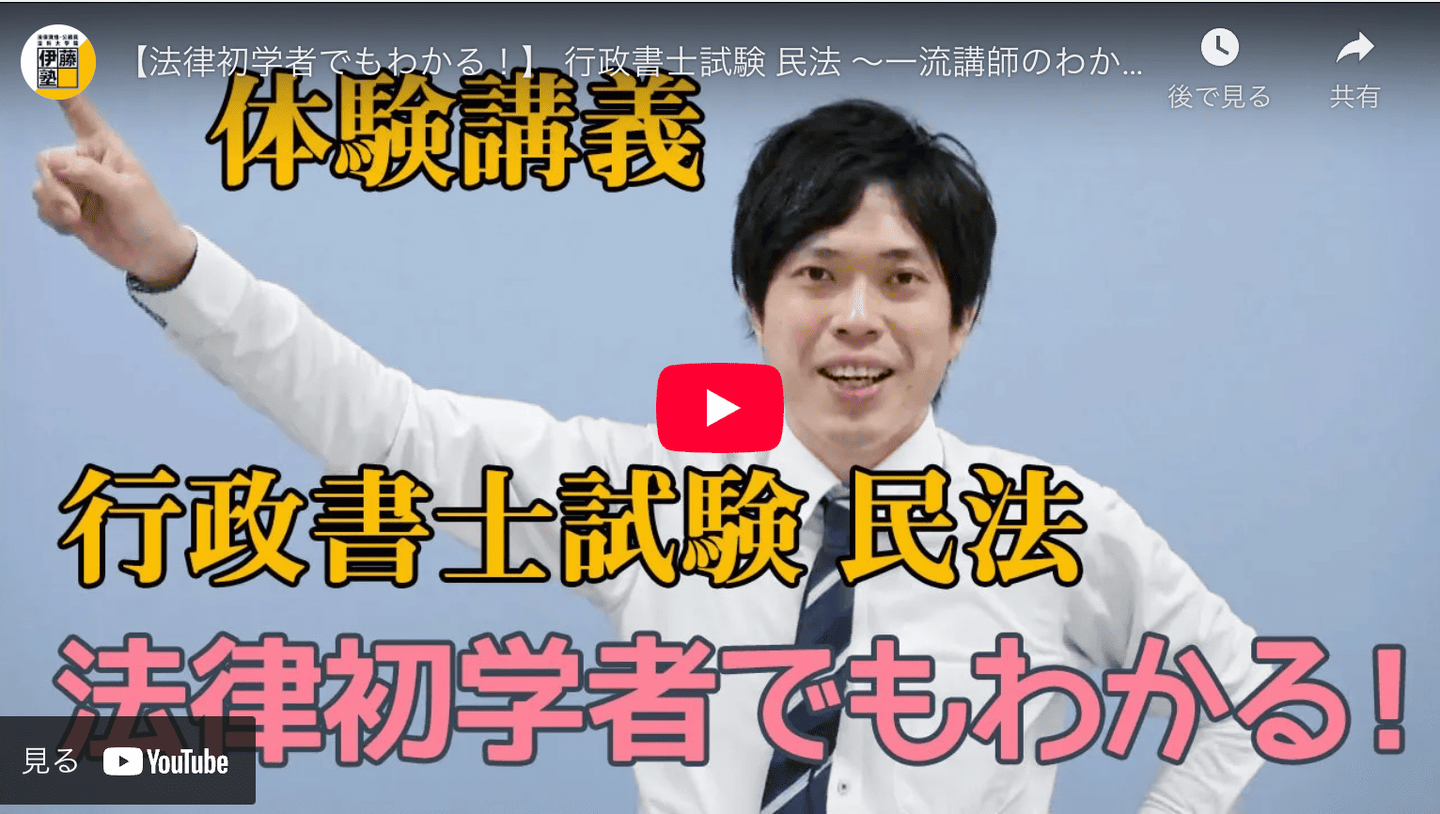【行政書士の受験生必見】民法の勉強法を各分野・出題形式に分けて解説
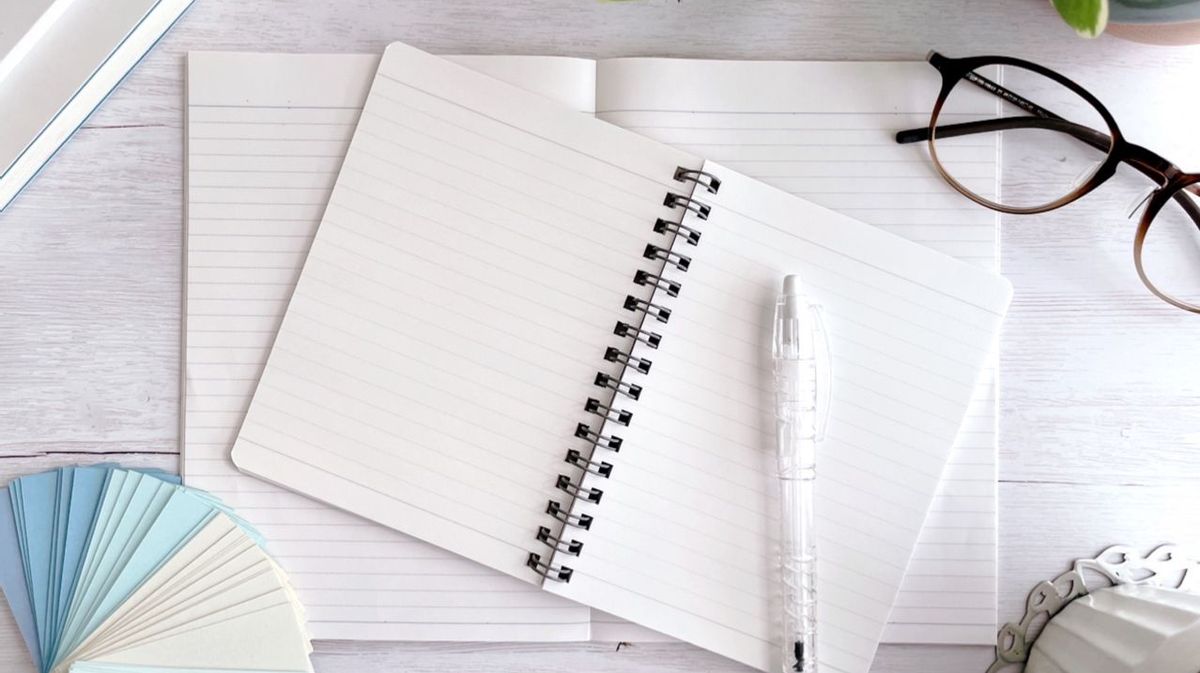
「民法の勉強法が分からない」
「行政書士試験の民法が苦手」
「どれだけ勉強しても得点が伸びない」
こんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
行政書士試験の民法は、試験の配点の25%を占める重要科目です。しかし、法律初学者にとって、とっつきにくいと感じる要素が多く、多くの受験生を苦しめています。
そこで、この記事では民法の勉強法について、合格に必要なポイントを徹底解説しました。
【この記事を読んで分かること】・民法の分野別の勉強法
(総則・物権・債権総論・債権各論・家族法)
・出題形式別の勉強法(択一式・記述式)
・民法で意識するべき3つのポイント
行政書士試験の民法でお悩みの方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士試験の民法とは?
2.【分野別】行政書士試験の民法の勉強法
2-1.総則の勉強法
2-2.物権の勉強法
2-3.債権法(総論)の勉強法
2-4.債権法(各論)の勉強法
2-5.家族法の勉強法
3.【出題形式別】行政書士試験の民法の勉強法
3-1.択一式の勉強法
3-2.記述式の勉強法
①書く訓練をすること
②部分点を狙うこと
4.行政書士試験の民法で意識するべき3つのポイント
4-1.まずは1周して全体像を掴む
4-2.過去問のストックが不足している
4-3.前年の出題テーマは出題されにくい
5.【法律初学者でもわかる!民法】一流講師のわかりやすい講義を体験してみよう
6.まとめ
1.行政書士試験の民法とは?
行政書士試験の民法は、試験の中核となる重要科目です。試験の配点の25%を占めており、択一式で9問、記述式で2問が出題されます。
民法とは、個人の財産、契約、身分関係などについて定めた法律で、大きく「財産法」と「家族法」に分けられます。「財産法」は取引社会の基本ルールを規定する法律で、次の4つの分野に分けられます。
・総則・物権法
・債権法(総論)
・債権法(各論)
行政書士試験の民法の9割は「財産法」からの出題です。
一方、「家族法」は、夫婦・親子などの家族関係を規定する法律です。行政書士試験でも1問は家族法から出題されます。次章では、それぞれの分野の特徴や勉強法を解説します。
2.【分野別】行政書士試験の民法の勉強法
民法を効率的に学習するには、分野ごとの特徴や勉強法を理解することが必要です。
ここでは、次の5つの分野に分けて、特徴や勉強法を詳しく解説します。
・物権
・債権法(総論)
・債権法(各論)
・家族法
それぞれの分野の特徴を掴み、効果的な学習方法を実践することで、民法の得点力を高めることができるでしょう。
2-1.総則の勉強法
民法の総則は、民法全体の共通ルールを定めた分野です。「権利の主体・客体」「法律行為」など、民法を理解するために必要な前提知識がたくさん含まれています。さらに「制限行為能力者」「意思表示」「時効」「代理」などは頻出論点の1つでもあります。
概念的な内容が多く、とっつきにくいと感じる人も多いですが、総則の理解度によって、民法全体を理解するスピードが変わってきます。
勉強のポイントは、多少分からなくても、立ち止まらずに一周してみることです。初めて総則を学ぶときは、知らない単語がたくさん出てくるため、細部までくっきりと理解することは難しいです。
しかし、民法全体を学んだ後で総則に戻ってくると、点と点が一気につながってくるような感覚が味わえるでしょう。民法全体が分かったあとで総則を復習すると、一気に理解度が深まります。
2-2.物権の勉強法
物権は、「物(財産)」についての権利を定めた分野です。中でも不動産物権変動(177条関係)や、動産物権変動(即時取得)などは、必ずといって良いほど出題される頻出論点です。繰り返し学習して、得点力を身につけましょう。
物権の勉強のコツは、「暗記」ではなく「理解」することです。過去問を通じて「何が問われているのか」を確認し、背後にある考え方を理解しましょう。例えば、「不動産物権変動(177条関係)」であれば、覚えるべきなのは「177条の第3者」の定義だけです。事例ごとの結論を暗記する必要はありません。
定義をおさえて、考え方さえ理解できれば、事例が違っても正解にたどり着くことができます。逆に、事例と結論を覚えているだけだと、過去問を少しアレンジされただけでも対応できないでしょう。「理解」を軽視して、事例と結論を覚えるだけの勉強法を続けてしまうと、いつまで経っても得点力は身につきません。
2-3.債権法(総論)の勉強法
債権法は、「人と人との権利関係」を定めたルールです。中でも「債権法(総論)」は、債権全体の共通ルールを規律している分野です。例えば、次のような分野は、行政書士試験でも頻出の論点です。
・債務不履行・債権譲渡
・相殺
・債権者代位権、詐害行為取消権
・多数当事者の債権・債務関係(連帯債務、連帯債権、保証債務など)
債権法の学習のポイントは、「物権」との違いを意識することです。
誰に対しても主張できる「物権」と違い、「債権」は当事者同士でしか主張できない権利です。だからこそ、いつも同じ結論となるわけではなく、それぞれの利益状況を分析して、妥当な結論を導くことが求められます。
正解にたどり着くには、民法の考え方を理解し、思考のプロセスを身につけることが不可欠です。「暗記」に頼っている人にとっては、「物権」よりも苦手意識を感じやすい分野かもしれません。
2-4.債権法(各論)の勉強法
債権法(各論)は、契約、事務管理、不当利得、不法行為の4つに分けられます。
中でも、特に大切なのは「契約」と「不法行為」です。
「契約」では、各契約の個別的なルールが決められています。売買や賃貸借など、多くの人にとって馴染みのある契約がメインとなるため、身近な事例に置きえると勉強しやすいでしょう。
また、債権各論の内容は、あくまで個別ルールであることも意識しておきましょう。例えば「契約不適合責任」であれば、次のようなイメージを持つと、理解が進みやすいです。
・まず、債権法(総論)の一般ルールとして「債務不履行、解除」などが決められている・その上で、売買契約の特徴にあわせた特別ルールとして、「契約不適合責任」が設けられている
一見複雑に見える債権法ですが、こういったイメージを持って勉強すれば、記憶に定着しやすいです。同じ条文が準用されているケースも多いため、横のつながりを意識すると、覚えるべきことも最小限に減らせます。
逆に、ここが抜けると体系が分からなくなり、迷子になってしまうので注意しましょう。
また、債権各論では「不法行為」も頻出のポイントです。
不法行為を勉強するときは、債務不履行との違いを意識すると良いでしょう。「債務不履行と不法行為では何が違うのか」「なぜ違うルールになっているのか」などを比較していくと、理解度が深まります。
2-5.家族法の勉強法
家族法は、親族・相続などの家族関係を定めた分野です。
夫婦関係、親子関係、相続や遺言などが中心で、出題数は1問であるケースが通常です。
重要度は低めですが、簡単な問題が出題される年もあります。そのため、あまり時間をかけすぎずに、基本的な事項を学習しておくと良いでしょう。暗記要素が強いため、予想論点や頻出論点に絞って学習することも効果的な方法です。
「財産法」と「家族法」同じ民法ではあるものの、考え方が全く異なります。基本的なルールや考え方をしっかりと理解し、解きやすい問題を確実に正答できるよう勉強していきましょう。
3.【出題形式別】行政書士試験の民法の勉強法
行政書士試験の民法では、択一式で9問、記述式で2問が出題されます。
特に記述式は、苦手意識を持っている人も多いでしょう。ここでは、択一式、記述式それぞれの効果的な勉強法を解説します。
3-1.択一式の勉強法
択一式の勉強では、問題集とテキストを何度も往復し、反復することが大切です。
基本的な内容を理解したら、まずは過去問に取り組んでみましょう。
このとき注意したいのは、答えの暗記にならないことです。過去問を解く目的は、知識を定着させて理解を深めていくことだからです。正答することが目的になってしまうと意味がありません。
・答えを暗記して解けたつもりになる・正答の選択肢が分かったら、どこが誤りなのかを考えずに次の問題に進む
・本番と同じように、消去法で答えを出す
こういった勉強法はできる限り避けるべきです。
大切なのは、正答を出すまでの思考過程です。
・なぜ誤りなのか
・どういった思考で正解の選択肢にたどりつけるのか
基本的な考え方の理解度が深まれば、未知の問題へも対応できるようになります。
「民法はどのように考えることが多いのか」。
このイメージが深まれば、知らない知識を聞かれても、推測できるようになるからです。
「知らなかったから仕方がない」
「覚えていなかったら仕方がない」
このように考え、あきらめていた問題への正答率も高くなるでしょう。あくまでも「理解」することを大切にして、反復・継続していけば、択一の得点力は目に見えて上がっていきます。
3-2.記述式の勉強法
記述式の勉強については、おもに以下の2点に留意しながら学習を進めていくことが重要です。
①書く訓練をすること②部分点を狙うこと
それぞれ解説します。
①書く訓練をすること
現代人は「書く」機会が減少しているため、「読むことはできるが、いざとなると書けない」という人が増えてきています。記述式でも同じようなことが起こりがちなため、実際に「書く」訓練をすることが重要です。
行政書士試験の記述式では、設問に対する解答を40字程度で端的に説明することが求められます。そのため、日頃から出題されそうな条文やキーワードを実際に「書く」訓練をしておくことが必要です。例えば、過去問などを活用して、繰り返し演習することが効果的でしょう。
②部分点を狙うこと
行政書士試験の記述式では、必要なキーワードが書かれていれば部分点がもらえます。つまり、完璧な解答が書けなくても、部分点を積み上げることで合格点に到達できるのです。
では、どうすれば部分点を取ることができるのでしょうか。
そのためには、やはり択一式の得点力を高めることが効果的です。択一式の勉強を通じて、民法の基本的な考え方を身につけられるからです。
民法の基本的な考え方を理解することは、記述式の問題でも重要なポイントとなります。
繰り返しお伝えしますが、民法は暗記科目ではありません。ただし、覚えなければいけないポイントもあります。例えば、物権で言及した「177条の第三者」の定義は、確実に覚える必要があります。そして、この覚えるべきポイントは、択一式でも記述式でも大きく変わりません。
① 覚えるべきポイントだけを確実に覚える② 基本的な考え方を理解する
③ 与えられた事例を当てはめて正解を導く
これらができれば、択一式でも記述式でも得点力は上がっていくでしょう。
択一式と記述式で勉強方法が大幅に変わるわけではありません。どちらも「理解」することを大切にして、反復・継続することが重要なのです。民法では、この点を強く意識しながら勉強を進めていきましょう。
※記述式の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→「記述対策」を制するものは行政書士試験を制する?得点アップの秘訣を解説
4.行政書士試験の民法で意識するべき3つのポイント
民法は行政書士試験の中でも特に重要な科目です。しかし、初学者にとってはとっつきにくく、勉強方法に悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこでこの章では、民法の勉強で意識するべき3つのポイントを解説します。
・まずは1週して全体像を掴む・過去問のストックが不足している
・前年の出題テーマは出題されにくい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
4-1.まずは1周して全体像を掴む
意識するべきポイントの1つ目は、まずは1周して全体像を掴むことです。民法の範囲は膨大で、各分野が深く関連しています。そのため、初学者が1度の学習で全体像を掴むのは難しいでしょう。
例えば、「総則」を勉強していても、物権や債権の知識がないと理解が難しいケースがあります。突然分からない単語が出てきて、戸惑うことも多いはずです。
民法の全体像を掴むためには、まずは一周してみましょう。因みに、民法で挫折する人の多くは、学習の前半で諦めています。
諦めず後半まで進んでいくうちに、前半で分からなかった内容が、突然理解できるケースも多いです。最初から全てを理解しようとするのではなく、ある程度割り切って、次の内容に進んでいきましょう。
「総則→物権→債権法」と粘り強く進めていくうちに、民法全体の構造が見えてくるはずです。
4-2.過去問のストックが不足している
意識するべきポイントの2つ目は、過去問のストックが不足していることです。前述のとおり、民法の出題範囲は膨大です。条文の数だけでも1000を超えており、判例も無数に蓄積されています。
一方で、行政書士試験で出題される民法の問題は、毎年11問しかありません。つまり、10年遡っても、過去問の数は110問しかないのです。さらに、2020年には120年振りの大幅な改正が行われました。改正民法に対応した問題となれば、過去問の数はさらに少なくなるでしょう。
このような状況では、過去問だけでは十分な演習を行うことはできません。
もちろん過去問は繰り返し行う必要がありますが、それ以外にも十分な演習が必要です。
過去問で出題されていないジャンルについても、受験指導校の問題集や参考書などを活用して、繰り返し演習しましょう。
※過去問の活用法は、次の記事で詳しく解説しています。
→行政書士は過去問だけで合格できる?合格者が語る!正しい活用法
4-3.前年の出題テーマは出題されにくい
意識するべきポイントの3つ目は、前年の出題テーマが出題されにくいことです。前述のとおり、民法は、出題範囲と問題数のバランスが悪い科目です。膨大な範囲がある一方で、出題される問題数は11題しかありません。そのため、直近で出題されたテーマが連続で出題される可能性は低くなります。
問題作成者の視点に立つと、11問の中で、なるべく多くの分野から出題しようと考えるからです。限られた時間で行政書士試験の民法を攻略するには、この発想が非常に大切です。
「勉強する範囲を厳選し、その内容を徹底的に反復・継続していく」これこそが、民法の勉強で大切なポイントだと言えるでしょう。
5.【法律初学者でもわかる!民法】一流講師のわかりやすい講義を体験してみよう
ここまで、民法の具体的な勉強法をお伝えしてきました。
「勉強法は分かったけど、そもそも難しくて勉強する気にならない」
「理屈っぽくて、とっつきにくい」
このように感じている方もいるかもれません。
民法に苦手意識を感じている方は、ぜひ次の動画もご覧ください。
行政書士試験業界で人気&実力ともTOPクラスの「伊藤塾 平林勉講師」が、法律初学者のあなたにもわかりやすいように民法を解説しています。きっと「あっ、法律って、こんなにわかりやすいんだ!」と実感していただけるはずです。
【法律初学者でもわかる!】 行政書士試験 民法 「一流講師のわかりやすい講義を体験してみよう!」
6.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉ 民法は、行政書士試験の中核となる重要科目
◉ 意識するべきポイントは次の3つ
・過去問のストックが不足している
・前年の出題テーマは出題されにくい
◉ 大切なのは、「理解」に重点を置いた勉強法
◉ 事例と結論を暗記してしまうと、得点力は伸びない
◉ 次の勉強法が実践できれば、高得点を期待できる
② 基本的な考え方を理解する
③ 与えられた事例を当てはめて正解を導く
行政書士試験の民法は、簡単ではありません。しかし、基本的な考え方さえ身につけば、心強い得点源にもなる科目です。
「勉強する範囲を厳選し、その内容を徹底的に反復・継続していく」
これができれば、限られた時間でも合格に大きく近づくことができるでしょう。
行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。