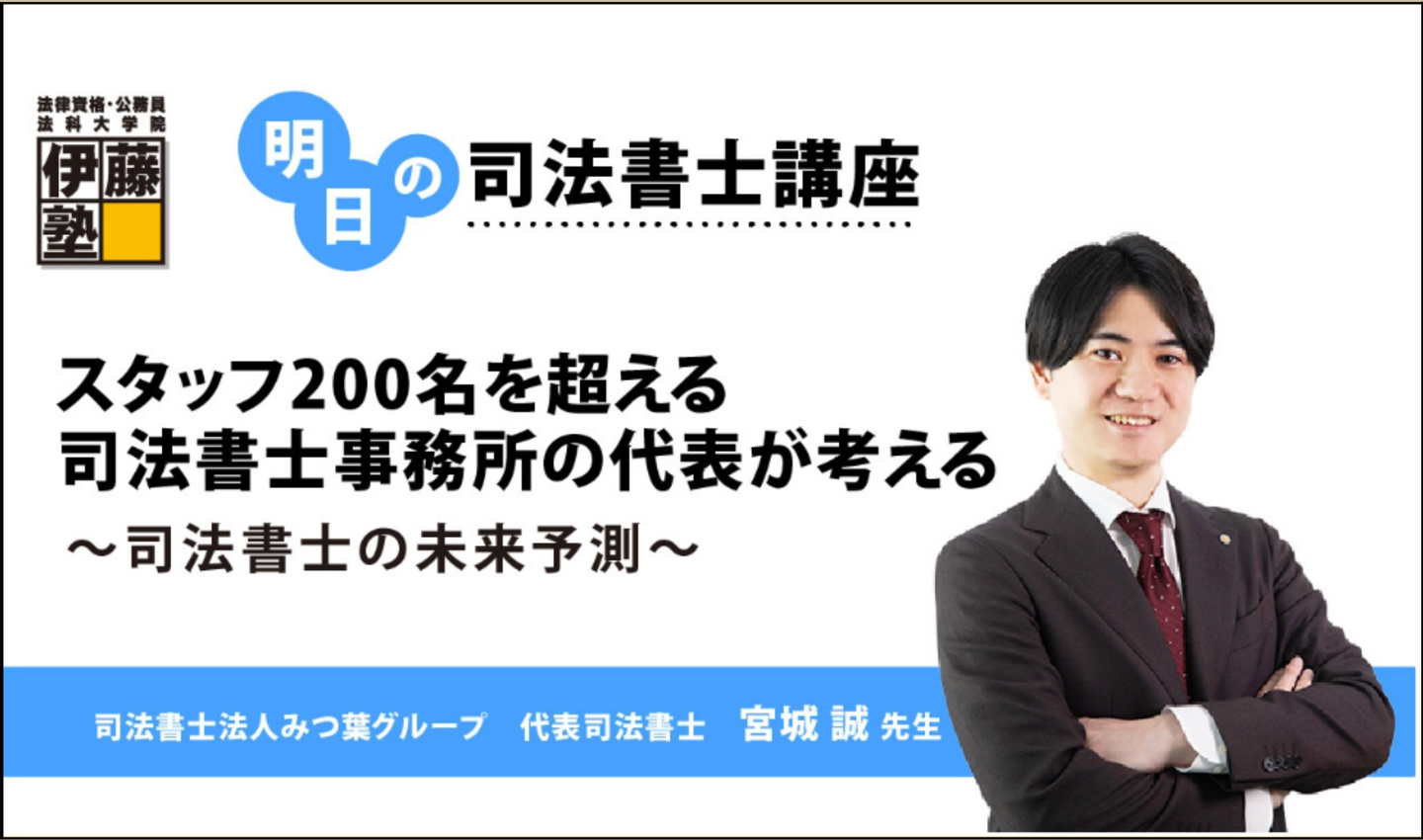AI時代の司法書士の将来性と活躍の秘訣について解説

近年、急速に進むAI化に伴い、様々な業界で仕事が自動化されるようになってきました。
そんな中、法律家である司法書士の仕事も、将来的にAIに奪われるのではないかとの声も多く聞かれます。
司法書士を目指す人にとって、司法書士の仕事に将来性があるかどうかは、気になるところではないでしょうか。
この記事では、様々な観点から司法書士の将来性について解説していきます。
司法書士として20年後、30年後も活躍するためのポイントも解説していきますので、司法書士の将来性に不安を抱いている方は、ぜひ最後までご覧下さい。
【目次】
1.司法書士には十分将来性がある
2.司法書士に将来性がある理由
2-1.司法書士の業務の多様化
2-2.高齢化社会に伴う業務の拡大
2-3.AIでは代替できない業務が多い
2-4.相続登記の義務化による需要の増加
3.司法書士に将来性がないと言われる理由
3-1.登記件数が減少傾向にある
3-2.AIの台頭によって仕事が奪われる
3-3.ブロックチェーン技術を活用した新しい登記システムの構築
4.司法書士として30年後も活躍するための秘訣は?
4-1.時代の変化に柔軟に対応する
4-2.コミュニケーションスキルを磨く
4-3.認定司法書士やダブルライセンスで対応できる業務範囲を増やす
4-4.コンサルティング業務など新しい分野の仕事にチャレンジする
5.まとめ
1.司法書士には十分将来性がある
インターネットや雑誌などで、司法書士の将来性に否定的な情報を目にする事があるかもしれません。
しかし、様々な観点から具体的に考察してくと、司法書士は十分将来性のある仕事だということが見えてきます。
司法書士の主な仕事は、不動産・法人に関する登記業務や裁判所・法務局等に提出する公的な書類の作成業務です。
基本的には書類作成の業務が多く、どうしてもAI化の波に呑まれてしまうイメージが強いかもしれませんが、司法書士の仕事はAIでは代替できないものも多く、全ての仕事をAIに任せる事は出来ません。
また、時代の流れや人口の減少に伴い、そもそも不動産を購入する母数も減っている事から、将来的に登記業務自体がなくなるのではないかと言われたりもします。
しかし、司法書士の仕事は多様化しており、メインとなる登記業務以外にも、専門知識を活かして様々なフィールドで活躍しています。
顧客と細やかなコミュニケーションをとり、それぞれの希望に応じてオーダーメイドのように業務を行なうことは、司法書士とクライアントの信頼関係を築く上で非常に重要です。
こうした観点から、司法書士は将来性のある仕事であり、資格取得のために時間を費やす意義は大いにあると言えるでしょう。
2.司法書士に将来性がある理由
司法書士に将来性がある理由としては、主に次の4つが挙げられます。
| 司法書士に将来性がある理由 |
| ◉司法書士の業務の多様化 ◉高齢化社会に伴う業務の拡大 ◉AIでは代替できない業務が多い ◉相続登記の義務化による需要の増加 |
司法書士を目指す不安を失くすためにも、ここでは様々な観点から司法書士の将来性について解説していきます。
2-1.司法書士の業務の多様化
司法書士に将来性がある理由として、まずは司法書士の業務が多様化している事が挙げられます。
司法書士の主な業務は、登記業務や公的機関への書類作成などですが、近年司法書士の業務内容は広がりを見せており、職業の枠を超えて様々なフィールドで活躍しています。
【司法書士の様々な業務】
| ・不動産(土地、建物)の登記 ・商業、法人の(会社設立、役員変更等)登記の申請 ・裁判所、検察庁、法務局等に提出する書類の作成 ・企業法務 ・成年後見業務 ・遺言、相続業務 ・財産管理業務 ・企業のコンサルティング業務 ・自治体のボランティアなどの社会貢献 ・供託手続き代理 ・簡易裁判所における訴訟・調停・和解代理 ・法律相談 ・多重債務者の救済 |
司法書士事務所に就職する以外にも、独立開業したり、企業の法務部で働く事も可能な司法書士は、各方面から需要の高い資格です。
※多様化する司法書士の詳しい業務内容を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
→司法書士とは 仕事内容、魅力から試験情報までを解説!
2-2.高齢化社会に伴う業務の拡大
高齢化社会に伴い司法書士の業務範囲が拡大している事も、司法書士の将来への展望が明るい理由の1つです。
高齢化に伴う司法書士の仕事としては、主に次のようなものが挙げられます。
【高齢化に伴い増加する司法書士の業務】
| ・成年後見に関する業務 ・相続、遺言に関する業務 ・死後事務委任契約等、財産管理に関する業務 ・民事信託に関する業務 |
高齢化社会が進む現代において、これらの業務に関する需要は今後も増していくことが予想されます。
依頼者と信頼関係を築き、柔軟にさまざまな業務に対応しなければいけないことを考えると、これらの仕事までAIに奪われてしまう可能性は低いと言えるでしょう。
2-3.AIでは代替できない業務が多い
司法書士の業務は多岐に渡りますが、AIでは代替できない業務が多いのも、司法書士の仕事がなくならない理由の1つです。
たしかに、書類作成業務や一部の事務作業についてはAIで仕事を自動化・定型化した方が効率がいいかもしれません。
しかし、「街の法律家」でもある司法書士の役割は、登記業務や書類作成業務に留まらず、依頼者と緻密なコミュニケーションをとらなければならない業務もたくさんあります。
また、書類作成業務といっても、ただ単に決まった書類を作成するのではなく、依頼者の希望に合わせてその都度最適な書類を作成する必要があります。
「この司法書士なら仕事を任せられる」と信頼関係を築きながら業務を進めていくのが、法律家である司法書士の使命であり、AIでは依頼者に合わせた柔軟な対応をするのは困難であると言えます。
2-4.相続登記の義務化による需要の増加
2024年4月1日から開始される相続登記の義務化に伴い、不動産登記関連の業務が増える事が予想されます。
相続登記が義務化されると、これまでのように、相続した土地の登記を放置できなくなります。そのため、不動産登記の専門家である司法書士の需要はますます高まると言えます。
また、相続登記に伴い、相続放棄のサポートや遺産分割協議書の作成など、相続に関する様々な業務を一括して依頼されるケースも増えるでしょう。
3.司法書士に将来性がないと言われる理由
司法書士に将来性がないと言われる主な理由は、次の3つです。
| 司法書士に将来性がないと言われる3つの理由 |
| ◉登記件数が減少傾向にある ◉AIの台頭によって仕事が奪われる ◉ブロックチェーン技術を活用した新しい登記システムの構築 |
以下、それぞれの理由について詳しく解説していきます。
3-1.登記件数が減少傾向にある
司法書士のメイン業務の1つである不動産登記の件数が減少していることは、司法書士の将来性がないことの理由の一つとして挙げられます。
たしかに、総務省が公表している統計によると、不動産登記の件数は年々減少傾向にあることがわかります。
参照:登記事件の件数及び個数 |総務省
しかし、相続登記の義務化が開始されることで、不動産登記の件数は今よりも上昇することが想定されます。
また、司法書士の業務の多様化が進む昨今、不動産登記以外の業務で活躍する司法書士も増えている事から、登記件数の減少と司法書士の将来性のなさは結びつかないと言えるでしょう。
3-2.AIの台頭によって仕事が奪われる
AI(人工知能)が発展することで、書類作成業務がメインの司法書士の仕事がなくなるのではないかと言われています。
確かに、人間よりもAIが行なった方が、迅速かつ正確に業務をこなせるケースもあります。
そのため、単純な書類作成業務や調べ物に関しては、AIに仕事を任せる時代が来るでしょう。
しかし、司法書士が行なう業務は、単純な書類作成業務だけではなく、依頼者の意思を確認しながら、依頼者の希望に沿った形で書類を作成していく必要があります。
依頼者の満足度が高くなる質の高いリーガルサービスを提供するためには、依頼者に寄り添ったこまやかなコミュニケーションが欠かせません。
人間の感情を汲み取る事ができないAIでは、司法書士業務を全て担うのは難しいと言えます。
3-3.ブロックチェーン技術を活用した新しい登記システムの構築
近年話題になっているブロックチェーン技術を活用した新しい登記システムが構築された場合、司法書士の仕事に影響を及ぼす恐れがあります。
ブロックチェーン技術を活用すれば、取引の信用性を担保した上で様々な取引を行なう事ができます。
インターネット上に蓄積された不動産に関する膨大なデータを利用し、質の高い取引が出来るようになれば、個人がインターネット上で登記手続きをする日が来るかもしれません。
しかし、ブロックチェーン技術を活用した不動産登記システムの導入はまだ現実的とは言えず、司法書士の仕事がすぐなくなるとは言えません。
また、たとえシステムが構築されたとしても、そこから個人の実用化に至るまでは時間がかかる事も想定されます。
4.司法書士として30年後も活躍するための秘訣は?
【スタッフ200名を超える司法書士事務所の代表が考える~司法書士の未来予測~】
司法書士の将来性について、第一線で活躍中の代表司法書士の先生が実務者目線で解説されています。ぜひ、ご覧ください。
司法書士として、今後20年、30年と活躍するための秘訣をまとめると、以下のとおりとなります。
| 司法書士として30年後も活躍するための秘訣 |
◉時代の変化に柔軟に対応する ◉コミュニケーションスキルを磨く |
4-1.時代の変化に柔軟に対応する
司法書士として長期に渡り活躍する為には、急速に変化する時代に合わせて柔軟に対応していく事が重要です。
司法書士の業務内容は年々変化しており、以前は紙ベースの申請書でしかできなかった登記業務も、現在ではオンラインで申請できるようになっています。
また、今後、AIシステムの活用により、これまで多くの時間を費やしてきた書類作成などの作業時間が減り、お客様の相談業務に十分な時間を当てられるようになることが予想されます。
AIを脅威と捉えるのではなく、生産性を上げるツールとして考えるならば、むしろお客様との信頼関係を構築する機会が増え、顧客を増やすことにも繋げられるチャンスと言うこともできるのです。
4-2.コミュニケーションスキルを磨く
司法書士に限ったことではありませんが、AI時代を生き抜く上で、必要不可欠な技術がコミュニケーションスキルです。
前述したように、書類作成などの作業部分をAIシステムに任せられるようになると、司法書士のメイン業務はお客様対応になっていくことが考えられます。
そうなった場合、コミュニケーションスキルを高めることは避けて通れない任務と言ってもよいでしょう。
コミュニケーションに関する様々な書籍がベストセラーになっているのも、多くの人が、AI時代を生き抜く上でコミュニケーションスキルは必要不可欠な技術であると認識しているからなのでしょう。
4-3.認定司法書士やダブルライセンスで対応できる業務範囲を増やす
司法書士として認定を受けたり、ダブルライセンスを取得して仕事をする事で、対応できる業務の幅を広げる事も重要です。
認定司法書士になれば、簡易裁判所における訴額140万円以下の裁判について、弁護士と同じように代理人になる事ができます。
訴額が比較的少額な事件については、弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうことから、相談を諦めてしまうケースも珍しくありません。
そのため、市民の身近な法律家として、司法書士がサポートできれば、仕事の依頼の幅も広がるでしょう。
また、行政書士、土地家屋調査士、宅建士、社労士、中小企業診断士などとのダブルライセンスで業務にあたれば、依頼者の悩みをワンストップで対応できる可能性が高くなり、同業者との差別化を図る事ができます。
さらに、ステップアップを目指し、司法試験に挑戦する司法書士も今後増えてくることでしょう。
常に自分自身を進化成長させていく向上心があれば、いかなる時代の変化も恐れる必要はないのです。
※行政書士とのダブルライセンスについては、こちらの記事をご覧ください。
→司法書士と行政書士の違いとは?仕事内容や試験の難易度・ダブルライセンスのメリットとは?
4-4.コンサルティング業務など新しい分野の仕事にチャレンジする
司法書士としての専門的な知識を駆使して、経営コンサルティング業務などの新しい分野の仕事に積極的にチャレンジしていく事も、司法書士として長く活躍するポイントの1つです。
現代社会には様々な企業が存在しますが、いかなる企業も経営戦略を立てる上で法的なサポートを必要としています。
司法書士は、会社設立時の登記申請において企業との接点が作れます。この貴重な機会を活かして、強固な信頼関係が築くことができれば、企業法務のパートナーとして、あるいは経営のアドバイザーとして長期のお付き合いができる可能性があるでしょう。
そのためにも、コミュニケーションスキルはもちろん、コンサルタントとして必要な様々なスキルやライセンスを取得したり、他の士業との人脈を拡げていくことにより、司法書士を超えた活躍が期待できます。
司法書士としての地位に甘んじる事なく、常に新しいことにチャレンジし続ければ、司法書士の未来は明るいものになるはずです。
5.まとめ
AI技術の台頭に伴い、司法書士の将来性を心配されている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、時代の流れに伴い多様化しつつある司法書士の業務を考えると、司法書士の将来性は決して暗くはありません。
むしろ、高齢化や相続登記の義務化などの影響により、今後、司法書士の重要性が増していくことが予想されます。
司法書士として活躍を続けるためには、時代の変化を恐れず、柔軟に対応していくことが必要不可欠です。
AI技術を、生産性を上げるための有効なツールとして活用することにより、本来、力を入れるべき顧客対応業務に多くの時間を割くことができ、司法書士としての活躍の場を拡げる一助となるでしょう。
また、事務作業をAIが担う時代には、これまで以上に対人スキルが重要となります。
司法書士の資格を取って満足するのではなく、コミュニケーションスキルの向上、ダブルライセンスの取得など、司法書士として進化成長し続けることにより、コンサルタントなど様々なフィールドで活躍することも可能になるでしょう。
伊藤塾では、開塾以来、単に合格を目指すだけではなく、“合格後を考える” を理念に、「明日の司法書士講座」など様々な取り組みを行っています。
合格はゴールではなくスタートです。
合格後のキャリアパスなどについても、豊富な事例と人脈をもつ伊藤塾にぜひご相談ください。

著者:伊藤塾 司法書士試験科
伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。