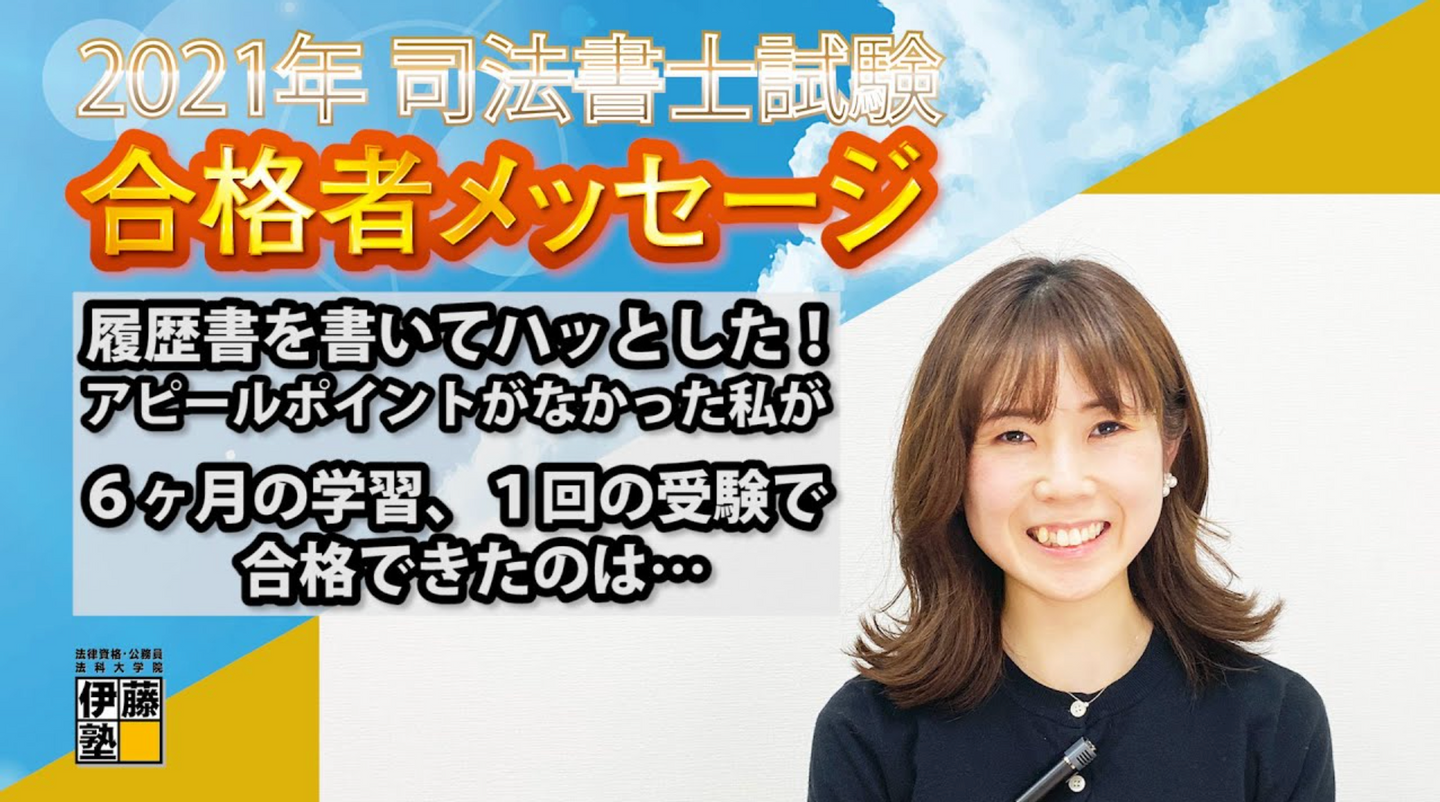行政書士から司法書士へ!必要な勉強時間は?科目の難易度や特徴も比較解説

行政書士から司法書士を目指す場合、必要な勉強時間はどの程度なのでしょうか?
司法書士試験では、一般的に3000時間の学習が必要と言われています。しかし、行政書士試験を受験した経験があれば、はるかに短い時間で合格できます。
個人差はあるものの、行政書士試験が終わった後、6ヶ月程度で翌年の司法書士試験に合格する人も珍しくはありません。学習経験を最大限に活かすことができれば、短期合格も決して夢ではないのです。
そこで本記事では、次の点を取り上げました。
・行政書士から司法書士を目指す勉強時間の考え方・行政書士試験の経験を活かして、6ヶ月で合格した人の体験談
・2つの試験で重なる科目の比較
・重ならない科目の勉強法
・なぜ行政書士が司法書士試験で有利なのか
司法書士へのステップアップを考えている方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士から司法書士を目指す勉強時間
1-1.行政書士試験の後、6ヶ月後の司法書士試験に合格する人もいる
2.行政書士試験と司法書士試験で重なる科目の比較|難易度・特徴など
2-1.憲法|大きなアドバンテージとなる科目
2-2.民法|合格に必要な内容の約60%は学習済み
2-3.商法|イチから学習するイメージで取り組む科目
3.行政書士と司法書士で重複しない科目は?
3-1.不動産登記法|民法(実体法)の理解が大きなアドバンテージ
3-2.商業登記法|会社法(実体法)の知識が土台
3-3.その他科目|民事訴訟法・民事執行法・民事保全法など
4.なぜ行政書士から司法書士を目指すのが有利なの?
4-1.午前科目の91%が重複している
4-2.法律的な考え方が身に付いている
4-3.「難関試験に本気で挑戦した」という経験がある
5.行政書士から司法書士に挑戦するか迷ったら、まずは勉強してみよう!
6.まとめ
1.行政書士から司法書士を目指す勉強時間
初学者から司法書士試験を目指す場合、一般的に3000時間の学習が必要と言われています。
行政書士試験の経験があれば、これよりもはるかに短い時間で合格できる可能性が高いでしょう。法律的な考え方が身についている上、「憲法・民法・商法」などの科目が共通しているからです。
特に民法は、司法書士試験でも最重要科目の一つです。本来なら膨大な勉強時間が必要ですが、行政書士試験に合格するレベルの実力があれば、司法書士試験でも60%程度は学習済みと考えて良いでしょう。憲法や商法でも、行政書士試験の経験は大きなアドバンテージとなります。
1-1.行政書士試験の後、6ヶ月後の司法書士試験に合格する人もいる
では具体的に、どの程度の時間を短縮できるのでしょうか?
これは一概には言えません。行政書士試験に合格した時点でのレベルや得意科目、そして学習環境によって大きく変わってくるからです。
例えば、2021年度司法書士試験に合格したOさんは、行政書士試験が終わった12月末に司法書士試験へのチャレンジを決めて、翌年の試験に合格しました。他にも、行政書士試験の経験を活かして半年程度で合格を勝ち取った人や、開業して実務をこなしながら合格した人も数多くいます。
いずれにせよ行政書士の経験を上手に活用すれば、司法書士試験学習期間が大幅に短縮されることは間違いありません。
以下では、実際に行政書士から司法書士試験へ短期合格した人の体験談を紹介します。5分程度の動画ですが、ぜひ自分が挑戦する姿をイメージしてみてください。
『6ヶ月の学習、1回の受験で合格できたのは…』2021年司法書士試験合格者メッセージ
2.行政書士試験と司法書士試験で重なる科目の比較|難易度・特徴など
行政書士試験と司法書士試験では、憲法、民法、商法の3科目が重複しています。
それぞれの科目について、試験問題の難易度や特徴を比較しつつ、行政書士から司法書士を目指す際のポイントを見ていきましょう。
2-1.憲法|大きなアドバンテージとなる科目
憲法は、行政書士試験の経験者にとって大きなアドバンテージになる科目です。
行政書士試験の憲法をしっかりと学習していれば、司法書士試験でも十分に太刀打ちできるでしょう。
特に最近は、行政書士試験の憲法が難化しているため、司法書士試験より難しいと言われることも多いです。「何を聞かれているのか分からない」と頭を悩ませるような問題が多く、解きにくいと感じていた人も多かったのではないでしょうか?
司法書士試験の憲法は、出題意図が明確でわかりやすい典型的な問題が多いです。行政書士試験よりも解答しやすいため、ほとんど対策せずに、行政書士試験の知識のみで合格している人もいます。「人権・統治」ともに、既存の知識をチューニングする程度の勉強でも、十分に対応できるでしょう。
一つだけ注意したいのは、学説(推論)問題が出題されることです。行政書士試験ではあまり扱いませんが、司法書士試験では最近まで出題されていました。ここ数年は見かけないため、傾向が変わりつつあるとも言われていますが、典型的な問題は押さえておきましょう。
2-2.民法|合格に必要な内容の約60%は学習済み
民法は、行政書士合格時の実力によって差が出やすい科目です。
行政書士合格者の平均レベルの実力であれば、司法書士試験でも「約60%」を学習済みと考えてよいでしょう。問題の難易度は同水準ですが、学習範囲にはかなりの差があります。
「総則・債権」では、大きなギャップを感じる人は少ないです。司法書士試験の方が若干範囲が広いですが、改めて勉強する内容はあまりありません。まずは過去問を解いてみて、苦手分野をチューニングするイメージで進めていきましょう。
一方、「物権」や「担保物権」「親族・相続法」では、学習範囲に差があります。
特に「担保物権」は、行政書士試験であまり勉強しない分野が、司法書士試験の重要分野となっています。先取特権、質権、根抵当権、譲渡担担保などは、細かな内容までしっかりと取り組むことが必要です。
「親族・相続法」も配点の差が大きく、ギャップを感じやすい分野です。行政書士試験では1問しか出ないため、そもそも勉強していない人も多かったはずです。しかし司法書士試験では4問が出題されます。細かな内容も問われるため、きちんと対策していた人でも、知識レベルは司法書士試験の「50%程度」だと考えておきましょう。
【民法の各分野の比較】
| 2つの試験の比較 | |
| 総則 | ・問題の難易度は同水準 ・学習範囲は司法書士が若干広め ・過去問をベースにしつつ、苦手分野を 中心に対策する |
| 物権 | ・司法書士試験の方が細かな知識が必要 ・行政書士試験の知識で対応できるのは 70%程度 |
| 担保物権 | ・最も力を入れて勉強するべき分野 ・先取特権、質権、根抵当権、譲渡担保 で大きなギャップがある ・行政書士試験の合格者でも十分な対策 が必要 |
| 債権 | ・問題の難易度は同水準 ・学習範囲は司法書士が若干広め ・過去問をベースにしつつ、苦手分野を 中心に対策する |
| 親族・ 相続法 | ・担保物権と並んで力を入れるべき科目 ・行政書士試験合格レベルでおよそ50% の到達率 ・複雑な問題は少ないので担保物権ほど 難しくはない |
2-3.商法|イチから学習するイメージで取り組む科目
商法は、行政書士試験ではマイナー科目に位置づけられます。
試験対策上、商法を捨てている人も多いのが実情でしょう。一方、司法書士試験では中心科目の一つなので捨てることはできません。多くの行政書士受験生にとって、イチから学習することが必要な科目です。
問題の難易度も、司法書士試験の方が全体的に高いです。
行政書士試験の商法では難問(Cランク)に位置づけられる問題が、司法書士試験ではAランクレベルとして出題されるようなイメージで考えておきましょう。しっかりと勉強した人でも、司法書士試験では初めての気持ちで取り組むことが必要です。
これまでの知識をベースにしつつ、講義などでイチから学習するイメージで進めていきましょう。
3.行政書士と司法書士で重複しない科目は?
それでは、重複しない科目についてはどのように勉強すれば良いのでしょうか?
不動産登記法、商業登記法、民事訴訟法・民事執行法・民事保全法などは、司法書士試験でしか出題されません。行政書士試験では全く勉強していないケースが通常でしょう。
しかし、本当にゼロからの学習となるわけではありません。実は「民法と不動産登記法」「会社法(商法)と商業登記法」「行政事件訴訟法と民事訴訟法」といったように様々な科目がつながっているからです。
行政書士試験の経験があれば、大きなアドバンテージをもって学習をスタートできます。
3-1.不動産登記法|民法(実体法)の理解が大きなアドバンテージ
不動産登記法は、「民法」で学んだ権利変動のプロセスを、不動産登記の世界でどのように反映させるかを学ぶ科目です。民法とは「手続法と実体法」の関係にあるので、「民法(実体法)」をどれだけ理解できているかが学習のカギとなります。
「不動産登記法が苦手…」という人は多いですが、しっかりと話を聞くと「そもそも民法の理解が足りていない」というケースが少なくありません。
行政書士試験で民法をしっかりと理解していれば、スムーズに学習を進められるでしょう。
まずは基本的な流れを押さえ、その後に応用問題へとステップアップしていきましょう。行政書士試験の知識を活かしつつ、着実に学習を積み重ねることが合格への近道です。
3-2.商業登記法|会社法(実体法)の知識が土台
商業登記法では、「会社法」の知識が欠かせません。
行政書士試験でも学習する「会社法」の知識と、登記実務をリンクさせて考える力を身に着けなければ、商業登記法は理解できないからです。会社法(実体法)を深く理解しているほど、商業登記法(手続法)の学習もスムーズに進んでいくでしょう。
そもそも、商業登記法の問題を解くためには、まずは会社の属性(公開or非公開、株式会社or特例有限会社、大会社or非大会社など)を把握することが必要です。つまり、会社法が分かっていなければ、いくら商業登記法だけ勉強しても正答することはできません。
行政書士試験の経験をベースにしつつ、会社法と商業登記の関係性を丁寧に学んでいきましょう。まずは実体法(会社法)を正確に押さえて、それから細かな知識や応用問題に取りかかるなど、段階的な学習が効果的です。
3-3.その他科目|民事訴訟法・民事執行法・民事保全法など
民事訴訟法、民事執行法、民事保全法は、行政手続法の民事版ともいえる科目です。
考え方は行政法と共通する部分が多いため、行政書士試験の学習経験が大いに役立つでしょう。
例えば、「民事訴訟法」は行政書士試験では扱いませんが、内容は「行政事件訴訟法」に近い科目です。原告適格、被告適格、訴えの利益など、行政書士試験の合格者にとって馴染みのある用語も多いでしょう。ゼロから学ぶよりも、はるかに効率よく学習を進められます。
その他の科目(司法書士法、供託法、刑法)は、新たな気持ちで学習する必要はありますが、勉強の進め方は似ています。行政書士試験で身に付けた考え方が、大いに発揮されるでしょう。一見初めて学ぶ分野のようで、意外と馴染みやすいと感じる人が多い科目です。
4.なぜ行政書士から司法書士を目指すのが有利なの?
行政書士から司法書士を目指す人は決して少なくありません。
これは司法書士試験が、実務上も試験対策上も、行政書士の経験を最大限に発揮できる試験だからです。伊藤塾でも例年「約30%」の人が司法書士試験の受験を検討しています。
また、最近増えているのが、行政書士として開業してから司法書士試験に挑戦するケースです。多くの人が、仕事を進めていくにあたって必要性を感じたり、他事務所との差別化を図るために司法書士資格の取得を決意しているようです。
それでは、なぜ「司法書士試験が、行政書士の経験を最大限に発揮できる」と言えるのでしょうか?行政書士試験の受験生が、司法書士試験で有利な理由について詳しく見ていきましょう。
◉行政書士から司法書士を目指す人が有利な理由
・午前科目の91%が重複しているから・法律的な考え方が身に付いているから
・「難関試験に本気で挑戦した」という経験があるから
4-1.午前科目の91%が重複している
行政書士試験と司法書士試験では、「憲法・民法・商法」という3科目が重複しています。
これは、司法書士試験の午前科目の配点の「91%」に相当する割合です。
特に憲法と民法については、行政書士試験と司法書士試験で求められる知識レベルはほぼ同じ水準です。行政書士試験の知識をベースに、不足している分野や出題傾向の異なる部分を重点的に学習すれば、十分に対応することができます。
商法についても、行政書士試験の勉強で基本的な知識や考え方は身についているはずです。ゼロからスタートする人と比べれば、学習のハードルは格段に低いでしょう。
4-2.法律的な考え方が身に付いている
法律的な考え方が身についていることも、大きなアドバンテージです。
行政書士試験の勉強をスタートしたばかりの頃を思い出してみてください。法律用語の理解、条文・判例の読み方、具体と抽象の置き換え、勉強の進め方など、基本的なスキルを身につけるだけでもかなりの時間と労力が必要だったはずです。
これらのスキルは、司法書士試験の学習においても強力な武器となるでしょう。
中には、「憲法・民法・商法以外はゼロからのスタート」「午後の科目は全て初学者と同じ」と考えている人もいますがこれは誤りです。
行政書士試験で培った知識や学習方法は、受験生が想像する以上に大きな力となって発揮されるはずです。
4-3.「難関試験に本気で挑戦した」という経験がある
そして何より大きいのは、「難関試験に本気で挑戦した」という経験があることです。
行政書士試験を通じて、資格試験への取り組み方や粘り強く取り組む精神力を身につけていることには、計り知れない価値があります。
・基本知識を身につけることがどれだけ重要か・「暗記」ではなく「理解」が大切とは、具体的にどういうことなのか
・なぜ「絞り込み」と「繰り返し」が重要なのか
・モチベーションが落ちたときはどうすればいいのか
・問題を解くときの勘所はどこなのか
・学力はどのようなイメージで伸びていくのか
・直前期にどのような心境になるのか
・失敗からどうやって立ち直ればいいのか
法律の知識以上に、こうした経験をしていることが圧倒的な差となって表れるのです。
行政書士から司法書士へチャレンジすることにハードルの高さを感じている人は少なくありません。しかし実際に挑戦すると、「行政書士試験は何回も受験してやっと合格できたのに、司法書士試験は1回目で合格できた」となる人が珍しくありません。
これこそ、まさに「難関試験に合格した経験」が如実に発揮された結果だと言えるでしょう。
5.行政書士から司法書士に挑戦するか迷ったら、まずは勉強してみよう!
ここまでの内容で、行政書士から司法書士へチャレンジするメリットをお伝えしました。
とはいえ、いざ勉強を始めるとなると迷いが生じることもあるでしょう。司法書士試験は気軽に始めて合格できるような試験ではないからです。本格的に受験するかどうかは、自分の人生設計を踏まえてしっかりと考えなければいけません。
「司法書士試験には興味があるけど、チャレンジするべきか迷っている」「勉強は続けたいけど、司法書士を目指す覚悟は決まっていない」
こういった方は、まずは「会社法」や「親族・相続法(民法)」の勉強から始めてみるとよいでしょう。これらの科目は、行政書士「試験」では手薄になりがちですが、行政書士「実務」では欠かせない知識です。司法書士試験の対策としてはもちろん、仮に受験しなかったとしても行政書士としての開業後に大きな武器となるはずです。
「迷ったときこそ、まずは勉強を始めてみる」…この姿勢こそが、次のステップへ進む第一歩になるのです。受験するかどうかは後から決めても問題ありません。少しでも「勉強を続けたい」という気持ちがあるのなら、ためらわずに一歩を踏み出してみてください。
※伊藤塾では、司法書士試験へのステップアップや、行政書士としての開業を考えている方に向けて、「家族法(親族・相続)集中講義」・「会社法集中講義」を開講しています。
6.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉行政書士から司法書士を目指すと、勉強時間を大幅に短縮できる
・重複する科目は「憲法・民法・商法」の3科目・「憲法」は行政書士試験の方が難しい傾向がある
・「民法」は60%程度の内容は学習済と考えてよい
・「商法」は行政書士試験の知識をベースにイチから学習する気持ちで取り組む
◉行政書士から司法書士を目指すメリット
・憲法、民法などは必要な知識レベルも同水準
・法律的な考え方が身についていることも大きい
・何より「難関試験合格の経験」があることが最大の強み
◉迷ったら、「会社法」や「親族・相続法」からまず勉強をしてみる
◉いずれも、司法書士試験対策だけでなく行政書士実務でも必要な内容だから
◉本格的な受験は後から決めてもOK
以上です。
行政書士から司法書士へ挑戦するハードルは、皆さんが考えている程高くはありません。行政書士試験の経験を活かすことができれば必ず合格への道が開けるはずです。
司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。ぜひ新たな一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。

著者:伊藤塾 司法書士試験科
伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。