宅建士試験「法令上の制限」の攻略法!覚え方や勉強法を解説

宅建士試験では、「法令上の制限」という分野でさまざまな法律に関する問題が出題されます。建築基準法や都市計画法、農地法や土地区画整理法など、聞いたことはあるもののどんな内容の法律なのか知らない方も多いのではないでしょうか。
日常生活と結びつきやすい民法や比較的内容を理解しやすい宅建業法と違い、法令上の制限は内容が理解しづらく難しいと、苦手意識を持っている人も多いです。
人によっては捨て科目にしてしまう場合もありますが、実は出題される内容は基本的な項目が多く、得点するポイントさえ掴んでしまえば誰でも得点源にできる分野でもあります。
得点源にすべき民法や宅建業法が難化した場合でも合格できるよう、法令上の制限でも安定して高得点を取れるだけの力を身につけましょう。
この記事では、宅建士試験の試験項目の一つである「法令上の制限」の覚え方や勉強法を解説していきます。
※法律知識ゼロの方でもわかりやすい講義で、短い学習時間で効率よく合格できる伊藤塾の「宅建士合格講座」から、「法令上の制限」都市計画法の一部を体験講義としてご覧ください。
担当:志水 晋介 講師
【宅建士合格講座】「法令上の制限」都市計画法 体験講義
【目次】
1. 宅建士試験における「法令上の制限」とは
1-1. 科目の特徴
1-2. 出題数
1-3. 頻出分野
1-4. 出題傾向
2. 法令上の制限で目指すべき点数は?
3. 法令上の制限で得点を伸ばすためのポイントや覚え方
3-1. 具体的な場面を想定しながら問題に取り組む
3-2. 丸暗記ではなく、規制の趣旨を理解する
3-3. 覚えるべきポイントを絞って勉強する
3-4. 一覧表やゴロ合わせを有効に活用する
3-5. 過去問を使って頻出分野を抑える
4. 受験指導校なら宅建士試験で高得点を取るコツがわかる!
5. まとめ
1. 宅建士試験における「法令上の制限」とは
宅建試験で出題される「法令上の制限」とは、土地の利用に関する制限について規定した法律のことです。
不動産取引で土地を購入しても、その土地を個人の自由にできるわけではありません。土地の所有者が無秩序に建物を建てた場合、隣地所有者とトラブルになったり、公平な土地利用ができなくなる恐れがあります。
トラブルや災害の防止、街の景観の維持やライフラインの効率的な整備など、機能的な都市活動を確保するためには土地の利用について一定のルールを設ける必要があります。法令上の制限で出題される主な法律には、以下のようなものがあります。
| ・建築基準法 ・都市計画法 ・国土利用計画法 ・農地法 ・土地区画整理法 ・宅地造成及び特定盛土等規制法 |
例えば、建築基準法では、災害時における避難経路の確保や緊急車両の経路確保を目的として、接道規制が設けられています。この規則によれば、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接していなければなりません(建築基準法43条1項)。この幅がない場合には、緊急時に消防車や救急車が敷地に入ってこれなくなってしまうからです。
他にもさまざま法律で土地の利用について制限が設けられていますが、宅建士試験では、各法令の制限の基本的な部分に関する出題がなされます。
1-1. 科目の特徴
法令上の制限で出題される法律は馴染みがない人も多く、場合によっては細かい暗記が必要になる場面もあります。専門用語も多く、一見すると内容も複雑に感じるケースも多いですが、その分、出題される問題は基礎的な内容が多く、法律の深い理解や重箱の隅をつつくような内容は出題されません。
例えば、令和5年の宅建士試験では、建築基準法に関する以下のような問題が出題されました。
【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
2 3階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
3 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
4 石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
引用:令和5年度 問題|REITO 一般財団法人不動産適正取引推進機構
初学者からすると、問題を見ても何を言ってるのかよくわからないと思います。しかし、この問題で得点するためには誤っている選択肢を一つ選択できればよいので、極端な話、他の3つの選択肢はわからなくても得点することは可能です。
この問題でいえば、「建築物が防火地域と準防火地域に渡っている場合、その全部について防火地域の規定が適用される」というルールを知っていれば、選択肢3が誤りだとわかります。法令上の制限に関する各規定は、不動産取引に密接に関わる宅建業者であれば必ず知っておかなければいけない重要な知識です。ポイントを抑えて、正確な知識を身につけましょう。
1-2. 出題数
宅建士試験では、法令上の制限に関する問題が毎年8問出題されます。宅建士試験では全50問出題されるので、出題率は全体の16%となります。ポイントを抑えて集中的に暗記すれば、誰でも安定して6〜7問は取れるようになります。他の科目での失点をカバーするためにも、他の受験生が苦手とする分野を得点源にしましょう。
1-3. 頻出分野
法令上の制限で出題される主な法律や出題数は、おおよそ以下のとおりです。
| 法令名 | 出題数 |
| 都市計画法 | 2問 |
| 建築基準法 | 2問 |
| 国土利用計画法 | 1問 |
| 農地法 | 1問 |
| 土地区画整理法 | 1問 |
| 宅地造成及び特 定盛土等規制法 | 1問 |
他の法令から出題されることもありますが、基本的にこれらの法律に関する規定について学んでおけば間違いありません。特に都市計画法及び建築基準法については例年必ず出題されているので、必ず得点したい科目でもあります。
1-4. 出題傾向
法令上の制限に関する問題は、過去問で出題されたことのある問題が角度を変えて出題されるケースが多いです。特に、出題数の多い都市計画法や建築基準法に関する問題では、基礎的な知識を問う問題が頻出します。
例えば、令和5年度の試験では、都市計画法に関する問題で以下のような選択肢が出題されました。
2 高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。引用:令和5年度 問題 問15|REITO 一般財団法人不動産適正取引推進機構
この選択肢では、「高度利用地区は、建築物の容積率・建蔽率・建築面積などに関する制限であり、建築物の高さに関する制限は高度地区である」という知識があれば誤りであるとの判断が可能となっています。基本的な知識だけで回答できるのはもちろん、この問題に関する知識も過去問で出題されたことがあります。
3 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。引用:平成28年度 問題 問16|REITO 一般財団法人不動産適正取引推進機構
この選択肢についても、前半部分の記述内容がよくわからなくても、後半部分における「建築物の高さの」という部分が間違っていることが分かれば、自信を持って誤りであると判断できるでしょう。
過去問を繰り返し解けば、試験当日の現場で「あっこの問題見たことある」という問題が増えます。自信のある回答が増えれば、時間制限で最後まで解き切れないというリスクを下げることもできるでしょう。
2. 法令上の制限で目指すべき点数は?
法令上の制限に関する分野では、8問中6問正解を目指しましょう。人によって得意・不得意は様々です。どの分野で何点獲得すべきかは、他の分野で何点取れるかにも関わってきます。例えば、得意な民法・宅建業法で満点を取れるのであれば、それだけで34点取れる(あと2〜3問正解で合格ラインに到達する)計算になります。
ただし、法令上の制限に関する分野は、専門用語が多くとっつきにくいイメージがある反面、覚えるコツさえ理解してしまえば堅実に得点を積み重ねられる分野です。民法や免除・その他の分野で得点を落としてしまった人は、法令上の制限で得点できればその分を上手くカバーできるかもしれません。
全体の7〜8割得点できないと合格できない試験であることを考えると、法令上の制限で最低でも6点は確保する目標を立てるのが、受験戦略上は有意義だといえるでしょう。
3. 法令上の制限で得点を伸ばすためのポイントや覚え方
苦手意識を持っている人が多い「法令上の制限」の分野で得点を伸ばすためには、以下のポイントを意識して勉強をしていくとよいでしょう。
| ・具体的な場面を想定しながら問題に取り組む ・丸暗記ではなく、規制の趣旨を理解する ・覚えるべきポイントを絞って勉強する ・一覧表やゴロ合わせを有効に活用する ・過去問を使って頻出分野を抑える |
3-1. 具体的な場面を想定しながら問題に取り組む
法令上の制限について難しく感じるのは、専門用語が多いことだけでなく、具体的な場面を想定しづらいからです。民法であれば日常生活に関わりのある話なので、具体的な場面を想定しやすいです。また、宅建業法についても、実際にアパートやマンションを借りたことがある人であれば、話の内容がスムーズに入ってくるでしょう。
一方、法令上の制限に関する分野で出題される法律については、日常生活で馴染みのない話であることも少なくありません。具体的なイメージを持たずにただ漠然と暗記しようと思っても、試験で得点に繋がる知識を身につけることはできません。
例えば、「地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。」という知識であれば、「津波の危険がある海沿いの地域については、災害のリスクが高いから家を建てられない場合がある」などと、自分の中で噛み砕いて理解することが重要です。
3-2. 丸暗記ではなく、規制の趣旨を理解する
数字の暗記が必要な場面もありますが、基本的には「なぜその規制が必要なのか」を考えながら勉強していくことが大切です。先ほどの災害危険区域に関する制限であれば、居住者の災害リスクを下げるために建築制限が設けられています。
また、建築基準法における接道規制の例でいえば、居住者に何かあった際に消防車や救急車が住宅まで侵入できるように規制が設けられています。専門用語が多く理解に時間がかかる場合もありますが、まずは「なぜそういう規制があるのか、なぜその数値になっているのか」を考えるクセをつけましょう。
3-3. 覚えるべきポイントを絞って勉強する
勉強する際は、覚えるべきポイントを絞って勉強してください。
法令上の制限に関する分野では様々な法律に関する規制が出題されますが、全ての法律について完璧な知識を身につけようとするのは非効率です。勉強する際は、頻出分野・頻出箇所に絞って勉強することをお勧めします。
例えば、都市計画法なら「開発許可が必要になる区域」、建築基準法なら「建築確認が必要になる建築物」などが繰り返し出題されています。繰り返し出題されている分野については、過去問学習を通して学んだり、受験指導校の講義で指摘してもらったりするのがお勧めです。
3-4. 一覧表やゴロ合わせを有効に活用する
数字を覚える際は、その分野に関する一覧表を作成して全体として覚えたり、自分で覚えやすいゴロ合わせなどを作ったりするのがお勧めです。例えば、都市計画法における「特別用途地区」と「特定用途制限地域」を理解したいのであれば、以下のような表を自分なりに作成してみましょう。
| 特別用途地区 | 特定用途制限地域 | |
| 定める 場所 | 用途地域内 | 用途地域が未指定 の区域 ※ ただし、市街化 調整区域内は✕ |
| 目的 | 用途地域内におけ る用途制限を加重 緩和するため | 用途地域ではない 区域における建築 制限 |
特別用途地区と特定用途制限地域の区別に聞かれている選択肢があったら、その都度表に戻ることを繰り返してください。その際、「なぜそのような規制が設けられているのか」も併せて検討しましょう。
また、ゴロ合わせは自分で覚えやすいものであれば何でも構いません。他の人に見せるわけではないので、できるだけ頭から抜けにくいゴロ合わせを考えてみましょう。
3-5. 過去問を使って頻出分野を抑える
法令上の制限に関する分野では、過去に出題された問題が角度を変えて出題されるケースが多いです。過去問を繰り返し解くことで、頻出分野や出題傾向を抑えることができるでしょう。
また、未知の選択肢があった場合に、どのように正解を導くかの訓練になります。選択肢の一つに自信がなくても、問題や他の選択肢次第では正解を導ける場合があります。また、未知の規制に対して制度趣旨から正誤を判断する訓練になるでしょう。
例えば、令和6年度の宅建士試験では、「天空率」という受験生にとって馴染みの薄い制限に関する選択肢が出題されました。試験会場で見たことのない単語を見かけて焦った受験生も多いと思いますが、この問題では正しい選択肢を一つ選べば良い問題だったため、他の選択肢が正解だと分かれば天空率に関する知識がなくても正解を導けることになります。「インプットを完璧に仕上げてからアウトプットとして過去問に取り組む」と考えている人も多いですが、ある程度のインプットを終えたら過去問も並行して行うようにしましょう。
4. 受験指導校なら宅建士試験で高得点を取るコツがわかる!
独学で宅建士試験に挑もうと考えている人も多いですが、効率良くスムーズに宅建士試験に合格したいのであれば受験指導校の質の高い講義を受けることをお勧めします。
「難しい」「覚えられない」と言われることが多い「法令上の制限」の分野については、独学で勉強しても苦手意識が先行してなかなか知識が身につかないケースがあります。また、初学者からすると、参考書を読んでも何を言っているのか理解できないことも多いでしょう。
受験指導校なら、宅建士試験を徹底的に研究している講師が、難解な法律について噛み砕いて解説してくれます。一覧表や具体例を通してわかりやすい説明を受けられるだけでなく、覚えるコツや試験で得点するポイントなどについてもアドバイスをもらえます。わからない点があれば講師に質問できるので、曖昧な知識のまま試験に臨むリスクも減らせるでしょう。周りの受講生と切磋琢磨することで、試験当日までモチベーションを保つことも受験指導校を活用するメリットです。
法令上の制限だけでなく宅建士試験全体で得点するコツをつかみたいなら、ぜひ受験指導校の活用を検討してみてください。
※2024年の宅建士試験に合格された伊藤塾の受講生の声をご紹介します。
2024年宅建士試験合格者 T.Sさん1コマ30分程度で、通勤時や昼休みのスキマ時間に学習しやすく、特に権利関係の宇津木講師と総復習講義の磯村講師の講義は、限られた時間内で重要事項のエッセンスをギュッと詰め込んだ授業内容だったので、繰り返し聴くことで理解が進みました。井内先生の宅建業法の授業では、宅建業の実務家としての経験をふまえたイメージしやすい講義が展開され、私のような業界外の人間にも理解しやすかったです。また、志水先生の「法令上の制限」の授業では、広範かつ複雑極まる学習内容について、ヤマ当てのようなことはせず網羅的に扱っていたため、本試験の国土利用計画法の出題で「事前届出制」が扱われた際も冷静に対処できました。
5. まとめ
◉ 法令上の制限では、「建築基準法」や「都市計画法」など土地の利用に関する制限の規定が出題される
◉ 過去に出題された問題が角度を変えて出題されるケースが多く、過去問を繰り返せば高得点が取れる
◉ 規制の場面を具体的に想定し、規制の趣旨を考えるクセをつける
宅建業法と違い苦手意識を持ちやすい法令上の制限ですが、正しい方向で勉強を続ければ必ず得点源にできる分野でもあります。勉強してもなかなか得点が伸びない人は、まずは過去問を繰り返し解くことをお勧めします。その上で、「なぜそのような規制が設けられているのか」を考えるクセをつけましょう。
宅建士試験に合格できれば、自分次第で様々なフィールドで活躍できるようになります。宅建士試験対策には、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。
「宅建士合格講座」の内容・特長について井内絢也講師がお伝えしていますので、初めての法律資格試験として、宅建士試験を目指そうとしている方、行政書士試験、他資格などのWライセンス取得を目指している方は、是非ともご視聴ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。
◉本試験の分析を徹底して行い、重要事項はもちろん、出題され易いテーマや、合格後の実務を見据えて、把握しておいた方が良い個所を重点的に学習
◉受験生のビジョンに合わせた「3コース」をご用意
◉ゼロから宅建士試験合格を目指せる「スタンダードコース」
◉難しい「権利関係」の講義時間を手厚くした「スタンダードコースプラス」
◉民法の学習経験者を対象とした「法律既修者コース」
◉分かりやすい講義でテキストを解説するので理解できる
◉講義内で問題の解き方もマスターできる
◉試験傾向を徹底分析して出題されやすいテーマを効率良く講義していくので結果、学習時間が少なくて済む
◉1コマ30分でスキマ時間でも勉強可能
◉スクーリング(4時間)やオンライン質問会(2回)もあるので、わからないことは講師に直接質問が可能など、受講生からの要望に応え、独学のデメリットも解消するため、講座全体を徹底的に改良しました。2025年の宅建士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾をご活用ください。
→2025年 宅建士合格講座

著者:伊藤塾 宅建士試験科
伊藤塾宅建士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、宅建士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。



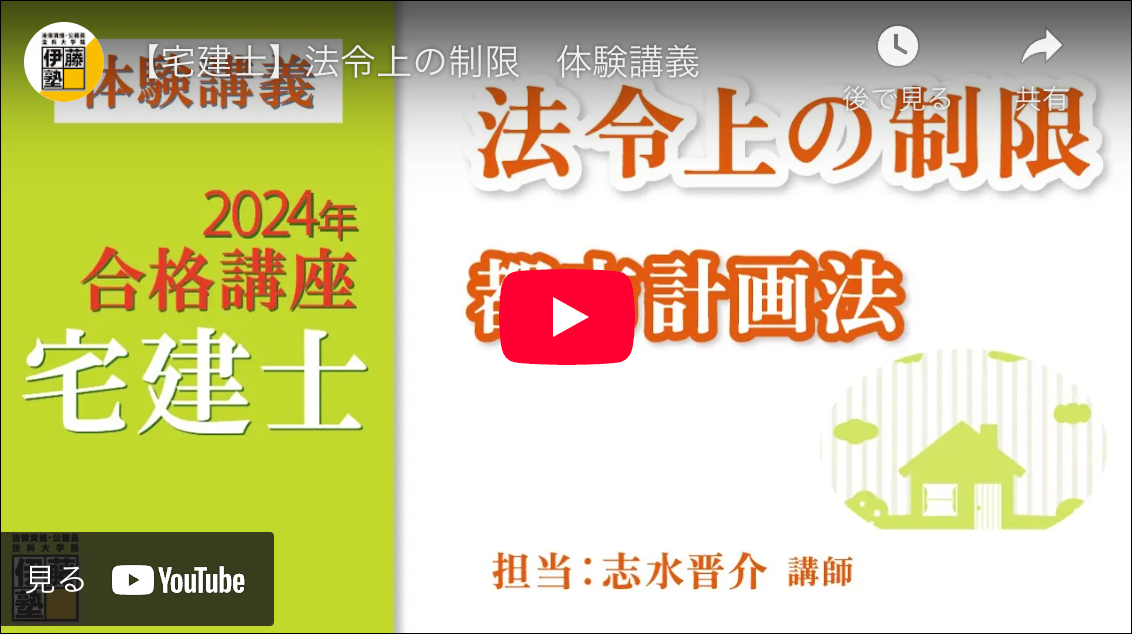
.png)













