宅建士試験における農地法の攻略法!覚え方をわかりやすく解説

宅建士試験では、法令上の制限と呼ばれる分野で農地法に関する出題があります。建築基準法や都市計画法のように頻出分野ではありませんが、毎年のように1問出題されているため、受験生としては押さえておきたい科目だといえます。
しかし、日常生活に関わりのない農地に関する法律ということもあり、苦手意識を持っている人も多いです。頻出分野である農地法3条・4条・5条の区別さえできてしまえば、あとはポイントを押さえて学習することで確実に本番で1点獲得することができるでしょう。
この記事では、宅建士試験で出題される農地法の覚え方や勉強法について、わかりやすく解説していきます。
【宅建士試験】 はじめの一歩シリーズ第20回 農地法を5分で整理『農地法』20
【目次】
1. 宅建士試験における農地法とは?
1-1. 農地法の特徴
1-2. 農地法における「農地」とは
1-3. 宅建士試験では「法令上の制限」で出題される
2. 農地法対策で押さえるべき3つの条文
2-1. 農地法3条(権利移動の制限)
2-2. 農地法4条(転用の制限)
2-3. 農地法5条(転用のための権利移動の制限)
3. 農地法の覚え方や得点するためのポイント
3-1. 農地法3条・4条・5条を正確に区別する
3-2. 過去問で出題形式やひっかけポイントを理解する
4. 受験指導校を活用して暗記ではなく理解を伴った学習を
5. まとめ
1. 宅建士試験における農地法とは?
まずは、宅建士試験で出題される農地法について、どのような科目なのか確認していきます。
1-1. 農地法の特徴
農地法は、農地の所有・利用に関する権利の設定や、農地を宅地等に転用する場合の制限などを定めた法律です。
農地は、農業生産における重要な資源です。農業に従事している人々の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって食料の安定供給を確保するためには、農地を効率的に利用することが必要不可欠になるでしょう。
もし農地がむやみに宅地へと変えられてしまうと、貴重な資源である農地そのものが減ってしまい、国民に対する食糧の安定的な確保ができなくなってしまいます。そこで、農地法では農地の売買や転用などについて一定の制限を設けて、農地を守ることになっているのです。実際、郊外で比較的安価な土地を宅地への転用目的で購入し、マイホームを建てようと検討している人も多いです。テレワークの普及に伴い、郊外への移住も増えてきているという社会情勢もあります。
農地の宅地転用の動きが今後も増えていく可能性があることを考えると、宅建士として知識を学んでおく重要性が高いといえるでしょう。
1-2. 農地法における「農地」とは
農地法における「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことを指します。一般的な田んぼや畑を想像してもらえればわかりやすいですが、ここで注意点があります。
・土地の登記簿上の地目ではなく、事実状態で農地かどうかが判断される・所有者や使用者の使用目的ではなく、客観的に農地かどうかが判断される
例えば、登記簿上で地目が「宅地」や「山林」と表記されていても、実際には農地として活用されているのであれば農地法の制限を受けることになります。また、自宅の一箇所にある土地を利用して家庭菜園などを営む場合には、農地法上の農地には該当しません。なお、農地と同様に「採草放牧地」についても農地法の適用を受けることになります。
採草放牧地とは、家畜の餌や肥料作りのために使われ定期的に雑草の刈り取りなどがされている土地や、家畜の放牧のために使われている土地のことです。採草放牧地も、食糧の安定確保のためには必要な土地であるとして、農地法の制限を受けることになります。
1-3. 宅建士試験では「法令上の制限」で出題される
宅建士試験では、「法令上の制限」の一つとして農地法に関する問題が出題されます。法令上の制限で出題される主な法律には、以下のようなものがあります。
| ・建築基準法 ・都市計画法 ・国土利用計画法 ・農地法 ・土地区画整理法 ・宅地造成及び特定盛土等規制法 |
農地法からは基本的に毎年1問出題されています。「1問しか出ないのであれば捨てていいや」と考えがちですが、宅建士試験は全体の7割以上取らなければ合格できない試験のため、捨て科目を作るのは得策ではありません。
宅建士試験で出題される農地法の範囲は狭く、出題される項目と覚えるコツさえ掴んでしまえば誰でも必ず得点できるようになります。出題される条文の区別をしっかりつけて、必要な部分は暗記で乗り切りましょう。
2. 農地法対策で押さえるべき3つの条文
宅建士試験で出題される農地法の条文は、主に以下の3つです。
| ・農地法3条(権利移動の制限) ・農地法4条(転用の制限) ・農地法5条(転用のための権利移動の制限) |
それぞれについて、どのような場面でどのような制限が課されているのか、許可を必要としない例外的なケースを明確に区別してください。
2-1. 農地法3条(権利移動の制限)
農地法3条では、農地や採草放牧地のまま所有権を移転したり、その他の権利を移転したりする場合の制限について規定しています。
重要な資源である農地について、転売目的で安易に売買が行われたり、農地を適正に管理できないにもかかわらず権利が移り続けて、荒廃することを避ける目的があります。例えば、農地を売買したり他の農家に貸したりする場合には、農業委員会の許可を得る必要があります。宅地に転用するわけではないので、権利移転後も農地や採草放牧地として利用することが想定されています。
農業委員会の許可を得ずに行われた権利移転は無効になり、悪質な場合には刑事罰を受ける恐れがあります。なお、農地に抵当権を設定する場合や農地を相続・時効取得する場合には、3条許可は不要になります。また、国や都道府県などが公共事業のために私人から農地を取得する場合にも、農業委員会の許可は不要になります。
【過去問出題例】
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
引用:令和5年度 問題 問21|REITO 一般財団法人不動産適正取引推進機構
正解:◯
2-2. 農地法4条(転用の制限)
農地法4条では、農地を宅地などに転用する場合の制限について規定しています。例えば、マイホームを建てるために自己所有の農地を宅地に転用したり、資材置場や駐車場等に転用したりする場合には、都道府県知事(市町村長)の許可を得る必要があります。
農地を無許可で転用した場合、元の状態に戻す義務が生じるだけでなく、場合によっては刑事罰の対象となる恐れもあるでしょう。
なお、国または都道府県が地域振興上または農業振興上の必要性が高い施設のために権利を転用・取得する場合には、4条許可は不要になります。また、2アール未満の農業用施設に転用する場合には4条許可は不要になることも覚えておきましょう。さらに、市街化区域内の農地であれば、市町村へ届出をすれば許可を得ることなく転用が可能となっています。
【過去問出題例】
自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
引用:令和5年度 問題 問21|REITO 一般財団法人不動産適正取引推進機構
正解:✕
解説
4条許可が不要になるのは、2アール未満の農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合に限られる。
2-3. 農地法5条(転用のための権利移動の制限)
農地法5条では、権利移転と転用が両方ある場合の制限について規定しています。例えば、マイホームを建てるために農地を売買するケースなどがこれに該当します。
権利移転と転用の両方が伴うケースでは、4条と同じように都道府県知事(市町村長)の許可が必要となります。
許可を得なかった場合には、原状回復義務が生じたり、刑事罰の対象となったりする恐れがあります。
なお、区画整理事業などで道路や公園等の公共施設を建設する場合などのケースでは、5条許可は不要となります。また、市街化区域内の農地であれば、農業員会への届出により権利移転と転用を行うことが可能です。
【過去問出題例】
法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
引用:令和5年度 問題 問21|REITO 一般財団法人不動産適正取引推進機構
正解:◯
3. 農地法の覚え方や得点するためのポイント
宅建士試験における農地法では、出題される範囲が限定的であるにもかかわらず、条文の区別がしづらいことから苦手意識を持っている人が多いです。ここでは、農地法の覚え方や得点するためのポイントについて解説していきます。
・農地法3条・4条・5条を正確に区別する・過去問で出題形式やひっかけポイントを理解する
3-1. 農地法3条・4条・5条を正確に区別する
農地法の分野で確実に得点したいのであれば、農地法3条・4条・5条を明確に区別することが重要です。人によって覚え方は異なりますが、表形式でそれぞれの違いを比較できるようにするのがお勧めです。
【農地法の許可に関する条文の比較表】
| 3条(権利移動の制限) | 4条(転用の制限) | 5条(転用のための 権利移動の制限) | |
| 適用対象 | 権利移動 ・農地→農地 ・採草放牧地→農地 ・採草放牧地→採草放牧地 | 農地→宅地 農地→採草放牧地 農地→その他 | 農地→宅地 農地→採草放牧地 農地→その他 採草放牧地→その他 |
| 許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事 (市町村長) | 都道府県知事 (市町村長) |
| 許可が不要に なるケース | ・土地収用法による収用や使用(転用) ・農林水産省令で定める場合 | ||
| ・国または都道府県が権利 を取得する場合 ※ 農業委員会の許可は不要 だが、遅滞なく届出を行う 必要があるケース ・遺産分割、相続等による 取得 ・民事調停法による取得 | 国または都道府県が地域振興上または 農業振興上の必要性が高い施設のため に権利を転用・取得する場合 | ||
| ・採草放牧地の転 用 ・2アール(200㎡) 未満の自己所有の 農地を農業用施設 等に供する場合 | ー | ||
| 市街化区域内 の特例 | なし | あらかじめ農業委員会に届け出ること で許可が不要になる | |
| 罰則 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | ||
過去問などで農地法の問題を解いたら、不明点をその都度比較表で確認するようにしましょう。繰り返し解いていけば、それぞれの適用対象について自分の中で明確に区別できるようになります。
例外的なケースばかりに目が行きがちですが、まずは原則を抑えてください。それぞれの条文の適用対象や許可権者を正確に区別した上で、許可が不要になる例外的なケースを頭に入れていきましょう。
3-2. 過去問で出題形式やひっかけポイントを理解する
農地法で確実に1点確保したいのであれば、宅建士の過去問学習を入念に行いましょう。
農地法の3条・4条・5条に関する比較表を自分なりに作成したとしても、それをただ眺めているだけでは得点力は身につきません。インプットも重要ですが、身につけた知識を得点に結びつけるためには、過去問と参考書を行ったり来たりすることが重要になります。
特に、宅建士試験では過去に出題された問題が繰り返し出題される傾向にあります。農地法についても、過去問で出題された問題を中心に勉強すれば、本番でも得点できる可能性が高くなるでしょう。
農地法は例年1問しか出題されないため、建築基準法や都市計画法などよりも問題に触れる量が少なくなりがちです。出題傾向やひっかけポイントなどを掴むためにも、少なくとも直近10年分くらいの過去問は解いておきましょう。
※宅建の独学合格について詳しく解説している記事はこちらです。
→ 宅建にゼロから独学合格は可能?きつい?一発合格を目指すための戦略
※宅建の独学合格の勉強法ついて詳しく解説している記事はこちらです。
→ 宅建士試験に独学で合格するための効率の良い勉強法とは?後悔しないための注意点も解説
※宅建合格の勉強時間ついて詳しく解説している記事はこちらです
→ 【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
4. 受験指導校を活用して暗記ではなく理解を伴った学習を
農地法に限らず、法令上の制限が苦手だったり宅建業法で満点を狙ったりしたい場合には、受験指導校の質の高い講義を受けることをお勧めします。
宅建士試験では基本的に複雑な内容の問題は出題されません。基礎的な内容を理解していれば誰でも合格できる試験です。しかし、法律の初学者が独学で試験に挑もうとすると、参考書を読んでも理解できない場合や、試験では重要ではない部分にばかり時間をかけてしまう恐れがあります。
受験指導校なら、試験で得点できる知識を噛み砕いて説明してくれるので、講義を受けるだけで自然と本番で得点するための力が身につきます。「講義と過去問だけで合格できる」と安心できれば、試験当日まで高いモチベーションを維持できるでしょう。
場合によっては暗記が必要になる場面もありますが、法律の学習は基本的に理解を伴う暗記でないと得点力が身につきません。仮に未知の問題が出題されたとしても、規制の趣旨やこれまでの出題傾向等を踏まえて正誤判断する力を身につけておく必要があります。宅建士試験に早期に合格したいなら、ぜひ受験指導校の活用を検討してみてください。
5. まとめ
◉ 農地法で確実の得点するためには、3条・4条・5条の区別をすることが重要
◉ 条文の区別をする際は比較表を使うと覚えやすい
◉ 過去問学習や受験指導校の講義を活用して理解を伴った暗記を
宅建士試験では、「法令上の制限」の分野において農地法の問題が1題出題されます。1問しか出題されないことやとっつきにくい内容であることから捨て科目にしてしまう人もいますが、頻出分野である条文に絞って勉強すれば、比較的短時間で得点源にすることも可能です。
出題は基本的に3条・4条・5条の許可に関するものに限られているので、過去問学習を通してそれぞれの条文の区別についてしっかり勉強しましょう。
宅建士資格を取得できれば、人生を大きく変えることができるかもしれません。宅建士試験対策には、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。「宅建士合格講座」の内容・特長については、下記動画にて井内絢也講師が詳しくお伝えしています。初めての法律資格試験として、宅建士試験を目指そうとしている方、行政書士試験、他資格などのWライセンス取得を目指している方は、是非ともご視聴ください。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。
◉本試験の分析を徹底して行い、重要事項はもちろん、出題され易いテーマや、合格後の実務を見据えて、把握しておいた方が良い個所を重点的に学習
◉受験生のビジョンに合わせた「3コース」をご用意
◉ゼロから宅建士試験合格を目指せる「スタンダードコース」
◉難しい「権利関係」の講義時間を手厚くした「スタンダードコースプラス」
◉民法の学習経験者を対象とした「法律既修者コース」
◉分かりやすい講義でテキストを解説するので理解できる
◉講義内で問題の解き方もマスターできる
◉試験傾向を徹底分析して出題されやすいテーマを効率良く講義していくので結果、学習時間が少なくて済む
◉1コマ30分でスキマ時間でも勉強可能
◉スクーリング(4時間)やオンライン質問会(2回)もあるので、わからないことは講師に直接質問が可能など、受講生からの要望に応え、独学のデメリットも解消するため、講座全体を徹底的に改良しました。2025年の宅建士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾をご活用ください。
→2025年 宅建士合格講座

著者:伊藤塾 宅建士試験科
伊藤塾宅建士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、宅建士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。



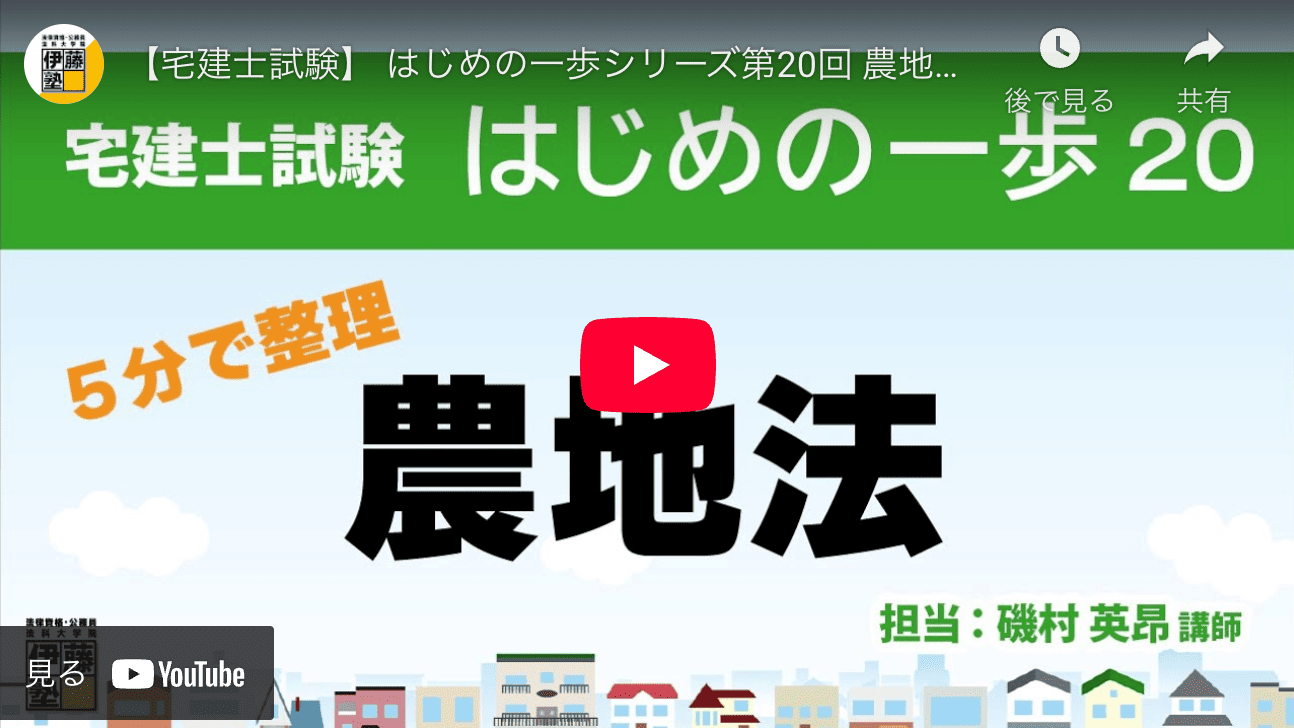
.png)













