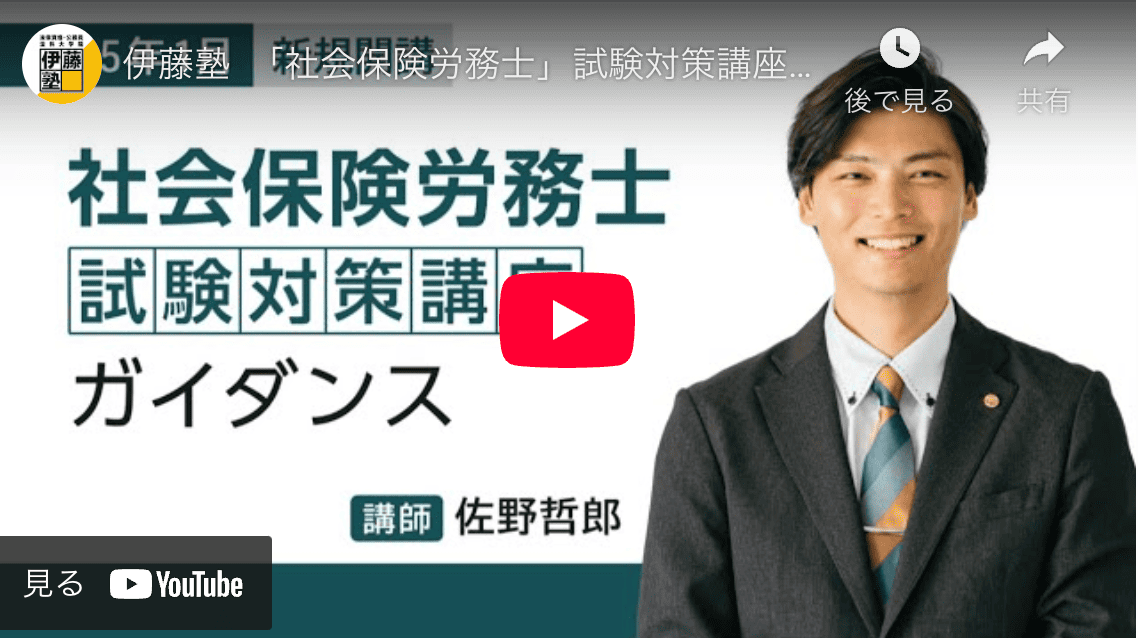社労士の独占業務とは?1号業務・2号業務の詳細と今後の展望を解説

社会保険労務士(以下、社労士)は、労働や社会保険に関する専門家として、多岐にわたる業務を担っています。なかでも、社労士にしか行えない「独占業務」として、1号業務(手続代行)・2号業務(帳簿作成)・紛争解決手続代理業務が法的に定められています。
本記事では、これら独占業務の詳細や、AIの進化に伴う社労士業務の将来性について詳しく解説します。
【目次】
1.社労士に独占業務はある?
2.社労士の独占業務とは
2-1.手続代行業務(1号業務)
2-2.帳簿作成業務(2号業務)
2-3.紛争解決手続代理業務
3.社労士の3号業務は独占業務ではない?
4.社労士の独占業務侵害になる具体例
4-1.コンサルティング会社が行う助成金申請手続
4-2.グループ会社間で行う労働社会保険手続業務
5.社労士の独占業務侵害をした場合の罰則
6.AI時代における社労士の独占業務の将来性
7.まとめ
1.社労士に独占業務はある?
社労士は業務独占資格で、いくつかの独占業務が社会保険労務士法に規定されています。
独占業務とは、その資格を有する者でなければ携わることができない業務のことをいい、無資格者が行うと罰則が適用されることがあります。
2.社労士の独占業務とは
社労士の業務は、社会保険労務士法第2条1項1号〜3号、2項で定められており、そのうち1号・2号業務については第27条で以下のように定められています。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行ってはならない。
また、紛争解決手続代理業務についても、第2条2項の中で以下のように定められています。
つまり、1号業務・2号業務・紛争解決手続代理業務は、社労士にしか行えない「独占業務」として法的に定められているのです。
それでは、1号業務・2号業務・紛争解決手続代理業務とは具体的にどのような業務なのか、3つの独占業務について詳しく解説していきましょう。
2-1.手続代行業務(1号業務)
1号業務とは、労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成したり、その作成した申請書等を代行してしかるべき行政機関へ提出する業務のことをいいます。具体的には以下のような業務が挙げられます。
【従業員の入退職時に必要な対応】<入社時>
・ハローワークへ、雇用保険の資格取得届の提出
・日本年金機構へ、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得届の提出
<退職時>
・ハローワークへ、雇用保険の資格喪失届・離職証明書(離職票の発行に必要になるもの)の提出
・日本年金機構へ、社会保険資格喪失届の提出 など【従業員が病気や出産で長期休業する場合に必要な対応】
・病気やけがによる場合 …協会けんぽ等へ、傷病手当金の支給申請
・出産による場合 …日本年金機構へ、産休取得申請書の提出/協会けんぽへ、出産一時金の支給申請書提出
・育児による場合 …ハローワークへ、育休取得申請書等の提出 など【助成金の申請書作成・代理申請業務】
雇用保険料を財源とする助成金(雇用調整助成金、キャリアアップ助成金など)の申請書の作成や行政機関への提出
2-2.帳簿作成業務(2号業務)
2号業務とは、労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成・賃金台帳の作成請負のことをいいます。
帳簿とは主に「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」「年次有給休暇取得管理簿」という4つの帳簿を指し、労働基準法という法律によって企業が作成するよう義務付けられています。いずれも、企業と従業員のトラブルを避けるために重要な帳簿書類です。
【労働者名簿】従業員の情報を一覧でまとめたもの。
企業が従業員の管理をしっかり行うために必要。【出勤簿】
従業員の出勤日や、始業終業時刻が記録されたもの。
勤務時間を正確に把握し、給与計算や労働基準法上のルールを守るために必要。【賃金台帳】
従業員に支払った給与や手当の内容を記録したもの。
給与支払いに関するトラブルを未然に防ぐために必要。【年次有給休暇取得管理簿】
各従業員の有給の使用状況や残日数が記録されたもの。
企業が従業員が適正に有給を使用しているか把握し、必要に応じて使用を促すために必要。
このほか、就業規則や各種労使協定の作成業務も2号業務に含まれます。
その企業で働くためのルールブックのようなもので、勤務時間や休憩時間・休日、給与の計算方法・支払方法、解雇・退職のルールなどが記載されたもの。
常時10人以上の従業員がいる企業には作成が義務付けられており、労働基準監督署に届出が必要。【36協定】
労使協定の代表例として、従業員に法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超えて働いてもらう場合に必要な36協定があります。企業が従業員に対して時間外労働(残業)を指示できる時間の上限や、残業が必要な理由を定めておきます。 労使協定は、企業と適正に選ばれた労働者代表者との間で締結されます。
参考:社会保険労務士会連合会
2-3.紛争解決手続代理業務
社労士のなかでも「特定社労士」という資格を持つ人だけができる業務として、紛争解決手続代理業務があります。
紛争解決手続代理業務とは、企業と従業員との間でトラブルが発生した際、特別な資格を持った社労士(特定社労士)が当事者の代理人として裁判外でトラブル解決のサポートを行うものです。このような紛争解決手続代理業務についても、社労士の独占業務とされています。
※特定社労士に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。
→特定社会保険労務士とは?社労士との違いや資格取得の方法を徹底解説
3.社労士の3号業務は独占業務ではない?
社労士の業務は、社会保険労務士法第2条1項1号〜3号で定められていますが、3号業務は独占業務ではありません。3号業務とは、労務管理や社会保険などに関する相談、アドバイス、コンサルティング業務を指します。
具体的には以下のようなものがあげられます。
【労働時間や残業管理についての相談】「従業員に長時間労働をさせないために、労働時間をどう調整すればいい?」
労働基準法をもとに、適切なシフトの組み方や残業時間の管理方法をアドバイスする。【職場環境改善のアドバイス】
「職場でハラスメントが起きているようだが、どう対処すべき?」
ハラスメント防止のための管理職向け研修資料の作成や、就業規則の改訂案を提示する。【人事評価制度や賃金体系の見直し】
「従業員の仕事に対するモチベーションを向上させて、生産性を高めたい」
公平性に配慮した人事評価制度の導入や、給与テーブルの作成を行う。
3号業務は社労士資格がなくても行うことができますが、上記のとおり労働関係法令に関する深い知見や経験が求められるため、社労士に依頼するのが安心と考える企業は少なくないでしょう。
4.社労士の独占業務侵害になる具体例
社労士の独占業務侵害の事例として、他士業者(弁護士を除く)による助成金等の申請や帳簿の作成などがよく挙げられますが、以下のような場合も業務侵害行為になりえます。
4-1.コンサルティング会社が行う助成金申請手続
社労士や社労士法人ではないコンサルティング会社等が助成金の申請手続を行った場合、それらの申請手続は社労士しか行えないとされている業務なので、社労士法違反となります。
例えば、経営コンサルティング会社がクライアント(企業)の人材不足という課題に間してアドバイスを行っているなかで、従業員定着を目的として非正規雇用労働者を正社員化した場合などに助成される「キャリアアップ助成金」の申請を提案するとします。この場合、社労士ではない会社が行えるのはこの提案までであり、実際の申請手続業務に関しては社労士にしか行うことができません。
※社労士の独占業務とされている助成金申請業務は、労働諸法令に基づく場合に限ります。また、他の法律により社労士以外の者が行うことができる旨定められている場合を除きます。
4-2.グループ会社間で行う労働社会保険手続業務
グループ会社の社員に関する入退職手続や各種給付などの労働社会保険手続を、一括して1つの子会社の人事労務部門に行わせているケースがあります。このケースでは、前提として親会社と子会社は別の法人格であり社労士法27条では「他人」の関係です。無資格である子会社が、「他人」である親会社の労働社会保険手続(社労士の独占業務)を行うと、社労士法違反となります。
「他人」である会社の労働社会保険手続を受託できるのは、社労士もしくは社労士法人だけなのです。
出典:全国社会保険労務士会連合会|業務侵害行為と業域保全
出典:全国社会保険労務士会連合会
5.社労士の独占業務侵害をした場合の罰則
社労士の独占業務(1・2号業務・紛争解決手続代理業務)は、社労士法によって、社労士や特定社労士のみが行えると定められています。この業務を無資格の者が行った場合、法律で罰則が科されることがあります。
【社会保険労務士法第27条第1項】「社会保険労務士の業務を行う資格を有しない者が、第2条第1項各号に掲げる業務を行ったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
社労士法に定められた独占業務は、専門的知識や法律の理解が必要です。無資格者が行うと労働者や企業に不利益を与えるリスクがあり、労働者や企業の権利を守るため、違反時には厳しい罰則規定が置かれているのです。
参考:社会保険労務士法第27条,第32条の2
6.AI時代における社労士の独占業務の将来性
近年、人工知能(AI)の進化により、さまざまな業界で業務効率化や自動化が進んでいます。社会保険労務士(社労士)の分野でも、労務管理や手続き業務の一部がAIやクラウドサービスで代替可能となりつつあります。しかし、社労士の独占業務は高度な専門性と倫理観が求められる分野であり、AIだけでは代替できない部分が多いのも事実です。
以下に、それぞれの独占業務についての将来性を考察します。
【1号業務(手続代行)】今後、書類作成自体は自動化が進む可能性があります。すでにクラウド型の労務管理ツールが普及し、多くの事務処理を効率化しています。ただし、複雑なケース(法改正の影響、特殊な事業形態など)の判断はAIに任せられず、社労士の専門知識が必要です。また、書類提出の代理業務は社労士の独占業務であり、AIが関与できてもその最終的な責任を負うのは社労士です。
【2号業務(帳簿作成)】AIはこれら帳簿の生成や更新をスピーディーに行えますが、内容の正確性や法的な適合性を保証するには社労士の確認が欠かせません。特に、法改正が頻繁に行われる日本の労働法制では、AIだけで最新のルールに対応することは難しいため、社労士の介在が重要です。
【紛争解決手続代理業務】この分野は、AIが直接関与することが難しい領域です。労働トラブル問題は感情的な側面が大きく、当事者間の交渉には共感力や調整能力が求められます。AIが提供するデータ分析や法的アドバイスはサポートに過ぎず、実際の交渉や説得は社労士が担うべき重要な役割です。
AIの登場で、単純な事務作業は効率化されることは間違いありません。しかし、それにより社労士がより高度な専門業務に集中できる環境が整うと考えることもできます。また、独占業務ではありませんが、3号業務としてのコンサルティング業務は、AI時代において特にその重要性が高まる領域です。
企業の労務管理や働き方改革、ハラスメント対策などの分野では、個別の事情を考慮した柔軟な提案が必要です。AIはデータを提供することは得意ですが、企業の文化や従業員の状況に合わせた具体的な改善策を示すことは現時点では難しいといえます。こうした課題に対し、社労士が提供するコンサルティングは、企業の成長を支えるために欠かせないサービスとなります。
社労士は専門知識だけではなく、「人と向き合う力」「問題を解決する力」「学び続ける力」を兼ね備えるべき職業です。これらのスキルを磨くことで、AI時代においても企業や労働者から必要とされる信頼性の高い専門家として活躍できるでしょう。
7.まとめ
最後に、今回の記事の要点をまとめます。
◉社労士の独占業務には、1号業務・2号業務・紛争解決手続代理業務の大きく3業務がある
◉社労士の独占業務を侵害した場合、懲役や罰金の厳しい処罰規定が置かれている
◉社労士は今後AIが普及しても、その専門性から企業・労働者から求められ続ける資格である
社労士という仕事は、企業と従業員の間に起きる様々な問題を解決するための専門的知識やコミュニケーション力、共感力が必要な職業です。簡単な仕事ではありませんが、だからこそ希少性、社会的価値が保たれているともいえます。
あなたも自分の市場価値を高めるため、社労士試験に挑戦してみませんか?社労士試験は、着実に正しい努力を積み重ねることで必ず合格できる資格試験です。
伊藤塾では、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士 合格講座を開講中です。
社労士の仕事に興味を持った方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科
伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。