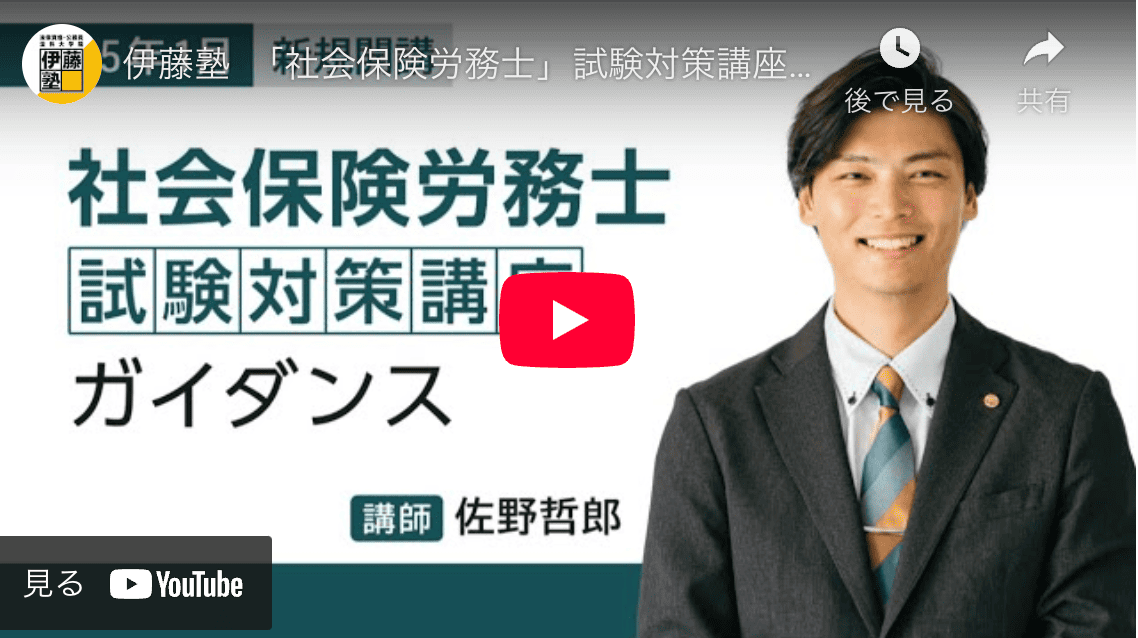社労士の事務指定講習は働きながら受講できる?落ちる可能性など詳しく解説

社会保険労務士(以下、社労士)の試験合格者にとって、実務経験がないことが登録への大きな壁となる場合があります。 そんな時のために用意されているのが、社労士の「事務指定講習」です。
事務指定講習は、社会保険労務士の試験に合格したものの、社労士登録をするために必要な「2年間の実務経験」を持っていない人が、社労士登録を行う要件を満たすためのステップです。
この講習は、社労士試験合格者が実際に社労士として活動を開始するために必要な知識やスキルを身につけることを目的に、実務経験の代わりとして実施されています。
当記事では、事務指定講習の概要から、講習の内容である通信指導課程とeラーニングの詳細、さらにはメリットや注意点、講習受講後の社労士登録の流れまでを包括的にご説明します。
今回の記事を読むことで、社労士登録の要件である事務指定講習についての理解が深まり、社労士試験合格後の選択肢の幅を広げることができるはずです。社労士の事務指定講習について「具体的な内容がわからない」「もっとよく知りたい」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1.事務指定講習の概要
1-1.日程
1-2.講習の対象者
1-3.講習を受講するための費用
1-4.講習内容
1-5.申込方法
2.通信指導課程の詳細
3.eラーニング講習の詳細
4.事務指定講習のメリット
4-1.修了すれば社労士登録の要件を満たせる
4-2.難易度は高くない
4-3.実務に沿った学習ができる
5.事務指定講習の注意点
5-1.実務経験と同等ではない
5-2.働きながら受講する時のスケジュール調整
5-3.受講料が掛かる
6.事務指定講習の修了とは
6-1.修了の要件
6-2.講習に落ちる人はいるのか
7.指定講習修了後の社労士登録の流れ
8.事務指定講習を受ける人の特徴
9.事務指定講習を受けない人の特徴
10.まとめ
1.事務指定講習の概要
事務指定講習は、正式名称を「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」といい、厚生労働大臣の認定を受けた全国社会保険労務士会連合会が毎年1回実施しています。この講習は、社労士登録の要件である「2年間の実務経験」がない社労士試験合格者が、社労士登録の資格を得るために用意されたプログラムです。
修了することにより、受講者は社労士登録に必要な条件を満たすことができるため、社労士としての業務を開始するための準備を進めることができます。
(参考:第44回 労働社会保険諸法令関係事務指定講習 受講案内)
1-1.日程
事務指定講習は年に1回の決められた期間中に募集が行われ、申込後は決められたスケジュールに沿って受講をしていきます。受講を希望する人は、全国社会保険労務士連合会がホームページで公表している募集スケジュールに従って必要な手続きを行い、申し込みをすることが可能です。
開催時期は年により異なりますが、おおよその期間は毎年同じです。参考までに、2024年度については下記日程で行われました。
・申込期間:2024年11月8日から11月29日・通信指導課程:2025年2月1日から4ヶ月間
・eラーニング講習:2025年7月11日から3ヶ月間
1-2.講習の対象者
講習の対象者「社労士試験に合格した者であって、まだ社労士の登録を受けていない者」です。すでに社労士登録をされている人は、受講することができません。
また、社労士試験合格後直後ではなく、年数が経っていたとしても、試験合格に有効期限はないため、講習に受講することができます。講習に定員は設けられておらず、対象者であれば募集期間内に申し込みをすることで誰でも受講することが可能です。
1-3.講習を受講するための費用
講習の受講費用は、税込77,000円です。
この費用には、通信指導課程とeラーニング講習で使用する講習資料も含まれています。
しかし、eラーニングを受講するための通信環境費用や、通信指導課程の課題を提出するための郵送費用は含まれていないため、必要に応じて別途で支払う費用が発生します。
1-4.講習内容
事務指定講習は、前半に通信指導家庭、後半にeラーニングという、2種類の形式の学習プログラムで構成されています。通信指導課程では、送られてきた教材を読んで自己学習して課題に取り組み、郵便による通信教育方式により添削指導を受けます。
eラーニングでは、社労士業務に関連する8科目について動画学習を行い、確認試験を通して知識を定着させます。2つの講座の具体的な内容については、後ほど詳しく説明します。
1-5.申込方法
講習に申し込みをする際は、振込用紙に必要事項を記入して、受講費用を全国社会保険労務士会連合会に支払います。詳細な記入事項や申込方法は、申込期間中に全国社会保険労務士会連合会のホームページにて公開されています。
2.通信指導課程の詳細
通信指導課程は、送られてきた講習教材を元に、社労士の実務で使用する書式を用いて課題に取り組む内容です。事例ごとに用意された60枚ほどのレポート課題をこなし、郵送で提出します。提出書類は添削されて返送されます。
講習は試験ではないため、レポートの出来栄えや理解度などで修了ができなくなることは殆どありません。ただし、期限内に提出がされないと修了が認められないため、翌年に改めて申し込んで受講することが必要になります。
通信指導過程の期間は4ヶ月間で設定されているため、その期間内にすべてのレポートを提出しなければなりません。あらかじめ送られてくる教材を使用し、好きな場所で自分のペースで学習を進めることができるため、集合して行う講習と比較すると、働きながらでも受講しやすくなっています。
3.eラーニング講習の詳細
eラーニング講習は、社労士試験に出てくる科目の講義をオンデマンド動画で受講し、理解度を確認するテストを受けることで、社労士業務の理解を深めるためのプログラムです。
通信指導課程と同様に、好きな場所で自分のペースで受講をすることができるため、自分のライフスタイルに合わせて学習スケジュールを組むことができます。
eラーニングの動画は、1科目3時間で構成され、全8科目が用意されています。eラーニング講習は3ヶ月の期間が設定されているため、計画的に受講をすれば、確認テストを含めても時間に余裕を持って修了することができるはずです。
4.事務指定講習のメリット
次に、事務指定講習を受講する主なメリットを3つご紹介します。
4-1.修了すれば社労士登録の要件を満たせる
事務指定講習の最大のメリットは、修了することにより社労士登録が可能になる点です。
これにより、社労士登録の要件である2年間の実務経験が不足している人でも、登録をして正式な社労士として業務をするためのステップを進めることができます。試験合格後すぐに開業をしたい人や、自ら社労士業務をする必要がある人にとって、大きな魅力となります。
4-2.難易度は高くない
事務指定講習は、社労士登録の要件である実務経験の代替とすることを目的としているため、修了するための難易度はさほど高くありません。
例えば、講習中の課題やテストにおいて、すべてを完璧に正解する必要はないのです。期間内にプログラムを全て学習し終えて、必要最低限の基準をクリアすることで、修了を認めてもらうことができます。
4-3.実務に沿った学習ができる
事務指定講習では、社労士が実際の業務で使用する様式を用いたレポート課題も用意されています。そのため、社労士試験の勉強により知識を持っている講習受講者が、実務上でも戦力となり得る知識や技能を学ぶことができます。
例えば、社会保険の適用や給付に関する具体的な事例に基づいた課題も用意されており、実務のような実践的なスキルを養うことが可能です。そのため、事務指定講習を修了することにより、実務経験が不足していてもある程度スムーズに実務に移行することが期待できます。
5.事務指定講習の注意点
一方で、事務指定講習を社労士登録要件とする際には、注意しなければならない点もあります。事務指定講習の注意点を、3つご紹介します。
5-1.実務経験と同等ではない
事務指定講習は社労士登録において実務経験の代わりとなるものですが、実際の業務で得られるような実績を完全に補えるわけではありません。講習では原則的な知識や基礎的な実戦スキルを学ぶことができますが、実務ではそれよりも臨機応変な対応が必要となるケースも多々あるためです。
事務指定講習で得られるのはあくまでも実務の土台となるものであり、講習修了後も、実際の業務を通じて経験を積み重ねていくことが重要になります。
5-2.働きながら受講する時のスケジュール調整
働きながら講習を修了するためには、自らしっかりとスケジュールの調整を行う必要があります。
通信指導課程やeラーニングは、自分で受講日時を設定しながら講習を進められますが、日時の指定がないため、計画的にスケジュール管理をしないと、期間内に修了できないリスクがあります。そのため、学習時間を確保するための計画性と自己管理能力が必要です。業務の合間を縫って学習を進めるには、計画的なスケジューリングが不可欠となる点に注意が必要です。
5-3.受講料が掛かる
事務指定講習を受講するには、77,000円という、決して少なくない費用がかかります。早々に社労士としての活躍を見据えている場合には不可欠な自己投資となりますが、投資コスト分の元を取るための覚悟が必要です。
また、開業を考える際には、受講料に加え、事務所の開設や初期費用といった開業資金も必要となる可能性があります。この講習受講費用は、2年間の実務経験を積めば掛からない費用です。そのため、現在の経済状況や、今後の社労士としてのキャリアプランなどを考慮した上で、自分にとって必要かどうかを判断することが重要です。
6.事務指定講習の修了とは
次に、事務指定講習を受講した場合に、どうすれば修了となり社労士登録の要件を満たすことができるのかを説明します。
6-1.修了の要件
講習の修了要件は、通信指導課程とeラーニング講習の全課程を期間内に終えることです。
具体的には、通信指導課程において用意されたレポートを全て提出し、eラーニングにおいて用意された講義動画を視聴した上で確認テストを全て完了させることが必要です。
講習は通信指導課程とeラーニングの2種類で構成されていますが、どちらか一方のみ修了とすることはできないため、一方の修了要件を満たさない場合には、翌年に改めてどちらも受講する必要があります。
6-2.講習に落ちる人はいるのか
事務指定講習は試験ではないため、基本的に「落ちる」という概念はありません。
ただし、通信指導課程の課題が期限内に提出されなかったり、あまりにも空白が多すぎたりする場合や、eラーニング動画を全て視聴しなかったなどの場合には、修了と認められずに修了証が発行されない可能性があります。そのため、受講をする際には決められたカリキュラムを着実にこなし、計画的に学習を進めることが重要です。
7.指定講習修了後の社労士登録の流れ
講習を修了して修了証を受け取ると、社労士登録の要件を満たすため、登録申請をすることが可能になります。登録には、必要書類の準備や、登録料の納入が必要です。
登録についての詳細は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 社労士登録は必要?費用や実務経験は? 4つの種別・登録手順をわかりやすく解説
登録申請後の審査に通過すると、正式に社労士としての業務を行うことができるようになります。
8.事務指定講習を受ける人の特徴
事務指定講習を受ける人の大半は、一般的に早期に開業したいという気持ちを持っている人です。また、実務経験があるのに会社から必要な実務証明を貰うことができない人や、すぐにでも自ら社労士業務を開始する必要がある人も、講習受講により社労士登録を目指す傾向にあります。
事務指定講習は2年間の実務経験に代わるものであり、スムーズに受講が完了すれば半年程度で社労士登録の要件を満たせるため、社労士登録を急ぐ人には、非常に有用な講習であると言えます。
9.事務指定講習を受けない人の特徴
一方で、事務指定講習を受けない人の特徴としては、2年以内に社労士として開業することを目指していない人や、実務を経験しながらスキルを積んでいきたいと考えている人が多い傾向です。また、講習費用を節約したいと考え、一旦は実務経験を積む方向を選択する人も少なくありません。
講習を受けるかどうかの選択は、個々のキャリア計画や経済状況によって変わってきます。
10.まとめ
事務指定講習は、早期の社労士登録を目指す人のために設けられた制度です。
内容は実務経験の不足を補うものであり、現場での戦力となる基本的な知識やスキルを学ぶことができます。
一方で、この講習だけで完全な実務能力を得ることは難しいため、講習を受講して社労士登録をした後にも、実務を通じて継続的に経験を積むことが求められます。
受講するかどうかは個人のキャリアプランや経済状況に応じて慎重に判断する必要がありますが、内容をよく理解しておくことで、社労士合格後の選択肢の一つとして考えることができるはずです。
このように、実務経験がなくても試験合格後に早期に実務を開始できる点は、社労士という資格の魅力の1つです。
専門性を持った士業として、早くにキャリアを築きたい方は、ぜひ社労士資格の取得を検討してみてください。
伊藤塾では、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講中です。
社労士の仕事に興味のある方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科
伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。