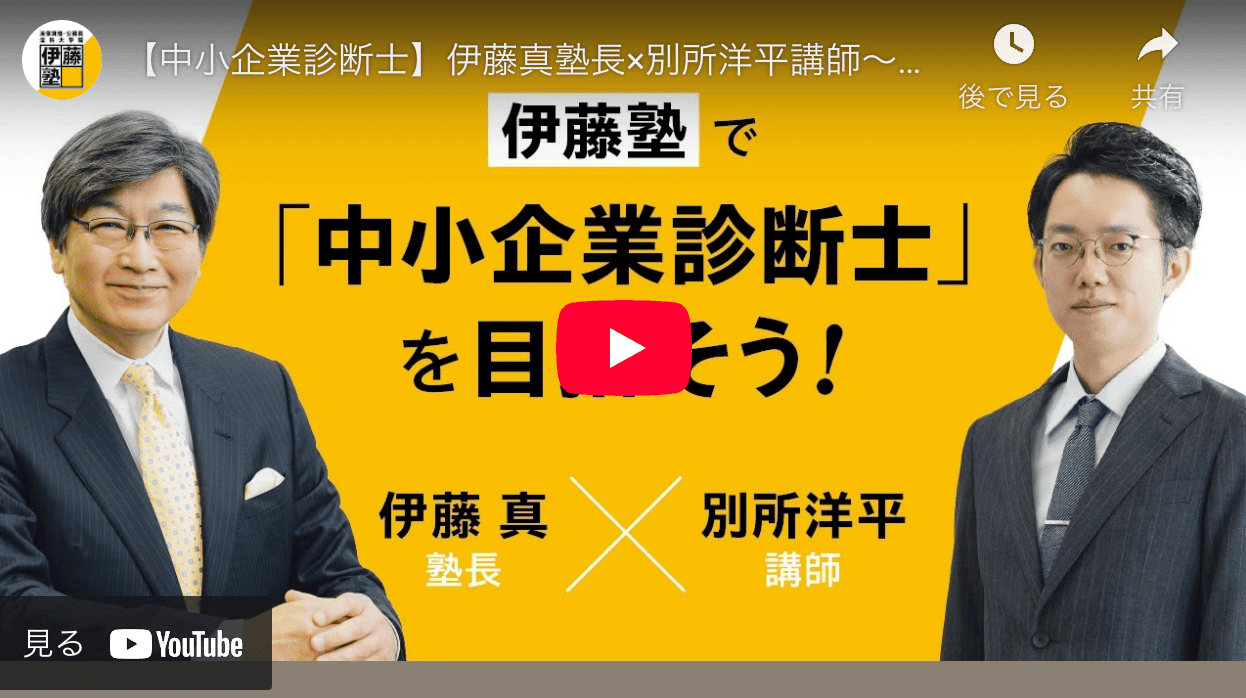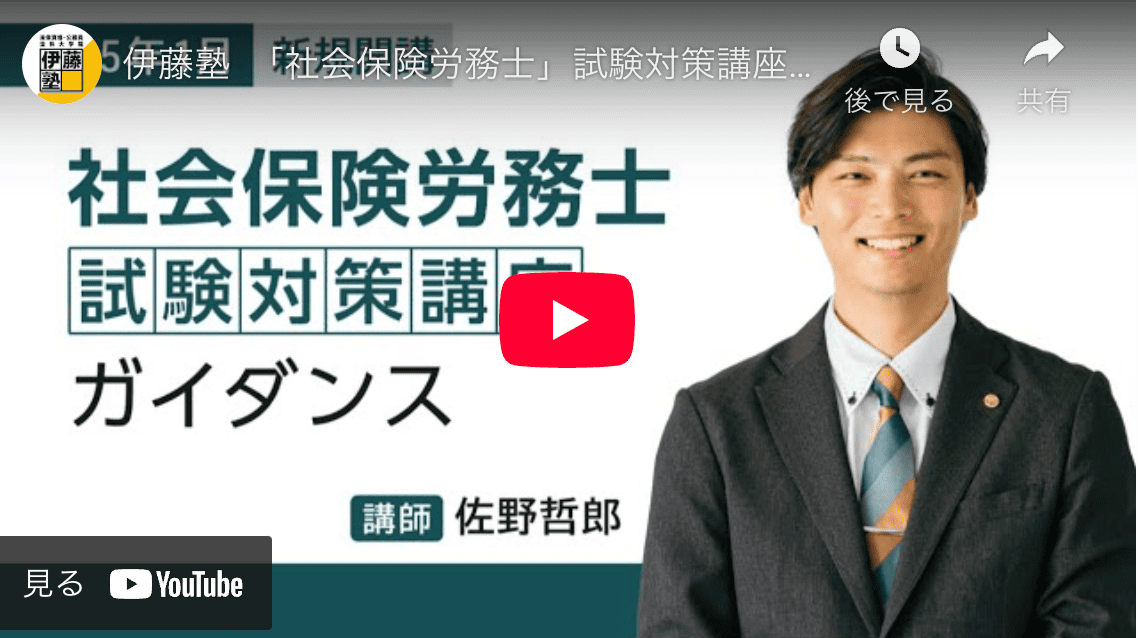社労士になれば人生変わるって本当?国家資格の専門家として生きる魅力を徹底解説

「社労士になって人生を変えたい」
「人生逆転を目指して社労士になる!」
そんな意気込みを持って資格取得を目指す方は少なくありません。
しかし同時に、
「社労士になるとどんな働き方ができるの?」
「資格を取れば食べていけるの?」
「今後は需要がなくなるからやめとけと言われたけど…」
などの不安や疑問の声も多く聞かれます。
社労士として活躍し、人生が変わったと感じている人は確かに多く存在します。ただし、その変化を実感するためには、社労士としての具体的な働き方や今後の需要をしっかりと理解しておくことが不可欠です。
この記事では、社労士になることで「人生が変わる」具体的なポイントを詳しく解説します。また、社労士としての可能性を最大限にするための心構えや必要なアクションについても具体的にお伝えしていきます。
現在の生き方を大きく変えたいと考えている方や、社労士としての働き方に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
1.社労士になると人生が変わる!4つのポイント
1-1.働き方の可能性が広がる
1-2.大幅な収入アップの可能性がある
1-3.専門家としての社会的信頼が得られる
1-4.大きな自信を得ることができる
2. 社労士になって人生を変える4つのキャリアパス
2-1.社労士として独立開業をする
2-2.勤務社労士としてキャリアを積む
2-3.副業として実務経験を積む
2-4.セカンドキャリアとして活用する
3. 「こんなはずじゃなかった」を防ぐための心構え
3-1.社労士になるだけでは人生は変わらない
3-2. 社労士の需要の変化と将来性を理解する
3-2-1.社労士では今後「食べていけなくなる」のか
3-2-2.今後の社労士に期待される業務
4. 社労士になって人生を変えるために必要なこと
4-1.開業のために必要なスキルを理解する
4-2.継続的に学習をする
4-3.実務経験を積む
4-4.資格取得後の自分を思い描く
5.おわりに
1.社労士になると人生が変わる!4つのポイント
まず初めに、なぜ社労士になることで「人生が変わる」と感じる人が多いのか考えてみましょう。
具体的なポイントは以下の4つです。それぞれ、解説していきます。
| ・働き方の可能性が広がる ・収入アップの可能性がある ・専門家としての社会的信頼が得られる ・自分を信じる力が強くなる |
1-1.働き方の可能性が広がる
1つめのポイントは、社労士になることで、働き方の選択肢を大きく広げることができることです。
例えば、現在の働く環境に不満を感じていても、転職先での待遇や自身のスキルに不安を感じ、独立や転職、副業に踏み切れない人は少なくありません。
しかし、社労士になることにより、独立や転職、副業を行うハードルを大きく下げることができます。専門性を持った資格であるからこそ、新たなキャリアへの一歩を安心して踏み出すことができるのです。
具体的には、次のようなキャリアへの方向性が広がります。
◉独立開業専門性が裏付けされた社労士としての開業が可能となるため、一般的な企業や独立よりも顧客や業務獲得のハードルを下げることができます。
◉転職
社労士は人事労務に関する専門的な知識を持ち、独占業務がある資格であるため、企業にとって大きな戦力となります。そのため、就職や転職において有利に働く部分が多く、大きなアドバンテージとなる場合が多いです。
◉副業
社労士という肩書き自体に専門家としての信頼があるため、社会保険に関する相談業務や労務関連のライティングなど、専門性を求められる業務を獲得しやすくなります。
このように、社労士になることによって、働き方の可能性を広げることができるため「人生が変わる」きっかけを作ることができるのです。
1-2.大幅な収入アップの可能性がある
2つめのポイントは、収入を大幅に上げられる可能性があることです。
例えば、開業をした場合であれば、自分の顧客獲得の達成率や業務の成果がダイレクトに収入に結びつきます。会社員とは異なり、自身の努力の結果がそのまま収入に反映されるため、専門性を活かしたサービスを適切に提供することにより、大幅な収入増も期待できます。
企業に勤めている場合は、社労士の資格手当が支給されたり、専門知識を活かして人事労務部門でキャリアアップを目指せる可能性があります。転職活動においても、社労士の資格は人事労務の専門知識を証明する強力な武器となり、給与交渉を有利に進められる可能性も高まります。
さらに、副業をする場合でも、専門性を持った業務を獲得することにより、一般的な副業と比べてより高い報酬を得ることが可能です。
このように、社労士になることで様々な形での収入アップが期待でき、経済的な余裕が持てる可能性が高くなります。
1-3.専門家としての社会的信頼が得られる
3つめのポイントは、専門家としての社会的信頼を得ることができることです。
社労士になることにより、会社や周囲の人々から、専門性や資格試験合格までの努力を客観的に認めてもらうことができます。
社会的信頼を得ることは、以下のような変化をもたらします。
| ◉ビジネス面 ・顧客への信頼を得やすくなる ・提案や意見が受け入れられやすくなる ・相手が前向きに耳を傾けてくれる ◉キャリアの拡大 ・転職や昇進の可能性が広がる ・専門性のある業務を任されやすくなる ◉人脈とネットワークの拡大 ・信頼できる人物として認められる ・周囲からの協力を得やすくなる |
これらのメリットは、社労士として活躍の場を広げ、多くの経験を積むための大きな力となります。
誠実に業務に取り組むことで、さらに信頼は深まり、良い循環を生み出していくでしょう。
周囲から信頼される社労士になることは、業務を円滑に進めるだけでなく、人生に大きな変化と成長をもたらす重要なステップとなります。
1-4.大きな自信を得ることができる
4つめのポイントは、資格試験に合格することにより大きな自信を得ることができるという点です。
社労士試験は合格率が10%を下回ることもある難関資格です。この試験に合格するためには、平均すると1000時間程度の学習時間が必要だと言われています。
だからこそ、合格を勝ち取ったときには、自分の努力を心から誇れるようになります。
また、資格試験の学習を通じて得られる達成感は「やればできる!」という自信に繋がり、その後の人生の新たな挑戦にも活きていくでしょう。
社労士試験の勉強で学習習慣が身に付くことにより、新しい分野の学習にも前向きに取り組めるようになり、さらなる成長につながります。
社労士資格取得に向けた学びのプロセスそのものが、あなたの人生に確かな自信と新しい可能性をもたらしてくれるのです。
2. 社労士になって人生を変える4つのキャリアパス
次に、実際に社労士になって「人生を変える」ための働き方を4つご紹介します。
| ・社労士として独立開業をする ・勤務社労士としてキャリアを積む ・副業として実務経験を積む ・セカンドキャリアとして活用する |
それぞれ解説していきましょう。
2-1.社労士として独立開業をする
1つめは、社労士として独立開業をする働き方です。
日本では会社員として企業に所属して働く人が大半を占めていますが、社労士として独立開業することは、働き方を大きく変化させることになります。
独立開業によって柔軟な働き方が可能になり、自身のライフスタイルに合わせて業務をすることができるようになります。さらに、営業活動や業務への取り組みが直接的に収益に結びつくため、努力が目に見える形で収入につながります。
事務所を運営していくことに対する責任も伴いますが、自分が事業を動かしているというやりがいも感じられるため、理想の自己実現を叶えることができる働き方です。
自分の裁量で経営判断を行い、顧客との関係を築きながらビジネスを成長させていく過程は、会社員としての働き方とは全く異なる経験であり、「人生を変える」ほどの大きな挑戦となるはずです。
2-2.勤務社労士としてキャリアを積む
2つめは、勤務社労士としてのキャリアを積むという働き方です。
雇用という安定した環境の中で経験を積むことで、着実に社労士としての専門性を高めていくことができます。
勤務社労士としての選択肢は、1つの企業の中で人事労務を担当するプロフェッショナルとして働くか、社会保険労務士法人に勤める社労士として専門的な業務の経験を積んでいくという、主に2つの道が考えられます。
◉企業内での活躍人事労務のプロフェッショナルとして社内で重要な役割を担う
◉社労士法人での勤務を通じて専門的スキルを磨く
独立開業をするよりも多くの顧問先に接触することが可能で、幅広い業務を経験することが可能
どちらにおいても、特定分野のエキスパートとして専門性を確立できるため、その後の転職や開業を検討している場合にも役立つ経験を積むことができ、自身のキャリアアップにつなげることができます。
独立開業と比較すると、安定性と専門性を両立させながらスキルアップをして人生を変えるきっかけにつなげることができる生き方です。
2-3.副業として実務経験を積む
3つめは、専門性を活かした副業を開始するという働き方です。
社労士として行う副業は、専門知識を活かした選択をすることができるため、一般的な副業と比較すると、効率的に収入を得やすいです。労務相談や就業規則の整備など、資格を持つ専門家としての業務を請け負うことで、限られた時間であっても高水準の報酬を目指すことができます。
また、副業を通じて実務経験を積むことにより、さらに専門知識を深め、自分自身のスキルアップにもつなげることができます。 多様な働き方の中で、社労士としての人脈を広げ、独立開業など新たなキャリアを切り開くきっかけにもなります。
副業は、収入増加だけでなく、自己成長や働き方の選択肢を広げるという意味でも、人生をより豊かにするための有効な手段となります。
2-4.セカンドキャリアとして活用する
4つめは、社労士をセカンドキャリアとする働き方です。
社労士は、会社員としてある程度の年数を重ねた後や、定年後のキャリアとしても注目されている職業です。50代、60代以降でも活躍できる専門職として、セカンドキャリアを考える多くの方にも注目されています。
2024年度の試験においても、受験者の4人に1人以上が50歳代以上となっており、ここからもミドルシニアと呼ばれる世代で受験に臨んでいる人の多さがわかります。
社労士がセカンドキャリアとして注目される理由としては、次のような理由が挙げられます。
・年齢を問わずスタートして活躍できる・これまでの職務経験を活かせる可能性がある
・独立開業をすることにより柔軟な働き方ができる
・生涯現役で居続けることができる
さらに、セカンドキャリアとして活用をする場合には、定年までに勤めた業界や分野の経験と社労士としての専門知識を組み合わせることで、より付加価値の高いサービスを提供することもできる点も魅力の1つです。
企業での経験を持つ社労士は、その業界特有の悩みや問題点を理解し、実践的なアドバイスができる点で、高い評価を得やすいのです。
まさに、豊かで充実した人生の第二章を築く非常に魅力ある専門資格といえるでしょう。
3. 「こんなはずじゃなかった」を防ぐための心構え
社労士になったことで「人生が変わった」と感じる人がいる一方で、「人生が変わると期待したのに、全く変わらない…」と感じる人も一定数は存在しています。
次に、人生が変わらなかった…と感じる人の共通点と、そのように感じてしまうことを防ぐポイントをお伝えしていきます。
3-1.社労士になるだけでは人生は変わらない
社労士になっても人生が変わらないという人の多くが、試験に合格したり社労士登録をするだけで人生が変わるはずだと誤った期待をしているように感じます。
社労士になることは、人生の選択肢を広げて人生を変えるきっかけになりますが、すぐさま「人生が変わる」わけではありません。
社労士になることをゴールにするのではなく、社労士という資格をどのように活用していくかが非常に重要になります。
資格を取得した後にどのようにキャリアを築き上げていくか、自分のスキルをどう磨き上げ、どんな方向で活用していくかをしっかりと考え実行することにより、人生が変わる実感を得ることができるのです。
3-2. 社労士の需要の変化と将来性を理解する
社労士として活躍をして「人生が変わった」と言えるようになるためには、社労士業界の現状と変化、今後の需要を正しく理解することが重要です。
3-2-1.社労士では今後「食べていけなくなる」のか
AI化やデジタル化の進展により、給与計算や行政手続きといった従来の定型業務は自動化が進んでいます。このような業務環境の変化から「社労士になっても食べていけない」「将来性がない」という声も上がっているのが現状です。
しかし、社労士に求められる本質的な価値は、むしろ今後さらに高まると考えられます。
3-2-2.今後の社労士に期待される業務
社労士に求められる業務は、従来の手続き代行業務から、企業ごとに合わせた柔軟なサービスへと変化しています。社会的な背景や企業が抱える課題を踏まえ、社労士に期待される役割としては、以下のようなことが考えられます。
・労働関係法令の改正への対応・テレワークや副業などの個別多様な働き方への対応
・複雑化する労務関連の法令順守への対応
・働きやすい職場環境の整備
・各企業の実情に合わせた人材育成や職場環境の改善提案
・メンタルヘルス対策や労使間トラブルの未然防止
このように、社労士の業務は定型業務から付加価値の高いコンサルティング業務へとシフトしており、これからも専門家の必要性は高まっていくと考えられます。
このような社会のニーズと企業の求めるものを理解することで、社労士として目指す方向が明確になり、人生の変化を実感できる働き方ができるようになります。
4. 社労士になって人生を変えるために必要なこと
最後に、社労士として「人生を変える」ために、資格試験の合格や社労士登録以外に必要なことを4つお伝えします。
| ・開業のために必要なスキルを理解する ・継続的に学習をする ・実務経験を積む ・資格取得後の自分を思い描く |
それぞれ解説していきましょう。
4-1.開業のために必要なスキルを理解する
社労士としての働き方として、誰しもが思い浮かべやすいものが独立開業かと思います。独立開業は社労士として代表的なキャリアパスですが、ただ単に社労士になるだけでは活動を続けていくことができない可能性が高くあります。
事務所を開業して継続していくためには、専門的な知識や経験以外にも、以下のようなスキルが不可欠です。
◉営業力
どんなに能力が高い社労士であっても、ただ待っているだけではお客さんは増えていきません。自分と契約をすればどのようなメリットがあるかを各所に宣伝し、自ら顧問先を探して仕事を獲得する営業力が不可欠です。
◉コミュニケーション能力
顧客に対して適切に対応するためには、専門知識を持っているだけでなく、それを相手にわかりやすく伝える能力が重要です。
相手が人事労務に関する悩みを持っていたとしても、それに対する解決策を提示するためには、適切なコミュニケーションができなければ解決に導くことは難しくなります。相手の立場に立って「悩みを正しく聞き出すこと」「専門的な知識をわかりやすく説明すること」ができる能力が不可欠です。
◉経営管理能力
開業をするということは、事務所の経営を自らしていくことになるため、事業主として経営していくためのスキルが不可欠です。
具体的には、財務管理のための知識、事業活動を継続させるためのリスク管理や経営戦略の立案などが求められます。また、顧客獲得のためのマーケティング能力も重要な要素となります。
4-2.継続的に学習をする
社労士として活躍をし続けるためには、社労士になったあとも継続的な学習が不可欠です。
「社労士への登録」はゴールではなく、プロフェッショナルとしての第一歩に過ぎません。
人事労務という分野は、社会情勢や働き方の変化に応じて頻繁に法改正が行われ、実務上の解釈や運用も日々進化しています。
例えば、近年では育児介護休業法の改正やフリーランス保護新法の施行、ハラスメント対策の強化など、法改正等による企業のコンプライアンス対応が重要視されています。これらの改正や実情を理解して対応ができなければ、顧客に適切なアドバイスを提供することはできません。
そのため、社労士には常に最新の法改正をキャッチアップし、実務への影響を理解した上で、クライアントに最適な解決策を提案する能力が求められます。専門書の購読や研修・セミナーへの参加、交流会での情報交換など、継続的な学習を通じて知識を更新し続けることで、周囲からの信頼も獲得することができます。
信頼される社労士として成長をすることにより、社労士としての「人生の変化」を実感することができるはずです。
4-3.実務経験を積む
社労士として登録をするためには「2年間の実務経験」が必要です。しかし、「2年間の実務経験」がない社労士試験合格者でも「事務指定講習」を受けることにより、社労士登録に必要な条件を満たすことができます。
この制度によって、実務経験がなくても社労士登録が可能となりましたが、社労士として活躍をしていくためには、多くの実務経験を積むことが必要不可欠です。なぜなら、今後の社労士に求められるのは、単なる知識だけでなく、実務経験に基づいた問題解決能力だと考えられるからです。
経験に基づいた、個別の実情に応じた解決策を見つけることや、最新の法改正に適合した手続きを行うことなどにより、顧問先からの信頼を得て社労士としてステップアップをすることができます。
このような実践を重ねることで、社労士としての成長や人生の変化を実感することができるのです。
※「事務指定講習」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→社労士の事務指定講習は働きながら受講できる?落ちる可能性など詳しく解説
4-4.資格取得後の自分を思い描く
社労士になって「人生を変える」ためには、社労士資格を取得する前からキャリアプランを思い描いておくことも必要です。
「こんな業務をしたいから社労士になりたい」
「あのような働き方をするために社労士になる!」
といった、確固たる目標を設定しておくことで、それを達成することにより人生の変化を実感することができます。
「人生を変えたいから社労士になる」といったように社労士になること自体を目標にしてしまうと、社労士になった後の人生の方向性が決まらずに、進む道を見失ってしまう可能性があります。
社労士の業務や働き方を具体的に理解した上で、自分の人生の計画に合わせて、明確な目標を持って社労士資格に臨むことで、社労士資格によって人生を変えることができるのです。
※社労士の将来性についてはこちらの記事にて詳しく解説しています。
→ 社労士の将来性を徹底解剖!AI時代に求められるスキルと今後の需要を解説
※社労士の仕事内容についてはこちらの記事にて詳しく解説しています。
→ 社労士ってどんな仕事?仕事内容や働き方のリアルをわかりやすく解説
5.おわりに
社労士になることは、人生を変える可能性を大きく秘めています。
実際に、社労士になって人生が変わったと感じる人は少なくありません。しかし、その可能性を現実のものとするためには、社労士試験に合格をし、社労士になるだけでは不足しているのも事実です。
大切なのは、資格取得の先にある「なりたい自分」を明確に描くことです。どのような社労士として、どのように働き、どのように生きていきたいのか。具体的な目標やビジョンを持ち、それを達成することにより人生の変化を実感として得ることができます。
社労士としての人生は、試験合格や登録がゴールではありません。専門知識以外にも求められる能力があり、決して平坦な道ではありませんが、社労士になることによって大きな可能性が得られることは間違いありません。
企業のあり方や個人の働き方が大きく変化する現代において、社労士の役割はますます重要になっています。常に変化を捉え、学び続けながら、専門知識とスキルを磨くことで、社労士という資格は、確実にあなたの人生を変えるでしょう。
伊藤塾では、2025年の合格を目指して、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講中です。
社労士試験に合格して人生を変える挑戦に臨みたい方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。
【社労士】伊藤真塾長×持田裕講師~伊藤塾で「社労士」を目指す意味とは~

著者:伊藤塾 社労士試験科
伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。