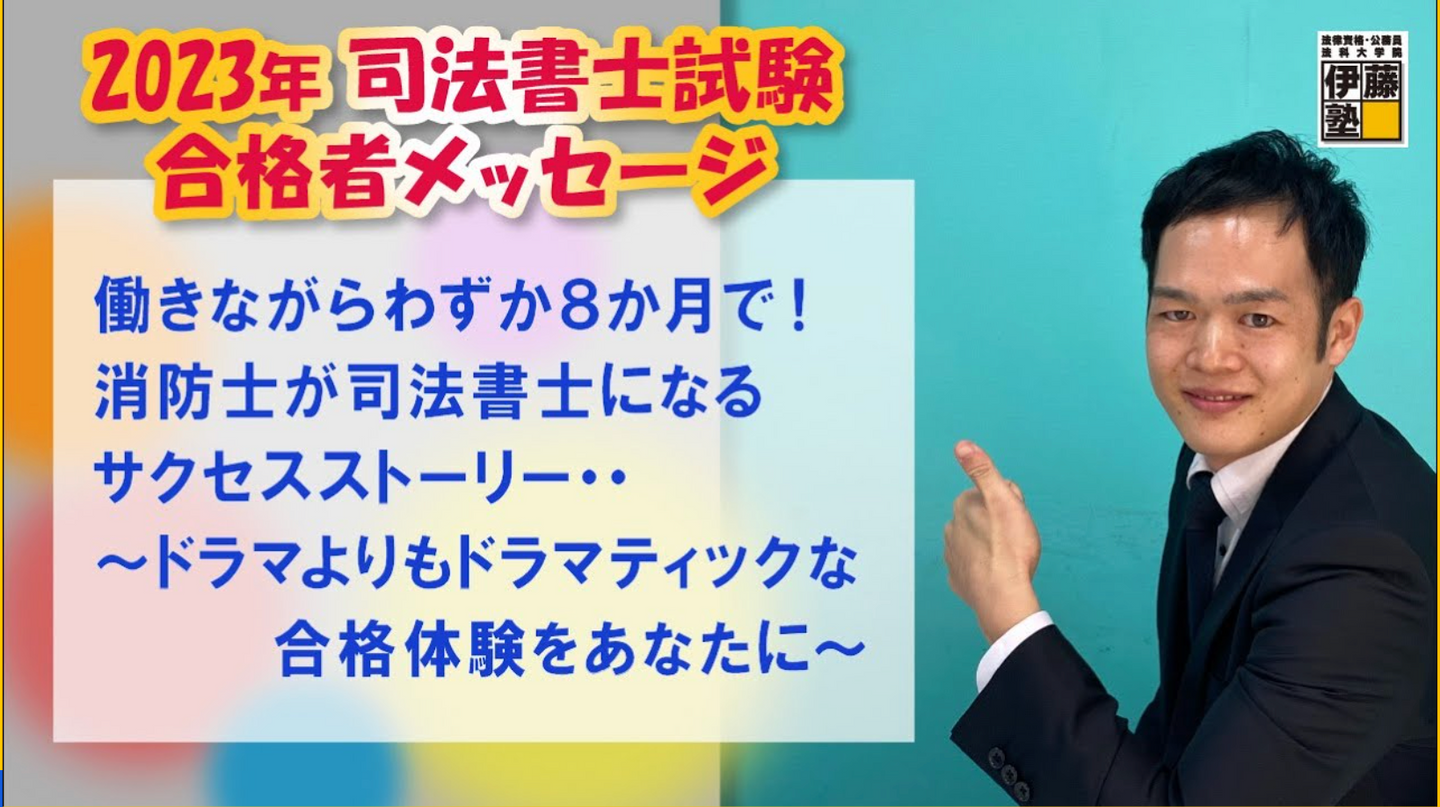「司法書士試験は簡単だった」は本当?誰でも合格できる理由を解説!

「司法書士試験は簡単だった」
SNSやインターネットで、こういった意見を耳にすることがあります。
これは本当なのでしょうか?
結論から言えば、司法書士試験は決して簡単な試験ではありません。
合格者に話を聞いても「簡単だった」という感想を聞くケースはほとんどなく、今も昔も間違いなく最難関資格の1つだと言えるでしょう。
本記事では、次の点を取り上げました。
◉この記事で分かること・司法書士試験の難易度
・簡単ではないが、誰でも合格できる理由
・短期合格する人の特徴
・働きながら、8ヶ月で司法書士試験に合格した人の体験談
司法書士試験に挑戦したい方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.司法書士試験が「簡単だった」という合格者は少ない
1-1.合格率は4%程度しかない
1-2.なじみのない法律科目が多い
1-3.午前の部・午後の部それぞれで基準点がある
2.昔の司法書士試験は簡単だった?
3.司法書士試験は簡単ではない…が誰でも合格できる試験
3-1.実質的な合格率は10%以上?
3-2.基本的な知識だけでも十分合格できる
3-3.仕事や家事・育児と両立できる
3-4.法律初学者から合格している人も多い
4.司法書士試験に簡単に合格している人の特徴
4-1.日々の学習を習慣化している
4-2.勉強する内容を絞り込んでいる
4-3.心構えやメンタルも軽視していない
4-4.なりたい自分像をはっきりさせている
5.司法書士試験の合格に必要な勉強期間は?
5-1.働きながら8か月で合格した人もいる
6.まとめ
1.司法書士試験が「簡単だった」という合格者は少ない
司法書士試験は、国家資格の中でも特に難関資格の一つとして知られています。
その理由として、合格率の低さ、専門的な法律科目の多さ、複数の基準点が設定されていることなどが挙げられます。
試験が終わった後、合格者に話を聞いても「簡単だった」という感想を聞くケースは殆どありません。司法書士試験の難しさについて、詳しく見ていきましょう。
1-1.合格率は4%程度しかない
司法書士試験の合格率は、例年4%程度と非常に低い水準で推移しています。
毎年約1万3千人が受験する中で、実際に合格できるのはわずか600人〜700人程度なのです。これは、数ある法律系国家資格の中でも、トップクラスに低い数字と言えるでしょう。
独学の場合、5回、6回と受験して、やっと合格する人も珍しくはありません。合格するには効率的な学習計画を立てて、正しい方法で勉強することが必要です。
1-2.なじみのない法律科目が多い
司法書士試験では、会社法、不動産登記法、商業登記法などの、聞き慣れない法律が出題されます。
特に、不動産登記法や商業登記法は、普段の生活で耳にする機会がなく、具体的なイメージがわきにくいでしょう。これらの科目の理解が、ここまで深く問われる試験は司法書士試験しかありません。法学部出身であったり、行政書士試験・予備試験などの学習経験があっても、全く触れたことのない人が大半のはずです。
さらに、記述式の問題も出題されるため、表面的な暗記だけでは太刀打ちできません。
初学者が、ゼロから1人で勉強しようとすると、膨大な量の勉強が必要となります。
※司法書士試験の試験科目は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→司法書士試験の試験科目は?配点や問題数・合格するためのポイントを解説
1-3.午前の部・午後の部それぞれで基準点がある
司法書士試験では、午前の部、午後の部それぞれで基準点が設定されています。
そして、一つでも基準点を下回ると、総合点が高くても不合格となってしまいます。そのため、苦手科目やコスパ(タイパ)の悪い科目であっても、十分な学習が必要となるのです。
他の資格試験でよくある「捨て科目」を前提とした戦略を取ることはできません。
得意科目に偏った学習だけで合格することは難しく、すべての科目でバランスの取れた学習が必要な試験と言えるでしょう。
※司法書士試験の基準点は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→【2024年度】司法書士試験の基準点や合格点はどうなる?過去の推移から分析予想!
2.昔の司法書士試験は簡単だった?
中には、昔の司法書士試験は簡単だったという人もいます。
しかし、実態は異なっており、むしろ現在の方が合格しやすいと言えるでしょう。
昭和時代のデータは確認できませんでしたが、平成時代と比較すると、合格率は明らかに現在の方が高くなっています。
【司法書士試験の合格率の推移】
| 出願者数 | 最終合格者数 | 合格率 | |
| 令和6年 | 16,837人 | 737人 | 4.4% |
| 令和5年 | 16,133人 | 695人 | 4.3% |
| 令和4年 | 15,693人 | 660人 | 4.2% |
| 平成16年 | 29,958人 | 865人 | 2.9% |
| 平成15年 | 28,454人 | 790人 | 2.8% |
| 平成14年 | 25,416人 | 701人 | 2.8% |
平成時代、司法書士試験の合格率は2%程度しかありませんでした。しかし、令和に入ってからの合格率は、安定的に4%を超えています。
これは、受験者数が減少しているにも関わらず、最終合格者の数が減っていないことが大きな要因です。おそらく、司法書士の需要が増加しているため、司法書士の数を増やそうとしているのでしょう。
相続登記の義務化などによって、司法書士の需要は確実に増えています。そうすると、今後もこの流れは続いていく可能性が高いです。
現在の司法書士試験は、以前と比べると非常に受かりやすくなっているのです。
昔は司法書士試験が簡単だったという話を聞くこともありますが、それは単なる思い込みに過ぎません。客観的なデータを見れば、現在の方が合格しやすい環境になっていることは明らかです。
正しい方法で勉強すれば、誰でも合格できる試験となっているとも言えるでしょう。
司法書士を目指す方にとって、今は絶好のチャンスかもしれません。
3.司法書士試験は簡単ではない…が誰でも合格できる試験
司法書士試験は、決して簡単な試験ではありません。しかし、正しい方法で勉強すれば、誰でも合格できる試験です。
以前と比べて合格しやすくなっており、実際の合格率も公表されている数字よりも高いと言われています。また、仕事や家事・育児と両立しながら勉強している人も多いです。法律初学者から合格した人も決して珍しくはありません。
司法書士試験に誰でも合格できる理由は以下のとおりです。
・実質的な合格率は10%以上?・基本的な知識だけでも十分合格できる
・仕事や家事・育児と両立できる
・法律初学者から合格している人も多い
それぞれについて、詳しく説明します。
3-1.実質的な合格率は10%以上?
司法書士試験の「実質的な合格率」は、おおよそ10%以上だと考えられます。
「合格率4%」というのは、あくまでも受験者全体に対する数字だからです。この中には、記念受験の人や、本気で勉強に取り組んでいない人、まだ試験範囲の学習が全て終わっていない人、当日欠席している人などが、かなりの数含まれています。
肌感ではありますが、合格を見据えて真剣に学習に取り組んだ人に限定すると、真のライバルは半分くらいにまで減少するといってもよいかもしれません。したがって、きちんと勉強しているだけでも、上位50%に入れると思って良いでしょう。
見かけの合格率だけを見て、「限られた人しか合格できない試験だ」と思うのは、あまりにももったいないです。正しい方法で勉強すれば、十分に合格圏内に入れる試験です。
※司法書士試験の合格率は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→司法書士試験の合格率はなぜ低い?2023年度の合格率や過去10年間の推移についても解説
3-2.基本的な知識だけでも十分合格できる
司法書士試験は、基本的な知識の理解を重視している試験です。
「合格率が低い=試験問題が難しい」というイメージを持つ人も多いですが、これは必ずしも正しいとは言えません。実際には、試験問題のほとんどが基本的な内容から出題されているのです。
司法書士試験で必要なのは、司法試験のような法的思考力ではなく、基本知識の積み重ねです。正答率が50%を超えるような問題を取りこぼさなければ、難しい応用問題に手を広げる必要はありません。
しっかりと基礎を固めて、典型的な問題に対応するスキルさえ身につけば、基本的な知識だけでも十分に合格点に達します。
3-3.仕事や家事・育児と両立できる
司法書士試験は、仕事や家事・育児とも両立しやすい試験です。
これは法務省のデータからも明らかで、司法書士試験最終合格者の平均年齢は40歳を超えています。
【令和5年度司法書士試験の最終結果】
| 平均年齢 | 41.5歳 |
| 20代の割合 | 17% |
| 30代の割合 | 31% |
| 40代の割合 | 31% |
| 50代の割合 | 15% |
| 60代以上の 割合 | 6% |
| 男性比率 | 67.2% |
| 女性比率 | 32.8% |
忙しい30代〜50代の合格者が約8割を占めており、多くの合格者が「勉強に専念できる環境ではなかった」と考えて良いでしょう。
「勉強に集中しないと合格できない難しい試験」といったイメージとは裏腹に、大半の人が仕事やプライベートと勉強を両立させて合格を勝ち取っているのです。
※こちらの記事もご一読ください。
→働きながら司法書士合格は無理じゃない!社会人合格者の勉強法を解説
→司法書士試験に1回の受験で合格したママたちの座談会
3-4.法律初学者から合格している人も多い
司法書士試験に対して、「法学部出身者が受ける試験」というイメージを持つ人もいます。
しかし実際には、司法書士試験をきっかけに、初めて法律を学び始めたという人が多いのも特徴です。
そもそも、司法書士試験の中心となる「不動産登記法・商業登記法」は、法学部でもあまり勉強しない法律です。予備試験や行政書士試験、宅建士試験などでも深く触れないため、ほぼ全員がゼロからのスタートと考えて良いでしょう。
そうすると、これまでの学習経験が合否に与える影響は大きくありません。正しい方法で勉強すれば、法律初学者でも十分に合格できる試験だと言えるでしょう。
※司法書士試験の勉強法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→司法書士は独学で合格できる?1年で合格するための勉強法も解説
4.司法書士試験に簡単に合格している人の特徴
前述のとおり、司法書士試験は決して簡単な試験ではありません。
しかし中には、簡単そうに合格している人もいます。もちろん簡単そうに見えるだけで、本当に簡単なわけではありませんが、短期合格している人がいるのは事実です。
では、「何回受験しても合格できない人」と「短期で合格できる人」の違いは何なのでしょうか?
短期合格者に共通している特徴は、主に以下の4つです。
・日々の学習を習慣化している・勉強する内容を絞り込んでいる
・心構えやメンタルも軽視していない
・なりたい自分像をはっきりさせている
これらの特徴をよく理解し、自分の学習に取り入れていけば、司法書士試験の合格に大きく近づけるでしょう。
それぞれの特徴について、さらに詳しく説明します。
4-1.日々の学習を習慣化している
司法書士試験に短期で合格している人は、日々の学習を習慣化しています。
仕事や家事・育児など、様々な制約がある中でも、勉強を習慣化することで、毎日の学習時間を確保しているのです。
習慣化するには、まずは自分の生活リズムをしっかりと分析し、勉強に充てられる時間帯を見つけることが大切です。そして、その時間を有効活用して、集中して勉強に取り組む習慣を身につけていきましょう。
机に向かう時間が取れない日は、通勤時間やスキマ時間を活用するなど、柔軟に対応しましょう。「全く勉強時間が取れない」と思っていても、ちょっとした時間を積み重ねていけば、思った以上に時間は確保できるものです。
司法書士試験は一朝一夕で合格できる試験ではありません。日々コツコツと学習を積み重ねていくことこそが合格への近道です。
4-2.勉強する内容を絞り込んでいる
勉強する内容を絞り込んでいることも、簡単そうに合格している人の特徴です。
司法書士試験の範囲は広く、膨大な法律知識を身につける必要があります。しかし、全ての内容を完璧にマスターする必要はありません。範囲が広いからこそ、合格に必要なポイントに絞って、集中的に学習することが求められるのです。
司法書士試験は、ものしり博士が合格する試験ではありません。必要な知識を絞り込んで、徹底的に繰り返し、実務で使えるレベルに落とし込んだ人だけが合格できる試験です。
SNSやインターネットで、様々な情報が乱立している時代だからこそ、信頼できる講師や教材を選び、そこで提供される情報に絞り込んで勉強することが欠かせないでしょう。
多くの情報に惑わされることなく、一本筋の通った勉強を継続した人だけが、合格を勝ち取れるのです。
4-3.心構えやメンタルも軽視していない
司法書士試験は、知識だけでなく、強靭なメンタルも要求される試験です。短期で合格できている人は、勉強のスキルとともに、心構えやメンタル面も重視しています。
試験の本番では、難しい問題や予想外の問題に直面することもあるでしょう。そんな時でも、動揺せずに冷静に対処できるメンタルの強さが合格のカギとなるのです。
また、勉強の過程では、モチベーションの維持も欠かせません。長丁場の受験勉強の中では、必ず心が折れそうになる瞬間があるからです。仲間と励まし合ったり、講師に相談したりしながら、前を向いて進んでいくことができなければ合格は難しいでしょう。
司法書士試験は、ひたすら勉強するだけで合格できる試験ではありません。スキルとメンタルの両面が要求される総合試験なのです。
合格するには、メンタル管理も軽視せず、必要な心構えなどもしっかりと習得することが大切です。
4-4.なりたい自分像をはっきりさせている
最も大きな特徴は、なりたい自分像を明確にしていることです。
司法書士試験に短期合格する人は、例外なく「なぜ司法書士を目指すのか」「合格後にどんな仕事をしたいのか」など、合格後のビジョンを具体的に描いています。
「家族のために安定した収入を得たい」「子供に誇れる親になりたい」
「困っている人の力になりたい」
「1人で生きていける専門スキルを身につけたい」 など
一人一人の想いは様々ですが、共通しているのは、合格後のイメージを常に意識して、モチベーションに変えているということです。
明確なビジョンがあるからこそ、勉強のつらい時期や、モチベーションが下がった時でも、心の支えとなり、乗り越えていく原動力になるのです。
合格者の話を聞くと、合格後の人生をイメージしながら、心の中でしっかりとしたゴールを決めて日々の学習に励んでいることがよく分かります。司法書士試験に合格するためには、自分なりのビジョンを持つことが何より大切だと言えるでしょう。
※司法書士試験合格後の姿をイメージしたい方は、こちらもご一読ください。
→「合格後の活躍 実務家レポート」
5.司法書士試験の合格に必要な勉強期間は?
司法書士試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に3,000時間と言われています。
これは、法律を勉強したことがない状態から、1人で合格するために必要な勉強時間の目安です。仮に1日8時間、週6日勉強をした場合には、合格までに約1年4ヵ月かかる計算になります。
もっとも、3,000時間という数字はあくまでも平均的な勉強時間に過ぎません。司法書士試験で必要なのは、とにかく長時間の勉強をすることではなく、質の良い勉強を継続して行っていくことだからです。
一般的に言われる勉強時間は、絶対的な基準ではありません。3000時間以上勉強して合格できない人もいれば、はるかに短い勉強時間で合格する人もたくさんいます。
短期合格に必要なのは、前述した合格者の特徴を理解して、合格者になりきって実践していくことです。学習範囲を絞り込んで、正しい方法で勉強していけば、世間のイメージ以上の短い勉強時間で合格することも難しくはありません。
※合格に必要な勉強時間は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→司法書士試験合格に必要な勉強時間とは?社会人・独学で合格できるか?も解説
5-1.働きながら8か月で合格した人もいる
実際に、伊藤塾の受講生の中には、働きながら1年もかからず司法書士試験に合格した人がたくさんいます。
その1人が、消防士として勤務しながら、8ヶ月で司法書士試験に合格した安井 良太さんです。安井さんは、司法書士になることを決意してから、毎朝4時に起きて講義動画を視聴するなど、仕事と勉強の両立に励んだそうです。
講義に追いつくのに必死で、模試では1度も基準点に届かず、ショックを受けることもありましたが、最後まで諦めずに勉強を継続したといいます。
安井さんが、なぜ8ヶ月で合格することができたのか、ぜひ合格体験談から感じとってください。
5分程度の短い動画ですが、強い意志を持って正しい方法で勉強すれば、8ヶ月という短期間でも合格できることを教えてくれるでしょう。
2023年司法書士試験合格
働きながらわずか8か月で!消防士が司法書士になるサクセスストーリー
6.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉司法書士試験が、簡単だったと感じている人は少ない
◉簡単ではないが、誰でも合格できる試験
・合格者の大半は、仕事や家事、育児と両立している
・半分以上は法律初学者から学習をスタートしている
◉司法書士試験に短期合格している人の特徴は4つ
・勉強する内容を絞り込んで、効率化している
・心構えやメンタルも重視している
・合格後の姿を、はっきりとイメージしている
◉合格者になりきって、正しい方法で勉強すれば、合格は決して難しくない
以上です。
司法書士試験の合格は、決して遠い夢ではありません。皆さん一人一人が、自分なりのペースで着実に学習を積み重ねていけば、必ず合格への道は開けるはずです。
司法書士試験に合格したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾をご活用ください。伊藤塾の司法書士試験対策講座は、合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。
ぜひ新たな一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートします。
→「伊藤塾 司法書士入門講座」はこちら

著者:伊藤塾 司法書士試験科
伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。