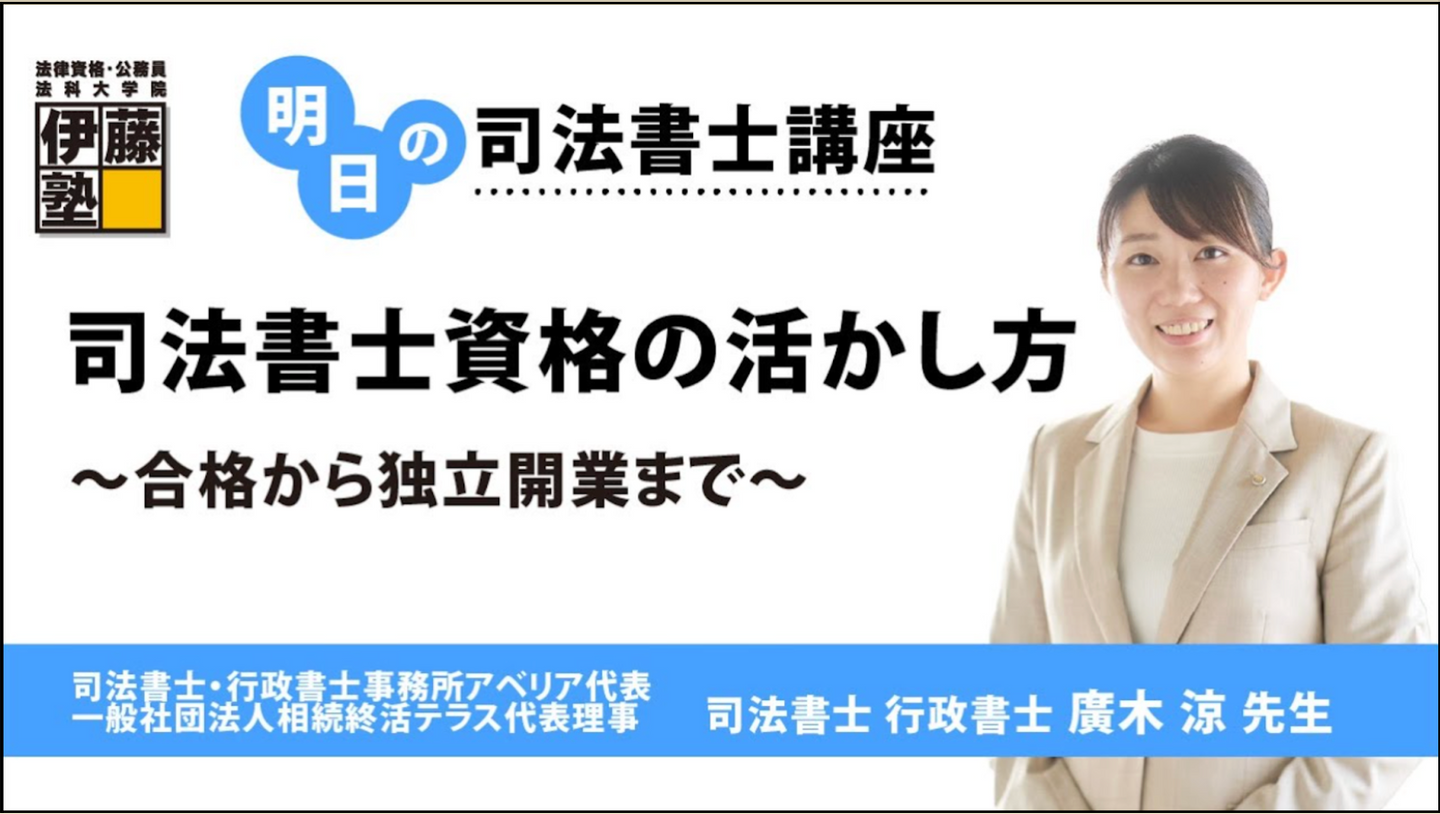司法書士の独立開業は厳しい?年収は?魅力や注意点を実体験を元に解説

「司法書士で独立開業したいけど、やっていけるか不安」
「失敗して廃業する人はどのくらいいる?」
「年収はどのくらい見込める?」
「独立開業にはどんなリスクがある?」
司法書士で独立開業を目指す方の中には、このような疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。
確かに、司法書士として独立開業するには、一定のリスクが伴います。
しかし一方で、高い年収を得られたり、仕事の自由度が圧倒的に増したり、自営業ならではの代えがたい魅力があるのも事実。
実際、伊藤塾の卒業生の中にも、しっかりと準備して開業し、自分らしい働き方を実現している人がたくさんいます。
そこでこの記事では、毎年数多くの司法書士を輩出している当塾が、実際の経験談を踏まえつつ
・司法書士で独立開業する魅力
・独立開業のリスクや注意点
・開業するための具体的な手順
・独立開業に向いている人の特徴や失敗する要因
などの気になるポイントについて、徹底解説します。
この記事を読むことで、司法書士の独立開業に関する疑問や不安が解消され、自分に合った働き方を見つけるためのヒントが得られるでしょう。
司法書士の独立開業に興味がある方は、ぜひご一読ください。
【目次】
1.司法書士として独立開業する3つのメリット
1-1.年収1000万以上も夢ではない
1-2.仕事の自由度が高い
1-3.開業後の「廃業率」が圧倒的に低い
2.司法書士で独立開業するリスクや注意点
2-1.(開業直後は)収入が不安定になる
2-2.一定の開業資金が必要になる
2-3.集客や営業努力が必要になる
3.司法書士として独立開業するまでの手順
3-1.ステップ① 司法書士資格を取得する
3-2.ステップ② 司法書士名簿に登録する
3-3.ステップ③ 司法書士事務所などで実務経験を積む
3-4.ステップ④ 独立に向けた計画を立てる
3-5.ステップ⑤ 事務所や設備を準備する
3-6.ステップ⑥ 開業届を提出し、挨拶回り等をおこなう
4.独立開業以外の働き方もある?
5.【Q&A】独立開業に関する4つの疑問
5-1.司法書士は何年で独立することが多い?
5-2.実務経験なしで独立開業することもできる?
5-3.独立開業に向いている人の特徴は?
5-4.失敗しやすい原因は何がある?
6.司法書士の独立開業のリアルは?実際の体験談を紹介
7.まとめ
1.司法書士として独立開業する3つのメリット
司法書士として独立開業するメリットには、大きく以下の3つがあります。
◉ 年収1000万以上も夢ではない
◉ 仕事の自由度が高い
◉ 開業後の「廃業率」が圧倒的に低い
それぞれ見ていきましょう。
1-1.年収1000万以上も夢ではない
司法書士は専門性の高い職業であるため、独立開業によって、高い年収を見込むことができます。
例えば、厚生労働省の統計によれば、司法書士の平均年収は970万円程度。
この中には、会社員の数字も数多く含まれているため、独立開業している司法書士に限れば、1,000万円以上稼いでいる人の割合がかなり高くなると考えられます。
※会社に勤務する司法書士の年収は「300万〜600万」程度となることが多いと言われています。
もちろん、開業してからすぐに大きく稼げる訳ではありません。
しかし、徐々にクライアントからの信頼を得られるようになると、高単価の案件が増えていきます。
一定の経験とスキルを積み重ね、クライアントから高い評価を得られるようになることで、高い報酬を得られる可能性が高くなるでしょう。
※司法書士の年収については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→司法書士の年収の現実とは?平均年収から収入を上げる方法まで徹底解説
1-2.仕事の自由度が高い
全てを自分で決められる自由度の高さも、司法書士として独立開業する大きな魅力です。
独立開業すると、働く時間や場所、休日、受託する業務の範囲など、全てを自分の裁量で決めることができます。育児や介護など、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な働き方も可能になるでしょう。
例えば、子育て中の司法書士であれば、子供の学校行事に合わせて休みを取ったり、在宅で仕事をしたりと、家庭との両立がしやすくなります。介護が必要な家族がいる場合も、時間の使い方を工夫することで、仕事と介護を無理なく続けられるはずです。
また、自分の得意分野や、興味のある案件に特化して業務を受託することも可能です。
会社勤めの場合、上司から割り当てられた仕事をこなさなければなりませんが、独立開業すれば自分の意思で仕事を選ぶことができるからです。
自分が面白いと感じる仕事に集中できるため、モチベーションを高く保つことができるでしょう。
ただし、自由度が高い分、全ての責任は自分に降りかかってきます。
仕事量のコントロールや、プライベートとの両立など、自己管理能力が求められる点には注意が必要です。
1-3.開業後の「廃業率」が圧倒的に低い
司法書士の独立開業は、開業後の「廃業率が非常に低い」のも大きなメリットです。
例えば、直近3年間の司法書士の廃業率は、毎年「2%」程度。
つまり、100人開業したとして、事務所を畳むことになる人は、3人もいない計算になります。
【司法書士の直近3年間の廃業率】
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
| 4月1日時点の会員数 | 22,632 | 22,724 | 22,718 |
| 業務廃止による 登録取消者数 | 515 | 464 | 437 |
| 廃業率 | 2.28% | 2.04% | 1.92% |
「士業は食えなくなった」なんて噂とは対照的に、司法書士の廃業率は年々減少傾向にあります。これは、司法書士の業務が社会に必要不可欠であり、常に安定した需要があるためだと考えられます。
難関資格であるため、他の士業と比べて有資格者の数が増えづらいのも、廃業率が低い理由の1つ。
過度な競争に晒されていないため、一度開業すれば長く続けやすい仕事だといえるしょう。
2.司法書士で独立開業するリスクや注意点
司法書士として独立開業することには、大きなメリットがある一方で、リスクや注意点も存在します。
ここでは、司法書士が独立開業する際に注意すべき点を、3つ紹介します。
◉(開業直後は)収入が不安定になる
◉ 一定の開業資金が必要になる
◉ 集客や営業努力が必要になる
それぞれ見ていきましょう。
2-1.(開業直後は)収入が不安定になる
独立開業する際に最も注意したいのが、収入の不安定さです。
会社員として働いている間は、毎月決まった額の給与が支払われるため、収入が安定しています。しかし、独立開業した場合、収入は自分で獲得した仕事の量に左右されます。
特に開業当初は、顧客獲得に苦戦することが多く、安定した収入を得るまでには時間がかかるでしょう。
収入が不安定な状況が続くと、生活や事務所の運営にも支障をきたす可能性があります。
開業する前には、日々の生計を維持するための生活防衛資金を確保しておくなど、入念な準備が必要となるでしょう。
また、ランニングコストを抑えるため、事務所の賃料などの固定費も、なるべく控えめに設定するのが賢明です。
2-2.一定の開業資金が必要になる
司法書士として独立開業するには、一定の開業資金が必要になります。
他の職種と比較すると、比較的安く開業できるケースも多いものの、ある程度の費用は必要です。
【司法書士が開業する際にかかる費用一覧】
| 事務所を賃貸するための初期費用 | 50〜100万円 |
| 事務用品の購入費用 | 20万円程度 |
| ホームページなどの開設費用 | 5万円程度 |
| 事務所用の資料・書籍などの購入費用 | 10万円程度 |
開業資金が不足している場合、例えば
・家賃がかからない自宅での開業を目指す
・スマートフォン、クラウドFAXなどを活用し、事務用品を最小限に抑える
等の工夫をすることで、初期費用を抑えることもできます。
ただし、それでも数十万円の開業資金は必要になるでしょう。
2-3.集客や営業努力が必要になる
司法書士として独立開業すると、自ら集客や営業活動に取り組むことが必要になります。
会社員とは異なり、仕事を受注するために自分から行動しないと、収入を得ることができなくなるからです。
特に開業したての頃は、知名度が低く、クライアントからの信頼も十分でないため、集客に苦戦することも多いです。ホームページやブログ・SNS等を活用した情報発信、知人への営業活動など、地道な営業努力が求められるでしょう。
一方で、少しづつ実績を積んでいけば、自然と仕事も増えていきます。クライアントと信頼関係を構築していくことで、リピーターを獲得できたり、既存クライアントから紹介をもらえる機会も多くなるでしょう。
大変な面もありますが、自分の力で仕事を獲得し、収入を増やしていく醍醐味を味わえるのも、独立開業ならではの魅力かもしれません。
3.司法書士として独立開業するまでの手順
では、司法書士として独立開業する場合、どのような手順が必要になるのでしょうか?
ここでは、一般的な流れを、6つのステップに分けて解説します。
ステップ①司法書士資格を取得する
ステップ②司法書士名簿に登録する
ステップ③司法書士事務所などで実務経験を積む
ステップ④独立に向けた計画を立てる
ステップ⑤事務所や設備を準備する
ステップ⑥開業届を提出し、挨拶回り等をおこなう
順番に見ていきましょう。
3-1.ステップ① 司法書士資格を取得する
司法書士として独立開業するための第一歩は、司法書士資格の取得です。
司法書士試験は年に1回行われます。
「7月に実施される筆記試験」、「10月に実施される口述試験」の両方に合格する必要があり、合格率は例年3~5%程度と、かなりの難関試験です。
しっかりと学習計画を立て、着実に勉強を進めていきましょう。
※司法書士試験の受験資格・スケジュール・難易度については、以下の記事で詳しく解説しています。
→司法書士になるには?受験資格・難易度・高卒でもなれるのかなど詳細解説
→令和6年(2024年)司法書士試験の試験日はいつ?口述試験の試験日程も解説
→司法書士試験の難易度は?合格率や税理士試験との比較など詳しく解説
3-2.ステップ② 司法書士名簿に登録する
試験に合格するだけでは、「司法書士」を名乗ることはできません。
司法書士としての業務を行うには、「司法書士名簿」に登録する必要があるからです。
登録には、
・新人研修を受講する
・司法書士会に登録申請をする
など、いくつかの手順が必要となります。
※司法書士としての登録については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→「司法書士合格後の流れとは?研修から登録までの詳細を徹底解説」
※認定司法書士に興味のある方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
→認定司法書士とは?司法書士との違いや特別研修・認定考査についても解説
3-3.ステップ③ 司法書士事務所などで実務経験を積む
司法書士としての登録が終わったら、司法書士事務所などで、実務経験を積みましょう。
独立開業を目標にしている人も、まずは司法書士事務所などに就職して、修行を積むことが一般的です。試験に合格しただけでは、現場で必要となる知識やスキルが不足しているからです。
事務所での実務経験を通じて、登記や相続手続きなどの具体的な業務の進め方を学ぶことができます。
先輩司法書士の仕事ぶりを間近で観察し、仕事の獲得方法や、クライアントとの接し方などの実践的なノウハウを吸収していきましょう。
また、この期間中に、独立開業後の人脈作りに努めることも大切です。
同僚の司法書士だけでなく、不動産業者や行政書士、税理士など、他の士業とも積極的に交流を図りましょう。これらの人脈は、独立開業後の顧客獲得や、業務提携にも役立つはずです。
3-4.ステップ④ 独立に向けた計画を立てる
実務経験と並行して、独立開業に向けた計画も作成していきましょう。
◉ どこで開業するのか
◉ 開業の時期はいつ頃を目標にするのか
◉ どのような業務をメインに受託するのか
◉ 開業資金はどの程度必要になるのか
◉ 必要な資金をどうやって調達するか
◉ 開業後の資金繰りをどうするか
など、決めるべきことは多岐にわたります。
具体的なスケジュールを立てて、着実に準備を進めていくことが大切です。
家族やパートナーにも相談し、協力を得ながら取り組んでいきましょう。
3-5.ステップ⑤ 事務所や設備を準備する
必要な準備が終わったら、いよいよ実際に独立開業する段階です。
事務所を開設するテナントを探したり、必要な事務用品を調達したりして、開業に向けた具体的な行動を進めていきましょう。
3-6.ステップ⑥ 開業届を提出し、挨拶回り等をおこなう
開業準備が終わったら、最後に、事務所のある地域を管轄する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出して、営業スタートです。
独立開業したら、挨拶状を送ったり、挨拶回りを行ったりして、自分の存在を知ってもらいましょう。地道な挨拶回りがきっかけとなり、思わぬところから仕事が舞い込んで来るケースも多いです。
顔の見える関係性を構築し、司法書士としての信頼を積み重ねていきましょう。
4.独立開業以外の働き方もある?
司法書士にとって、独立開業は魅力的な選択肢ですが、自分には合わないと感じる人もいるかもしれません。
しかし、司法書士としてのキャリアを諦める必要はありません。
独立開業以外にも、司法書士として活躍できる働き方はいくつも存在するからです。
例えば、司法書士事務所に勤務する方法があります。
独立開業には、集客や事務所運営などのリスクがつきものですが、勤務司法書士であればそれらのリスクを負わずに、司法書士業務に専念できます。
毎月安定した収入を得られるのも大きなメリットです。
また、一般企業の法務部に就職する道もあります。
不動産業や金融機関など、司法書士の専門知識を必要とする企業は少なくありません。
企業内で、司法書士としてのスキルを発揮できる場合もあるでしょう。
また、今は無理だと思っていても、司法書士としての経験を積んでいくうちに、独立への自信がつく人も大勢います。
実際、司法書士の廃業率は、わずか「2%」程度。多くの人が、独立して活躍できているという事実を忘れてはなりません。
独立開業するか勤務司法書士としてのキャリアを積んでいくかは、自分のライフスタイルや目標に合わせて、じっくり考えてみてください。
※司法書士の就職については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→司法書士は就職できない?40代や未経験は?就職先を探す5つの方法
5.【Q&A】独立開業に関する4つの疑問
5-1.司法書士は何年で独立することが多い?
司法書士の独立開業までの期間は人それぞれですが、一般的には2年から5年程度の実務経験を積んでから独立する人が多いです。
司法書士としての専門知識やスキルを身につけ、事務所運営に関するノウハウを学ぶためには、ある程度の期間は必要になるでしょう。また、この期間中に必要な開業資金を貯める方も多いです。
ただし、あまりに長く勤め過ぎると、独立するタイミングを逃してしまう場合もあるため、注意が必要です。
5-2.実務経験なしで独立開業することもできる?
司法書士の資格を取得すれば、実務経験なしで独立開業することも可能です。
特に、合格前から司法書士事務所で働いていた人の場合、すぐに開業することも多いです。
ただし、合格後いきなり独立するのは、かなりリスクが高い行為であるのも事実。
試験合格後の研修で、基本的な実務については学べるものの、実務経験があるに越したことはありません。
未経験から試験に合格した場合は、やはり司法書士事務所などに就職し、経験を積んでから独立するのが無難でしょう。
5-3.独立開業に向いている人の特徴は?
いくつか特徴はあるものの、例えば
・専門性が高い
・営業力がある
・行動力がある
・差別化のポイントがはっきりしている
等の特徴がある人は、独立開業して大きく成功している傾向があります。
5-4.失敗しやすい原因は何がある?
司法書士として独立開業する際に失敗しやすい原因は、ある程度決まっています。
例えば、
・開業のための準備が不足していた
・報酬の安さだけをアピールしていた
・営業努力が足りていなかった
などが挙げられます。
逆にいえば、上記の要因さえ気をつけておけば、司法書士として開業して成功する確率も、一段と高くなるでしょう。
6.司法書士の独立開業のリアルは?実際の体験談を紹介
司法書士としての独立開業は、大きなチャレンジであり、そこには様々な不安や障壁があるかもしれません。
しかし、実際に独立開業した先輩の体験談を聞くと、独立のメリットや醍醐味が鮮明に伝わってきます。
・先輩たちが、どんな理由で独立を決意したのか
・どのような壁を乗り越えてきたのか
独立の過程で経験した喜びや苦しみを知ることは、司法書士としてのキャリアを考える上で、大いに参考になるでしょう。
ここでは、試験に合格した後、司法書士事務所への就職を経て、実際に独立した司法書士の体験談を紹介します。司法書士の独立開業のリアルを知るために、是非ご覧ください。
【明日の司法書士講座】司法書士資格の活かし方~合格から独立開業まで~
7.まとめ
この記事では、
◉ 司法書士が独立開業するメリット
◉ 独立開業のリスクや注意点
◉ 開業するまでの流れ
についてお伝えしました。
司法書士の独立開業は、仕事の自由度が高く、1000万以上の年収を得られる可能性もある魅力的な選択肢の1つです。
独立開業ならではの、リスクや注意点も存在するものの、しっかりと準備して開業すれば、充実したキャリアを築くことができるでしょう。
司法書士の独立開業に興味を持たれた方は、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
その挑戦が、あなたの人生を変える大きな転機になるかもしれません。
司法書士試験の合格に向けて勉強を開始したい方は、ぜひ法律専門指導校である伊藤塾をご活用ください。
伊藤塾の司法書士試験対策講座は、試験合格者の半数近くが利用しているという確かな実績を持っています。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、皆さんの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 司法書士試験科
伊藤塾司法書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの司法書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、司法書士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。