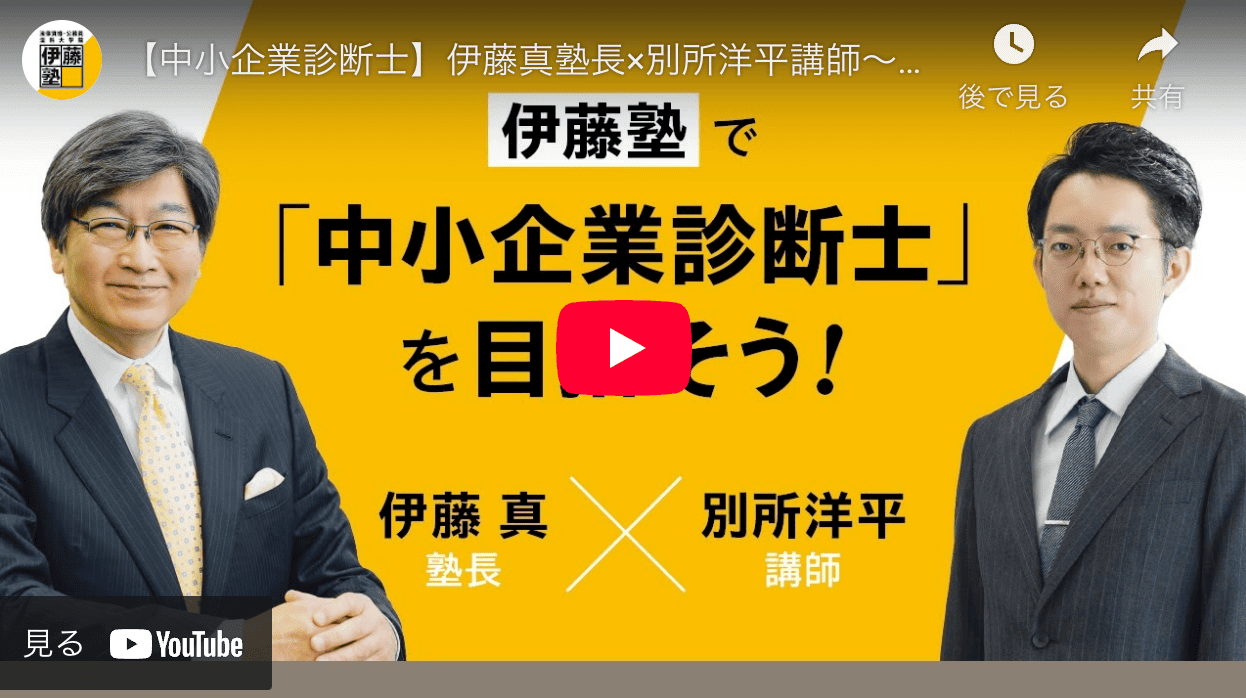中小企業診断士の実務従事とは?要件や知り合いの会社でも可能かなど詳しく解説

中小企業診断士の登録を申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。
中小企業診断士2次試験に合格後、3年以内に「実務補習を受講した日数」または「実務に従事した日数」の合計が15日以上であること。
合格者の多くは「実務補習」を受講していますが、実務補習は平日の参加が必要であったり、限られた地区のみで開催されているなど、受講することが難しい人もいます。
その場合は、実務補習ではなく「実務に従事した日数(実務従事)」を活用して登録を目指すことになります。
本記事では中小企業診断士の登録要件である「実務従事」について解説します。
実務従事を通して診断士に登録しようか迷っている人や、中小企業診断士に興味がある人はぜひ最後までご一読ください。
【目次】
1.実務従事について
1-1.中小企業者に対する経営の診断助言業務
1-2.経営の窓口相談業務
1-3.実務従事の対象となる中小企業について
1-3-1.実務従事の対象となる中小企業等
1-3-2.実務従事の対象とならない中小企業等
2.実務従事で登録する人のパターン3選
2-1.本業で中小企業に診断助言業務を行なっている
2-2.知人や親戚の会社に対して診断助言業務を行う
2-3.民間団体等の実務従事サービスを利用する
3.中小企業診断士の実務従事に関するよくある質問
3-1.オンラインの実務従事はおすすめ?
3-2.知り合いの企業で実務従事って何すればいい?
3-3.実務従事は何日必要?実務補習と合算できる?
3-4.実務従事と実務補習はどちらがオススメ?
4.まとめ
1.実務従事について
診断士に新規登録する際の「実務に従事した日数(実務従事)」は以下の2つに分類されます。
・中小企業者に対する経営の診断助言業務・経営の窓口相談業務
多くの場合は前者の「中小企業者に対する経営の診断助言業務」を通じて、診断士に登録します。
1-1.中小企業者に対する経営の診断助言業務
経営の診断助言業務の要件は、「中小企業等の経営者等に直接、経営診断助言を行なった日数や、それに付随する業務を行なった日数」です。なお、実務に従事した日数のことをポイント(実務従事ポイント)と表現することもあります。
実務従事は、有償支援か無償支援かは関係ありません。また、1日で2社に対して診断助言を行なった場合も「実務従事1日」としてカウントされます。
以下に経営の診断助言業務の例を挙げます。
①診断士が事業として行う中小企業者に対する経営の診断、助言業務② 国(中小企業庁等)の委嘱を受けて行う診断助言業務(例えば、ミラサポ専門家派遣事業による診断助言業務)
③ 都道府県・政令指定市(中小企業支援センター等)の委嘱を受けて行う診断助言業務
④中小企業基盤整備機構の委嘱を受けて行う診断助言業務
⑤中小企業関係団体等(商工会、商工会議所等)の委嘱を受けて行う診断助言業務
⑥医療又は歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人及びNPO 法人に対する診断助言業務
⑦国際協力機構(JICA)等からの委託等で行う中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における診断助言業務
⑧中小企業に勤務し経営者からの指示で行う自社に対する診断助言業務、ただし所属部門のルーティンワークを除く
⑨金融機関や大企業等に所属し、取引先等中小企業者に対して行う診断助言業務
本業等で、中小企業との関係を持っている人であれば比較的容易に実務従事要件を満たせるでしょう。一方で、実務従事先となるような中小企業と関わりがない人も多いでしょう。
近年は「実務従事サービス」といって、実務従事要件を満たすサービスを提供する民間団体などが増えていますので、これらを利用するのもオススメです。
1-2.経営の窓口相談業務
経営の窓口相談業務は以下のようなものが挙げられます。多くは診断士に登録した後に携わることが多い仕事です。そのため、これから中小企業診断士に登録しようとする人であれば、これら窓口相談業務に既に携わっている人は少ないと考えられます。
・国(中小企業庁等)の委嘱を受けて行う窓口相談業務(例えば、よろず支援拠点事業による窓口相談業務)・都道府県・政令指定市(中小企業支援センター等)の委嘱を受けて行う窓口相談業務
・中小企業基盤整備機構の委嘱を受けて行う窓口相談業務
・中小企業関係団体等(商工会、商工会議所等)の委嘱を受けて行う窓口相談業務
・医療又は歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)、社会福祉法人及びNPO 法人に対する窓口相談業務
・国際協力機構(JICA)等からの委託等で行う中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における窓口相談業務
1-3.実務従事の対象となる中小企業について
実務従事の対象となる中小企業等は次の通りです。
1-3-1.実務従事の対象となる中小企業等
実務従事の対象となる会社等は以下の通りです。
(参考: Q&A 申請書、証明書等の作成要領|中小企業庁)
・個人
・中小企業団体(事業協同組合、企業組合など)
・医療法人
・社会福祉法人
・NPO法人
実務従事は個人も対象となるため、知人の個人事業主(フリーランス)を対象に実務従事を行う人もいます。
1-3-2.実務従事の対象とならない中小企業等
以下の法人等は、実務従事の対象となっていませんので、注意しましょう。
・学校法人・職業訓練法人
・宗教法人
・商店会
・一般社団法人
・一般財団法人
・商工会、商工会議所
・農業協同組合
・独立行政法人など
2.実務従事で登録する人のパターン3選
実務従事で登録するパターンについて主な3つを紹介します。
2-1.本業で中小企業に診断助言業務を行なっている
本業がコンサルティング会社や金融機関等で、中小企業に対して診断助言業務を行なっている人は、実務従事要件をすぐに満たすことができるでしょう。なお、登録時に提出が必要な「診断助言業務実績証明書」には診断先の押印が必要です。
2-2.知人や親戚の会社に対して診断助言業務を行う
知人や親戚が経営している会社に対して診断助言業務を行うことで実務従事の要件を満たす人もいます。
実務従事では個人事業主も対象となるため、意外と身近に実務従事が可能な人がいたりします。「中小企業診断士試験に合格したので、診断助言をさせて欲しい」と伝えると快く承諾してもらえることもあるようです。
2-3.民間団体等の実務従事サービスを利用する
実務従事を経て診断士に登録する人の多くは、実務従事サービスを利用しています。
基本的には実務補習と同じようなサービスで費用はかかりますが、実務従事は各社が特色を出してカリキュラムを作成しています。一般的な実務従事サービスのメリットとデメリットは次の通りです。
【メリット】・主催企業が得意なテーマ(補助金、WEBマーケティング等)を学ぶことができる
・診断士に登録した後の活躍をイメージしやすい
・費用が実務補習よりも安い場合が多い
・実務補習が開催されていない地域でも開催されることもある
・オンラインで実施しているものがある
・土日のみで開催されるものがある
実務補習はスケジュールや開催地区の関係で参加が難しい人でも、実務従事であれば参加できるということは多いです。
・オンライン開催の場合、診断業務を進めにくいことがある
・実績が少ないサービスの場合、品質が不安
・自分が受けたいタイミングで開催されていないことがある
・実務補習と比べて、総合的な診断ではなく、分野を絞った内容になることが多い
実務従事にはメリットとデメリットがあるため、実務補習と実務従事の両方に参加して、合計15日を確保する人も多いです。
3.中小企業診断士の実務従事に関するよくある質問
ここでは中小企業診断士の実務従事に関するよくある質問に回答します。
3-1.オンラインの実務従事はおすすめ?
実務補習は全国7地区(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡)で開催されていますが、自宅の近くでは開催されていない人も多いと思います。また、育児などで外出したくない人などには、オンラインの実務従事がおすすめです。
対面実施に比べると、交流を深めることが難しいこともありますが、オンラインだからといって、実務従事の質が極端に下がることは少なく、オンラインの実務従事で満足という人も多いです。申し込む前に、オンラインの実務従事を実施する団体の評判や口コミを調べてみると良いでしょう。
3-2.知り合いの企業で実務従事って何すればいい?
実務従事では経営の診断助言業務を行いますが、具体的な内容に対する指定はありません。知り合いの企業で実務従事をする場合に、何をすべきか分からない場合は、まずはヒアリングから始めてみましょう。
ヒアリングの内容をまとめることで、診断業務になります。
診断士の2次試験のように今後の施策案をまとめることで、助言業務になります。もし心配である場合は、合格者同士でチームを組んだり、診断士の先輩を巻き込んで実施するのも良いでしょう。
3-3.実務従事は何日必要?実務補習と合算できる?
中小企業診断士に登録するためには、中小企業診断士2次試験に合格後、3年以内に「実務補習を受講した日数」または「実務に従事した日数」の合計が15日以上であることが必要です。そのため、実務従事のみで登録を目指す場合は15日必要になります。
また、実務補習と実務従事の日数は合算することができます。
例)「実務補習の8日間コースと実務従事を7日間で合計15日を満たす」など。
3-4.実務従事と実務補習はどちらがおすすめ?
実務従事と実務補習はそれぞれメリット、デメリットがあります。
ここでは、判断の目安をご紹介します。
・オンラインで実務従事を受講したい人
・休日のみで実務従事を行いたい人
・補助金やwebマーケティングのように特定の分野を勉強したい人
・民間のコンサルティングについて興味がある人
◉実務補習がオススメな人は次の通りです。
・対面で交流を深めたい人
・その地域で診断士として活動していきたい人
・中小企業診断協会など公的機関について興味がある人
・診断士の仲間と実務補習の話題で盛り上がりたい人
※中小企業診断士試験の実務補習についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→中小企業診断士の実務補習を解説!日程は?働きながらはきつい?
4.まとめ
今回の記事では中小企業診断士の実務従事の要件や内容について紹介しました。
まとめると次の通りです。
◉実務従事は「中小企業者に対する経営の診断助言業務」と「経営の窓口相談業務」がある
◉経営の診断助言業務は「中小企業等の経営者等に直接、経営診断助言を行なった日数や、それに付随する業務を行なった日数」が要件
◉経営の窓口相談業務は、主によろず支援拠点などの公的機関の窓口相談業務のこと
◉多くの合格者は経営の診断助言業務で登録要件を満たす
◉実務従事先は法人だけでなく、個人事業主も対象
◉多くの人は民間企業などが実施している実務従事サービスを受講して登録する
◉実務従事サービスはオンライン実施や、休日のみの実施により参加しやすいものがある
◉実務補習と比べて、実務従事は独自性の高いカリキュラムが多い
以上です。
近年、実務従事サービスを提供する民間団体の増加に伴い、実務従事を利用する人も増えています。実務従事を通じて中小企業にコンサルティングを行う経験は、診断士として今後独立する、しないに関わらず、大きな財産となるでしょう。
中小企業診断士は、経営コンサルティングに関する唯一の国家資格と言われ、独立開業はもちろん、企業内でのキャリアアップも見込める資格としてビジネスマンから高い人気を得ています。
司法試験合格者数No.1の受験指導校・伊藤塾では、この度、皆様からのリクエストにお応えし、2025年合格目標 中小企業診断士試験 合格講座を開講しました。
もし、あなたが中小企業診断士に興味をお持ちなら、ぜひ私たちと一緒にチャレンジしてみませんか?
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。

著者:伊藤塾 中小企業診断士試験科
伊藤塾中小企業診断士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、中小企業診断士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。