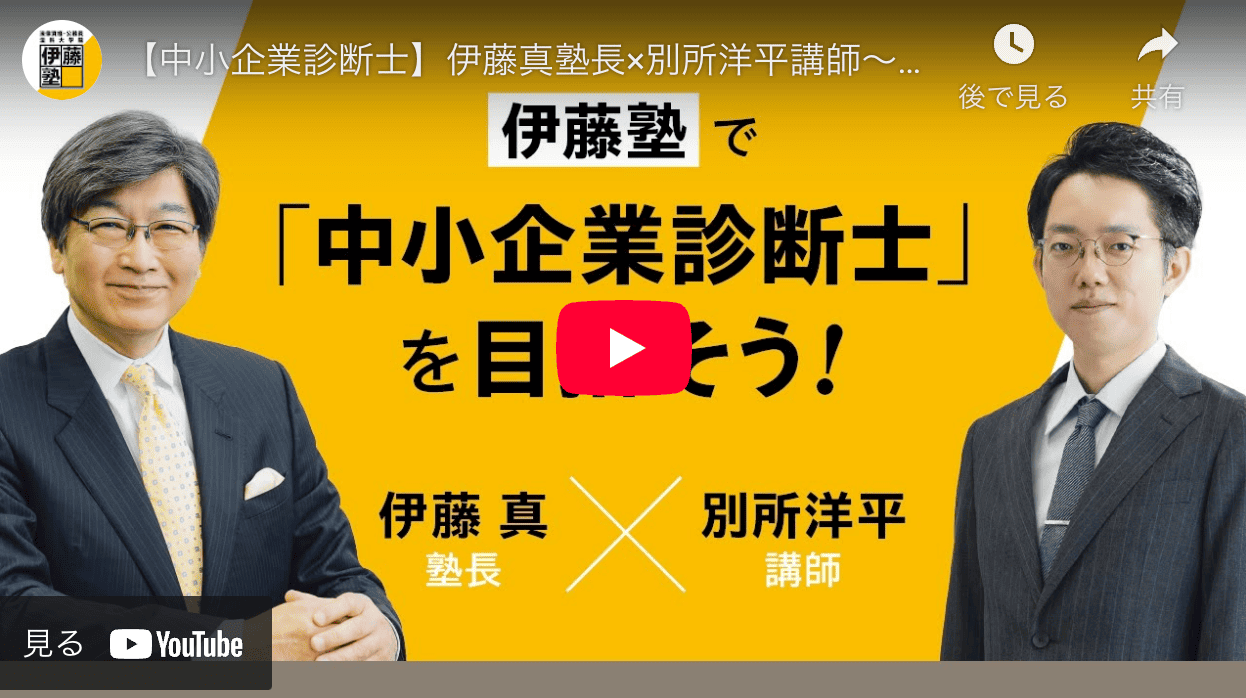中小企業診断士の口述試験を徹底解説!対策方法や服装まで紹介

中小企業診断士試験は1次試験と2次試験があり、2次試験には筆記試験と口述試験があります。口述試験は、2次筆記試験の合格者のみが受験できる最終試験です。
本記事では、口述試験について、概要から具体的な対策方法まで解説します。
これから中小企業診断士を目指す人や、口述試験に興味がある人はぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.口述試験の概要
1-1.口述試験の日程・スケジュール
1-2.口述試験の受験資格
1-3.口述試験の試験形式・時間
1-4.口述試験の受験料
1-5.口述試験の持ち物
1-6.口述試験の際の服装・ネクタイは必要か?
2.口述試験の合格基準・合格率
2-1.口述試験の合格基準
2-2.口述試験の合格率
3.口述試験の内容と対策方法
3-1.口述試験の内容
3-2.口述試験の対策方法
3-2-1.事例企業を頭に入れる
3-2-2.与件文の専門用語を理解する
3-2-3.わからない問題でも何か答える
4.中小企業診断士の口述試験に関するよくある質問
4-1.過去問はどこで手に入る?模範解答はない?
4-2.口述試験は対策なしでも合格できる?
4-3.口述試験の勉強時間はどれくらい必要?
5.まとめ
1.口述試験の概要
中小企業診断士「口述試験」の概要について説明します。
1-1.口述試験の日程・スケジュール
令和6年度の中小企業診断士2次試験の日程は以下の通りです。
| 申込受付期間 | 令和6年8月23日(金) ~9月17日(火) |
| 筆記試験日 | 令和6年10月27日(日) |
| 口述試験の受験資格 を得た方の発表日 | 令和7年1月15日(水) |
| 口述試験日 | 令和7年1月26日(日) |
| 合格発表日 | 令和7年2月5日(水) |
| 実施地区 | 札幌・仙台・東京・ 名古屋・大阪/広島・ 福岡の7地区 |
※令和6年度中小企業診断士第2次試験案内より作成
口述試験は例年、1月下旬の日曜日に実施されます。口述試験の約10日前に、筆記試験の合格発表があります。
令和6年度の中小企業診断士試験の場合は、令和7年1月15日(水)に筆記試験の合格発表(口述試験の受験資格を得た方の発表)があり、口述試験は令和7年1月26日(日)に行われます。なお、口述試験の実施地区は原則、筆記試験と同じになります。
ただし、転勤を伴う住居の移転など、やむを得ない理由(試験当日の出張などは認められません)の場合は受験地区を変更することができます。
1-2.口述試験の受験資格
口述試験を受験できるのは、中小企業診断士「2次筆記試験」の合格者です。
2次筆記試験に合格した年度の口述試験のみ受験することが可能です。翌年度に持ち越すことはできません。
1-3.口述試験の試験形式・時間
試験は個別面接形式です。時間は10分程度です。
面接官2〜3人に対して、受験生が1人の面接です。筆記試験の事例を元に、4問程度が出題されます。なお、参考資料の持ち込みはできません。
1-4.口述試験の受験料
2次筆記試験の申し込み時に支払った受験料(17,800円)に含まれるため、口述試験にあたって追加の受験料は不要です。
1-5.口述試験の持ち物
受験票のみ必須です。
試験会場の待機場所は電子機器が使用できないため、プリントアウトした2次試験問題などを持っていくと良いでしょう。
1-6.口述試験の際の服装・ネクタイは必要か?
服装については指定はありません。
多くの受験生はスーツまたはビジネスカジュアルで出席します。男性の場合、ネクタイは必須ではありませんが、あった方が無難でしょう。
2.口述試験の合格基準・合格率
口述試験の合格基準や合格率について紹介します。
2-1.口述試験の合格基準
口述試験の合格基準は「評定が60%以上であること」です。
ただし、採点項目や採点基準は公開されていません。
2-2.口述試験の合格率
口述試験の合格率は下表の通りです。
例年、合格率は99%台であり、ほとんどの受験生が合格しています。
| 年度 | 筆記試験の 合格者数 | 口述試験の 合格者数 | 合格率 |
| 令和 5年度 (2023年度) | 1,557 | 1,555 | 99.9% |
| 令和 4年度 (2022年度) | 1,632 | 1,625 | 99.6% |
| 令和 3年度 (2021年度) | 1,605 | 1,600 | 99.7% |
| 令和 2年度 (2020年度) | 1,175 | 1,174 | 99.9% |
| 令和元年度 (2019年度) | 1,091 | 1,088 | 99.7% |
不合格の受験生には、体調不良等で受験ができなかった場合も含まれます。
合格率が非常に高く、口述試験では回答の質よりも、コミュニケーション能力が重要視されています。
3.口述試験の内容と対策方法
口述試験の具体的な内容と対策方法を紹介します。
3-1.口述試験の内容
口述試験の試験時間は10分程度です。受験生1人に対して、面接官が2〜3人います。
口述試験の最初に「名前と生年月日を和暦で述べてください。」と言われます。和暦ですので昭和X年や、平成Y年などと答えてください。
出題される問題は4問程度です。各質問には2分を目安に回答するよう指示されます。2次筆記試験の4つの事例からそれぞれ1題ずつ出題されるか、2つの事例から2題ずつ出題されます。
多くの場合は2つの事例から2題ずつ出題されます。また、場合によっては問題への回答に対して、追加で質問される場合があります。
口述試験の問題例は以下の通りです。
例1:X島に訪れた人をターゲットとして、近隣飲食店と協力する際にどのような方向性で進めるべきか。例2:赤字の飲食事業売却の際に留意すべきことは何か
例3:材料高騰の対策について説明してください。
回答時間が短すぎる場合や、回答の方向性が違っている場合に追加質問される場合が多いです。なお、筆記試験では事例Ⅰは人事・組織が主な範囲となりましたが、口述試験では事例と分野の関係性はありません。そのため、例えば事例Ⅰであってもマーケティングの問題が出題される場合があります。
3-2.口述試験の対策方法
中小企業診断士の口述試験は合格率が99%台と非常に高いです。
しかし、口述試験において全く回答ができない場合は不合格になる可能性があります。ここでは対策方法を紹介します。
3-2-1.事例企業を頭に入れる
口述試験では、筆記試験で出題された事例を元に問題が出されます。
また、資料の持ち込みができないため事例企業の状況を覚えておく必要があります。与件文を丸暗記する必要はありませんが、その企業の状況や強みなどを整理しておくと良いでしょう。
3-2-2.与件文の専門用語を理解する
口述試験は2次筆記試験の与件文を元に出題されるため、与件文中の専門用語については意味を覚えておくことがオススメです。2次筆記試験の問題を読み返し、理解が不十分な単語の意味をインターネットや1次試験の参考書などで調べると良いでしょう。
3-2-3.わからない問題でも何か答える
口述試験の問題は、何を回答すれば良いかわかりにくい問題がしばしば出題されます。
わからない問題があった場合でも、無言にならず、間違っても良いので何か回答することを心がけましょう。
何か回答することで、面接官から助け舟を出してくれる場合も多くあります。例えば、間違った回答をしていた場合に、面接官から「XXという視点ではどう考えられますか?」や、「XXはYYですので、売上はどうなりますか?」など、論点を絞ってくれることがあります。一方で、無言になってしまうと時間がロスする上に、次の問題に移ってしまう可能性があります。
中小企業診断士の口述試験はコミュニケーション能力が求められます。過度に緊張せず、自信を持って回答するようにしましょう。
4.中小企業診断士の口述試験に関するよくある質問
ここでは中小企業診断士の口述試験に関するよくある質問に回答します。
4-1.過去問はどこで手に入る?模範解答はない?
口述試験の過去問は公開されていません。そのため、模範解答もありません。
4-2.口述試験は対策なしでも合格できる?
口述試験は問題に対して全く回答できなければ、不合格となる可能性があります。そのため、合格率が高いからといって何も対策せず試験に臨むことはリスクがあります。
口述試験は筆記試験から3ヶ月程度時間が経過しているため、事例企業の状況を覚えていない人が多いです。2次筆記試験の時ほど勉強する必要はありませんが、口述試験前は対策をしておくことがオススメです。
4-3.口述試験の勉強時間はどれくらい必要?
口述試験の勉強時間は5〜10時間を目安にすると良いでしょう。
事例企業の状況把握や知識の補充などで5〜10時間勉強すれば十分合格できる水準に達します。もちろん、時間に余裕があれば10時間以上勉強するのも良いと思います。勉強を通じて得た知識は中小企業診断士に合格した後でも役に立ちますので、無駄にはなりません。
ただ、口述試験の合格率は99%と高いため、忙しい人は過度に時間をかける必要はないでしょう。
5.まとめ
今回の記事では中小企業診断士の口述試験の日程や持ち物、合格率や対策方法について紹介しました。まとめると次の通りです。
◉中小企業診断士の口述試験は約10分間の個別面接形式
◉2次筆記試験の4つの事例を元に、4題程度出題される
◉採点基準や過去問は公開されていない
◉口述試験は合格率が99%台と高い
◉資料の持ち込みは不可のため、事例企業を頭に入れておく必要がある
◉対策方法としては事例企業を覚えておくこと、与件文中の専門用語の意味を覚えることがおすすめ
◉口述試験ではわからない問題でも何か回答すること
◉口述試験ではコミュニケーションが大切
口述試験の合格率は高いですが、全ての問題に答えられない等の場合は、不合格となる可能性があります。事例企業を頭に入れておくことと、わからない問題でも答えることを意識して本番に挑んでください。
司法試験合格者数No.1の受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、待望の中小企業診断士試験講座を2025年1月より開講しました。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。

著者:伊藤塾 中小企業診断士試験科
伊藤塾中小企業診断士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、中小企業診断士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。