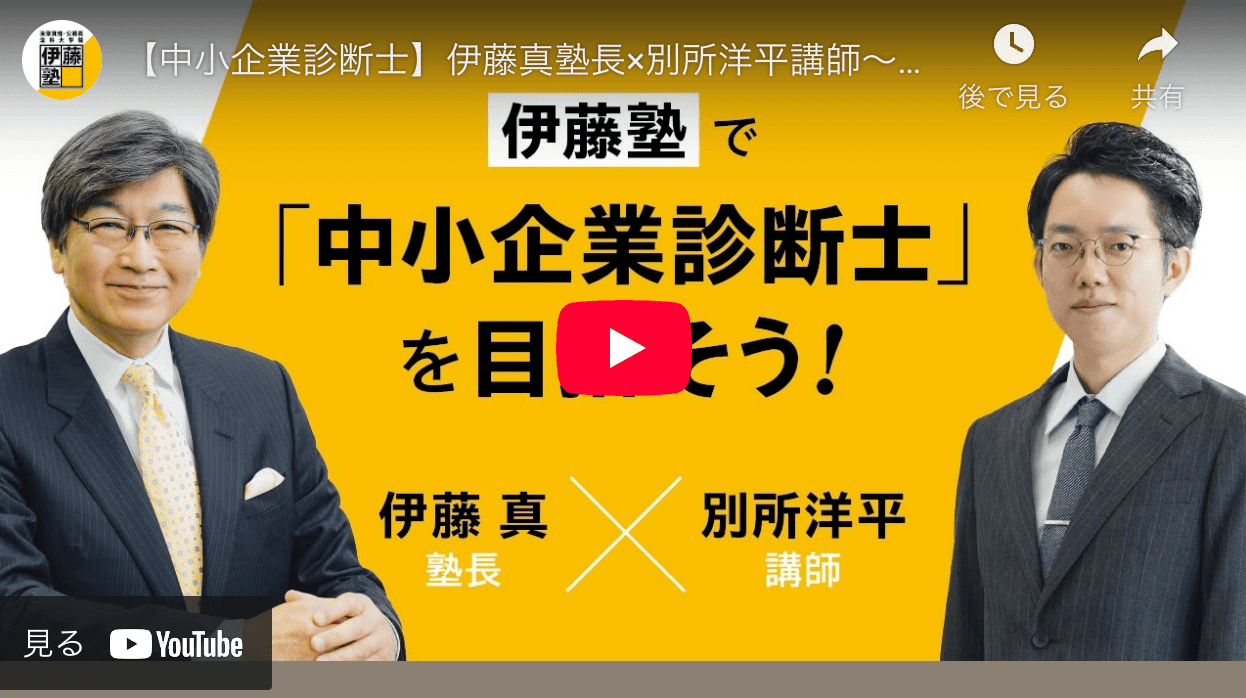中小企業診断士の試験科目は?科目ごとの特徴や攻略法、試験免除についても解説

中小企業診断士は、経営の診断や助言などを通じて中小企業の活性化を支援する、企業経営の専門家です。
近年、中小企業診断士の人気は高まっており、受験者は増加傾向にあります。そんな中、中小企業診断士の試験にはどのような科目があるのか、気になっている人も多いのではないでしょうか。
中小企業診断士の試験科目は、1次試験が7科目、2次試験が4科目あります。
また、1次試験では科目合格制度があります。
合格点(100点満点中60点)以上の科目は、翌年と翌々年の試験でその科目を免除することができます。
本記事では、中小企業診断士の試験科目を紹介し、試験免除についても解説します。また、科目ごとの特徴や攻略法なども詳しく解説してまいります。
これから中小企業診断士に挑戦するか迷っている人や、中小企業診断士に興味を持っている人はぜひ最後までご覧ください。
※科目合格制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→中小企業診断士の科目合格制度を徹底解説!戦略的な活用法と注意点も
【目次】
1.1次試験は7科目ある
1-1.1次試験の概要
1-2.1次試験の合格基準
1-2-1.1次試験の合格率
1-2-2.科目別の合格率
1-3.1次試験の試験科目について
1-3-1.経済学・経済政策
1-3-2.財務・会計
1-3-3.企業経営理論
1-3-4.運営管理(オペレーション・マネジメント)
1-3-5.経営法務
1-3-6.経営情報システム
1-3-7.中小企業経営・中小企業政策
2.試験科目の一部免除について
2-1.科目合格による免除
2-2.他資格保有等による免除
3.2次試験は4科目ある
3-1.2次試験の概要
3-2.2次試験の合格基準
3-3.2次試験の試験科目について
3-3-1.事例Ⅰ:組織・人事
3-3-2.事例Ⅱ:マーケティング・流通
3-3-3.事例Ⅲ:生産・技術
3-3-4.事例Ⅳ:財務・会計
4.中小企業診断士の試験科目に関するよくある質問
4-1.合格率はどれくらい?難しい?
4-2.中小企業診断士の勉強時間は?1,000時間必要?
4-3.中小企業診断士の仕事内容は?稼げる?
5.まとめ
1.【1次試験】は7科目ある
中小企業診断士の1次試験は7科目あり、企業経営に必要な幅広い知識が問われます。
1-1.【1次試験】の概要
中小企業診断士の1次試験はマークシート方式です。
試験1日目の科目は、経済学・経済政策、財務会計、企業経営理論、運営管理です。
試験2日目の科目は、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策です。
試験は、例年8月上旬の土日に開催されています。
<試験科目>
| 日程 | 時間帯 | 試験科目 | 試験時間 |
| 1日目 | 午前 | A. 経済学・経済政策 | 60分 |
| B. 財務・会計 | 60分 | ||
| 午後 | C. 企業経営理論 | 90分 | |
| D. 運営管理 (オペレーション ・マネジメント) | 90分 | ||
| 2日目 | 午前 | E. 経営法務 | 60分 |
| F. 経営情報システム | 60分 | ||
| 午後 | G. 中小企業経営・ 中小企業政策 | 90分 |
配点:各100点(マークシート方式)
1-2.【1次試験】の合格基準
1次試験の合格基準は下記の通りです。
(1) 第1次試験の合格基準は、総点数の 60% 以上であって、かつ1科目でも満点の 40% 未満がないことを基準とする。(2) 科目合格基準は、満点の 60% を基準とする。
したがって、1次試験は7科目700点満点の試験のため、総得点が420点以上かつ、40点未満の科目が無ければ合格となります。
1-2-1.【1次試験】の合格率
中小企業診断士試験1次試験の合格率推移を確認してみましょう。
試験が始まった平成13年からの推移を見ると、1次試験の合格率は15.7%〜51.3%と大きく変動していますが、過去5年間では、概ね30%〜40%で推移しています。
さらに、直近3年間は、20%台後半で安定している様子が伺えます。
| 年度 | 受験者数(全科目 を受験した者) | 合格者数 | 合格率 |
| 令和6年度 (2024年度) | 18,209 | 5,007 | 27.5% |
| 令和5年度 (2023年度) | 18,755 | 5,560 | 29.6% |
| 令和4年度 (2022年度) | 17,345 | 5,019 | 28.9% |
| 令和3年度 (2021年度) | 16,057 | 5,839 | 36.4% |
| 令和2年度 (2020年度) | 11,785 | 5,005 | 42.5% |
参照:中小企業診断士試験 申込者数・合格率等の推移
令和6年度 中小企業診断士第1次試験に関する統計資料
1-2-2.【1次試験】の科目別の合格率
1次試験の合格者を除いた場合の、科目合格率は以下のようになっています。
| 科目 | 令和6年度 受験者数 | 令和6年度 合格者数 | 令和6年度 合格率 | 令和5年度 合格率 |
| 経済学・ 経済政策 | 17383人 | 2487人 | 14.3% | 13.1% |
| 財務・会計 | 17108人 | 2584人 | 15.1% | 14.3% |
| 企業経営理論 | 16773人 | 6696人 | 39.9% | 19.8% |
| 運営管理 | 17417人 | 4663人 | 26.8% | 8.7% |
| 経営法務 | 14976人 | 1981人 | 13.2% | 25.6% |
| 経営情報 システム | 16699人 | 2603人 | 15.6% | 11.4% |
| 中小企業経営 中小企業政策 | 16175人 | 899人 | 5.6% | 20.6% |
例えば、令和5年度試験では経営法務の科目合格率は25.6%と高く、運営管理は8.7%と低い結果となりました。
一方で、令和6年度試験では経営法務の科目合格率は13.2%と低く、運営管理は26.8%と高くなっています。
このように、中小企業診断士の1次試験は年度によって科目合格率が大きく異なります。
したがって、過去問で勉強した際に、点数だけで一喜一憂するのではなく、その年度の難易度も加味して評価すると良いでしょう。
1-3.【1次試験】の試験科目について
1次試験の学習内容について気になっている人も多いのではないでしょうか。
まず最初に、合格に必要な学習時間を確認してみましょう。
(勉強時間については個人差が大きいため、あくまで「目安」としてご認識ください。)
| 科目 | 勉強時間 |
| 財務・会計 | 各150時間 |
| 企業経営理論 | |
| 運営管理 | |
| 上記以外 | 各80〜100時間 |
合格に必要な勉強時間は、すべての科目が等しいわけではなく、財務・会計、企業経営理論、運営管理の3科目が各150時間程度、その他の科目(経済学・経済政策、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・中小企業政策)が各80〜100時間程度といわれています。
大学時代に専攻していたり、すでに知識がある場合には、上記より少ない勉強時間で合格することも可能でしょう。
科目ごとの特徴や勉強方法について、次章で詳しく解説していきます。
※中小企業診断士の勉強時間については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→中小企業診断士の勉強時間は1000時間?短時間で合格するコツを紹介!
1-3-1.経済学・経済政策
経済学・経済政策ではマクロ経済学やミクロ経済学について学びます。
マクロ経済学では、国単位の経済活動を対象に、金融政策が経済にどのような影響を与えるかや、国内総生産(GDP) などについて学びます。
ミクロ経済学では、消費者や企業の意思決定などについて学びます。
数式やグラフが多く出てくるため、初めて経済学を勉強する人にとっては、要点を掴みにくい科目かもしれません。
丸暗記ではなく、理解して覚えることができれば、応用問題にも対応でき、点数が安定するようになります。
また、経済学の歴史は250年ほどで、時代の流れとともに議論が深まってきました。
経済学の歴史の流れをストーリーとして覚えることができれば、強固な知識となるでしょう。
科目合格率は令和5年度が13.1%、令和6年度は14.3%です。
1-3-2.財務・会計
財務・会計では財務諸表の読み方や、経営分析などを中心に勉強します。
また、投資評価や企業価値の算定方法についても学びます。
普段から経理業務に携わっている人であれば、比較的簡単に合格できると思いますが、初めて勉強する人にとっては簿記のルールを覚えるまでが大変だと思います。
また、企業の財務状況から経営分析を行う方法を学ぶため、活用できる機会が多く、面白いと感じる人も多いでしょう。
一方で、数字が苦手な人は苦手意識を持ちやすい科目でもあります。
財務会計は計算方法やルールが決まっていますので、根気よく暗記をしていくことが大切です。
特に、実際に電卓を使ったりして、手を動かしながら覚えていくことがオススメです。
科目合格率は令和5年度が14.3%、令和6年度は15.1%です。
また、財務会計は2次試験との関連が強い科目です。
1-3-3.企業経営理論
企業経営理論では経営戦略論、組織論、マーケティング論などについて学びます。
経営企画部などに所属しており、事業計画書を作成したことがある人であれば知っている専門用語は多いでしょう。
また、中小企業診断士の受験生は興味のある分野が多いと思いますので、モチベーション高く勉強できている人が多い傾向にあります。
一方で、試験問題は様々な切り口から出題されるため、言葉の内容を暗記しているだけでは正答が難しく、得点が伸び悩む人も多いです。
教科書を読んで理解するだけでなく、過去問演習を多く経験することで試験問題特有の難しさに慣れておくと良いでしょう。
科目合格率は令和5年度が19.8%、令和6年度は39.9%です。
令和6年は非常に科目合格率が高かったため、令和7年以降は難しくなると考えられます。
また、企業経営理論は2次試験との関連が強い科目です。
1-3-4.運営管理(オペレーション・マネジメント)
運営管理では、生産管理と店舗・販売管理などについて学びます。
生産管理では工場での知識(QCDや5Sなど)を学習します。製造業勤務の人であれば、馴染み深い分野かもしれません。
また、店舗・販売管理では商品の仕入れや在庫管理などを学びます。
小売店での陳列方法や価格設定なども勉強するため、学習内容と実体験が結びつき、楽しく勉強できる人も多いです。
運営管理は、製造業から小売業まで範囲が広いため、苦手な分野ができてしまいやすい科目です。
特に工場について馴染みがない人は、考え方を理解しづらいかもしれません。
教科書だけではイメージが湧きづらい場合は、Youtubeなどで工場や設備の動画を見るなどして、視覚的に覚えていくと良いでしょう。
科目合格率は令和5年度が8.7%、令和6年度は26.8%です。
また、運営管理は2次試験との関連が強い科目です。
1-3-5.経営法務
経営法務では会社法や知的財産権などを学習します。
法人の種類(株式会社や合同会社など)や、どのような場合が権利の侵害となるか、などを暗記する必要があります。
法律に関する仕事をしている人は、比較的容易に合格できるでしょう。
理解よりも暗記が重視される科目ですが、なぜその法律や仕組みが整備されたかを考え、体系立てて暗記していくことがポイントです。
経営法務は、診断士になった後も、知識を使う機会が多い科目です。
試験合格だけでなく、実際に相談された時を意識して勉強することをオススメします。
科目合格率は令和5年度が25.6%、令和6年度は13.2%です。
1-3-6.経営情報システム
経営情報システムでは情報通信技術や情報システム開発などを学習します。
例えば、コンピュータのメモリやOSなど、ハードウェアやソフトウェアの用語と役割を学んだり、システム構成や開発方法などを勉強します。
普段からパソコンやシステムを使う機会が多い人にとっては、馴染み深い科目だと思います。
一方で、パソコンやシステムに苦手意識のある人は、勉強が進みづらい科目でしょう。
他の科目と比べて、経営情報システムの用語は、DNSやSMTPのようにアルファベットの略称が多いです。
このような用語は正式名称を覚えることで、意味と関連づけがしやすくなります。
例えば、DNSはDomain Name System(ドメイン ネーム システム)の略称で、IPアドレスとドメイン名を紐付ける仕組みのことです。
もちろん、用語によっては正式名称でも覚えづらいこともあると思いますが、似たような単語が出題された時に、正しく選べるようにもなります。
科目合格率は令和5年度が11.4%、令和6年度は15.6%です。
1-3-7.中小企業経営・中小企業政策
中小企業経営・中小企業政策では日本における中小企業の位置付けや、国が行なっている支援内容などについて学びます。
統計データから、中小企業や小規模事業者の事業者数や従業員数を暗記したり、業種ごとの特徴を学習します。
細かな論点が多いため、合格点を取るために必要な頻出論点から効率良く勉強することがポイントです。
科目合格率は令和5年度が20.6%、令和6年度は5.6%です。
2.【1次試験】試験科目の一部免除について
中小企業診断士の1次試験では、以下の場合、試験科目の一部が免除されます。
| ①科目合格による免除 ②他資格保有等による免除 |
それぞれ詳しく解説します。
2-1.科目合格による免除
中小企業診断士試験には科目合格制度があります。
科目合格基準は、満点の 60%です。
つまり、7科目の合計点数が60%以上とならず、1次試験が不合格になった場合でも、60点を超えている科目があれば、その科目は合格となります。
科目合格した翌年度と、翌々年度の1次試験では試験を免除することができます。
したがって、1年目で3科目合格を目指し、2年目で残りの4科目を合格することで1次試験を突破するという計画も可能です。
なお、科目免除は受験申し込みの際に申請する必要があります。
要件を満たしていた場合でも、申請しない場合は受験する必要があります。
※中小企業診断士の科目合格についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→ 中小企業診断士の科目合格制度を徹底解説!戦略的な活用法と注意点も
2-2.他資格保有等による免除
中小企業診断士の1次試験は他資格を保有していることで、試験を免除できる制度があります。
免除の対象となるのは、経済学・経済政策、財務・会計、経営法務、経営情報システムです。
| 免除科目 | 対象者 |
| 経済学・経済政策 | 大学等の経済学の教授など (通算3年以上) |
| 経済学博士 | |
| 公認会計士試験で経済学を 受験して合格した者 | |
| 不動産鑑定士(試験合格者) 不動産鑑定士補 | |
| 財務・会計 | 公認会計士(試験合格者) 会計士補 |
| 税理士 | |
| 経営法務 | 弁護士、司法試験合格者 |
| 経営情報システム | 技術士(情報工学部門登録者) |
| ITストラテジスト 応用情報技術者など |
なお、科目免除は受験申し込みの際に申請する必要があります。
要件を満たしていた場合でも、申請しない場合は受験する必要があります。
3.【2次試験】は4科目ある
3-1.【2次試験】の概要
2次試験は筆記試験と口述試験(面接)があります。
例年、筆記試験は10月下旬、口述試験は1月下旬に実施されます。
なお、口述試験は筆記試験合格者のみが受験することができます。
2次試験の筆記試験は4科目(4事例)の試験です。制限時間は80分、配点は各100点です。
2次試験の筆記試験は記述式です。
問題冊子の与件文に事例企業(実際の企業を元にしたモデル企業)の状況が記載されており、問題文に沿って企業の分析や助言を行います。
| 科目(事例) |
| A 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 I |
| 組織(人事を含む)を中心とした 経営の戦略及び管理に関する事例 |
| B 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 II |
| マーケティング・流通を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例 |
| C 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 III |
| 生産・技術を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例 |
| D 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 IV |
| 財務・会計を中心とした経営の戦略及び管理に関する事例 |
3-2.【2次試験】の合格基準
2次試験の合格基準は下記の通りです。合格率は18%ほどの試験となっています。
筆記試験における総点数の 60% 以上で、かつ、1科目でも満点の 40% 未満がなく、口述試験における評定が 60% 以上であることを基準とします。なお、口述試験を受ける資格は、当該年度のみ有効であり、翌年度に持ち越しすることはできません。
3-3.【2次試験】の試験科目について
3-3-1.事例Ⅰ:組織・人事
事例Ⅰは組織・人事が主な論点です。事例企業が抱える組織・人事上の問題や、どのような施策に取り組むべきか、助言を行います。
1次試験の企業経営理論の知識が必要で、比較的人数の多い規模の企業について出題される傾向があります。
3-3-2.事例Ⅱ:マーケティング・流通
事例Ⅱはマーケティング・流通が主な論点です。どのような顧客に自社の製品を販売するかや、どのような新製品を開発すべきかなどを助言します。
1次試験の企業経営理論や運営管理(商品管理)の知識が必要で、小売業やサービス業の事例が多い傾向にあります。
3-3-3.事例Ⅲ:生産・技術
事例Ⅲは生産・技術が主な論点です。工場での生産計画や生産性向上などについて、分析や助言を行います。
1次試験の企業経営理論や運営管理(生産管理)の知識が必要で、製造業について出題されます。
3-3-4.事例Ⅳ:財務・会計
事例Ⅳは財務・会計が主な論点です。
与件文は短いですが、貸借対照表や損益計算書が記載されています。
計算問題が多く、電卓が必須の試験です。
1次試験の企業経営理論や財務・会計の知識が必要です。
※中小企業診断士の2次試験についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→ 中小企業診断士2次試験を解説!試験概要から出題傾向・対策まで
4.中小企業診断士の試験科目に関するよくある質問
ここでは中小企業診断士の試験科目に関するよくある質問に回答します。
4-1.合格率はどれくらい?難しい?
近年、中小企業診断士試験の1次試験の合格率は概ね30%〜40%で推移しています。
また、2次試験の合格率は18%台で推移しています。
2次試験は1次試験の合格者の中で、上位18%に入る必要があり、難易度が高い試験といえます。
※中小企業診断士試験の合格率についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→ 中小企業診断士の難易度は?合格率や攻略法を徹底解説!
4-2.中小企業診断士の勉強時間は?1,000時間必要?
中小企業診断士の勉強時間は1,000時間が目安とされています。
ただし、本業でコンサルティングを行なっていたり、診断士試験に関連する業務を行なっている人は、もっと短い時間で合格することも可能でしょう。
1次試験の勉強時間は7科目で800時間が目安で、2次試験の勉強時間は4科目で200時間が目安となります。
勉強の質を高めることができれば、短期間での合格も可能なため、社会人の多くは受験指導校を利用しています。
※中小企業診断士試験の勉強時間についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→ 中小企業診断士の勉強時間は1000時間?短時間で合格するコツを紹介!
4-3.中小企業診断士の仕事内容は?稼げる?
中小企業診断士の仕事は大きく「診る(みる)・書く・話す」の3つがあります。
◉ 診る仕事:企業診断や経営支援など
◉ 書く仕事:本や記事などの執筆など
◉ 話す仕事:セミナーや研修講師など
中小企業診断士は経営コンサルティングの専門家として多岐に活躍の機会があります。
近年は事業承継やM&A、海外進出などの分野のニーズが高く、副業で活躍している診断士も多いです。
また、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が調査した「中小企業診断士活動状況アンケート調査 結果について」によると、中小企業診断士の年収は、中央値が「501万円〜800万円」、全体の約3分の1が年収「1,000万円以上」となっており、高年収が目指せる資格といってよいでしょう。
ただし、中小企業診断士の年収は個人差が大きく、高年収を実現するためには、提供するサービスの品質向上や営業力の強化が必要不可欠です。
※中小企業診断士の仕事内容についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→ 中小企業診断士の仕事内容は?何ができる?向いてる人やキャリアパスも紹介!
5.まとめ
今回の記事では中小企業診断士の試験科目を中心に、科目合格制度や免除制度についても紹介しました。まとめると次の通りです。
◉中小企業診断士の1次試験は7科目ある。
・経済学・経済政策
・財務・会計
・企業経営理論
・運営管理(オペレーション・マネジメント)
・経営法務
・経営情報システム
・中小企業経営・中小企業政策
◉科目免除の方法は①科目合格による免除、②他資格保有等による免除 の2つがある。
◉科目合格の基準は満点の60%である。
◉科目合格は翌年と翌々年度の1次試験において、合格科目を免除することができる。
◉他資格保有等による免除は、経済学・経済政策、財務・会計、経営法務、経営情報システムの4科目に設定されている。
◉科目免除は申し込み時に申請する必要がある。申請しない場合は受験が必要となる。
◉中小企業診断士の2次試験は4科目(4事例)
・事例Ⅰ:組織(人事を含む)を中心とした経営戦略および管理に関する事例
・事例Ⅱ:マーケティング・流通を中心とした経営の戦略および管理に関する事例
・事例Ⅲ:生産・技術を中心とした経営の戦略および管理に関する事例
・事例Ⅳ:財務・会計を中心とした経営の戦略および管理に関する事例
中小企業診断士試験は簡単な試験ではありませんが、試験勉強を通じて得た知識やスキルは、一生の財産となります。
将来のキャリアアップや自己成長を目指す方は、ぜひ中小企業診断士試験に挑戦してみてください。
司法試験合格者数No.1の受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、中小企業診断士合格講座を開講中です。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。
【中小企業診断士】伊藤真塾長×別所洋平講師~伊藤塾で「中小企業診断士」を目指そう!~

著者:伊藤塾 中小企業診断士試験科
伊藤塾中小企業診断士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、中小企業診断士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。