中小企業診断士の科目合格制度を徹底解説!戦略的な活用法と注意点も
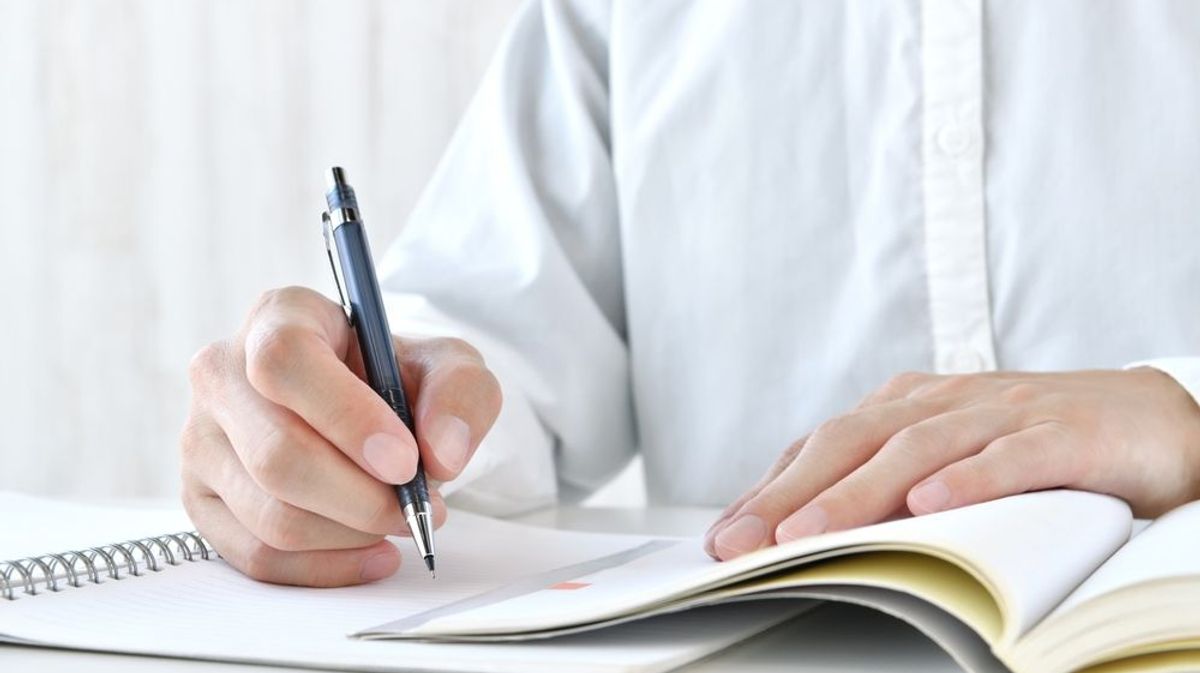
中小企業診断士は、日本で唯一の経営コンサルタントの国家資格として高い評価を受けており、多くのビジネスパーソンが取得を目指しています。しかし、その合格率は例年10%前後という難関試験であり、特に1次試験は7科目という多くの試験科目に合格する必要があります。
そこで注目したいのが「科目合格制度」です。この制度は、1次試験不合格者のうち、個別の科目で基準点(60点)以上を獲得した場合、その科目を「科目合格」として認定し、翌年と翌々年の試験でその科目の受験を免除できる制度です。
本記事では、この科目合格制度の仕組みや具体的な活用方法、注意点について詳しく解説します。また、科目合格制度を利用して、2年で合格を目指す学習プランや、科目別の合格率データ、他の資格による免除制度との併用方法なども紹介します。
中小企業診断士を目指す方はもちろん、すでに受験されている方にとっても、戦略的な試験対策のヒントとなる情報が満載です。ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1. 中小企業診断士試験の科目合格制度とは
1-1. 科目合格の基準
1-2. 科目合格の有効期限
2. 科目合格の3つの活用方法
2-1. 2年間かけて科目合格を積み重ねるケース
2-2. 得意科目を戦略的に活用するケース
2-3. 他の資格保有による科目免除を活用するケース
3. 科目合格のその他のメリット
3-1. 履歴書・名刺への記載
3-2. モチベーション維持
4. 1次試験の科目別合格率
5. 科目合格制度を活用する際の心構え
6.受験指導校を利用すれば、半年程度で1次試験合格も!
7. まとめ
1. 中小企業診断士試験の科目合格制度とは
中小企業診断士試験の科目合格制度は、1次試験不合格者を対象に、各科目で一定以上の得点を獲得した場合に与えられる制度です。この制度により、翌年と翌々年の試験で該当科目の受験が免除されます。
科目合格制度は、2005年(平成17年度)から導入された制度で、受験者の負担を軽減し、段階的に合格を目指すことを可能にしています。
1-1. 科目合格の基準
1次試験の合格基準は、総得点が満点の60%以上かつ各科目で40%以上を獲得することです。しかし、科目合格はこれとは別の基準で判定されます。
科目合格の基準は以下の通りです:
◉各科目で満点の60%以上(60点以上)を獲得すること
◉試験委員会が相当と認めた得点比率であること
1-2. 科目合格の有効期限
科目合格した場合、科目合格した翌年と翌々年の試験まで、該当科目の受験免除を申請することができます。なお、1次試験に合格した時点で、それまでの科目合格の効力は消滅します。つまり、1次試験合格後に再度1次試験を受験する場合は、全ての科目を受験する必要があります。
2. 科目合格の3つの活用方法
科目合格制度を効果的に活用することで、段階的に1次試験合格を目指すことができます。以下に、具体的な活用例をいくつか紹介します。
2-1. 2年間かけて科目合格を積み重ねるケース
最初から2年計画で1次試験合格を目指す例として、1年目で7科目全てを受験し、仮に4科目で科目合格を獲得したとします。そうすると2年目で科目合格した4科目を免除し、残りの3科目を受験して1次試験合格を目指すことになります。この方法では、翌年の受験科目数が減少するため、各年の勉強負担を軽減しながら着実に合格に近づくことができます。
2-2. 得意科目を戦略的に活用するケース
科目合格を獲得した科目の中に得意科目がある場合、必ずしもその科目を免除する必要はありません。以下のような戦略的な活用も考えられます。
1年目は7科目全てを受験し、4科目で科目合格を獲得(うち1科目が得意科目)したとします。 2年目は得意科目を除く3科目で免除を申請し、得意科目を含む4科目の受験に集中することができます。この場合、4科目受験で400点満点中240点以上かつ各科目40点以上で合格となります。得意科目で高得点を獲得できれば、他の科目でやや点数が低くても合格の可能性が高まります。
2-3. 他の資格保有による科目免除を活用するケース
中小企業診断士試験では、他の資格保有による科目免除制度もあります。この制度と科目合格による免除を組み合わせることで、さらに効率的に1次試験合格を目指すことができます。
例えば、公認会計士や税理士の資格取得者は、「財務・会計」の科目が免除されます。 この場合、1年目では6科目を受験し、3科目で科目合格を獲得したとします。 2年目では4科目を免除(公認会計士試験合格による1科目(財務・会計) + 科目合格による3科目)し、残り3科目を受験ということも可能です。このように、他の資格による免除と科目合格を組み合わせることで、受験科目数をさらに減らすことができます。
3. 科目合格のその他のメリット
科目合格には、試験対策以外にもいくつかのメリットがあります。
3-1. 履歴書・名刺への記載
科目合格を獲得した場合、以下のように履歴書や名刺に記載することができます。
例えば、「◯◯年度中小企業診断士試験科目合格者(科目名)」などと書けます。これにより、中小企業診断士資格取得に向けて努力していることをアピールできます。就職・転職活動や営業活動において、自身の専門性や学習意欲をアピールする材料となるでしょう。
3-2. モチベーション維持
複数年にわたって試験対策を行う場合、モチベーションの維持が課題となることがあります。科目合格という具体的な成果を得ることで、学習のモチベーションを高く保つことができます。
4. 1次試験の科目別合格率
科目合格を目指す上で、各科目の難易度を把握しておくことは重要です。
以下は、令和6年度中小企業診断士試験における1次試験の科目別合格率です。(比較のために令和5年度の合格率も掲載しています。)
| 科目 | 令和6年度 受験者数 | 令和6年度 合格者数 | 令和6年度 合格率 | 令和5年度 合格率 |
| 経済学・経済政策 | 17383名 | 2487名 | 14.31% | 13.11% |
| 財務・会計 | 17108名 | 2584名 | 15.10% | 14.28% |
| 企業経営理論 | 16773名 | 6696名 | 39.92% | 19.83% |
| 運営管理 | 17417名 | 4663名 | 26.77% | 8.72% |
| 経営法務 | 14976名 | 1981名 | 13.23% | 25.58% |
| 経営情報システム | 16699名 | 2603名 | 15.59% | 11.40% |
| 中小企業経営 中小企業政策 | 16175名 | 899名 | 5.56% | 20.63% |
出典:令和5年度 日本中小企業診断士協会連合会 中小企業診断士第1次試験に関する統計資料
令和6年度 日本中小企業診断士協会連合会 中小企業診断士第1次試験に関する統計資料
上記表において、令和6年度と令和5年度の各科目の合格率を比較してみましょう。
令和6年度は「企業経営理論」の合格率が最も高く、「中小企業経営・中小企業政策」の合格率が最も低いという結果となりました。しかし、令和5年度は「経営法務」の合格率が最も高く、「運営管理」がもっとも合格率が低くなっています。このように、科目ごとの合格率は、年度によって大きなばらつきがあることがわかります。
また、令和5年度はすべての科目が合格率30%未満であり、令和6年度は企業経営理論のみ30%を超えたものの、残り6科目はすべて30%未満の合格率となっています。
つまり、科目合格を獲得するためには、どの科目についても十分な準備が必要であるといってよいでしょう。
5. 科目合格制度を活用する際の心構え
科目合格制度を活用しながら中小企業診断士試験に挑戦する際は、以下のような心構えを持つことが大切です。
①長期的な視点を持つ
2年間という長期にわたる学習計画を立てる際は、焦らず着実に前進することを意識しましょう。小さな目標を設定し、一つずつクリアしていくことで、モチベーションを維持できます。
②柔軟な戦略の調整
学習を進める中で、当初の計画通りにいかないこともあります。その場合は、柔軟に戦略を調整し、最適な方法を常に模索する姿勢が重要です。定期的に学習計画を見直し、必要に応じて修正を加えましょう。
③継続的な情報収集
試験制度や出題傾向は年々変化する可能性があります。最新の情報を常にチェックし、学習計画に反映させましょう。日本中小企業診断士協会連合会 のウェブサイトや専門誌などを定期的に確認することをおすすめします。
④バランスの取れた学習
得意科目に偏らず、全科目をバランスよく学習することが重要です。特に苦手科目の克服に時間をかけることで、総合的な実力向上につながります。
⑤健康管理とストレス対策
長期間の学習は精神的にも肉体的にも負担が大きいため、適切な健康管理とストレス対策が欠かせません。規則正しい生活リズムを保ち、適度な運動や趣味の時間を確保しましょう。
6.受験指導校を利用すれば、半年程度で1次試験合格も!
科目合格制度の特徴と活用の仕方について述べてきましたが、合格までに時間的な余裕がある受験生にとっては、有益な制度といえるでしょう。
しかし、数年にわたる長い学習期間において、モチベーションと集中力を維持し続けることは容易なことではありません。
特に最近は、タイムパフォーマンスを重視し、短期集中で結果を出したい方が圧倒的に増えてきていますし、可処分時間の少ない社会人の方なら、なおさら短期間での合格を切望されているのではないでしょうか。そのような方には、ぜひ受験指導校を利用されることをおすすめします。
例えば、伊藤塾の場合、2025年1月に学習を始めて同年8月の1次試験合格を目指す「1次試験合格講座」、9〜10ヶ月程度の学習期間で中小企業診断士試験完全合格を目指す「1次・2次合格講座」など、受験指導校でしか成し得ない最短最速での合格が達成できる講座をご用意しています。短期間、短時間での合格を目指したい方は、ぜひご活用ください。
2025年1月新規開講「中小企業診断士試験対策講座ガイダンス」
7. まとめ
中小企業診断士試験の科目合格制度は、受験者にとって非常に有用な制度です。この制度を活用することで、以下のようなメリットがあります。
①年ごとの学習負担を軽減できる
②得意科目から順に合格を積み重ねられる
③長期的な学習計画を立てやすい
④履歴書や名刺に記載してアピールできる
⑤学習のモチベーション維持につながる
ただし、科目合格制度を活用する際は、以下の点に注意が必要です:
◉科目合格の有効期限は翌年と翌々年まで
◉1次試験合格後の再受験では科目合格が無効になる
科目合格制度は、中小企業診断士を目指す受験者にとって大きな味方となります。本記事の情報を参考に、自身に最適な受験戦略を立て、合格を目指してください。
伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、中小企業診断士合格講座を開講中です。詳細については、中小企業診断士講座特集 |伊藤塾をぜひご覧ください。
中小企業診断士という高度な専門資格の取得は、決して容易ではありません。しかし、適切なカリキュラムや教材を使って効果的に勉強することで、着実に合格を手にすることができます。
伊藤塾は、皆様の中小企業診断士試験合格への道のりを全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 中小企業診断士試験科
伊藤塾中小企業診断士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、中小企業診断士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。
















