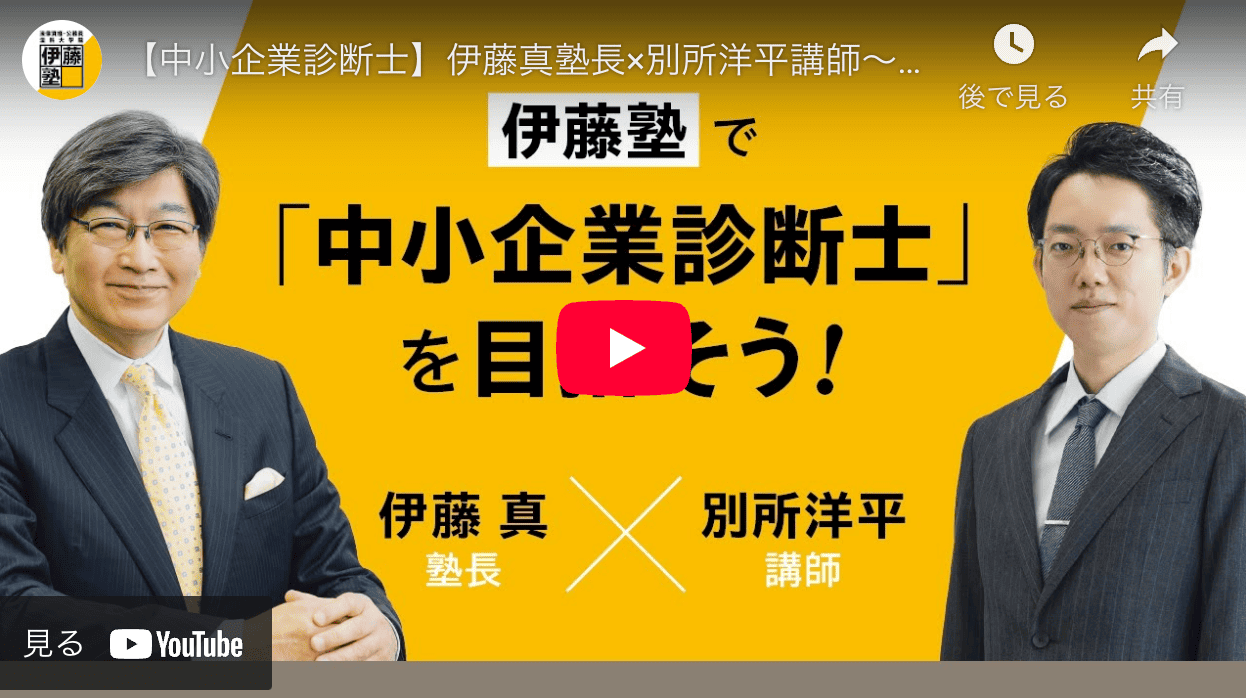中小企業診断士2次試験を解説!試験概要から出題傾向・対策まで
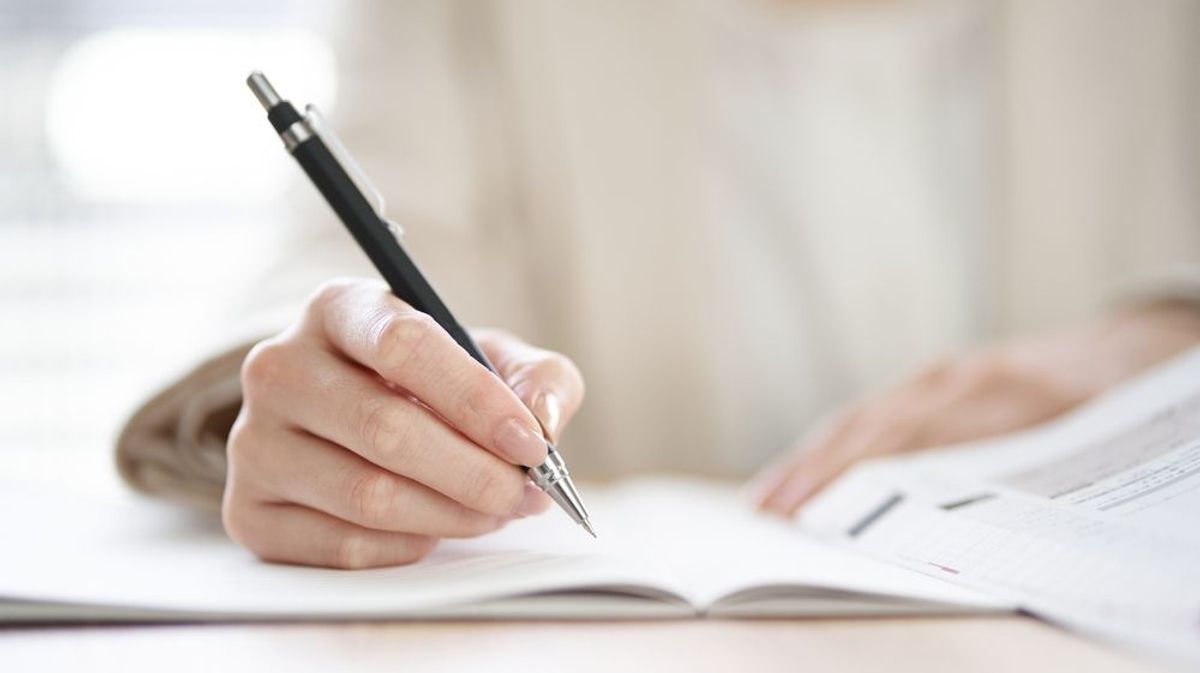
中小企業診断士は、経営の診断や助言などを通じて中小企業の活性化を支援する、企業経営の専門家です。中小企業診断士の人気は年々高まっていて、キャリアアップの資格として目指す人も増えています。
中小企業診断士になるためには、中小企業診断士試験に合格する必要があります。中小診断士試験は1次試験と2次試験に分かれ、1次試験は経済学・経済政策、財務会計、経営法務など7科目から成り、筆記で行われます。2次試験は筆記試験と口述試験があり、ケーススタディを通じた実践的な経営診断の能力が問われます。
2次試験は合格率が約18%と難易度の高い試験です。本記事では中小企業診断士試験の2次試験について概要から対策方法まで、詳しく解説します。中小企業診断士に興味がある人や、中小企業診断士の2次試験対策について知りたい人はぜひご覧ください。
※1次試験を含めた中小企業診断士試験についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→中小企業診断士試験とは?日程・科目・受験資格など試験内容を分かりやすく解説!
【目次】
1.中小企業診断士【2次試験】の概要
1-1.【2次試験】(筆記試験)について
1-1-1.受験資格
1-1-2.試験形式・時間
1-1-3.受験料
1-1-4.持ち物
1-2.【2次試験】(口述試験)について
1-2-1受験資格
1-2-2.試験形式・時間
1-2-3.受験料
1-2-4.持ち物
1-2-5.会場・実施地区
1-3.2次試験の合格基準・合格率
1-3-1.筆記試験の合格率
1-3-2.口述試験の合格率
2.【2次試験】の出題傾向と対策方法
2-1.筆記試験の傾向と対策
2-1-1.事例Ⅰ:組織・人事
①出題傾向
②対策方法・ポイント
2-1-2.事例Ⅱ:マーケティング・流通
①出題傾向
②対策方法・ポイント
2-1-3.事例Ⅲ:生産・技術
①出題傾向
②対策方法・ポイント
2-1-4.事例Ⅳ:財務・会計
①出題傾向
②対策方法・ポイント
2-2.口述試験の傾向と対策
2-3.【2次試験】攻略のポイント
2-3-1.【1次試験】の知識をしっかり固める
2-3-2.過去問分析を徹底する
2-3-3.時間配分を徹底する
2-3-4.論理的かつ簡潔な回答を意識する
2-3-5.模擬試験や第三者からのフィードバックを活用する
3.中小企業診断士の【2次試験】に関するよくある質問
3-1.過去問はどこで手に入る?模範回答はない?
3-2.【2次試験】に合格するために必要な勉強時間は?
3-3.独学でも合格できる?
4.まとめ
1.中小企業診断士【2次試験】の概要
中小企業診断士試験は1次試験と2次試験に分かれており、2次試験は筆記試験と口述試験があります。口述試験は筆記試験の合格者のみが受験できます。
◉2次試験の日程・スケジュール(令和6年度試験の場合)
| 申込受付期間 | 令和6年8月23日(金) ~9月17日(火) |
| 筆記試験日 | 令和6年10月27日(日) |
| 口述試験の受験資格 を得た方の発表日 | 令和7年1月15日(水) |
| 口述試験日 | 令和7年1月26日(日) |
| 合格発表日 | 令和7年2月5日(水) |
| 実施地区 | 札幌・仙台・東京・ 名古屋・大阪/広島・ 福岡の7地区 |
※令和6年度中小企業診断士第2次試験案内より作成
例年、2次試験の筆記試験は10月下旬の日曜日、口述試験は1月下旬の日曜日となっています。また、2次試験は1次試験開催地区の那覇・金沢・四国地区での実施はありません。
1-1.【2次試験】(筆記試験)について
1-1-1.受験資格
中小企業診断士 1次試験合格者。(受験する2次試験の実施年度と同年度、または昨年度の1次試験合格者。例えば、令和6年度の2次試験を受験するためには令和5年度または令和6年度の1次試験に合格する必要があります。)
1-1-2.試験形式・時間
| 時間 | 分数 | 配点 | 試験科目 |
| 9:40~11:00 | 80分 | 100点 | A 中小企業の診断及び 助言に関する実務の事例Ⅰ |
| 11:40~13:00 | 80分 | 100点 | B 中小企業の診断及び 助言に関する実務の事例Ⅱ |
| 14:00~15:20 | 80分 | 100点 | C 中小企業の診断及び 助言に関する実務の事例Ⅲ |
| 16:00~17:20 | 80分 | 100点 | D 中小企業の診断及び 助言に関する実務の事例Ⅳ |
筆記試験は事例Ⅰ〜Ⅳの4事例あり、各80分の試験です。
問題冊子の与件文に事例企業(実際の企業を元にしたモデル企業)の状況が記載されており、問題文に沿って企業の分析や助言を行います。
事例Ⅰ〜Ⅲでは、解答の字数制限が30〜150文字程度の問題が5題程度出題されます。事例Ⅳでは論述問題に加えて、CVP分析(損益分岐点分析)や経営数値(企業の経営状況を表す財務や業績に関する数値データ)の算出といった計算問題が出題されます。
※2次試験のみ電卓の持ち込みが可能
1-1-3.受験料
17,800円(非課税)
口述試験の受験料も上記に含まれます。
1-1-4.持ち物
(a) 受験票・写真票(規定の写真を貼付)
(b) 筆記用具:黒鉛筆またはシャープペンシル(HBまたはB程度)、消しゴム、鉛筆削り、時計、電卓など
(c) 写真が貼られている本人確認書類(運転免許証など)
時計はスマートウォッチのような通信ができるものは不可。電卓は関数電卓は不可となっています。電卓は1台のみ机上に置くことができます。定規、マーカー、色鉛筆は使用可能ですが、解答用紙には使用できません。
1-2.【2次試験】(口述試験)について
2次試験の口述試験の概要は次の通りです。
1-2-1受験資格
2次筆記試験の合格者
2次筆記試験に合格した年度の口述試験のみ受験することが可能です。翌年度に持ち越すことはできません。
1-2-2.試験形式・時間
個別面接形式。時間は10分程度です。
面接官2〜3人に対して、受験生が1人の個別面接です。筆記試験の事例を元にした4問程度が出題されます。なお、参考資料の持ち込みは不可です。
1-2-3.受験料
2次筆記試験の申し込み時に支払った受験料(17,800円)に含まれるため、口述試験にあたって追加の受験料は不要です。
1-2-4.持ち物
受験票
1-2-5.会場・実施地区
原則、筆記試験と同じ地区で受験となります。
1-3.【2次試験】の合格基準・合格率
2次試験の合格基準は次の通りです。
①筆記試験の合格基準は総点数の60%以上であって、かつ1科目でも満点の40%未満がないこと②口述試験の合格基準は評定が60%以上であること
1-3-1.筆記試験の合格率
2次試験(筆記試験)の合格率の推移は下の通りです。
合格率は18%台で推移しています。1次試験の合格者の上位18%に入る必要があるため、難易度が高い試験といってよいでしょう。
| 年度 | 受験者数(全科目 を受験した者) | 合格者数 | 合格率 |
| 令和 5年度 (2023年度) | 8,241 | 1,557 | 18.9% |
| 令和 4年度 (2022年度) | 8,745 | 1,632 | 18.7% |
| 令和 3年度 (2021年度) | 8,757 | 1,605 | 18.3% |
| 令和 2年度 (2020年度) | 6,388 | 1,175 | 18.4% |
| 令和元年度 (2019年度) | 5,954 | 1,091 | 18.3% |
出典:日本中小企業診断士協会連合会 申込者数・合格率等の推移
1-3-2.口述試験の合格率
2次試験(口述試験)の合格率の推移は下の通りです。
合格率は99%台であり、ほとんどの受験生が合格しています。不合格の場合の多くは体調不良等で受験ができなかった場合と言われています。
| 年度 | 筆記試験の 合格者数 | 口述試験の 合格者数 | 合格率 |
| 令和 5年度 (2023年度) | 1,557 | 1,555 | 99.9% |
| 令和 4年度 (2022年度) | 1,632 | 1,625 | 99.6% |
| 令和 3年度 (2021年度) | 1,605 | 1,600 | 99.7% |
| 令和 2年度 (2020年度) | 1,175 | 1,174 | 99.9% |
| 令和元年度 (2019年度) | 1,091 | 1,088 | 99.7% |
出典:日本中小企業診断士協会連合会 申込者数・合格率等の推移
2.【2次試験】の出題傾向と対策方法
2次試験では4事例が出題されます。事例ごとに主な論点が異なります。
| 科目(事例) |
| A 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 I |
| 組織(人事を含む)を中心とした 経営戦略 及び管理に関する事例 |
| B 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 II |
| マーケティング・流通を中心とした経営の戦略 及び管理に関する事例 |
| C 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 III |
| 生産・技術を中心とした経営の戦略 及び管理に関する事例 |
| D 中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 IV |
| 財務・会計を中心とした経営の戦略 及び管理に関する事例 |
2-1.筆記試験の傾向と対策
筆記試験は4事例(科目)で制限時間80分、配点は各100点です。
事例ごとにモデル企業の状況が記載された与件文がA4で3〜4ページあります。各事例の傾向と対策やポイントを紹介します。
2-1-1.事例Ⅰ:組織・人事
①出題傾向
事例Ⅰは組織・人事が主な論点です。
一次試験の企業経営理論の知識が必要です。比較的人数の多い規模の企業について出題される傾向があります。次のような問題が出題されます。
◉令和6年度,第2問(一部抜粋)『なぜ、A社は、首都圏の市場を開拓するためにプロジェクトチームを組織したのか。また、長女(後の2代目)をプロジェクトリーダーに任命した狙いは何か。100字以内で答えよ。』
◉令和5年度,第4問(設問1,一部抜粋)
『どのように組織の統合を進めていくべきか。80字以内で助言せよ。』
②対策方法・ポイント
(a)与件文を中心に回答を作成する2次試験で必要な知識は1次試験で既に学習済みです。
2次試験では、暗記した知識を使いこなすことが求められます。一方で、知識のみで作成した回答では合格点には届きません。
与件文を中心に回答を作成することがコツです。与件文の中では、事実ベースで状況が記載されています。1次試験の知識をベースにして、なぜその施策を行ったか、狙いや意図を与件文から読み取ることが大切です。
(b)時系列を意識して回答を作成する事例Ⅰでは過去、現在、未来などの時系列を意識することがポイントです。
慣れないうちは、時系列がズレた回答になることが多いためです。基本的には次の3段階を意識すると良いでしょう。①過去:創業当時や先代の時代など、過去を分析することで企業の特徴が見えてきます。
②現在:時代の変化に伴う、現在直面している課題を把握する。
③未来:①と②を踏まえた短期的、中長期的な未来への施策を助言する。
(c)組織人事の視点から回答を作成する過去の施策の分析といった設問は、与件文から読み取れることが多いです。一方で、長期的な施策の助言のような設問では、何を答えれば良いか判断しにくい場合があります。その場合は、組織人事という視点から回答の方向性を探ることがコツです。例えば、与件文から読み取れる組織人事の課題をクリアにすることで、売上向上などの課題をクリアしていくような流れです。
2-1-2.事例Ⅱ:マーケティング・流通
①出題傾向
事例Ⅱはマーケティング・流通が主な論点です。
1次試験の企業経営理論や運営管理(商品管理)の知識が必要です。事例Ⅰと比べて、小規模の企業がモデルとなることが多いです。次のような問題が出題されます。
◉令和6年度,第3問(一部抜粋)『こうした食器愛好家のニーズを充足する新規事業を手がけたいと考えている。どのような事業内容にすべきか、100字以内で提案せよ。』
◉令和5年度,第3問(一部抜粋)
『B社が取るべきプロモーションやイベントについて、100字以内で助言せよ。』
②対策方法・ポイント
(a)「誰に、何を、どのように」を意識する事例Ⅱはマーケティングが中心となるため、「誰に、何を、どのように」という視点で回答を作成すると、大きなミスをしにくいです。特に「誰に」に対してはニーズの把握が重要なため、 与件文からニーズを読み取り、施策を考えることがコツです。(b)強みを活かした回答にする
事例Ⅱでは、新商品開発や新規事業について出題されます。
この際、何を書けばいいか分からず、突拍子もない回答をしてしまうことがあります。
困った時は、強みを活かせないかという視点で考えることがコツです。 与件文には事例企業の強みに関する記述が多くあります。強みを活かした回答は、論理的で実現可能性が高いため、得点が高くなりやすいです。
2-1-3.事例Ⅲ:生産・技術
①出題傾向
事例Ⅲは生産・技術が主な論点です。
1次試験の企業経営理論や運営管理(生産管理)の知識が必要です。製造業について出題されます。次のような問題が出題されます。
◉令和6年度,第2問(一部抜粋)『生産能力の向上を図る検討を進めている。どのように工程改善を進めるべきか、100字以内で助言せよ。』 ◉令和5年度,第4問(設問1)
『収益性の低下が生じている。どのような対応策が必要なのか、120字以内で述べよ。』
②対策方法・ポイント
(a)製造業の共通課題を把握しておく事例Ⅲの事例企業は製造業ですが、金属加工業、食品製造業、革製品製造業など製造する製品は様々です。一方で、製造業の共通の課題が題材となることが多いです。過去問演習や中小企業白書などから製造業の共通の課題を知っておくことで、回答を書きやすくなります。
例)
◉熟練工の高齢化:ノウハウを次世代に繋げるために、マニュアル整備やシステム化などが必要となる。
◉急激な物価高:収益性を改善するために、生産性の向上、付加価値の高い製品の開発、販売価格の交渉などを実施する必要がある。
(b)設問から回答の切り口を正確に把握する。
事例Ⅲでは、設問ごとに何をすべきかを正しく理解しないと得点が伸びません。
生産性を向上させたいのか、品質を向上させたいのかなど、設問から回答の切り口を正しく読み取ることがポイントです。
製造業ではQ(品質)、C(コスト)、D(納期)が基本的な考え方としてあります。
一次試験で学習した知識を整理して暗記することで、設問で何が問われているか、正しく把握しましょう。
2-1-4.事例Ⅳ:財務・会計
①出題傾向
事例Ⅳは財務・会計が主な論点です。与件文は短いですが、貸借対照表や損益計算書が記載されています。計算問題が多く、電卓が必須の試験です。
1次試験の企業経営理論や財務・会計の知識が必要です。次のような問題が出題されます。
◉令和6年度,第3問(設問2,一部抜粋)『この新機械の試験的導入における正味現在価値を計算せよ。』◉令和5年度,第3問(設問3,一部抜粋)
『計算結果により、当該設備投資を初年度期首に実行すべきか、2年度期首に実行すべきかについて、根拠となる数値を示しながら50字以内で説明せよ。』
②対策方法・ポイント
(a)基本的な計算式をしっかりと暗記する事例Ⅳでは計算問題が多く出題されるため、計算式を覚えておく必要があります。与件文には年金現価係数のような、計算上必要な値は記載されていますが、式は載っていません。
頻出問題を中心に式を暗記することが大切です。
簡単な問題は早く正確に解けるようにしておくことがポイントです。
(b)難しい問題でも途中式・計算過程は回答する事例Ⅳの中には、計算結果と計算過程の両方を回答する設問があります。
残り時間が短くて計算結果を出せない場合や、途中までしか分からない場合であっても、計算の過程を回答することで部分点が貰える可能性があります。
多くの受験生が合否のボーダーラインにいるため、部分点の1点が合格に繋がることがあるので、計算過程だけでも回答しましょう。
2-2.口述試験の傾向と対策
口述試験は筆記試験の事例をもとに出題されます。多くの場合は、4つの事例のうち2つ事例が選ばれ、それぞれ2問ずつ出題されます。場合によっては4つの事例で1問ずつ出題されることもあります。
出題内容は、幅広い分野から出題されます。事例Ⅰだからといって、人事組織とは限りません。また、資料を持ち込みできないため、どのような事例企業であるかを事前に思い返しておく必要があります。
一方で、合格率が99%以上と高く、滅多に不合格になることはありません。落ち着いてコミュニケーションを取ることが大切です。面接官によっては、「他に考えられることは?」「XXという視点からはどのように考えられる?」と優しくフォローしてくれる場合もあるため、過度に緊張する必要はありません。
2-3.【2次試験】攻略のポイント
2次試験では、与えられた事例に対して論理的な解答が求められます。そのため、2次試験に合格するためには以下のポイントが重要です。
・1次試験の知識をしっかり固める・過去問分析を徹底する
・時間配分を徹底する
・論理的かつ簡潔な回答を意識する
・模擬試験や第三者からのフィードバックを活用する
それぞれ解説します。
2-3-1.【1次試験】の知識をしっかり固める
2次試験は、1次試験の知識をベースに、実際のビジネス課題に対する解決策を論述する形式です。1次試験の範囲で学んだ知識が基礎になりますので、1次試験の知識を復習し、特に重要な理論やフレームワークを活用できるようにしておくことが大切です。
2-3-2.過去問分析を徹底する
過去の2次試験の問題を解くことで、試験の傾向や出題されやすいテーマを把握できます。また、模範解答や解説を参考にして、どのような回答が求められているのか理解することが重要です。繰り返し解くことで、解答の精度とスピードを上げることができます。
2-3-3.時間配分を徹底する
2次試験は時間が限られているため、適切な時間配分が合否を左右します。各設問に対してどれだけの時間をかけるかを事前に決め、実際の試験ではその時間を守るように練習することが大切です。解答に行き詰まった場合でも、次の問題に進む勇気を持ちましょう。
2-3-4.論理的かつ簡潔な回答を意識する
2次試験では、事例問題に対して論理的な解答が求められます。複雑な表現や余計な説明を避け、簡潔に問題点を指摘し、解決策を提示する練習をすることが大切です。具体的な数値やフレームワークを使って、説得力のある解答を心がけましょう。
2-3-5.模擬試験や第三者からのフィードバックを活用する
自分一人で勉強するだけでなく、模擬試験や過去問の解答について、講師など第三者からフィードバックをもらうことが効果的です。自分では気づきにくい弱点を指摘してもらうことで、解答の質を向上させることができます。
3.中小企業診断士の【2次試験】に関するよくある質問
ここでは中小企業診断士の2次試験に関するよくある質問に回答します。
3-1.過去問はどこで手に入る?模範回答はない?
中小企業診断士2次試験の過去問は一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会のHPに掲載されています。ただし、模範解答は公開されていません。
そのため、受験指導校では、受験生が回答した答案と、実際の得点を照らし合わせることで、どのような回答であれば、どれくらいの得点であるかを分析し、それらのデータを元に、確度の高い模範解答を作成しています。
3-2.【2次試験】に合格するために必要な勉強時間は?
中小企業診断士試験の2次試験対策には200時間程度が必要といわれています。
1次試験実施後の8月から10月末までの約3ヶ月(=90日)で対策しようと考えれば、平均2.2時間の学習が目安となります。もちろん、学習時間と点数が必ずしも比例するわけではありません。特に、2次試験は記述式であるため、個人の理解度や能力によって必要な学習時間は変わってきます。
2次試験は、与えられた事例に対して、論理的な思考力や問題解決能力を用いて、具体的な解決策を提案する能力が問われます。そのため、単なる知識の詰め込みではなく、実践的なトレーニングを通じて、中小企業診断士としての思考力を養う必要があります。
3-3.独学でも合格できる?
費用面から、独学で中小企業診断士試験に合格できるのか気になっている人は多いと思います。結論から言うと、中小企業診断士試験は独学でも合格することは可能です。
ただし、2次試験に合格するためには、1次試験の合格者の中でも上位18%に入る必要があり、しっかりとした対策が必要です。特に、2次試験は筆記試験となっているため、独学の場合、日頃の学習において自分の解答が適切なのかどうか、抜け漏れのチェックなど自身で根気強く行っていかねばならず、大きな労力がかかることを覚悟しなければいけないでしょう。
そのため、もし独学での受験を迷っている場合には、まずは過去問を解いてみることから始めてみてください。普段からコンサルタントとして働いている人や、税理士の方であれば簡単と感じるかもしれません。
過去問を見て、合格をイメージできるようであれば、独学でチャレンジしてもよいでしょう。しかし、もし、限られた勉強時間の中で無駄なく効率よく、できるだけ短期間での合格を目指したい場合には、中小企業診断士試験を知り尽くした受験指導校のカリキュラムを活用されることをおすすめします。
4.まとめ
今回の記事では中小企業診断士の2次試験の概要から、筆記試験や口述試験の出題傾向や対策方法について紹介しました。まとめると次の通りです。
◉中小企業診断士の2次試験は筆記試験と口述試験がある
◉2次試験では4つの事例があり、出題内容は以下の通り
・事例Ⅱ:流通・マーケティングを中心とした出題
・事例Ⅲ:生産・技術を中心とした出題
・事例Ⅳ:財務・会計を中心とした出題
◉筆記試験は合格率は18%台と低い
◉口述試験は合格率は99%台と高い
◉筆記試験では論理の通った回答が大切
◉口述試験ではコミュニケーションが大切
◉2次試験攻略のポイントは以下の通り
・過去問分析を徹底する
・時間配分を徹底する
・論理的かつ簡潔な回答を意識する
・模擬試験や第三者からのフィードバックを活用する
2次試験は簡単な試験ではありませんが、試験勉強を通じて得た知識やスキルは、一生の財産となるでしょう。将来のキャリアアップや自己成長を目指す方は、ぜひ中小企業診断士試験に挑戦してみてください。
司法試験合格者数No.1の受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、待望の中小企業診断士試験講座を2025年1月より開講しました。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。

著者:伊藤塾 中小企業診断士試験科
伊藤塾中小企業診断士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、中小企業診断士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。