宅建の試験科目や内容は?配点や科目別の難易度・5問免除制度を解説
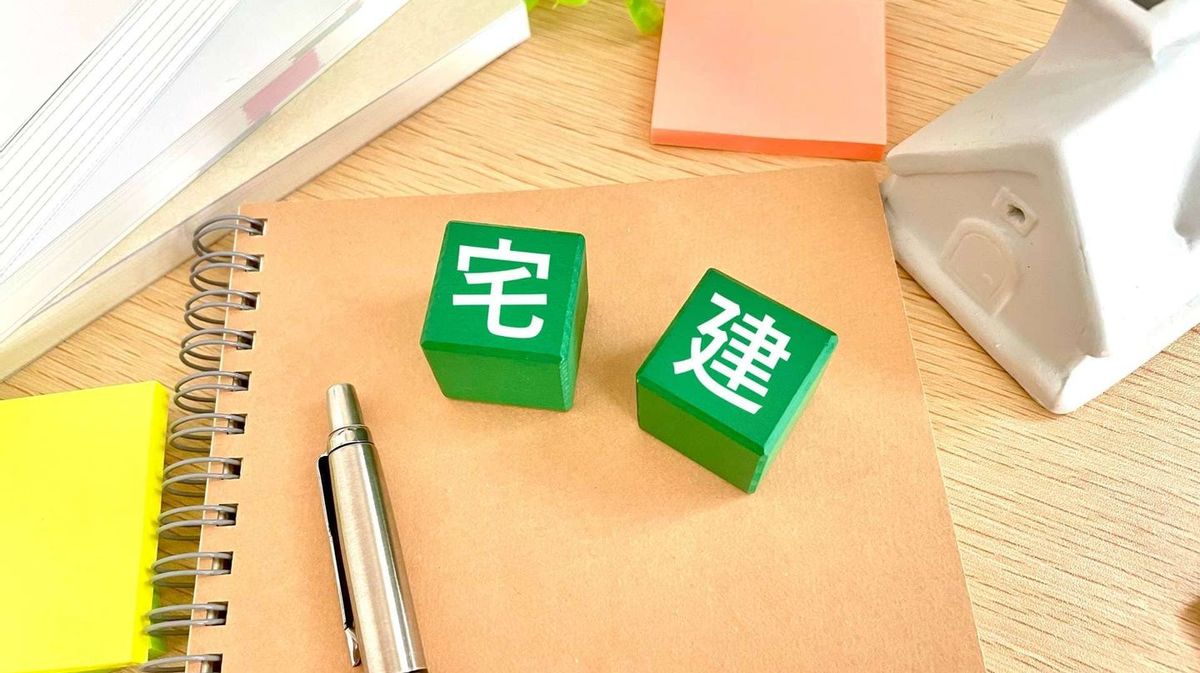
宅建士試験は毎年20万人前後が受験する法律系の国家資格です。
試験では不動産取引に関する法律の知識が問われます。科目毎に出題される問題数や出題傾向が異なるので、最短での合格を実現するには科目毎の特性をしっかり把握しておくことが重要です。
この記事では、宅建の試験科目や試験内容、配点や科目別の難易度について解説していきます。宅建試験における科目免除制度についても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.宅建とは?
2.宅建の試験基準および試験内容
3.宅建の主な試験科目・配点・目標点・勉強法
3-1.権利関係(民法等)
3-2.宅建業法
3-3.法令上の制限
3-4.税その他(免除科目含む)
4.宅建の5問免除制度とは
5.宅建の試験科目についてよくある質問(Q&A)
5-1.宅建に科目合格制度はある?
5-2.宅建の試験科目に優先順位はある?
5-3.宅建の試験科目で捨て科目はある?
6.まとめ
1.宅建とは?
宅建とは、「宅地建物取引士(宅建士)」の略称で、不動産取引に関する専門知識を持つ国家資格、または、不動産取引に関する専門家のことをいい、宅建業法に基づき、不動産取引の公正性を確保する役割を担います。
主な業務は不動産取引の場面における重要事項の説明です。不動産に関する専門知識のない方が不測の損害を被らないよう、契約に関する項目を説明する重要な仕事です。
不動産業を営む場合、従業員の数に応じて一定数の宅建士資格保有者の設置が義務付けられていることを考えると、国家資格の中でも需要の高い資格だと言えるでしょう。なお、宅建試験について気になる方はこちらの記事もご覧ください。
→ 宅建とは?試験の詳細や宅建士の仕事内容など資格のすべてを徹底解説!
→ 宅建に合格するとすごい?一発合格は可能?宅建のリアルを解説
→ 宅建士試験はどれくらい難しい?偏差値60相当?合格への道筋を解説
→【500時間必要?】宅建士試験の合格に必要な勉強時間について徹底解説!
2.宅建の試験基準および試験内容
宅建の試験基準および試験内容は、宅建業法7条および8条で次のように規定されています。
・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
・土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
・宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
・宅地及び建物の価格の評定に関すること。
・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
※ 出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。
参照:宅建試験の概要|一般財団法人 不動産適正取引推進機構
※宅建の試験日や合格発表までの流れを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
→【2025年最新】宅建の試験日は?申込み・持ち物・合格発表など試験の詳細を解説
3.宅建の主な試験科目・配点・目標点・勉強法
宅建の試験科目は一般的に次の4つに分類されます。
| 試験科目 | 問題数 |
| 権利関係 (民法等) | 14問 |
| 宅建業法 | 20問 |
| 法令上の制限 | 8問 |
| 税・その他 | 8問 |
試験形式は四肢択一のマークシート形式で、配点は1問につき1点の50点満点です。ここでは、科目ごとの特徴や目標点、勉強法などについて解説していきます。
3-1.権利関係(民法等)
◉目標点:14問中10問(10点)
権利関係は、宅建業法に次いで問題数が多い重要科目です。民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法などの法律から出題され、具体的な事例を通して法律の理解が求められます。
民法の出題範囲は広いですが、理解を伴った勉強をする事で得点源に出来る科目でもあります。条文の暗記ではなく、条文の趣旨や制度の意味を理解するよう心がけてください。法律初学者からすると苦手意識を持つ受験生が多い科目なので、得点源に出来ればライバル達に差をつける事が出来るでしょう。
他の科目でも共通しますが、権利関係を得点源にするにはアウトプット重視の勉強をする事が重要です。テキストで一通りの知識を学んだら、過去問や問題集を通して知識の定着を図りましょう。
特に民法は事例問題の出題が多く問題文も長いので、初めて問題を見た時には問題を理解する事すら大変です。繰り返し問題を解く事で、民法の出題形式に慣れておく事が本番で得点するためのポイントだと言えるでしょう。また、問題を解く際は複雑な事例を簡単な図にするクセをつけると、問題文を理解するスピードも上がります。
※ 権利関係(民法)の学習のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建の権利関係(民法)が苦手な方へ!得点力アップの秘訣を教えます
3-2.宅建業法
◉目標点:20問中18問(18点)
宅建業法は宅建の中でもっとも出題数が多い科目です。出題される問題の難易度も比較的易しいものが多いため、出来れば満点を目指したい科目です。
宅建業法では、不動産取引の場面における手続き面に関する理解が求められます。頻出項目は以下の3つです。
・重要事項説明書(35条書面)
・契約書(37条書面)
・自ら売主制限(8種制限)
勉強を進める際は、法律の趣旨からなぜそのような規定になっているかを考えながら問題を解く事が大切です。特に宅建業法の目的が不動産購入者の利益保護にあるので、問題を解く際にも常に購入者の視点に立って考えるクセをつけるようにしましょう。また宅建業法の出題は過去問からの出題が多いので、繰り返し過去問を解く事も重要です。
さらに宅建業法は法改正が頻繁に行われる部分でもあるので、最新の情報を常にチェックしておくようにしましょう。
3-3.法令上の制限
◉目標点:8問中6問(6点)
法令上の制限では、都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法など、不動産取引に関する様々な法律から出題されます。
専門用語が多く取っ付きにくい印象のある科目ですが、問題の特徴と解答のコツさえ掴めば安定して得点出来る科目でもあります。まずは出題頻度の高い都市計画法と建築基準法を中心に学習を進めましょう。勉強する際は、他の科目と同様に制度趣旨を理解することが重要です。法律そのものを暗記するのではなく、過去問を通して出題のポイントを理解するような勉強を行いましょう。
※法令上の制限」の攻略法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→ 宅建士試験「法令上の制限」の攻略法!覚え方や勉強法を解説
3-4.税その他(免除科目含む)
◉目標点:8問中5問(5点)
税その他では、固定資産税・登録免許税などの不動産関係絡みの税知識や、地価公示法・不動産鑑定評価基準などの不動産に関する基礎知識、および不動産に関する直近の統計などから出題されます。
税金関係は複雑で専門的な知識が問われます。苦手意識を持つ人も多い分野ですが、出題範囲を絞り効率よく学習すれば、比較的短期間で目標点をクリアすることも可能です。他の科目と同様に出題範囲を絞って学習し、勉強した範囲の学習を確実に得点できるようにしましょう。また統計に関しては最新のデータが出題されるので、出題されそうなデータには目を通しておくようにしましょう。
4.宅建の5問免除制度とは
宅建には、一定の要件を満たすことで試験問題が5問免除されるという制度があります。対象者が試験の申込時に免除の申請をすると、試験の最後に出題される5問(「税・その他」の中の「その他」から出題)が免除され合格ラインも5点低く設定されます。
5問免除制度の対象者は、登録講習を受けて登録講習修了試験に合格した者です。この登録講習は宅地建物取引業に従事している人(従業者証明書(宅建業法第48条第1項)を所有している人)しか受講できません。
登録講習は、2か月の通信教育と合計2日間のスクーリング(講習)で構成されています(有料)。従業者証明書を持っていればアルバイトでも講習を受講できます。なお、過去に宅建業者に勤めていた期間があったとしても、現在宅建業に従事していなければ登録講習を受講できないことに注意してください。
5.宅建の試験科目についてよくある質問(Q&A)
5-1.宅建に科目合格制度はある?
税理士試験や中小企業診断士試験には科目合格制度が存在しますが、宅建士試験にはありません。そのため合格点に満たなかった場合には、翌年、一から受験し直すことになります。
なお、5問免除制度における登録講習修了者証明書の有効期限は3年です。もし5問免除制度を使って不合格だった場合でも、講習後3年以内に行われる試験であれば免除を利用することができます。
5-2.宅建の試験科目に優先順位はある?
宅建試験の試験科目をどのような順番で勉強するか迷う方も多いですが、一般的には出題数が多く対策に時間がかかる科目から勉強していくケースが多いです。
出題数がもっとも多く法律初学者が勉強しやすい宅建業法から始める方が多いですが、法律の基礎を学ぶために権利関係(特に民法)から学ぶのも良いでしょう。もし都市計画法や建築基準法、不動産絡みの税金に関する法律に興味があるのであれば、勉強のモチベーションを保つために「法令上の制限」や「税その他」を並行して学ぶのもお勧めです。
ただし、宅建業法や権利関係の勉強を疎かにすると合格を手にすることはできません。「法令上の制限」や「税その他」はあくまでも目標点をクリアすることだけを考えて勉強し、宅建業法や権利関係で満点を取れる勉強をするのが受験対策上有用だと言えるでしょう。
5-3.宅建の試験科目で捨て科目はある?
宅建試験に捨て科目はありません。というのも宅建試験の合格ラインは例年7割程度なので、捨て科目を作ると他の科目だけはカバーしきれないほどの失点をする可能性があるからです。
例えば、2023年(令和5年)に行われた試験の合格点は36点(得点率72%)でしたが、2020年(令和2年)に行われた試験の合格点は38点(得点率76%)となっています。捨て科目を作ってしまうと、得点率76%には届かない可能性が高くなります。
安定して合格点を得点できるようにするには、初めから捨て科目を作らないようにするのが良いでしょう。権利関係と宅建業法で満点を取れるだけの実力を身につけ、他の科目で大量失点しないことを目標に据えることをお勧めします。
6.まとめ
◉宅建士試験の試験科目は大きく分けて下記4つ① 権利関係(民法等)14問
② 宅建業法 20問
③ 法令上の制限 8問
④ 税・その他(免除科目)8問
◉宅建の5問免除制度
登録講習を受けて登録講習修了試験に合格すると、宅建士試験の最後に出題される5問が免除される
宅建に合格するためには、出題数の多い権利関係や宅建業法でできるだけ得点を稼ぐ必要があります。
勉強を進める際は、出題された条文を丸暗記するのではなく法律や制度の趣旨を常に考えることが重要です。また、テキストを読んでインプットすること以上に、過去問学習を通じたアウトプット重視の勉強を進めることも合格に必要な要素です。
ただし、法律の初学者が独学で効率の良い勉強をするのは非常に困難です。1人でテキストを読んでも理解できない場合が多く、難解な法律用語にモチベーションが保てず挫折してしまう方も少なくありません。もし、最短での宅建合格を目指しているなら、受験指導校の講義を活用して合格に必要な知識を効率良く身につけてみてはいかがでしょうか。
「今年はさらにバージョンアップしたコースをご用意!!「2025年合格目標 宅建士合格講座」 のご紹介です!」
伊藤塾の「宅建士合格講座」は、2025年からバージョンアップし、よりカリキュラムが充実しました。◉本試験の分析を徹底して行い、重要事項はもちろん、出題され易いテーマや、合格後の実務を見据えて、把握しておいた方が良い個所を重点的に学習
◉受験生のビジョンに合わせた「3コース」をご用意
◉ゼロから宅建士試験合格を目指せる「スタンダードコース」
◉難しい「権利関係」の講義時間を手厚くした「スタンダードコースプラス」
◉民法の学習経験者を対象とした「法律既修者コース」
◉分かりやすい講義でテキストを解説するので理解できる
◉講義内で問題の解き方もマスターできる
◉試験傾向を徹底分析して出題されやすいテーマを効率良く講義していくので結果、学習時間が少なくて済む
◉1コマ30分でスキマ時間でも勉強可能
◉スクーリング(4時間)やオンライン質問会(2回)もあるので、わからないことは講師に直接質問が可能など、受講生からの要望に応え、独学のデメリットも解消するため、講座全体を徹底的に改良しました。2025年の宅建士試験に合格したい方は、ぜひ伊藤塾をご活用ください。
→2025年 宅建士合格講座

著者:伊藤塾 宅建士試験科
伊藤塾宅建士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、宅建士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。



.png)













