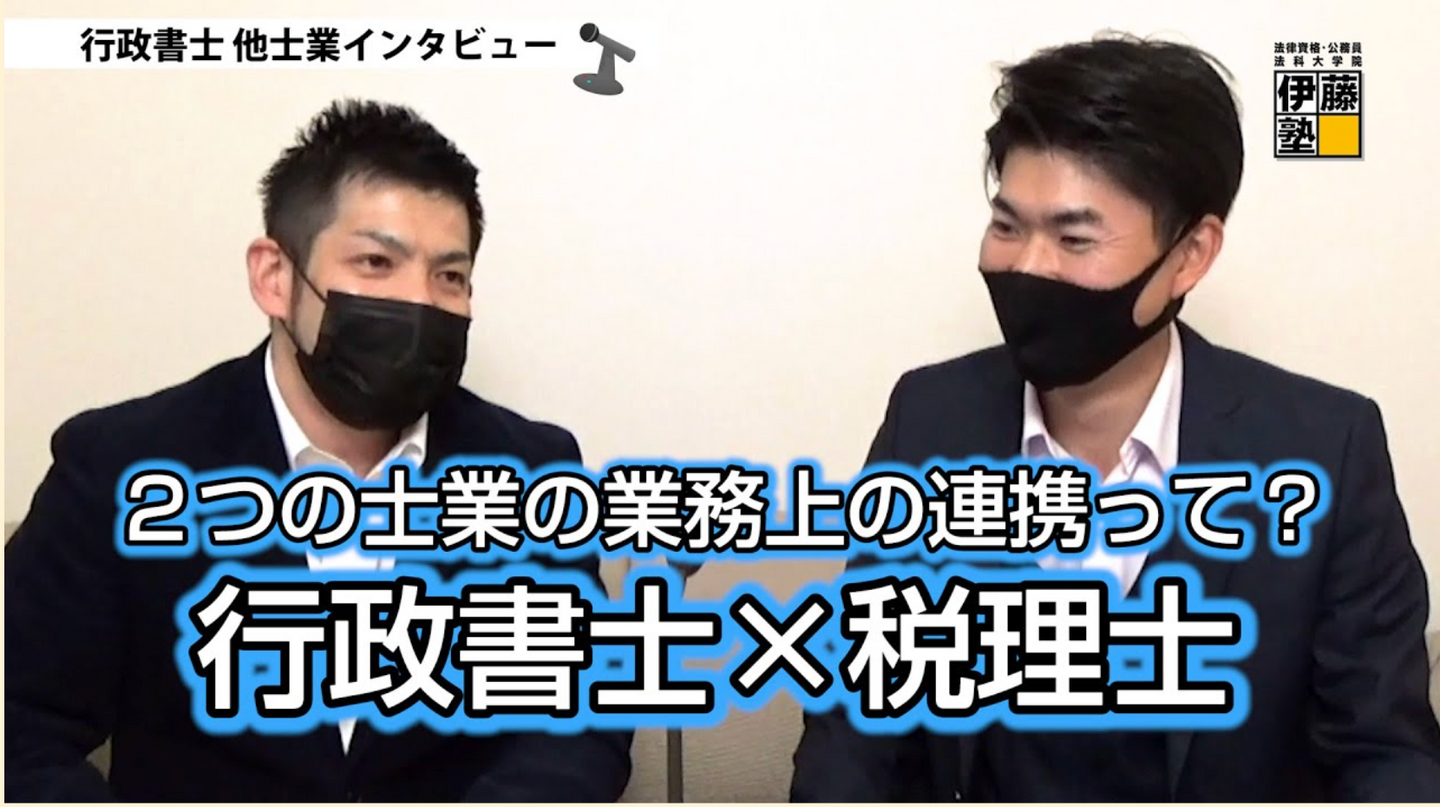行政書士と税理士の違いを完全解説!仕事内容・難易度・共通点など

行政書士と税理士は、どちらも難易度の高い国家資格です。
・「街の法律家」と呼ばれる行政書士
・「税のスペシャリスト」である税理士
得意としている専門ジャンルは異なりますが、どちらも依頼者の悩みを解決するために活動しています。本記事では、次の点を取り上げました。
・行政書士と税理士の仕事内容の違い
・試験の難易度の違い
・それぞれに向いている人の特徴
・行政書士と税理士の共通点
行政書士と税理士の違いが知りたい方は、是非ご一読ください。
【目次】
1.行政書士と税理士の仕事の違い
1-1.行政書士の仕事内容
1-2.税理士の仕事内容
1-3.行政書士と税理士の違い
2.税理士は行政書士の仕事もできる?
3.どっちが難しい?行政書士と税理士の難易度の違い
3-1.行政書士試験の難易度
3-2.税理士試験の難易度
4.向いている人の違い
4-1.行政書士に向いている人の特徴
4-2.税理士に向いている人の特徴
5.行政書士と税理士の共通点
5-1.どちらも「8士業」の1つである
5-2.仕事内容が法律で決まっている
6.【対談動画】行政書士と税理士に繋がりはある?
7.まとめ
1.行政書士と税理士の仕事の違い
行政書士と税理士は、ともに国家資格を持つ専門職です。しかし、その仕事内容には大きな違いがあります。
行政書士は「街の法律家」です。書類の作成や許認可申請の代理などを通じて、行政と国民をつなぐ役割を担っています。
一方、税理士は「税金のスペシャリスト」です。税務に関する書類の作成や申告、税務相談などを行っています。それぞれの仕事内容について詳しく見ていきましょう。
1-1.行政書士の仕事内容
行政書士は、次の3つを独占業務としています。
・官公庁に提出する書類に関連する業務・権利義務に関する書類に関連する業務
・事実証明に関する書類に関連する業務
例えば、飲食業や建設業の許可申請、在留資格の取得(入管業務)など、様々な分野における手続きを行っています。これらは、行政書士の独占業務となっているため、行政書士以外が行うことはできません。
行政書士が扱う書類の数は「1万種類」を超えるとも言われており、士業の中でも、特に幅広いジャンルを扱っています。契約書の作成、遺言書の作成なども行政書士の業務の一部です。法律の知識を活かして、個人や企業の権利を守り、スムーズな手続きをサポートするのが行政書士の仕事です。
1-2.税理士の仕事内容
税理士は、次の3つを独占業務としています。
・税務書類の作成・税務の代理
・税務相談
具体的には、確定申告や法人の決算、税務調査への対応、税務コンサルティングなどを行うのが、税理士の仕事です。会計業務に付随して、経営や資金繰りの相談を行っている税理士も多く、ビジネスを広範囲からサポートしています。
ここ数年は、社会の急激な高齢化によって、個人の相続に関する業務も増えてきています。
1-3.行政書士と税理士の違い
行政書士と税理士の違いをまとめると、次のようになります。
| 行政書士 | 税理士 | |
| 役割 | 行政手続きの専門家 | 税金の専門家 |
| 独占業務 | ・官公庁に提出する 書類に関連する業務 ・権利義務に関する 書類に関連する業務 ・事実証明に関する 書類に関連する業務 | ・税務書類の作成 ・税務の代理 ・税務相談 |
| 仕事の ジャンル | ・士業の中でも特に幅広い (扱う書類の数は1万以上) | 税務に特化している |
どちらも専門職である点は共通していますが、税理士の方が、より1つのジャンルに特化しています。個人・法人・事業規模などの違いはあるものの、基本的には税務に関する内容が中心となるからです。
一方、行政書士が扱うジャンルは人によって様々です。
・入管業務を専門としている行政書士
・相続業務を専門としている行政書士
・建設業を専門としている行政書士 など
行政書士が取り扱う「許認可申請」の数は、1万種類を超えていると言われています。
(出典:許認可等の統一的把握結果|総務省)
全ての許認可申請に精通することは現実的ではないため、特定ジャンルに特化して実績を積んでいく人が多いです。
2.税理士は行政書士の仕事もできる?
税理士は、行政書士試験を受けなくても行政書士として登録できます。そのため、税理士は行政書士の仕事もできると思っている人もいるかもしれません。
【行政書士法 第二条(資格)】次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
五 税理士となる資格を有する者
しかし、法律上認められていることと、実際にできることは全く別の話です。そもそも、税理士と行政書士では、担当する職務領域が違います。例えば、相続の場面で考えると、相続税の計算は税理士の専門ですが、遺言書の作成は行政書士の専門です。
それぞれの分野で、必要な知識やスキルは全く異なります。実際、税理士の数は8万人を超えていますが、このうち行政書士として登録している人は10%未満(5千人程度)しかいません。
(出典:行政書士の登録状況(令和4年度)|総務省)
多くの事務所では、複数の税理士と行政書士が連携して業務を行っているのが実情です。つまり、法律上認められているからと言って、税理士が行政書士の仕事もできるとは限らないのです。税理士が行政書士業務を行うには、必要な知識とスキルを身につける必要があります。
3.どっちが難しい?行政書士と税理士の難易度の違い
行政書士試験と税理士試験は、どちらも難易度の高い国家試験です。法律系の試験である行政書士試験と、会計系の試験である税理士試験を比較することは難しいですが、あえて比較すると次のようになります。
| 行政書士試験 | 税理士試験 | |
| 合格率 | 10%〜14% | 18%〜20% |
| 勉強時間 | 600時間〜1,000時間 | 2,000時間〜3,000時間 |
| 合格の期間 | 3ヶ月〜3年 | 2〜3年 |
| 特徴 | ・法律系の国家試験 ・科目合格制はなし ・短期集中でも合格 できる | ・会計系の国家試験 ・科目合格制 ・数年かけて合格する 人が多い |
3-1.行政書士試験の難易度
行政書士試験は、法律に関する知識が問われる国家試験です。民法や行政法、行政書士の業務に関し必要な基礎知識など、幅広い科目で構成されています。出題形式も、択一式・多肢選択式・記述式など様々です。
【行政書士試験の合格率】
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| 2024年(令和6年度) | 47,785 | 6,165 | 12.90% |
| 2023年(令和5年度) | 46,991 | 6,571 | 13.98% |
| 2022年(令和4年度) | 47,850 | 5,802 | 12.13% |
| 2021年(令和3年度) | 47,870 | 5,353 | 11.18% |
| 2020年(令和2年度) | 41,681 | 4,470 | 10.72% |
参照:最近10年間における行政書士試験結果の推移|行政書士試験研究センターより一部抜粋
合格率は例年10%〜14%前後と、比較的低い水準です。合格には幅広い法律知識が求められますが、合格率からイメージするほど難しい試験ではありません。
勉強の進め方を間違えてしまうと、数年かけて合格できない人もいますが、正しい方法で効率的に対策すると、数ヶ月で合格する人もいます。今まで法律に触れたことのない人にとっても、合格を目指しやすい試験といえるでしょう。
3-2.税理士試験の難易度
一方、税理士試験は、税に関する専門知識が問われる難関試験として知られています。簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法など11科目で構成されており、11科目中5科目に合格することが必要です。
【税理士試験の合格率】
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2024年度 | 34,757 | 5,762 | 16.6% |
| 2023年度 | 32,893 | 7,125 | 21.7% |
| 2022年度 | 28,853 | 5,626 | 19.5% |
| 2021年度 | 27,299 | 5,139 | 18.8% |
| 2020年度 | 26,673 | 5,402 | 20.3% |
| 2019年度 | 29,779 | 5,388 | 18.1% |
合格率だけを見ると、行政書士試験より高いですが、決して簡単な試験ではありません。
科目合格制が取られているため、1年1科目といった流れで進めていく人も多いです。合格に必要な期間は行政書士試験よりも長く、2〜3年かかるケースが通常です。
4.向いている人の違い
行政書士と税理士は、それぞれ向いている人の特徴が異なります。どちらの職業も、高度な知識と経験が必要とされる専門職ですが、求められるスキルや適性には違いがあるのです。ここでは、行政書士と税理士それぞれに向いている人の特徴を説明します。
4-1.行政書士に向いている人の特徴
行政書士に向いているのは、法律家として働きたい人です。
行政書士試験は、本格的な法律系国家資格試験の中で、登竜門のような位置づけにある資格です。合格すると、官公庁に対する許認可申請や、各種の書類作成など、法律的な側面から依頼者の問題を解決していくことができます。
さらに、行政書士試験に合格したことをきっかけに、司法書士試験や司法試験など別の法律資格に挑戦する人もいます。未経験からでも法律職として働きたい、法律家にキャリアチェンジしたいという人にとっては、うってつけの資格だと言えるでしょう。
4-2.税理士に向いている人の特徴
一方、税理士は、会計・経理などの数字を扱った仕事が好きな人に向いている資格です。
・企業の経理部で働いていて、会計業務が得意だった人
・簿記の資格を持っており、勉強がとても楽しいと感じられた人
・企業の財務状況を分析することに興味がある人
上記のような特徴がある人は、税理士として活躍できる可能性が高いでしょう。
税理士の特徴は、独立開業しやすいだけでなく、就職・転職にも強いことです。また、経営コンサルタントのような一面もあるため、お金の側面から企業の経営をサポートしていきたい人にもオススメの資格です。税理士になれば、会計の専門家として、多くの企業から頼られる存在になれるでしょう。
5.行政書士と税理士の共通点
行政書士と税理士には、いくつか共通点もあります。例えば、どちらも「8士業」の1つに数えられていることや、仕事内容が全て法律で決まっていること等が挙げられます。
5-1.どちらも「8士業」の1つである
行政書士と税理士は、どちらも8士業の1つに数えられています。
8士業とは、「士業」の中でも特に「職務上必要な場合に、住民票や戸籍などの書類を請求できる権限が認められている職種」です。
具体的には、弁護士、司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士の8つの職業が、8士業と呼ばれています。いずれの職業も、社会からの信頼は抜群に高く、国民の権利を守るために重要な役割を果たしています。
5-2.仕事内容が法律で決まっている
仕事内容が法律で決まっていることも、行政書士と税理士の共通点です。どちらの仕事も、担当できる業務の範囲や進め方などは、全て法律によって決められています。
これはメリットでもありますが、一方で差別化が難しいという欠点にも繋がります。
依頼を受けた仕事だけを単にこなしていくだけでは、生き残っていくのは難しいでしょう。
大切なのは、依頼者とコミュニケーションをとり、信頼関係を構築していくことです。
・依頼者は何に悩んでいるのか
・本質的な問題点はどこにあるのか
依頼者は、必ずしも自分の抱えている悩みを分かりやすく伝えてくれるとは限りません。
複雑な事情があって相談しにくいケース、そもそも自分でも気づいていないケースなど様々です。
そのため、行政書士・税理士いずれも、見えないところを察する力が求められます。依頼者に寄り添い、法律で定められた範囲内で、どれだけの付加価値を提供できるかが、専門家としての腕の見せどころといえるでしょう。
6.【対談動画】行政書士と税理士に繋がりはある?
それぞれ異なった仕事を扱う「行政書士」と「税理士」ですが、2つの職業に仕事上の接点はあるのでしょうか?
伊藤塾の井内講師と税理士の先生に、「行政書士と税理士の繋がり」について対談をしていただきました。
実務家ならではの視点から、両者の関係性について深掘りしていきます。ぜひご覧ください。
7.まとめ
最後に、今回の記事のポイントをまとめます。
◉ 行政書士は、行政手続きの専門家
◉ 税理士は、税務のスペシャリスト
◉ どちらも「8士業」の1つで、異なった独占業務を持っている
◉ 試験の合格率は、税理士試験の方が若干高い
◉ ただし、税理士試験は科目合格制となっており、合格までに数年かかる人が多い
◉ 未経験からでも挑戦しやすいのは、行政書士試験
◉ 正しい勉強をすれば、数ヶ月で合格する人もいる
◉ 行政書士と税理士が連携することで、質の高いサービスを提供できる
行政書士試験に挑戦したい方は、ぜひ法律資格専門の指導校である伊藤塾へご相談ください。
伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「行政書士合格講座」を開講しています。
→「2025年合格目標 行政書士合格講座」はこちら
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。