【2024年】行政書士試験科目「一般知識等」から「基礎知識」への改正と対策について解説
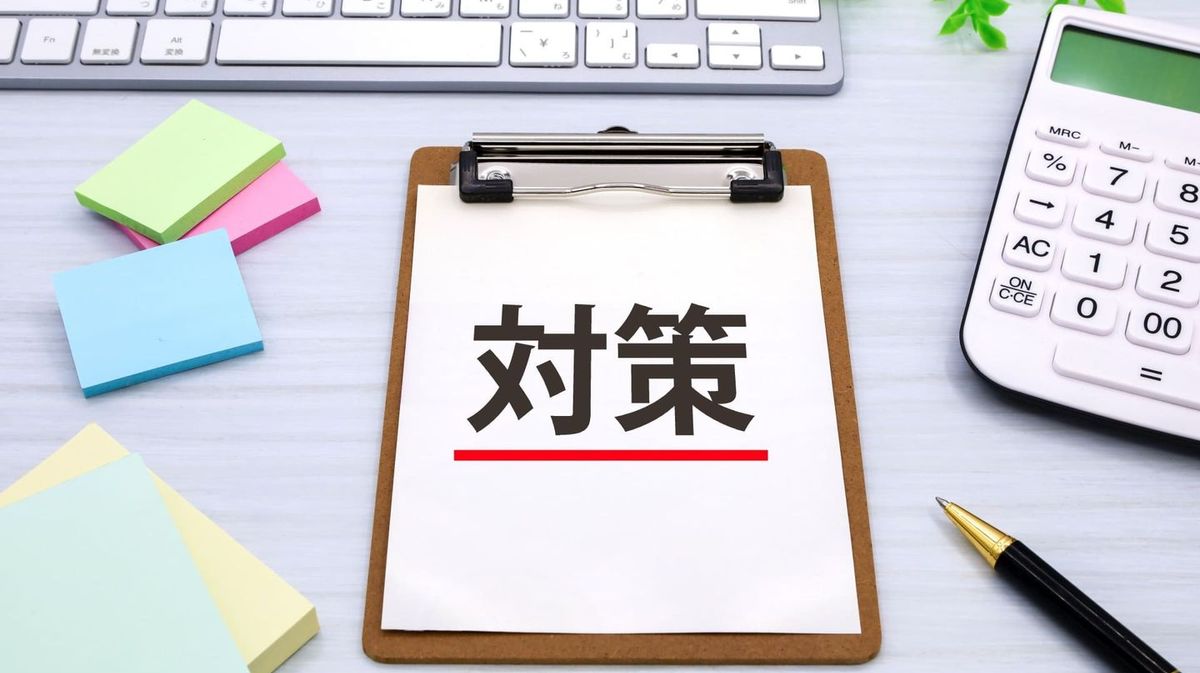
行政書士試験では、例年「行政書士の業務に関連する一般知識等」として出題されていた科目が、令和6年(2024年)に行われる試験から、「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」として改正され出題されるようになります。
法令等科目と違い、基礎知識科目(旧一般知識等科目)は試験範囲が広く、どうやって対策をすればいいのかわからない受験生も多いと思います。
そこで、この記事では、基礎知識科目(旧一般知識等科目)の勉強を始める時期や、合格基準点を超えるための具体的な勉強法について解説していきます。
過去問の有効性や満点を取る必要性についても解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.行政書士試験の試験科目は2024年度より改正される!
1-1.試験科目
1-2.出題数および配点
1-3.合格基準点
2.行政書士試験の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策とは?
2-1.一般知識
2-2.行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令
2-3.情報通信・個人情報保護
2-4.文章理解
3.行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)は満点を目指すき?
4.行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策で過去問は有効?
5.行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策はいつから始めるべき?
6.行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策を効率良く進めるなら受験指導校を利用するのがおすすめ
7.まとめ
1.行政書士試験の試験科目は2024年度より改正される!
行政書士試験では、例年「行政書士の業務に関し必要な法令等」と「行政書士の業務に関連する一般知識等」の大きく2つの試験科目が出題されていました。
しかし、「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に伴い、令和6年度(2024年度)以降の行政書士試験では、試験科目の一部が変更されることになりました。
近年、行政手続きのデジタル化や複雑さを解消するためのサポートをはじめ、時代のニーズに合わせた新たな業務が次々に誕生するなど、行政書士の活躍の幅は年々広がっています。
こうした流れの中で、顧客ニーズの多様化に対応し、住民に幅広い法務サービスを提供できるよう、行政書士試験においても、実態に合わせた知識が問われるようになりました。
1-1.試験科目
試験科目の具体的な変更点は、次の通りです。
| 【新】 令和6年(2024年) 以降の試験科目 | 【行政書士の業務に関し必要な法令等】 ・憲法 ・行政法 ・民法 ・商法(会社法を含む) ・基礎法学 |
| 【行政書士の業務に関し必要な基礎知識】 ・一般知識(従来の「政治・経済・社会」含む) ・行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 (行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法等) ・情報通信、個人情報保護 ・文章理解 | |
| 【旧】 令和5年(2023年) 以前の試験科目 | 【行政書士の業務に関し必要な法令等】 ・憲法 ・行政法 ・民法 ・商法(会社法を含む) ・基礎法学 |
| 【行政書士の業務に関連する一般知識等】 ・政治、経済、社会 ・情報通信、個人情報保護 ・文章理解 |
参照:「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改正について 概要|総務省
【行政書士の業務に関し必要な法令等】に関して変更はありませんが、【行政書士の業務に関連する一般知識等】は【行政書士の業務に関し必要な基礎知識】に変更となります。
従来出題されていた「政治、経済、社会」については、基礎知識科目の中の「一般知識」から出題されることになりました。
また、新たに「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」が試験科目に追加されました。
「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」では、従来より「一般知識等」の範囲内で出題される可能性のあった「行政書士法」、「戸籍法」、「住民基本台帳法」等が出題されます。
参照:「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改正について 概要 別紙2|総務省
1-2.出題数および配点
行政書士試験における各科目の出題数および配点は次の通りです。
なお、令和6年度(2024年度)の行政書士試験における、各科目の具体的な配点はまだ公表されていないため、令和5年度(2023年度) に行われた行政書士試験の配点についてご紹介します。
【出題数】
| 行政書士の業務に関し必要な法令等 | 46題 |
| 行政書士の業務に関し必要な基礎知識 | 14題 |
【配点】※令和5年度(2023年度)の配点
| 試験科目 | 出題形式 | 出題数 | 満点 | |
| 法令等 | 択一式 | 5肢択一式 | 40問 | 160点 |
| 多肢選択式 | 3問 | 24点 | ||
| 記述式 | 3問 | 60点 | ||
| 計 | 46問 | 244点 | ||
| 一般知識等 ※令和6年度からは 基礎知識に変更 | 択一式 | 5肢択一式 | 14問 | 56点 |
| 合計 | 60問 | 300点 | ||
前述の通り、令和6年度(2024年度)以降の試験では、試験科目の名称が変更になります。
しかし、出題数は例年通りとなっていることから、配点についても大きな変更はないと推測されます。
1-3.合格基準点
行政書士試験では、例年3つの合格基準点が設定されています。
令和5年度(2023年度) に行われた行政書士試験では、①「法令等科目」、②「一般知識等科目」、③試験全体の得点数、それぞれに設定された合格基準点を超えない限り、合格を手にすることはできませんでした。
令和6年度(2024年度)以降の試験からは、試験科目が若干変更されますが、試験範囲や出題数が変わるわけではないので、例年通り3つの基準点が設けられると推測されます。
なお、参考までに、令和5年度(2023年度) に行われた行政書士試験の合格基準点を掲載しておきます。
| 基準① | 行政書士の業務に関し 必要な「法令等科目」 の得点が、満点の50% 以上である者 | 満点:244点 合格基準点:122点 得点率:50% |
| 基準② | 行政書士の業務に関連 し必要な「基礎知識科 目」の得点が、満点の 40%以上である者 | 満点:56点 合格基準点:24点 得点率:42.86% |
| 基準③ | 「試験全体の得点」 が、満点の60%以上で ある者 | 満点:300点 合格基準点:180点 得点率:60% |
参照:令和5年度行政書士試験合否判定基準|一般財団法人 行政書士試験研究センター
2.行政書士試験の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策とは?
行政書士試験で出題される基礎知識科目(旧一般知識等科目)は出題範囲が広く、どうやって対策したらいいのかよくわからない方も多いと思います。
基礎知識科目(旧一般知識等科目)の勉強に時間をかけすぎてしまい、配点の大きい法令等科目の勉強が疎かになってしまうと、本試験で全体の合格基準点に届かなくなってしまう恐れがあります。
ここでは、基礎知識科目(旧一般知識等科目)で効率良く得点するための勉強法について、出題分野ごとにそれぞれ解説していきます。
2-1.一般知識
行政書士試験における基礎知識科目(旧一般知識等科目)の中の「一般知識」分野では、従来から出題されている「政治・経済・社会」の問題だけでなく、歴史や時事問題など、多岐に渡る一般知識に関する問題が出題されます。
例えば、令和5年度(2023年度) に行われた行政書士試験では、日本のテロ対策や平等と差別、社会保障・社会福祉に関する問題などが出題されています。
出題範囲が広いため、出題範囲全てを網羅的に勉強するのは非効率です。
満点を目指すのではなく、他の科目の足を引っ張らない程度に得点する、という戦略を立てるのがお勧めです。
具体的な勉強方法は、参考書をやり込むというよりも、ニュースアプリ等で日常的に時事問題に触れる機会を作るなど、幅広い知識を浅く身につけることを意識すると良いでしょう。
また、日本だけでなく世界で起きている様々な出来事に対して、「なぜそうなるのか?」と常に疑問を持つようにすると、幅広い知識を長期記憶として蓄えやすくなるでしょう。
2-2.行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令
「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」の分野にはさまざまなものがありますが、「行政書士試験の施行に関する定め」の一部改正について 概要 別紙2|総務省によると、主に「行政書士法」「戸籍法」「住民基本台帳法」等の知識が問われます。
具体的にどのような問題が出題されるかはわかりませんが、これらの科目は、平成17年までは行政書士試験の試験科目だったため、出題されていた当時の問題を解けば、問題の出題傾向を大まかに掴めるでしょう。
ただし、法改正に伴い、すでに問題自体が成立しなくなっている可能性もあるため、当時の問題をそのまま暗記するような勉強は避けてください。
市販の問題集で学ぶのもよいですが、法改正への対応や、出題範囲を効率良く学ぶためにも、受験指導校の講座を利用したり、模試で出題された問題をストックしておく勉強法がお勧めです。
2-3.情報通信・個人情報保護
「情報通信・個人情報保護」の分野では、基本的なIT用語に関する知識や、情報公開法・個人情報保護法・公文書管理法・プロバイダ責任法などの、細かな法律に関する出題がされます。
広範な知識を問われる「一般知識」の分野とは異なり、情報通信・個人情報に関する知識について問われる分野ということもあり、出題範囲が比較的絞りやすいのが特徴です。
特に、IT用語やその定義に関する基本的な知識については、深く理解しなくても、なんとなく用語の意味がわかれば得点できる問題も多いです。
過去問や模試などで出題された問題については、確実に得点できるように準備しておきましょう。
2-4.文章理解
「文章理解」の分野では、評論文や随筆など、特定の文章に対する理解力や表現力が問われます。
出題形式は様々ですが、高校・大学受験における現代文をイメージするとわかりやすいかもしれません。
「一般知識」分野と同様に対策しづらく感じるかもしれませんが、特別な知識は必要なく、問題を解くコツさえ掴んでしまえば、得点源にできる分野でもあります。
過去問や模試の問題を解きながら、時間内に適切な解答を導くコツを掴む勉強法がお勧めです。
3.行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)は満点を目指すべき?
令和5年度(2023年度)の行政書士試験では、一般知識等科目において、56点満点中24点以上の得点が必要でした。
約40%の得点率で一般知識等科目の合格基準点を超えられると考えると、無理に満点を目指す必要はありません。
そもそも、基礎知識科目(旧一般知識等科目)に関する出題範囲は広範で、問題の予測をすることが非常に困難です。
あまりに勉強時間をかけすぎてしまうと、配点の高い法令等科目の勉強にかける時間がなくなってしまうおそれもあります。
そのため、基礎知識科目(旧一般知識等科目)については、合格基準点を少し超えるくらいの得点を目指し、全体の合格基準点については、法令等科目でカバーする学習戦略を立てるのが良いでしょう。
4.行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策で過去問は有効?
行政書士試験の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策として、過去問を活用することは有益です。
「一般知識」分野で、全く同じ問題が出題されることはありませんが、具体的にどのような問題が出題されるのか、どの程度の知識がなければ解けないのかを知るためには、過去問は最良の素材となります。
また、比較的出題傾向が定まっている「情報通信・個人情報保護」の分野については、過去問を解くことで大まかな出題傾向を掴むことが出来ます。
さらに、「文章理解」においては、過去問で問題演習を重ねておくことで、解答を導くコツを掴むことができるでしょう。
5.行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策はいつから始めるべき?
行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)の対策をいつから始めるべきかは、人それぞれ異なるため一概には言えません。
しかし、範囲が広く、勉強する範囲を絞りづらいことを考えると、なるべく早めに勉強を開始することをお勧めします。
民法や行政法などの法令等科目と違い、「一般知識」分野に関する知識は一朝一夕では身につきません。
日本だけでなく、世界で起きる様々な出来事に対してアンテナを張っておき、広い知識を身につけることが必要だからです。
また、「文書理解」の分野では、問題を解くコツを掴むためにも、できるだけ問題演習を重ねておく必要があります。
もちろん、必要以上に勉強時間を割くべきではありませんが、日常生活において気になるニュースについては調べる癖をつけておくのが、「一般知識」分野の対策として重要になるでしょう。
6.行政書士の基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策を効率良く進めるなら受験指導校を利用するのがおすすめ
行政書士試験において基礎知識科目(旧一般知識等科目)対策を効率よく進めたいなら、受験指導校の対策講座を利用するのがお勧めです。
行政書士試験で出題される基礎知識科目(旧一般知識等科目)は、その出題範囲が膨大で、自分1人で効果的な勉強をするのは困難です。
特に、自分の興味のある分野だと、必要以上に学習時間を割いてしまい、民法や行政法などの配点が高い科目の勉強が疎かになってしまう恐れもあります。
一方で、勉強の方向性を間違えてしまうと、勉強時間を割いたにも関わらず、本番で得点が伸びず、合格基準点を満たさない可能性もあるでしょう。
受験指導校では、それぞれの学習進度に合わせた様々な対策講座が用意されています。
本番で得点するためのコツや、学習範囲を絞ったテキストで効率よく学習すれば、基礎知識科目(旧一般知識等科目)にかける勉強時間を短縮でき、その分を法令等科目の勉強時間に回すことできるでしょう。
7.まとめ
令和6年(2024年)に行われる行政書士試験から変更となる基礎知識科目(旧一般知識等科目)では、次の4つの分野に関する問題が出題されます。
①一般知識(従来の「政治・経済・社会」含む)
②行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令(行政書士法・戸籍法・住民基本台帳法等)
③情報通信、個人情報保護
④文章理解
①については、世界中で起きている幅広い知識を身につけるために、日頃からニュース等を確認する習慣をつけおきましょう。
また、②、③については、ある程度出題される分野が決まっているため、過去問などで出題傾向を把握し、得点しやすい分野については、基本的な知識をしっかり固めておく必要があります。
いずれにせよ、行政書士合格を目指すなら、基礎知識科目(旧一般知識等科目)については合格基準点をクリアできるような得点を目指し、法令等科目で全体の合格基準点をカバーできるような戦略を立てるのが良いでしょう。
伊藤塾では、法律を初歩からしっかり学習していくことができる「合格講座」を開講しています。

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

















