行政書士が独立開業するには?年収・資金・成功のポイントを解説!
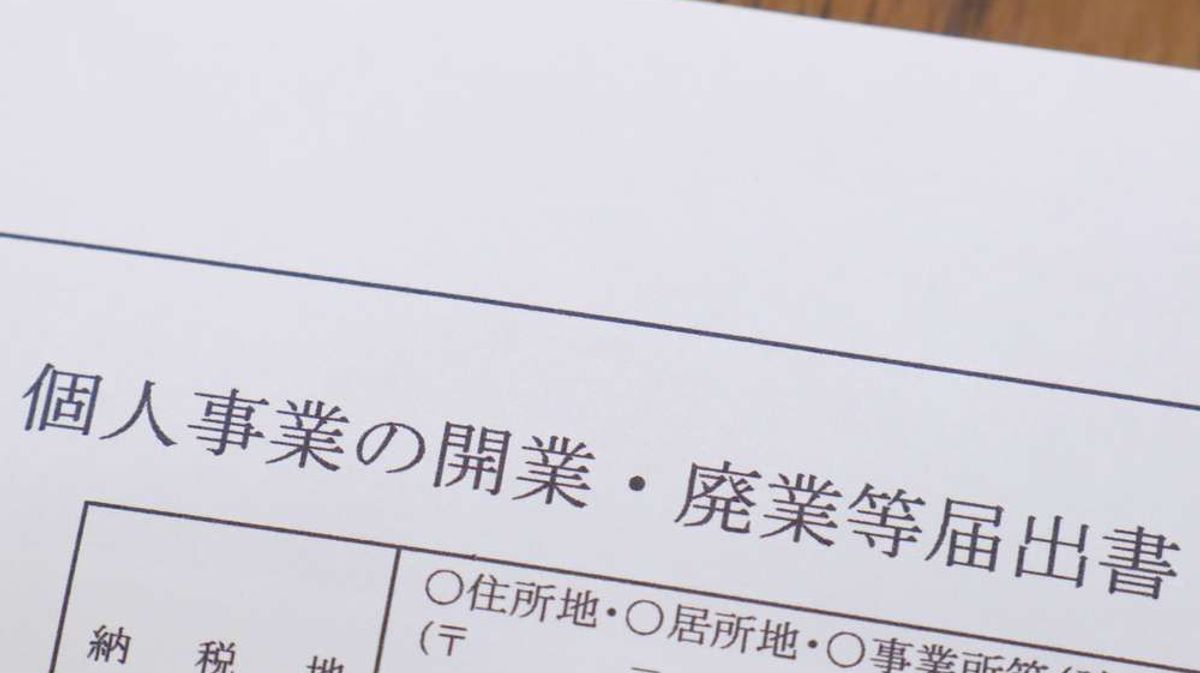
近年、行政書士の働き方は多様化しており、勤務行政書士として働くだけでなく、一般企業の法務部で専門知識を活かして働いたり、独立開業して自分のライフスタイルに合った働き方をしているなど、人によってさまざまです。
自由度の高い職業である行政書士は、資格を取得すればすぐに独立開業できる上、事業が軌道に乗れば一般のサラリーマンと比べて高い収入を得ることが可能となっています。また、司法書士や社労士など、ダブルライセンスで仕事の幅を広げることができれば、同業者との差別化を図ることができ、クライアントからの信頼も得やすくなるでしょう。
一方で、行政書士として独立開業する場合、どのような手順を踏んで開業すればいいのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。開業して失敗する可能性はないのか、開業資金はどれくらい必要なのかなど、独立開業することについて不安な点も多いと思います。
そこで、この記事では、行政書士が独立開業するための手順や成功するためのポイント、開業資金や独立開業するメリット・デメリットなどについて、詳しく解説していきます。
行政書士の独立開業についてよくある質問もまとめましたので、行政書士の資格に興味がある方や、行政書士として独立開業を目指している方は、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.行政書士で独立開業すれば年収1,000万円も夢じゃない!
2.行政書士が独立開業で成功するためのポイントとは?
2-1.専門分野を取り扱うことで同業者との差別化を図る
2-2.事務処理能力を高めて顧客満足度を上げる
2-3.営業と集客に力を入れる
2-4.士業間の人脈を広げて横のつながりを作る
2-5.ダブルライセンスでワンストップな対応を行う
3.行政書士で独立開業する流れ
3-1.行政書士資格を取得する
3-2.開業資金や備品の準備をする
3-3.事務所の所在地や事務所名を決める
3-4.行政書士名簿に登録申請する
3-5.事務所の調査が行われる
3-6.税務署に開業届を提出する
4.行政書士が独立開業するにはいくらかかる?開業資金の目安は?
4-1.行政書士が開業する際にかかる費用一覧
4-2.行政書士が独立開業する際に利用できる助成金や補助金とは?
5.行政書士として独立開業するメリット
5-1.年収が上がる可能性がある
5-2.自分のライフスタイルに合わせて自由に働ける
5-3.定年を気にせず働く事ができる
5-4.知名度が上がれば様々な分野で活躍できる
6.行政書士として独立開業するデメリット
6-1.軌道に乗るまでに時間がかかる可能性がある
6-2.通常業務のほかに事務所経営まで考える必要がある
6-3.廃業のリスクがある
7.行政書士なら未経験でも独立開業できる!
8.行政書士の独立開業に関するよくある質問【Q&A】
8-1.行政書士として独立開業しても仕事がないって本当?現実は?
8-2.自宅で開業することができる?条件は?
8-3.独立開業までにどれくらい実務経験を積む必要がある?
8-4.独立開業で稼ぎやすい業務ジャンルは?
8-5.独立開業でつまずきやすいポイントとは?
9.まとめ
1.行政書士で独立開業すれば年収1,000万円も夢じゃない!
行政書士は、同じ法律系の資格である弁護士や司法書士と比べ、稼げない資格として名前が挙げられることもありますが、実は平均年収は決して低くはありません。厚生労働省が公表しているデータによると、令和4年に調査した時点での行政書士の平均年収は579万8,000円となっています。
参照:行政書士|job tag 職業情報提供サイト 日本版O-NET(厚生労働省)
同じく、厚生労働省が公表しているデータによると、令和4年度におけるサラリーマンの平均年収は457万6,000円となっているため、行政書士の平均年収は、サラリーマンの平均年収よりも100万円以上高いことがわかります。
参照:令和4年分民間給与実態統計調査結果
行政書士は、資格を取得したらすぐに独立開業できる職業です。実務能力を磨き、クライアントの信頼を勝ち取ることができれば、アイデア次第では独立開業してすぐに平均年収以上を稼ぐことは十分可能です。もちろん、独立開業したからといって、必ずしも全員が平均年収以上に稼げるわけではありませんが、事業が軌道に乗れば、同じ法律家である弁護士や司法書士よりも稼いで、年収1,000万円に到達することも夢ではありません。
※なお、行政書士の年収の詳しい解説については、こちらの記事をご覧下さい。
→ 行政書士の年収の現実は?中央値や雇われ・女性の年収も解説
2.行政書士が独立開業で成功するためのポイントとは?
行政書士は、他の法律系の資格と比べて開業しやすいのが特徴ですが、資格取得後、単にお客様からの依頼を待っているだけでは、独立開業で成功することができません。行政書士が独立開業して成功するためのポイントは、次の通りです。
| 行政書士が独立開業で成功するための5つのポイント |
| ●専門分野を取り扱うことで同業者との差別化を図る ●事務処理能力を高めて顧客満足度を上げる ●営業と集客に力を入れる ●士業間の人脈を広げて横のつながりを作る ●ダブルライセンスでワンストップで対応する |
行政書士の資格取得を検討している方のなかには、年収1,000万円を超える事を目標にしている方もいると思います。独立開業で成功するためのポイントをしっかり理解して、いち早く年収1,000万円を達成しましょう。
2-1.専門分野を取り扱うことで同業者との差別化を図る
独立開業で成功するためには、同業者が取り扱ってない専門分野を取り扱うなどして専門性を高め、周りとの差別化を図ることが重要です。
行政書士のメイン業務は、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成業務ですが、これらの業務はどの行政書士でも対応できる分野なので、業務単価が低く設定されることが多いです。その点、例えば外国人在留資格の手続きなどの専門性の高い業務分野は、扱える行政書士が少ないことから、総じて業務単価も高く設定できることが多く、得意分野にすることができれば年収を上げやすい傾向にあります。
また、対応できる行政書士が他にいなければ、その分野に関する仕事が回ってきやすくなるため、仕事を獲得しやすくもなるでしょう。
法律の基本的な知識に加えて、専門的な分野に関する知識を身につけることができれば、幅広い知識を活かして企業に対してコンサルティングを行なったり、セミナーを開催して報酬を得たり、自身の経験や知識を書籍化することで、印税収入を得ることも可能になるでしょう。
2-2.事務処理能力を高めて顧客満足度を上げる
独立開業して成功するためには、事務処理能力を高めてクライアントの満足度を上げることも重要です。いくら専門性に特化していて、他に頼れる行政書士がいなかったとしても、事務処理能力が低く、仕事をスムーズに進められない状態で仕事を受けてしまうと、当然ながら顧客は離れていってしまいます。
行政書士として成功するためには、顧客満足度を高めリピーターになってもらったり、周囲の人に紹介してもらうことで仕事を獲得することも非常に重要です。
クライアントに満足してもらい、次に続く仕事をするためには、行政書士としての基本的な事務処理能力を高める事が重要になってくるのです。
事務処理能力を上げるためには、行政書士としての経験を積む事も重要ですが、最低限のパソコンスキルを習得したり、ITツールやコミュニケーションツールを導入して、業務効率化を図る必要があります。さまざまなツールを導入するとなるとその分コストもかかるため、開業当初は少し経済的に大変かもしれません。しかし、導入する事で業務効率化を実現でき、仕事を円滑にこなせるようになるのであれば、将来のために導入しておくことは損ではありません。
2-3.営業と集客に力を入れる
行政書士として、どんなに質の高いサービスを提供したとしても、それをできる限り多くの人に知ってもらわなければ仕事は増えません。つまり、実務能力と同じように、営業力や集客力も独立開業には必要な能力になるのです。
集客するには色々な方法がありますが、1番集客しやすいのは、WebサイトやSNSを有効活用して集客する方法です。
近年、法律家を探す際はインターネットで情報を集める事が多くなりました。お客様のニーズやお悩み解決できることを訴求したWebサイトを作成し、サイトを検索上位に表示させるSEO(検索エンジン最適化)を施すなど適切に運用する事ができれば、最小限のコストで多くの人に営業をかける事ができるようになります。また、コラム記事やSNSで情報を発信する事で、事務所自体に興味を持ってもらい、そこから成約に繋げる方法も有効です。
何の知識もなく、いきなりWebサイトを作ったり、SNSを効果的に運用するのは難しいかもしれませんが、最近では、 WebサイトやSNSの運用代行業者もたくさんあるため、必要に応じて利用を検討してみると良いかもしれません。
2-4.士業間の人脈を広げて横のつながりを作る
独立開業したばかりの行政書士が効率よく仕事を獲得するためには、士業同士の人脈を広げる事も重要です。たとえば、同じ行政書士との人脈を広げておけば、案件が多くて手が回らないときに仕事を回してもらえたり、こちらの専門分野に関する仕事を回してもらえることがあります。
また、弁護士や司法書士との人脈を広げておくことで、行政書士の専門分野である書類作成業務に関する仕事を、紹介してもらえることがあります。士業間の人脈を広げる方法としては、行政書士の研修会やセミナーに参加したり、飛び込みで営業をかけたりする方法があります。
また、開業したら近隣の同業者の事務所や他の士業の事務所に挨拶にいくことで、開業している事をアピールするのも良いでしょう。なお、伊藤塾では、伊藤塾卒業生が業種の垣根を越えて交流を深め、共に学び合い、社会に貢献できる人材として活躍するためのプラットフォームとして同窓会という組織を運営しています。
行政書士同士だけでなく、司法書士、弁護士などと交流できる場は貴重です。このような形で、伊藤塾では合格後も受講生を応援し続けています。
2-5.ダブルライセンスでワンストップな対応を行う
行政書士として独立開業し、年収1,000万円を目指すのであれば、専門分野に注力するだけでなく、ダブルライセンスで業務の幅を広げることも検討すべきでしょう。
ダブルライセンスとは、2つ以上の資格を持って働く事です。たとえば、司法書士と行政書士の2つの資格を持っていれば、行政書士では扱えない登記申請業務や、訴額140万円以下の訴訟代理人としての業務も扱えるようになるため、仕事の幅が広がることになります。
行政書士と相性の良い資格としては、社労士や宅地建物取引士などが挙げられますが、たとえば社労士とのダブルライセンスで働く場合には、会社の設立に関する書類作成及び代理申請業務から、会社設立後の労務管理に至るまで一貫して行なうことができるようになります。依頼する側としても、ワンストップで対応してくれるのであれば依頼しやすくなることから、顧客を獲得しやすくなるでしょう。
※行政書士のダブルライセンスについては、こちらの記事をご覧ください。
→ 行政書士のダブルライセンスでおすすめの資格は?相性や年収についても解説
3.行政書士で独立開業する流れ
そもそも自分で開業したことがない人にとって、どのような流れで開業すればいいかがわからない方も多いでしょう。行政書士として独立開業する場合の流れは、次の通りです。
【行政書士として独開業する流れ】
| 行政書士資格を取得する |
| ⬇︎ |
| 開業資金や備品の準備をする |
| ⬇︎ |
| 事務所の所在地や事務所名を決める |
| ⬇︎ |
| 行政書士名簿に登録申請する |
| ⬇︎ |
| 事務所の調査が行われる |
| ⬇︎ |
| 税務署に開業届を提出する |
将来的に行政書士として独立開業を目指している方は、このフローチャートを見れば、おおまかな流れをイメージしてもらえるかと思います。
以下で詳しく解説していきます。
3-1.行政書士資格を取得する
まずは、行政書士として仕事をするために、行政書士資格を取得する必要があります。行政書士資格を取得する方法としては、行政書士試験に合格して資格を取得するのが一般的な方法ですが、ほかにも、公務員として行政事務を一定年数経験する方法や、弁護士・弁理士・公認会計・税理士のいずれかの資格を持つことで、行政書士資格を得る方法などがあります。
行政書士試験ルートで資格を得ようとする場合、毎年1回、11月に行われる試験に合格する必要があります。令和4年(2022年)11月に行われた行政書士試験の合格率は12.13%でしたが、試験内容や評価方法などから、法律系の資格の中では比較的チャレンジしやすい試験となっており、コツコツと毎日勉強を続けることができれば、誰でも合格に手が届く試験となっています。
※なお、行政書士試験の難易度や合格率については、こちらの記事をご覧ください。
→ 行政書士試験の難易度ランキングや偏差値は?初心者・独学で合格できるかも解説
→ 行政書士試験の合格率はどのくらい?合格率が低い理由や推移についても解説
3-2.開業資金や備品の準備をする
独立開業する際にはいろいろとお金がかかるため、あらかじめ開業資金を準備しておくと安心です。
後述するように、開業資金にはさまざまな種類のものがありますが、基本的なものとしては、行政書士の登録費用や事務所の賃貸料、従業員の人件費やパソコンやコピー機などの備品代、通信量等が挙げられます。もし、自宅で1人で開業するのであれば、事務所の賃貸料や従業員の人件費はかからないため、開業コストを抑えることができるでしょう。
3-3.事務所の所在地や事務所名を決める
独立開業して仕事をするのであれば、事務所の所在地や事務所名についても考えておく必要があります。事務所の所在地は、集客に大きく関わる重要なポイントです。駅前で人通りの多い繁華街であれば、その分飛び込みで相談にくる可能性も高いですし、郊外であれば、同業者のライバルが少なく、顧客を独占できる可能性があります。
また、許認可等の公的書類の作成や申請業務をメインで行なう行政書士の仕事の特性を考えるのであれば、法務局や県庁に近い場所に事務所を構えると、申請の際にかかる移動時間を短縮することができます。
近年、インターネットの普及から、許認可等の申請において電子申請で行なうことができるケースも増えてきていますが、官公庁の近くに事務所があれば、何かあったときにすぐに対応しやすくなります。加えて、士業関係の事務所が多い場所に事務所を開設することで、横の繋がりを持つことができ、仕事を紹介してもらいやすくなります。
顧客獲得の競争が激しくなることも想定されますが、士業同士で良好な関係を築くことができれば、安定した経営の構築に役立つでしょう。このように、自宅で開業するにせよ、行政書士事務所自体が少ない地域で開業するにせよ、事務所の所在地は将来的にどうやって顧客を獲得していくかも踏まえて、慎重に検討する必要があります。
3-4.行政書士名簿に登録申請する
行政書士資格を取得したとしても、日本行政書士会連合会の行政書士名簿や各都道府県の行政書士会に登録しなければ、行政書士として業務を行なうことはできません。たとえ、行政書士資格取得の要件を満たしていたとしても、未登録のまま行政書士として名乗ったり、業務を行なってしまうと、行政書士法違反となり罰則の対象となります。
行政書士登録は、各都道府県の行政書士会に「行政書士登録申請書」を提出することで行ないます。なお、各行政書士会によって金額は異なりますが、登録には一定の入会金や登録手数料がかかります。たとえば、東京都行政書士会であれば、入会金として20万円、登録手数料で2万5千円、会費3ヵ月分として2万1千円を登録時に支払う必要があります。
参照:登録・入会のご案内|東京都行政書士会
3-5.事務所の調査が行われる
行政書士として開業するためには、行政書士名簿に登録するために、各行政書士会によ事務所調査を受ける必要があります。
行政書士事務所は、仕事ができる環境であればなんでもいいわけではなく、「顧客のプライバシーを守れる構造・設備となっている」ことが必要です。
守秘義務を保てる環境が整備されており、行政書士として業務を滞りなく行なうことができなければ、行政書士としての登録を拒否されてしまう可能性もないとは言えません。調査自体は、行政書士の登録申請からおおむね1ヵ月程度でされるケースが多いため、それまでに開業の準備をしっかり進めておく必要があります。
事務所の調査は、各行政書士会の担当者が事務所に訪問して行なうケースと、申請者が提出した事務所の写真により行なうケースがあります。調査自体はそこまで厳しいものではありませんが、調査の担当者と良好な関係を築くことができれば、今後の方針についてアドバイスをもらえたり、人脈を広げられる可能性もあるため、いい印象を持ってもらえるよう、事前準備はしっかりと行なうようにしましょう。無事に事務所調査をクリアすると、行政書士名簿への登録が完了します。
3-6.税務署に開業届を提出する
行政書士名簿への登録が完了したら、事務所のある地域を管轄する税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
この開業届は、事業を開始した日から1ヵ月以内に行なう必要があるため、忘れないように注意してください。なお、開業届を提出する際に、税金申告の方法についても選択する必要があります。白色申告や青色申告のメリットやデメリットをしっかり把握した上で、どちらにするかを慎重に決めましょう。
4.行政書士が独立開業するにはいくらかかる?開業資金の目安は?
行政書士として独立開業をする際に、開業資金としてどれくらい準備すればいいのか気になる方も多いと思います。
最低限必要なものは仕方がないとしても、開業したばかりでこれから事業がうまくいくかどうかがわからない時期には、できる限り開業資金を抑えたいと考えるのが本音でしょう。ここからは、独立開業する際にかかる費用について解説していきます。
4-1.行政書士が開業する際にかかる費用一覧
行政書士は、他の士業と比べても比較的安く開業できると言われていますが、それでも総額で100万円以上開業資金として必要になる可能性があります。行政書士が開業する際にかかる費用を一覧でまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
※下記はあくまでも大まかな目安です。登録費用以外は、実際には金額に大きく幅があることをご理解ください。
| 行政書士登録費用 | 約28万円 |
| 名刺やコピー機などの事務用品の購入費用 | 約10〜15万円 |
| ホームページ開設・販促費用 | 約5万円 |
| 事務所用の資料・書籍などの購入費用 | 約10万円 |
| 事務所を賃貸する場合にかかる初期費用 | 約100万円 |
この他にも、従業員を雇うのであれば、人数分の人件費がかかることになります。
もし、自宅で開業するのであれば、事務所賃貸にかかる初期費用や備品代をある程度浮かせることができるため、開業資金を抑えることができるでしょう。
4-2.行政書士が独立開業する際に利用できる助成金や補助金とは?
行政書士として独立開業する場合、これから行政書士として働くためにさまざまなお金がかかります。自己資金だけで何とかしようとしても、どうしてもお金が足りないことも多いでしょう。
国や各自治体では、開業資金にかけるお金がなく、独立開業を諦めてしまうことがないよう、さまざまな助成金や補助金を用意しています。
例えば、東京都が実施している創業助成事業や、日本政策金融公庫の創業支援の融資、各自治体・金融機関・信用保証協会が実施する開業支援に関する融資などが挙げられますが、一定の要件を満たせばもらえる助成金や補助金は、他にもたくさんあります。まずは、それぞれの自治体に助成金や補助金について確認してみることをおすすめします。
参照①:TOKYO創業ステーション|創業創生事業
参照②:創業時に利用できる主な融資制度
参照③:起業家育成資金|埼玉県
5.行政書士として独立開業するメリット
行政書士として仕事をするのであれば、独立開業して自由に働きたいと考える方が多いと思います。行政書士として独立開業するメリットは、次の通りです。
| 行政書士として独立開業するメリット |
| ●年収が上がる可能性がある ●自分のライフスタイルに合わせて自由に働ける ●定年を気にせず働く事ができる ●知名度が上がれば様々な分野で活躍できる |
将来的に行政書士として成功する夢を持って行政書士試験の勉強をしている人は、これから解説する独立開業のメリットを、自分のモチベーションにしていただけると幸いです。
5-1.年収が上がる可能性がある
独立開業して事業が軌道に乗れば、行政書士事務所で従業員として働くよりも年収が大幅に上がる可能性があります。行政書士事務所で従業員として働く場合、給料制で働くことが多く、収入には限界があるからです。
しかし、独立開業すれば自分の好きなように自由に働くことができます。単価の高い専門分野の実務能力を身につけて、クライアントの信頼を勝ち取ることができれば、勤務行政書士よりも年収が上がる可能性が高いです。
事業が軌道に乗るまでは、積極的に営業活動を行なうことで人脈を広げ、次につながるような仕事を獲得していかなければいけません。行政書士として年収を上げるためには、実務能力を上げることはもちろん、常に新しいことにチャレンジしていく精神も重要な要素となるでしょう。
5-2.自分のライフスタイルに合わせて自由に働ける
独立開業すれば、企業のルールに縛られる事なく自由に働くことができます。行政書士の資格を持って、一般の企業に就職した場合、企業のルールの枠内で仕事を行なうことになります。
ルールに沿って業務を行なうことで働きやすい側面もあるかもしれませんが、その分自由に働くことができなくなるため、少し窮屈に感じてしまうこともあるでしょう。しかし、独立開業した場合には、決まったルールに縛られることもないため、自分が思うように仕事をすることができます。就業規則等も自分で決めることができるため、毎日9時から18時まで決められた時間に仕事をするのではなく、仕事の進捗状況に合わせて仕事をする時間を決めることができます。
また、平日の日中に時間を作りやすくなるため、家族との時間や趣味に費やす時間が作りやすくなり、プライベートを充実させることもできるでしょう。気分転換をするためにカフェで仕事をしたり、子どもの送り迎えの時間を考慮しながら働くことができるなど、自分のライフスタイルに合わせて自由に働くことができるのが、独立開業する魅力の一つであると言えるでしょう。
5-3.定年を気にせず働く事ができる
行政書士として独立すれば、定年を気にせずに働くことができます。
顧客のプライバシーに関わる情報を扱う事が多い行政書士は、1度クライアントと良好な関係を築く事ができれば、年数が経過すればするほど信頼関係が増していく傾向にあります。
定年間近になると、若い頃のようにバリバリ働くのは難しいかもしれませんが、開業後に人脈を広げてクライアントとの信頼関係を築いておけば、そこから依頼される仕事だけで生活していくことも十分に可能です。老後の生活に不安を抱いている人にとって、定年を気にせず働けるのは大きなメリットだと言えるでしょう。
5-4.知名度が上がれば様々な分野で活躍できる
独立開業して行政書士として知名度を上げる事ができれば、メイン業務である書類作成業務以外でも、様々な分野で活躍する事ができます。たとえば、行政書士ができる仕事としては、次のようなものがあります。
【多様化する行政書士の働き方】
| ●中小企業に法務的観点から幅広いアドバイスを行なうビジネス コンサルタント ●成年後見人として、認知症患者の権利や自由を保護する ●交通事故における、後遺障害等級認定の申請を代理して行なう ●帰化申請や在留資格取得の代理業務 ●「街の法律家」として市民相談会を開催する ●著作権などの知的財産権を保護する業務または活動 ●自治体などの各種公的委員会 ●民事調停委員、家事調停委員 ●行政改革推進委員 など |
行政書士として知名度が上がれば上がるほど、各方面から仕事の声がかかる可能性が高くなり、業務の幅を広げる事ができるでしょう。
6.行政書士として独立開業するデメリット
独立開業して成功を目指すのであれば、メリットだけではなくデメリットも頭に入れておく必要があります。一般的に言われている、行政書士として独立開業することのデメリットは、次の通りです。
| 行政書士として独立開業するデメリット |
| ●軌道に乗るまでに時間がかかる可能性がある ●通常業務のほかに事務所経営まで考える必要がある ●廃業のリスクがある |
デメリットをしっかり把握して、そのデメリットをどうすれば回避できるのかをしっかり考えることが大切です。以下を参考にしていただければと思います。
6-1.軌道に乗るまでに時間がかかる可能性がある
行政書士が独立開業するにあたって1番大変なのは、仕事が軌道に乗るまでにある程度の時間がかかる可能性があることです。特に、開業した当初は、まだ知名度も人脈もないことから、最初の仕事を獲得するまでのハードルが高いです。そのため、開業当初は、集客のためのWebサイト作りやSNS運用、挨拶回りなどの実務以外の部分に時間を費やすことも多いでしょう。
開業後、ゼロから集客する場合は、最低でも半年〜1年程度、売上がないリスクを想定して、生活費や活動費を貯蓄しておくことをおすすめします。もっとも、獲得した仕事に真摯に向き合い、誠実に対応していくことでクライアントの信頼を勝ち取ることができれば、そこから次の仕事につながるケースも多いです。
6-2.通常業務のほかに事務所経営まで考える必要がある
勤務行政書士と異なり、開業した場合には、実務だけでなく事務所の経営に関することまで対応しなければいけません。
独立開業した行政書士は、実務家であると同時に事務所の経営者です。勤務行政書士であれば、与えられた仕事をしているだけで給料をもらうことができますが、開業した行政書士の場合、実務と並行して営業したり事務所の経営方針を考えたり、経理業務を行なったりする必要があります。仕事がある程度軌道に乗り、金銭的余裕が生まれてきたら、経理担当の事務員を雇ったり、税務に関することを税理士に外注するとよいでしょう。
しかし、開業してまもなくはそこまでの金銭的余裕がないケースがほとんどなので、これらの業務を全て自分で行わなくてはいけないことに、独立開業の難しさがあるといえます。
6-3.廃業のリスクがある
行政書士として独立開業する場合の大きなデメリットとして挙げられるのは、廃業のリスクが常に隣り合わせであることです。
勤務行政書士の場合、何もしなくても仕事を割り当てられることになりますが、開業した行政書士の場合、自分から積極的に仕事を取りに行かない限り仕事が勝手に増えることはなく、仕事がないということはつまり収入が減少することを意味します。士業の場合、業務の性質上、成功報酬型の場合が多く、クライアントによっては業務終了から何ヵ月も報酬を支払ってくれないケースも少なくありません。
あまりに、報酬を支払ってくれない状態が続いてしまうと、事務所の資金繰りがうまくいかなくなってしまう可能性が高くなります。独立開業すると自由に働くことができる反面、その分のリスクを自分で負うことになります。開業と廃業は隣り合わせであることを常に意識して、実務だけでなく営業や集客に力を入れることをおすすめします。
7.行政書士なら未経験でも独立開業できる!
行政書士は、実務経験が浅くても独立開業して自由に働くことができる数少ない資格のひとつです。行政書士の主な仕事は、官公署に対して提出する書類の作成業務やその書類の提出を代行する業務です。
書面作成業務であれば、ある程度雛形が決まっているため、専門用語さえ理解できるだけの法律知識を持っていれば、比較的スムーズに書類を作成することができるでしょう。クライアントが行政書士に書面作成や申請代行を依頼するのは、「専門書類の内容を理解できず、自分で1から調べるには時間も手間もかかってしまうから」です。
つまり、多少書面作成に時間がかかってしまったとしても、自分ではできないことをしてもらったことに、クライアントは満足感を感じるのです。
もちろん、ある程度、実務経験を積んでから独立したほうがスムーズに仕事を進められるのは間違いありませんが、未経験であっても仕事を的確にこなすことができるのは、行政書士という職業の大きな魅力であるといえるでしょう。行政書士として年収1,000万円を目指したい方や幅広い分野で働きたいと考える方は、未経験でも思い切って独立開業にチャレンジしてみる価値はあるでしょう。
8.行政書士の独立開業に関するよくある質問【Q&A】
8-1.行政書士として独立開業しても仕事がないって本当?現実は?
行政書士として独立開業しても、誰でも簡単に仕事を獲得できるわけではありません。自由に働くことを夢見てとりあえず独立開業してみたくらいの意識でいると、開業後に仕事を得ることができず、3年以内に廃業してしまう可能性も高まります。
ただし、実際に独立開業して成功している先輩行政書士がいる以上、実務能力をあげて集客に力を入れれば、たとえ未経験からであっても成功することは十分可能です。
8-2.自宅で開業することができる?条件は?
行政書士で独立開業する場合、事務所の賃貸料を節約したり、通勤時間を短縮したりすることを目的として、自宅で開業することを検討している方も多いと思います。
ただし、自宅開業を行なうためには、次の条件を満たす必要があります。
| 構造要件 | ・事務所の設置にあたっては、業務取扱上の秘密 を保持しうるよう明確な区分を設けるととも に、他人が容易に侵入できない構造でなければ ならない ・不特定多数人に認識され、その依頼に応じられ るよう適当な場所に設置しなければならない |
| 設備要件 | 事務所の設備は、概ね次の通りとする。 ・事務スペース及び接客スペース ・照明及び機器を作動させるための電源設備及び 通信回線設備 ・事務用机・椅子 ・書類等保管庫(容易に移動できないもの、鍵が かかるもの) ・電話 ・プリンター・FAX・コピー機等 ・パソコン等 ・用紙・事務用品等収納庫又は収納棚 ・業務用図書及び図書棚 |
行政書士は、業務の性質上、顧客のプライバシーに関する情報を取り扱うことになります。それらの機密情報を保持するために、自宅で開業する場合には、構造要件が定められています。また、行政書士として適切な業務を行なうためには、最低限の設備を有していることが条件となります。
ただし、設備要件については「概ね」と記載されているため、必ずしも記載されている備品全てを揃えなくてはいけないわけではありません。機密情報を適切に管理し、行政書士として業務をする事ができるのであれば、足りない備品があっても問題ないと言えるでしょう。
8-3.独立開業までにどれくらい実務経験を積む必要がある?
行政書士は、資格を取得したらすぐに開業する事ができますが、開業後の実務の負担を考えるのであれば、2〜3年の実務経験を経てから開業するのが安心です。
ただし、2〜3年というのはあくまでも目安の数字であり、自分が開業して上手くいく自信や経営プランがあれば、いつ開業しても問題ないと言えるでしょう。
8-4.独立開業で稼ぎやすい業務ジャンルは?
行政書士が独立開業して稼ぎやすいジャンルは次の通りです。
| 建築・産業廃棄物 | ・建設業許可申請・産業廃棄物許可申請 など、行政書士が扱えるジャンルの中 でも需要が多いジャンル ・1社と契約できるとその後継続的な仕事 を依頼されやすい |
| 運輸・交通 | ・個人から法人まで幅広い依頼が期待で きて、案件が確保しやすいジャンル ・「一般貨物自動車運送事業経営許可申 請」の場合、平均報酬が40〜45万円と かなり高い |
| 外国人在留資格 | ・ライバルが少なく、平均単価も高い ・在留資格の申請を行うためには、「申 請取次行政書士」になる必要がある |
| 遺言・相続 | ・高齢化の影響で需要は多い ・弁護士や司法書士との人脈を広げてお くと、案件を獲得しやすい |
| 飲食店 | ・飲食店が建設されやすい繁華街に事務 所があれば、案件を獲得しやすい |
なお、行政書士の年収や報酬単価の高い業務については、こちらの記事もご覧ください。
→ 行政書士の年収の現実は?中央値や雇われ・女性の年収も解説
8-5.独立開業でつまずきやすいポイントとは?
独立開業でつまずきやすい一番のポイントは、思っているよりも集客が難しいことです。
行政書士としてどんなに魅力的なサービスを提供していたとしても、一般の方にその存在を知ってもらわない限りは、仕事に結びつきません。開業すると実務能力を高めることだけに注力しがちですが、まずは集客や営業について学び、仕事を獲得することに注力することをおすすめします。
9.まとめ
自由な働き方に憧れたり、年収1,000万円を稼ぎたいなどの夢を持って行政書士試験にチャレンジしている方にとって、独立開業して成功することは必須であると言えるでしょう。
行政書士は、未経験からでもすぐに独立開業することができ、実務経験が浅くても活躍できる可能性が高い職業です。
実務能力を磨き、営業や集客に力を入れてクライアントとの信頼関係を築くことができれば、独立開業しても成功する可能性が高くなるでしょう。
開業してすぐは、なかなか仕事が軌道に乗らず苦しい時期もあるかもしれませんが、この記事で説明した「成功するための5つのポイント」を押さえておけば、独立開業して年収1,000万円を稼ぐことも夢ではありません。
伊藤塾では、合格後も受講生の皆様の成功を応援し続けるために、さまざまな機会をご用意しています。
→ 伊藤塾が選ばれる理由 -行政書士試験-
ぜひ、あなたの夢の実現のために、伊藤塾をご活用ください。
→「2025年合格目標 行政書士合格講座」はこちら

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

















