行政書士の年収の現実は?女性・雇われ・開業・中央値など比較解説
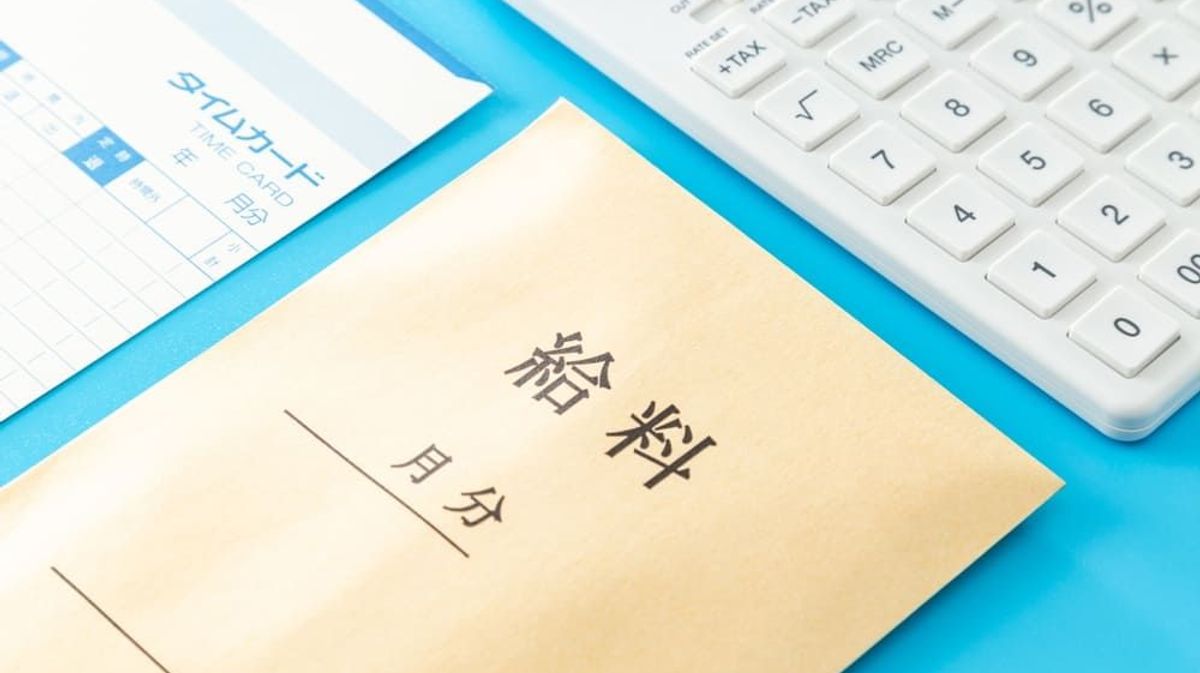
「街の法律家」とも呼ばれる書面作成の専門家である行政書士が、やりがいのある仕事であることは間違いありません。しかし、「行政書士は稼げない」と言われることもあり、現実的にどれくらい稼げるのか、気になる方も多いのではないでしょうか?
行政書士は自由度の高い資格で、働き方や仕事内容によって年収は大きく異なります。
もし、行政書士として年収1,000万円以上稼げるのであれば、資格取得のモチベーションも上がるのではないでしょうか?
このコラムでは、行政書士の年収の現実や、女性の平均年収などについて解説していきます。行政書士として、1,000万円以上稼ぐコツについても解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.行政書士の平均年収は低い?中央値は550万円程度
1-1.勤務・雇われなら平均年収は500万以下
1-2.ダブルライセンスなら年収の倍増も可能
1-3.独立開業すれば1,000万円以上も夢じゃない!?
1-4.女性でも男性と同じように稼ぐことができる
2.行政書士の業務別から見た報酬額
2-1.書類作成業務
2-2.許認可申請の代理業務
2-3.相談業務
3.そもそも行政書士とは?
4.行政書士で年収アップさせるための方法とは?
4-1.独立開業し営業活動に力をいれる
4-2.ダブルライセンスで業務の幅を広げる
4-3.専門性の高い高単価の業務に力を入れる
5.行政書士になる方法とは?
5-1.行政書士試験に合格する
5-2.特認制度を利用する
6.行政書士試験なら働きながら資格取得が可能!
7.まとめ
1.行政書士の平均年収は低い?中央値は550万円程度
厚生労働省が公表しているデータによると、令和5年に調査した時点での行政書士の平均年収は、551万4,000円となっています。
参照:行政書士|job tag 職業情報提供サイト 日本版O-NET(厚生労働省)
令和4年度における給与所得者の平均給与は、男女合計で460万円であることを考えると、行政書士の平均年収は、サラリーマンの平均よりも高いことがわかります。
参照:令和5年分民間給与実態統計調査
また、行政書士の年齢別平均年収でみると、45歳〜49歳で698万900円となっていることから、実務経験を積み、クライアントからの信頼を勝ち取ることができれば、十分稼げる資格であることがわかります。
1-1.勤務・雇われなら平均年収は500万以下
ただし、行政書士の資格を取れば、誰でも平均年収以上に稼げるわけではなく、当然知識や経験が浅く、他の士業とのつながりなどが何もない場合には、収入が上がらないこともあるでしょう。
とくに、行政書士事務所で勤務したり、行政書士の資格を活かして一般企業で働く場合には、一般のサラリーマンと同程度の収入になると考えてよいでしょう。もちろん、事務所の規模や仕事内容によっても給与体系は異なるので、一概にはいえません。
しかし、独立開業した場合や、ダブルライセンスで働く場合のように、突出した収入を得ることは難しいといえるでしょう。
たとえば、令和5年度における行政書士の求人データを見ると、全国の求人平均賃金は月収26万9,000円となっています。事務所勤務の場合には、こういった額を一つの目安と考えても良いでしょう。
参照:行政書士|job tag 職業情報提供サイト 日本版O-NET(厚生労働省)
1-2.ダブルライセンスなら年収の倍増も可能
行政書士だけでなく、ほかの資格とのダブルライセンスで仕事をすれば、行政書士の平均年収の倍以上稼ぐことも十分可能です。ダブルライセンスとは、2つ以上の資格を取得することで、行政書士と併せて取得したい資格としては、次のような資格が挙げられます。
【行政書士と併せて取得したい資格】
◉司法書士 ◉税理士 ◉社会保険労務士 ◉宅地建物取引士 ◉ファイナンシャルプランナー など |
保有している資格が多ければ多いほど、扱える仕事の幅が広くなり、個人の信用も増していくでしょう。行政書士の資格を取得して、事務所に雇われながら仕事をするのであれば、将来を見据えてダブルライセンスを取得しておくと、高収入を狙うことができるでしょう。
※ダブルライセンスについては、こちらの記事も併せてご覧ください。
→ 行政書士のダブルライセンスでおすすめの資格は?相性や年収についても解説
1-3.独立開業すれば1,000万円以上も夢じゃない!?
行政書士として独立開業すれば、年収1,000万円を目指すことも夢ではありません。
行政書士は、資格取得後における働き方の自由度が高い資格です。本人の能力やアイデア次第では、弁護士や司法書士など、ほかの法律系の資格にも負けないくらい稼ぐことができるでしょう。
もちろん、独立開業したからといって必ずしも全員が高い収益が得られるわけではありません。他のあらゆる資格と同様、場合によっては仕事が思うように増えず、開業してから数年後に廃業となってしまうリスクもゼロではありません。
ただし、行政書士として数年キャリアを積み、ほかの士業との横のつながりを大事にするなど、開業後に向けて事前準備をしっかりしておけば、開業した初年度から、行政書士の平均年収以上の年収を達成することも十分可能なのです。
※行政書士の独立開業の詳しい解説については、こちらの記事をご覧下さい。
→ 行政書士が独立開業するには?年収・資金・成功のポイントを解説!
1-4.女性でも男性と同等の収益を得ることができる
なかには、女性が男性と同じように収益を得ることが難しい職業も存在しますが、行政書士であれば、基本的には収入面において男女差はありません。
行政書士のおもな業務は、書類作成業務です。これらの業務は、性別によって仕事の質に影響が出るわけではないため、女性でも制限なく仕事をすることができます。なかには、相続や離婚など、個人のセンシティブな情報に関する書面を作成することもあり、とくに女性顧客の場合であれば、男性の行政書士に依頼することを躊躇してしまうケースもあるでしょう。
そういった面でも、女性行政書士の需要は高く、仕事を獲得する面で、男性よりも優位に話が進むケースも少なくありません。一度資格を取得してしまえば、定期更新なども必要なく、生涯仕事を行うことができる資格なので、結婚や出産で一時的に休職したあとでも、再就職や独立開業がしやすいのも、行政書士の大きな魅力のひとつといえるでしょう。
2.行政書士の業務別から見た報酬額
行政書士ができる業務は多岐にわたり、業務内容によって報酬額がある程度決まっています。ここでは、大きく
「書類作成業務」
「許認可申請の代理業務」
「相談業務」
の3つに分けて報酬額を確認してみましょう。
2-1.書類作成業務
行政書士のおもな業務は、契約書や官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成業務です。書類作成業務の内容やそれぞれの報酬額の目安は、おおむね次のとおりです。
| 書類作成業務と報酬の目安 | |
| 契約書関係 | 約3万円 |
| 就業規則 | 約8万5,000円 |
| 遺産分割協議書 | 約5万円 |
| 遺言執行手続きに関する書面 | 約24万円 |
| 知的資産経営報告書 | 約67万円 |
遺言執行手続きに関する書面や知的資産経営報告書の作成業務などの専門性の高い書面に関しては、行政書士の業務のなかでもとくに高単価な業務となっています。
年収を上げたいのであれば、なるべく専門的な知識を身につけ、高単価な案件を獲得していくことが重要になるでしょう。なお、遺産分割協議書の作成等もおこなうことができますが、行政書士が対応できるのは、あくまでも書面の作成のみです。
争っている当事者の仲を取り持ち、遺産分割調停をおこなうなど、遺産分割の争いを根本的に解決することはできないことに、注意が必要です。
2-2.許認可申請の代理業務
個人や会社がさまざまな事業を開始する際に、都道府県や市区町村に対しておこなう「許可」や「認可」の申請を、本人に代理しておこなう許認可申請の代理業務も、行政書士の立派な業務の一つです。
| 許認可申請の代理業務と報酬の目安 | |
| 建設業許可申請 (法人・新規・知事宛) | 約14万円 |
| 飲食店営業許可申請 (深夜・酒類) | 約9万円 |
| 旅館業許可申請 | 約20~30万円 |
| NPO法人設立認証手続き | 約15~25万円 |
| 医薬品製造販売許可申請 | 約34万円 |
| 医療法人設立認可申請 | 約56万円 |
| 帰化許可申請 | 約20~30万 |
薬局開設許可申請で診療所の手続きを同時に請け負うケースなど、複数の申請を同時におこなう場合には、その分報酬も高額になります。その他にも、行政書士がおこなうことができる許認可申請の代理業務が多岐にわたるため、詳しくはこちらのページもご参照ください。
参照:令和2年度報酬額統計調査の結果 (令和3年1月実施)|日本行政書士連合会
2-3.相談業務
行政手続きに関する相談を受けたり、「街の法律家」として、悪徳商法などの相談を受けることも、行政書士の重要な業務の一つです。
薬局の開設にかかわる相談や飲食店営業許可申請に関する相談など、行政手続きに関する相談であれば、1時間5,000円程度の報酬を得ることができるでしょう。
行政書士は、中小企業の申請者が不安に思う点につき、法務的観点から幅広いアドバイスをおこない、起業・創業支援から事業承継支援に至るまで、全ての段階で申請の手伝いをすることができるやりがいのある仕事です。とくに、専門的な知識を駆使し、経営者の抱える経営課題や法務問題に対して適切なアドバイスをおこなうコンサルティング業は、業務単価が高く、契約数が多くなれば、その分年収アップが見込める業務のひとつであるといえるでしょう。
3.そもそも行政書士とは?
行政書士とは、行政手続を専門とする法律家で、自治体や各省庁などの官公庁に提出する公的な書類を、本人の代わりに作成、提出するのがおもな業務となります。
書面作成のスペシャリストである行政書士が作成できる書面の種類は多岐に渡り、行政に関わる許認可申請に関わる書面であれば、ほとんどの書面を作成することができます。たとえば飲食店を経営するために必要な保健所の飲食店営業許可申請や、建築工事を行う際の建設業許可申請などが挙げられます。
これらの専門的な申請にかかる書面作成だけでなく、申請にかかる手続きを本人に代わって行うことも可能です。さらに、行政書士としての専門的な知識や経験を活かし、企業の経営コンサルティングや医療ビジネスコンサルタントなどのコンサルティング業務を行うことも可能です。
行政書士は、働き方の自由度が高く、独立開業してしまえば定年なく働くことができるのも、大きな魅力の職業です。働き方の多様化が進む現代において、行政書士として活躍する場は年々広まっているため、本人の能力次第では、高額な年収を得ることも夢ではありません。
※行政書士の仕事について詳しく知りたい場合には、こちらの記事もご覧ください。
→ 行政書士とは 仕事内容と資格の活かし方
4.行政書士で年収アップさせるための方法とは?
行政書士としての年収をアップさせるためには、次の3つのポイントを意識してください。
| 行政書士として年収アップさせる3つの方法 |
| ◉独立開業し営業活動に力をいれる ◉ダブルライセンスで業務の幅を広げる ◉専門性の高い高単価の業務に力を入れる |
行政書士として年収1,000万円を目指すには、やみくもに働くのではなく、ビジネスプランをしっかり立てる必要があります。ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
4-1.独立開業し営業活動に力をいれる
行政書士として年収1,000万以上を目指すのであれば、独立開業することはかかせませんその上で、積極的に営業活動をおこない、確実に仕事を獲得していかなくてはいけません。
開業したての頃は、仕事を選ばずさまざまな仕事をこなし、自分の名前を売ることも重要ですが、ある程度クライアントとの信頼関係を築くことができたら、メインの顧客層を想定し、その層のニーズに応じた営業活動をおこなうことが大切になってきます。
行政書士としての営業方法には、広告やホームページの作成、人脈を使った営業やSNSの活用など、さまざまな手法がありますが、とにかく自分の名前を売り込み、安定的に仕事を獲得していくことが、非常に重要です。
業務経験が乏しい段階で営業活動をおこなうのは、非常に勇気のいることかもしれませんが、行政書士として収入アップを狙うためには、自身の強みを生かした営業活動をおこなうことは、必須であるといえるでしょう。
4-2.ダブルライセンスで業務の幅を広げる
行政書士として収入を上げたいと考えるのであれば、ダブルライセンスで業務の幅を広げることも検討すべきでしょう。とくに、社労士や宅地建物取引士など、業務としての関連性が高い資格であれば、ダブルライセンスのアドバンテージを生かした業務をおこなうことができます。
また、2つ以上の資格を取得していれば、営業活動の際にも自身の強みを売り出しやすくなるだけでなく、ダブルライセンス率が高い行政書士において、ライバルたちに置いていかれずに済むことになります。
膨大なデータを扱ったり、定型フォーマットを利用した書類作成は、近い将来AIがおこなう可能性もあることを考えると、行政書士一本で仕事をしていくのではなく、ダブルライセンスで自身の地位を確立しておくことが重要になるのです。
4-3.専門性の高い高単価の業務に力を入れる
書類作成業務の単価が低い行政書士が年収を上げるためには、専門性の高い業務に力を入れ、業務単価を上げることも重要になります。業務単価が高い業務としては、たとえば、平均報酬額が12万円以上の「建設業許可申請」などが挙げられます。
参照:令和2年度報酬額統計調査の結果 (令和3年1月実施)|日本行政書士連合会
建設業許可申請は毎年更新が必要な更新なので、申請がスムーズにいけば、毎年依頼してもらうことができるところも良いところでしょう。また、在留資格認定証明書交付申請などの外国人の手続きに関する業務も、高額な報酬を得られやすい業務といえます。
高単価案件専門の行政書士であれば、これらに関する案件が集まりやすくなるため、必然的に年収が上がりやすくなるといえるでしょう。
さらに、たとえば、行政書士として経験を積み、知名度を上げることができれば、企業とコンサルティング契約を結ぶことで、高額な報酬を得ることも可能です。
コンサルティング契約に決まった報酬額はありませんが、契約内容によって報酬相場は異なるため、対応できる業務の幅が広がれば広がるほど、年収を上げることができるでしょう。
5.行政書士になる方法とは?
身近な街の法律家として、やりがいのある専門業務ができる行政書士になるための方法は次の2つです。
| 行政書士になる2つの方法 |
| ◉行政書士試験に合格する ◉特認制度を利用する |
行政試験に合格する方法が一般的ですが、特認制度を利用することで、行政書士試験を受けることなく行政書士として働くことが可能となります。ここでは、それぞれの制度について詳しく解説していきます。
5-1.行政書士試験に合格する
行政書士になる一番オーソドックスな方法は、行政書士試験に合格することです。試験科目は、「法令等科目」と「基礎知識」の大きく2つに分類されます。
【行政書士試験の試験科目】
| 法令等科目 | 基礎知識 |
| ・民法 ・憲法 ・行政法 ・商法、会社法 ・基礎法学 | ・一般知識 ・行政書士法等行政 書士業務と密接に 関連する諸法令 ・情報通信 ・個人情報保護 ・文章理解 |
令和4年度行政書士試験の結果は、合格率12.13%とかなり低い数字になっていますが、行政書士試験は絶対評価の試験であり、300点満点中180点を取ることができれば、必ず合格することができます。
※ただし、法令科目および基礎知識で各々の基準点を超える必要があります。
また、令和4年度の試験では、最年少合格者が15歳、最年長合格者が78歳となっており、対策を立ててコツコツと勉強を継続できれば、誰でも合格を手にすることができる試験となっています。
試験は年1回しか行われませんが、独立開業すればある程度自由に働けるうえ、年収1,000万円も狙える資格であることを考えると、資格取得に向けて勉強する価値は十分にあるといえるでしょう。
5-2.特認制度を利用する
「特認制度」を利用すれば、行政書士試験を受けることなく、行政書士として仕事をすることができます。特任制度とは、行政書士の業務に近い業務をおこなう職業に一定期間従事した場合に、行政書士の資格取得が認められる制度です。
【特任制度】
| ・弁護士 ・弁理士 ・公認会計士 ・税理士 ・「国または地方公共団体の公務員として行政事務 を担当した期間」、もしくは「行政法人または特定 地方独立行政法人の役員または職員として行政事務 に相当する事務を担当した期間」が通算して17年以 上(中卒の場合は20年以上)の者 |
これらの職業に従事する者は、行政書士がおこなう、官公庁への提出書類の作成や申請代行等につき、日常で取り扱うことが多い職業であり、行政書士としての実務経験に近い経験値があるとみなされることから、行政書士としての勤務を許されることになるのです。
ただし、弁護士や公認会計士などは行政書士より資格取得の難易度が高く、また、公務員として働く期間も17年以上と長いことから、行政書士として働くことを1番に考えるのであれば、行政書士試験に合格することを目標にするのが現実的です。
6.行政書士試験なら働きながら資格取得が可能!
行政書士試験は、働きながら合格を目指すことができる試験です。仕事を続けながら資格取得を目指すことで、仕事を失うリスクもありませんし、家族や周囲からの同意も得られやすいというのも、行政書士試験にチャレンジしやすい理由の一つであるといえます。
行政書士試験に合格すれば、独立開業して年収1,000万円を目指すこともできますし、資格を持っていれば、転職にも有利になるでしょう。
行政書士試験は、効率良く、計画的に、コツコツと勉強を続けることができれば、誰でも合格できる試験です。将来的に仕事の幅を広げたいと考えているのであれば、できるだけ早めに勉強を開始することをおすすめします。
7.まとめ
行政書士試験に合格後の働き方は多岐にわたり、行政書士として独立開業を目指す人もいれば、ダブルライセンスを取得し、幅広い知識を基に、さまざまなフィールドで活躍する方もいます。
行政書士として独立開業し、専門性の高い業務に従事できれば、サラリーマンとして働くよりも高額な収入を得ることは十分可能です。
もし、将来的に今の職業からの転職を考えているのであれば、転職活動でも優位に働く行政書士の資格取得に向けて、仕事をしながら勉強を開始してみるのはいかがでしょうか。
伊藤塾なら、仕事の合間を縫って効率良く計画的に試験勉強を進めることが可能です。
少しでも気になる方は、一緒に試験合格に向けて勉強を始めてみませんか?

著者:伊藤塾 行政書士試験科
伊藤塾行政書士試験科は1995年の開塾以来、多数の法律家を輩出し、現在も業界トップの行政書士試験合格率を出し続けています。当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、行政書士試験や法曹に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。

















