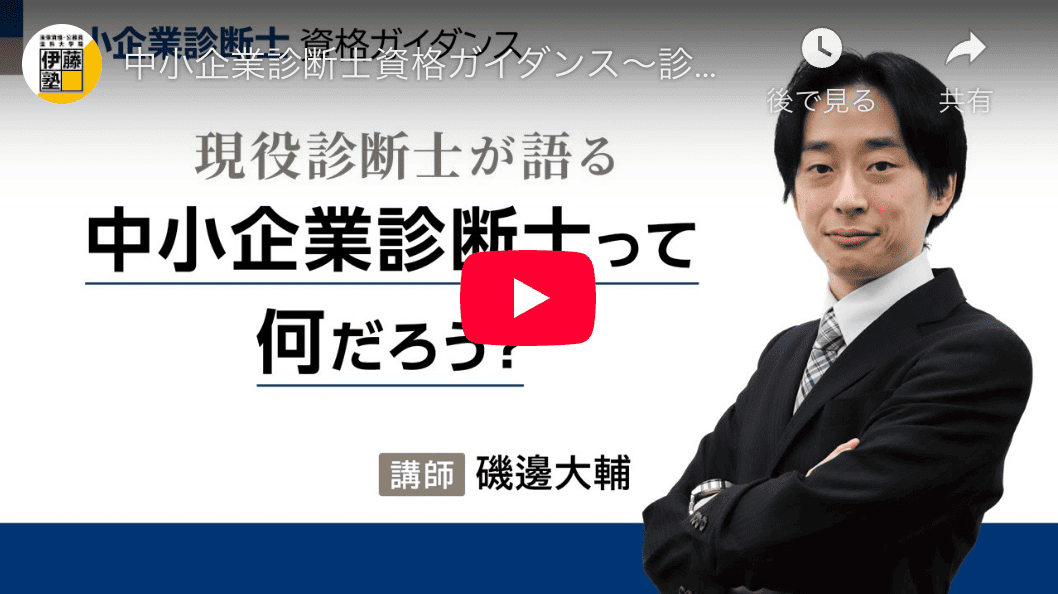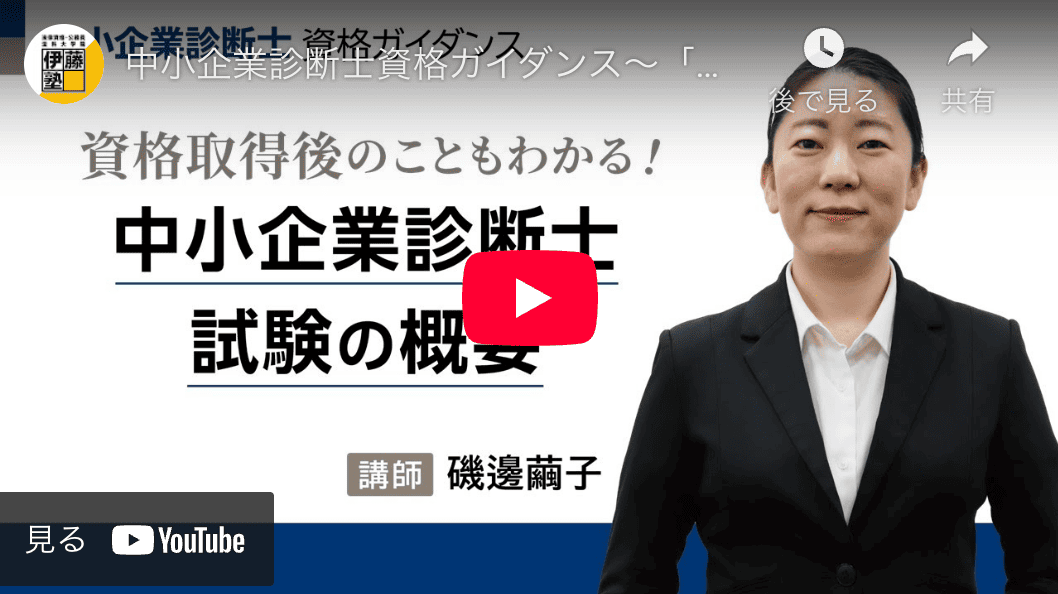中小企業診断士の仕事内容は?何ができる?向いてる人やキャリアパスも紹介!

中小企業診断士とは、経営の診断や助言などを通じて中小企業の活性化を支援する、企業経営の専門家です。
近年、中小企業診断士は人気が高まっており、キャリアアップの資格として診断士を目指す人も増えています。しかし、具体的な仕事内容や診断士ができることについてはあまり知られておらず、気になっている人も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では中小企業診断士の具体的な仕事内容、向いてる人の特徴やキャリアパスについて、詳しく解説してまいります。
中小企業診断士に興味のある方は、ぜひ最後までご一読ください。
【目次】
1.中小企業診断士とは?
2.中小企業診断士の具体的な仕事内容
2-1.経営コンサルティング業務
2-1-1.マーケティング:市場調査・商品企画・広告宣伝・顧客管理
2-1-2.採用・人事:採用支援や人事制度評価作成
2-1-3.財務:融資支援や補助金申請支援
2-1-4.IT・DX:システム開発や導入支援、パッケージソフトの導入支援
2-1-5.事業承継、M&A
2-1-6.認証支援(経営革新計画、経営診断書、ISO、HACCPなど)
2-2.公的業務(専門家派遣、相談員業務など)
2-2-1.専門家派遣
2-2-2.相談員業務
2-2-3.補助金事務局業務
2-3.本や記事の執筆
2-4.セミナーや研修講師など
3.中小企業診断士の活かし方は?キャリアや働き方について紹介
3-1.独立診断士としてのキャリア
3-2.企業内診断士としてのキャリアパス
3-2-1.昇進、異動、転職で診断士を活用
3-2-2.副業で活躍
4.中小企業診断士に向いてる人の特徴
4-1.経営や経済に興味関心が深い人
4-2.人の役に立つことが好きな人
4-3.コミュニケーション能力が高い人
5.中小企業診断士の仕事内容に関するよくある質問
5-1.どれくらい稼げる?年収は?
5-2.中小企業診断士の将来性は?
5-3.中小企業診断士になるためには?
6.まとめ
1.中小企業診断士とは?
現役診断士の伊藤塾講師が語る「中小企業診断士ってなんだろう?」
中小企業診断士は、経済産業大臣から認定された唯一の経営コンサルタントの国家資格であり、中小企業の経営課題を分析し、改善策を提案してサポートをしていく専門家です。中小企業診断士の主な役割は以下の通りです。
◉ 経営課題の分析と解決策の提案
◉ 事業計画の策定支援
◉ 経営改善のためのアドバイス
◉ 補助金の申請支援
◉ 創業・事業承継の支援
◉ 企業と行政、企業と金融機関などのパイプ役
中小企業の経営者や起業家にとって、中小企業診断士は「企業経営のホームドクター(町医者)」と言えるでしょう。
2.中小企業診断士の具体的な仕事内容
中小企業診断士の仕事内容は大きく「診る(みる)・書く・話す」の3つがあります。
◉ 診る仕事:企業診断や経営支援など
◉ 書く仕事:本や記事などの執筆など
◉ 話す仕事:セミナーや研修講師など
ここではさらに掘り下げて、診断士の仕事内容を詳しく解説します。
2-1.経営コンサルティング業務
中小企業診断士の主な業務は経営コンサルティングです。
コンサルティングでは企業の経営状況を分析し、直面している課題を解決する方法を助言します。企業によって課題は異なりますが、大きく次のような仕事があります。
2-1-1.マーケティング:市場調査・商品企画・広告宣伝・顧客管理
売上に直結するマーケティングは、企業からのニーズが高いです。
仕事内容としては、市場調査や競合分析の資料を作成したり、商品設計(誰に、何を、どのように販売するかなど)の相談相手となります。イメージとしては、経営者の頭の中にあるアイデアを言語化し、ブラッシュアップするお手伝いです。
2-1-2.採用・人事:採用支援や人事制度評価作成
少子化などにより中小企業は人材採用が難しくなっています。
そのため、人材採用の支援や、社内の評価制度の整備を通じた人材の定着率向上など、多様な支援が求められています。賃上げ等の対応により、助成金を受けることができることもあるため、社労士などの他種の専門家と連携することでより多くのニーズに応えることができます。
2-1-3.財務:融資支援や補助金申請支援
企業の決算やキャッシュフローの状況を見極めながら、融資の支援や補助金の提案などを通じて財務面から経営を後押しします。税理士と協業することもあり、優遇税制や保険などの知識を活かすことができる分野です。
2-1-4.IT・DX:システム開発や導入支援、パッケージソフトの導入支援
中小企業ではIT人材が不足しており、外部の人材を活用したいというニーズが高いです。自社システムの開発支援やパッケージソフトを導入する仕事があります。
中小企業はシステム化が進んでいない場合も多く、システムの選定や導入までといった伴走支援が求められます。システムの理解だけでなく、顧客へのヒアリングを通して実務フローの理解も必要となります。
2-1-5.事業承継、M&A
近年、ニーズが高まっている分野です。経営者の年齢は、2000年時点で「50歳〜54歳」が最も多かったですが、2015年時点では「65歳〜69歳」となっていて、高齢化傾向にあります(2022年版 小規模企業白書より)。
経営者の引退に伴い、親族や従業員に承継させたり、M&A(合併や買収)により事業を存続させたりするケースが増えています。スムーズに事業承継を実施するために、どの方法が適切であるか、何に注意するべきかなどを適切に助言していく力が中小企業診断士に求められています。
2-1-6.認証支援(経営革新計画、経営診断書、ISO、HACCPなど)
国際機関や行政は多様な認証、認定制度を設けています。これらの認証申請をサポートする仕事です。ここでは3つ紹介します。
①経営革新計画、事業継続力強化計画など
中小企業は経営革新計画や事業継続力強化計画などを策定し、認定されることで、融資や税制が有利となったり、様々な支援を受けることができるようになります。
中小企業診断士はこれらの資料の作成を支援します。
・経営革新計画とは中小企業が「新事業活動」に取り組む際の中期的な経営計画書です。
・事業継続力強化計画は防災や減災のための事前対策に関する計画です。
②経営診断書の作成(産廃診断書の作成)
経営診断書とは、企業の経営状態や課題を分析し、改善のための提言やアドバイスをまとめた文書です。産業廃棄物収集運搬業では許可申請が必要ですが、その際に「経営診断書(財務診断書)」の提出が必要な場合があります。
この経営診断書は中小企業診断士が作成するケースが多く、財務的な視点から診断書を作成します。
③ISOやHACCP(ハサップ)など
製造業を中心に、品質管理の認証の取得支援ニーズは高いです。食品製造会社ではHACCPやFSSC22000のように多くの認証制度があるため、プロジェクトを推進する人材が求められています。
資料を作成するだけではなく、認証を受けるために必要な施策を洗い出すなど、包括的な支援が必要です。他にも、近年はカーボンニュートラルやSDGs関連の認証制度も整備され、今後さらに支援のニーズが高まると考えられます。
2-2.公的業務(専門家派遣、相談員業務など)
中小企業診断士の仕事には公的業務と民間業務があります。
公的業務とは国や地方自治体、商工会議所などのような公的機関から委託されて行う業務です。公的業務以外の、企業と直接契約するような業務を民間業務と言います。
公的業務には主に以下の3つがあります。
2-2-1.専門家派遣
専門家派遣とは、中小企業を支援している公的機関が、中小企業の課題を解決するために専門家を企業に派遣しその解決を図る指導助言を行うことです。
商工会、商工会議所、産業振興公社や地方自治体など様々な公的機関が実施しています。中小企業が公的機関に専門家派遣を依頼し、相談内容に対して中小企業診断士などの適任な専門家を派遣し課題解決に向けた助言を行います。
2-2-2.相談員業務
相談員業務とは主に経営相談員として、商工会議所などの公的機関で窓口対応を行います。相談内容は、資金繰りや人材採用など様々で、これから創業する人も来ます。
地域によっては特定の業種が多いこともありますが、多様な中小企業の悩みを聞くことができるため、中小企業診断士としてスキルアップできる良い機会となります。
2-2-3.補助金事務局業務
補助金事務局業務とは、補助金の審査員として申請書の内容をチェックする仕事です。多くの補助金が認定されるためには、申請した上で採択される必要があります。
申請した計画書の内容を専門家として確認する仕事が補助金事務局業務です。
2-3.本や記事の執筆
執筆の仕事は中小企業診断士になったばかりの人も、ベテランの診断士も活躍する機会が多いです。専門分野の知見や、中小企業支援の事例をもとにした本や記事だけでなく、取材記事の作成もあります。紙媒体だけでなく、WEBコラムとして記事を作成することもあります。
2-4.セミナーや研修講師など
中小企業診断士は商工会議所などでセミナーを実施したり、企業で研修講師をします。テーマは多様ですが、近年はAIの活用法が多く開催されています。自分の得意な領域とニーズの高いテーマがあれば、企画が通りやすいでしょう。
研修はワークショップを取り入れたものが人気が高いです。初心者がいきなり研修を組み立てるのは難しいですが、既にある研修をもとにカスタマイズすることで、オリジナリティのある研修を行うことができます。
例えば、経営シミュレーション研修として「マネジメントゲームMG®️」や、チームのコミュニケーション力強化を目的とした「レゴ®️シリアスプレイ®️」などがあります。
3.中小企業診断士の活かし方は?キャリアや働き方について紹介
中小企業診断士は独立して活躍することもできますが、副業としても活用できる資格です。一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会の「中小企業診断士活動状況アンケート調査」(2021年5月)によると、独立診断士が48.3%、企業内診断士が46.4%となっています。
ここでは中小企業診断士を取得した後に、どのように活用できるかをご紹介します。自分に合った活かし方や、キャリアプランの参考にしてください。
3-1.独立診断士としてのキャリア
中小企業診断士を目指す人の中には、独立したいと思っている人も多いのではないでしょうか。経営コンサルタントになるためには資格は必要なく、中小企業診断士は必須ではありません。しかし、中小企業診断士を持っていれば、一定の能力があることの証明になります。
また、公的業務などに応募する場合は中小企業診断士が必要な場合がほとんどのため、独立のために診断士を取得する人は多いです。中小企業診断士として活動したい業界や分野を選定し、専門家としてキャリアを築いていきます。
例えば、金融機関勤務の経験があれば資金調達コンサルタントとして開業したり、IT業界出身であれば、システム導入専門家などとして活動することができます。診断士として活動していく中で、求められているニーズが分かってくるため、積極的に挑戦していく姿勢が大切です。
3-2.企業内診断士としてのキャリアパス
企業内診断士は、本業でも副業でも中小企業診断士を活用できます。
3-2-1.昇進、異動、転職で診断士を活用
中小企業診断士は本業での昇進、異動、転職などで活用できます。これらは資格そのものが役に立つこともありますが、資格の取得を通じて得た知識によって、仕事の成果につながることが多々あります。
例えば金融機関勤務であれば、中小企業に対して財務面だけでなく経営的なアドバイスができるようになるでしょうし、IT技術者であれば顧客の業務を理解した上で適切なシステムを構築できるようになります。中小企業診断士の異動先としては新規事業部や経営企画部などが多いです。中小企業診断士の取得が後押しとなる事例があります。
転職では中堅や大手のコンサルティング会社やM&A業界へ挑戦する人が多いですが、中小企業診断士事務所へ転職する人もいます。
3-2-2.副業で活躍
中小企業診断士として副業で活躍する企業内診断士は多いです。例えば、資料作成や執筆業務などは平日の夜や休日に作業時間を確保すれば、取り組みやすい仕事です。また、地方の企業が副業人材のノウハウを活用したいケースもあります。さらにリモートワークの普及によって、場所を選ばずにできる仕事も増えてきました。
副業でも本業でも診断士の仕事が変わることはなく、自分の得意な分野でサービスを提供すれば顧客を確保することができるでしょう。
4.中小企業診断士に向いてる人の特徴
中小企業診断士の仕事内容やキャリアパスから中小企業診断士に向いている人の特徴を紹介します。私は中小企業診断士に向いているのかな?と思っている人はぜひご覧ください。
4-1.経営や経済に興味関心が深い人
経営や経済に対して強い関心を持つ人は、中小企業診断士に向いています。日頃から経営や経済に関する情報収集をしている人は、経営者の意思決定に際し、他社の成功事例や、経済状況を考慮した助言をすることができます。経営や経済に興味がある人は、診断士としての役割を果たしやすいでしょう。
4-2.人の役に立つことが好きな人
中小企業診断士は感謝される機会の多い仕事です。人の役に立ちたい人に向いています。大きなプロジェクトの支援はもちろんですが、誰にでもできそうな資料作成や事務作業でも、労働力不足の企業からすれば有難いサポートです。他にも経営者の相談相手となることで感謝される機会も多く、診断士になってよかったと感じることも多いでしょう。
4-3.コミュニケーション能力が高い人
中小企業診断士はコミュニケーション能力が求められます。特に、診断士は「聞く力」が大切です。顧客の状況をしっかりとヒアリングすることが、良い解決策を考えるポイントです。
聞く力が高い診断士は、「あの人に相談したら、毎回やるべきことが明確になる」と評判も高い印象です。人と関わることが好きな人は診断士が向いているでしょう。
5.中小企業診断士の仕事内容に関するよくある質問
ここでは中小企業診断士の仕事内容に関するよくある質問に回答します。
5-1.どれくらい稼げる?年収は?
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会が調査した「中小企業診断士活動状況アンケート調査 結果について」によると、中小企業診断士の年収は「501万円〜800万円」が中央値となっています。
また、全体の約3分の1が年収「1,000万円以上」であり、高年収が目指せる資格です。ただし、中小企業診断士の年収は個人差が大きく、高年収を実現するためには、提供するサービスの品質や営業力が大切です。
※中小企業診断士試験の年収についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→中小企業診断士の平均年収は?中央値や年収1,000万以上の秘訣も徹底解説
5-2.中小企業診断士の将来性は?
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会「データでみる中小企業診断士2016年版」によると、中小企業診断士の過半数が今後コンサルティング市場が拡大すると回答しました。経営環境が厳しさを増していく中で、経営コンサルティングへのニーズは多様化し、市場は拡大していくことが予想されます。
また、野村総合研究所とオックスフォード大学の共同研究では「人工知能やロボット等による代替可能性が低い100種の職業」に中小企業診断士が選ばれています。AIに代替されにくいことを理由に中小企業診断士の挑戦を決めた人も少なくありません。
5-3.中小企業診断士になるためには?
中小企業診断士になるためには、中小企業診断士試験に合格する必要があります。
中小企業診断士試験は1次試験と2次試験があり、1次試験では7科目、2次筆記試験では4科目(事例)が出題されます。合格率は5%〜8%程度で、合格に必要な学習時間は、一般的にはおよそ1,000時間と言われています。(ただし、受験指導校などを利用した場合、1,000時間より大幅に短縮することが可能です。)
伊藤塾講師が解説「資格取得後のこともわかる!中小企業診断士試験の概要」
※中小企業診断士試験についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→中小企業診断士試験とは?日程・科目・受験資格など試験内容を分かりやすく解説!
6.まとめ
今回の記事では中小企業診断士の仕事内容を中心に、働き方やキャリアパス、向いてる人の特徴について紹介しました。まとめると次の通りです。
◉中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対して診断・助言を行う専門家
◉経営コンサルティング業務が主な仕事であり、具体的には下記業務がある
・マーケティング関連の仕事:市場調査、競合分析、商品設計など
・人事関連の仕事:人材採用や人事評価制度の作成支援など
・財務関連の仕事:融資支援や補助金申請支援など
・ITやDX関連の仕事:システム開発やパッケージソフトの導入支援など
・事業承継やM&Aの支援
・認証支援の仕事:経営革新計画やISOなど
・公的業務:専門家派遣、相談員業務や補助金事務局業務など
・本や記事の執筆や、セミナーや研修講師の仕事もある
◉独立診断士は専門家としてキャリアを築く
◉企業内診断士は昇進、異動や転職で診断士を活用
◉副業でも診断士は活用できる
◉中小企業診断士に向いているのは経営や経済に興味がある人
◉コミュニケーション能力が高い人や人の役に立つことが好きな人も向いている
試験は簡単とは言えませんが、試験勉強を通じて得た知識やスキルは、一生の財産となるでしょう。将来のキャリアアップや自己成長を目指す方は、ぜひ中小企業診断士試験に挑戦してみてください。
司法試験合格者数No.1の受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、中小企業診断士合格講座を開講中です。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートさせていただきます。

著者:伊藤塾 中小企業診断士試験科
伊藤塾中小企業診断士試験科が運営する当コラムでは、学生・社会人問わず、法律を学びたいと考えるすべての人のために、中小企業診断士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。