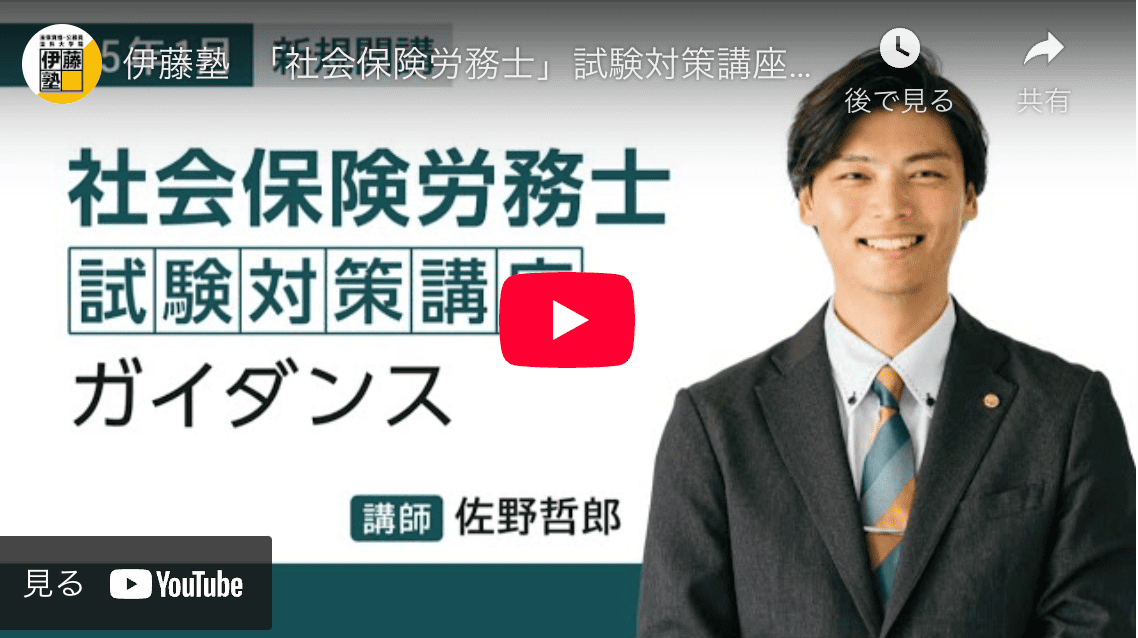社労士試験の勉強時間とは?最短で合格するための勉強方法とスケジュール管理のコツ

社会保険労務士(以下「社労士」)試験を目指す皆さんにとって、合格するためにどれくらいの勉強時間が必要かは大きな関心事でしょう。
本記事では、一般的な勉強時間の目安から、ライフスタイルに合わせた効率的な学習方法まで、合格に向けて知っておきたい情報を詳しく解説します。
社労士試験は効率よく勉強すれば働きながらでも短期合格できる試験です。ぜひ参考にしてください。
※社労士試験の詳細については、こちらの記事で詳しく解説しています。
→社労士試験とは?試験日程や科目・合格点など試験内容について分かりやすく解説
【目次】
1.社労士試験合格のために必要な勉強時間は?
1-1.独学の場合
1-2.受験指導校や通信講座を利用する場合
1-3.社労士試験合格のために確保したい勉強期間
2.社労士試験の難易度は?
2-1.社労士試験の合格率
2-2.社労士試験の難易度が高いといわれる3つのポイント
3.勉強を開始するベストなタイミングと効率的なスケジュール
3-1.社労士試験の前年の5〜9月に開始する場合
3-2.試験前年の10〜12月、試験を受ける年の1〜2月に開始する場合
4.短時間・短期間で社労士試験に合格するためには?
4-1.社労士試験のポイントは横断学習
4-2.勉強期間を3分割で考える
4-3.社会人でも勉強時間を確保するコツ
4-3-1.スキマ時間の活用とながら勉強
4-3-2.周囲の理解を得る
4-3-3.生活リズムを一定に保つ
4-3-4.週単位・月単位での計画、タスクの優先順位付け
4-4.受験指導校を利用する
5.まとめ
1.社労士試験合格のために必要な勉強時間は?
社労士試験合格のために必要な勉強時間は、およそ1,000時間といわれています。1,000時間というと膨大な時間数でイメージしにくいですが、社会人の生活スタイルで現実的に置き換えると平日2時間・土日5時間確保できる場合で、約1年(330日)で到達すると考えるとわかりやすいでしょう。
一方で、他の国家資格試験と比較して社労士試験だけが長時間の勉強をしなければならないわけではありません。以下は他の資格試験との比較表です。独立開業可能な国家資格となると、どの資格もおよそ1,000時間という勉強時間が必要になるのがわかります。
| 国家資格 | 勉強時間 |
| 司法書士 | 2,000~3,000時間 |
| 弁理士 | 2,000~3,000時間 |
| 土地家屋調査士 | 1,000~1,500時間 |
| 中小企業診断士 | 800~1,000時間 |
| 社会保険労務士 | 800〜1,000時間 |
| 行政書士 | 600~1,000時間 |
| FP1級 | 400~600時間 |
| 宅地建物取引士 | 400~600時間 |
なお、ここで紹介している勉強時間はあくまで平均的な勉強時間であり、必ずこの時間が必要というわけではありません。大学や実務経験などで基礎知識を身につけているか、独学か受験指導などを活用するかどうかなどによっても合格までにかかる勉強時間は変わってきます。
1-1.独学の場合
独学の場合は、1,000時間以上の時間が必要になると考えたほうがよいでしょう。社労士試験では専門的な用語や難解な判例が頻出となるため、特に法律に触れたことがない人や実務経験がない人にとって独学は相当ハードルが高いものとなります。
また、社労士試験の試験科目は大きく分類すると10科目と広範囲です。これらの科目(法律)は相互に関連していたり、似ているようで違う紛らわしい項目が多数存在します。問題自体も難解な条文を読み解く必要があり、基礎知識がない状態の人が一人で理解するには膨大な時間がかかるのが通常です。それでも、コツコツと勉強を進めることができれば、必ず合格基準に到達できる試験です。
1-2.受験指導校を利用する場合
社労士試験は、受験指導校を利用した場合、独学の場合と比較して勉強時間は短く、800〜1,000時間ほどで合格基準に到達できる可能性が高いです。
受験のプロが合格のためのノウハウを元にカリキュラムを組んでいるので、より効率的に勉強でき、講師に質問もできるため、難しい論点のインプットもスムーズです。集中して取り組めば、800時間以下の勉強時間でも合格は可能です。
1-3.社労士試験合格のために確保したい勉強期間
独学の場合、勉強開始から試験本番まで1年間は確保できるとよいでしょう。
受験指導校などを利用すれば、半年ほどで合格できるケースもありますが、基本的にはすべての科目を合格できる水準まで理解するためのインプットとアウトプットの時間を踏まえると、1科目あたり1ヶ月ほど確保できるのが理想です。仕事などをしておらず専業で勉強できる場合を除いて、独学での合格にはおおむね1年程度はかかると思っていただいた方がよいでしょう。
2.社労士試験の難易度は?
社労士試験は難易度が高い試験として知られています。
幅広い知識が要求されるため、しっかりとした学習計画と長時間の勉強が必要です。試験内容は労働法規や社会保険法規など、多岐にわたる分野から出題されており、全科目で合格基準を満たすことが求められます。
2-1.社労士試験の合格率
社労士試験の合格率は過去10年の平均値では6.2%です。
| 試験年度 | 受験人数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2014年(平成26年) | 44,546 | 4,156 | 9.3% |
| 2015年(平成27年) | 40,712 | 1,051 | 2.6% |
| 2016年(平成28年) | 39,972 | 1,770 | 4.4% |
| 2017年(平成29年) | 38,685 | 2,613 | 6.8% |
| 2018年(平成30年) | 38,427 | 2,413 | 6.3% |
| 2019年(令和元年) | 38,428 | 2,525 | 6.6% |
| 2020年(令和2年) | 34,845 | 2,237 | 6.4% |
| 2021年(令和3年) | 37,306 | 2,937 | 7.9% |
| 2022年(令和4年) | 40,633 | 2,134 | 5.3% |
| 2023年(令和5年) | 42,741 | 2,720 | 6.4% |
| 平均 | 6.2% | ||
このように、毎年の合格率はほぼ一貫して10%未満という低い水準になっています。
2-2.社労士試験の難易度が高いといわれる3つのポイント
社労士試験の難易度が高いといわれる理由は、主に以下の3点であるといえます。
①試験範囲の広さと法改正の頻度②科目ごとの合格基準の設定
③法改正が毎年あり、知識をアップデートする必要がある
※社労士試験の難易度についての詳細は、こちらの記事で詳しく解説しています。
→社労士の難易度は?合格率の推移や他資格と比較して分かりやすく解説!
3.勉強を開始するベストなタイミングと効率的なスケジュール
社労士試験の勉強を始めるタイミングはいつでもOKです。ただし社労士試験は毎年1回、8月の最終週に実施されますので、何月に始めるか次第でスケジュールの戦略を変える必要があります。
今回は、独学で受験される場合を想定して、開始のタイミングを2つのパターンに分けて解説します。
3-1.社労士試験の前年の5〜9月に開始する場合
勉強期間は、1年〜1年3ヶ月です。社労士試験は毎年8月に実施されますので、試験が終わったこのタイミングで勉強を開始する人の割合がもっとも多いのではないでしょうか。
インプットを2回転するスケジュールが組める勉強期間なので、初学者の方にとってもちょうどいい期間になっているといえます。
| 約1年の勉強期間の場合のモデルスケジュール | |
| 時期 | 勉強内容 |
| 受験前年の5〜12月 インプット1回転目 | 全体的な内容のインプット (1回転) |
| 1問1答形式の問題集を中心に、 理解を優先した問題演習を行う | |
| 受験当年の1〜4月 インプット2回転目 | 年金等難解科目の再インプット (2回転) |
| 過去問演習を取り入れながら、 理解を深めつつ暗記や横断的な 知識整理を行う | |
| 受験当年の5〜6月 アウトプット中心 | 1問1答形式の問題集、科目別の 問題演習を行う |
| 受験当年7〜8月 | 1ヶ月で全科目10年分過去問3周 模試や答練を活用してテキスト にない知識のインプット 法改正論点の確認 |
3-2.試験前年の10〜12月、試験を受ける年の1〜2月に開始する場合
勉強期間は、6ヶ月〜10ヶ月です。単純計算だと月間100時間以上、1日3〜4時間ほど勉強時間を確保することが必要になってくるので、仕事をしながらの受験であればギリギリのスタートといえそうです。
初学者というよりは、2年目以降の経験者向きのスケジュールのイメージです。初学者でも、法学部系の学部出身であったり、実務経験により基礎知識があったり、また専業で勉強できる環境にあるなど毎日の勉強時間を多めに確保できる人にはおすすめのスケジュールです。
| 約9ヶ月の勉強期間の場合のモデルスケジュール | |
| 時期 | 勉強内容 |
| 受験前年の10月〜 受験当年の6月前半 インプット+ アウトプット | 全体的な内容のインプット |
| 過去問演習、法改正情報のインプット を並行して行う 基礎的な論点や頻出論点を重点的に マスター | |
| 受験当年の6月後半 〜7月 アウトプット | 苦手分野に絞った再インプット 全科目の過去問、答練の周回 |
| 受験当年の8月 | 苦手分野、暗記できていない分野の 克服 |
4.短時間・短期間で社労士試験に合格するためには?
時間に制限がある社会人の場合、そもそもおよそ1,000時間の勉強時間の確保が難しいこともあるでしょう。誰しも、できれば勉強時間を短縮して社労士試験に合格したいと考えるはずです。ここでは、勉強時間を短縮するためのポイントやコツをご紹介します。
4-1.社労士試験のポイントは横断学習
社労士試験は出題科目が多く暗記量も膨大なので、科目ごとに覚えようとするととても非効率です。そこで、似た項目はグルーピングし、科目をまたいでまとめて暗記するのがおすすめです。グルーピングすることで、効率よくインプットしていくことができます。
例えば、社労士試験には複数の科目で「端数処理」という頻出論点があります。ほぼ全科目、いたるところで登場する上に「1円未満切り捨て」や「100円未満切り捨て」など違いが微妙で複雑です。
このような「似ているけれど少し違う」ものは試験で狙われやすいので、科目を横断して効率よくインプットするとよいでしょう。
例)「1円未満切り捨て」と「1,000円未満切り捨て」の整理の一部。
| 1円未満切り捨て | |
| 科目 | 端数処理の対象 |
| 雇用 | 基本手当の日額、再就職手当の額 常用就職支度手当の額 |
| 厚年 | 毎支払期月に支払う年金額 |
| 国年 | 毎支払期月に支払う年金額 |
| 1,000円未満切り捨て | |
| 科目 | 端数処理の対象 |
| 徴収 | 賃金総額、特別加入保険料算定基礎額の総額 追徴金、延滞金計算時の労働保険料の額 |
| 健保 | 標準賞与額の決定 |
| 厚年 | 標準賞与額の決定 |
4-2.勉強期間を3分割で考える
短期間で社労士試験に合格するためには、限りある時間をどのように使うかが非常に重要です。勉強の戦略を立てずに闇雲に時間を消費してしまっては、短期合格は難しいからです。ここでは、実際に合格した人の年間スケジュールを紹介しますので、参考にしてみてください。
| インプット期 (4月末頃まで) |
| ▶︎受験指導校などで講義受講 ▶︎テキストの読み込み ➡︎とにかくインプット ▶︎基礎的な知識が問われるタイプの『問題集』 を使って理解を深める ★この時期は“暗記”よりも“理解”することに集中 |
| アウトプット期 (5月〜7月上旬まで) |
| ▶︎『問題集』『過去問題集』演習 ➡︎覚える→忘れる→覚え直しを繰り返す ▶︎受験指導校の答練や模試を受験 ➡︎アウトプットにより理解不足の論点や 暗記できていない項目を洗い出す ▶︎7月頃から統計白書対策 ▶︎法改正への対応 ★「直前に覚えるリスト」を作りながら勉強を 進める |
| 直前総仕上げ期 (試験前1ヶ月) |
| ▶︎「直前に覚えるリスト」を集中して覚え直す ▶︎全科目横断復習 ★当日に向けた体調管理 |
図のように【インプット→アウトプット→直前総仕上げ】の3つに期間を区切り、計画的に実力を完成させていきます。ポイントは「記憶の定着までには復習の繰り返しが必要である」ことを前提にスケジュールを組むことと、直前総仕上げ期にどのタスクを残すかを意識しながら勉強を進めることです。
社労士試験は試験範囲が広く、覚えることが膨大です。一度理解して覚えたつもりでも、数週間、数ヶ月後には忘れてしまいます。その前提でアウトプット期に「覚える→忘れる→覚え直す」を繰り返せるスケジュールを組むことが重要です。
そしてさらに重要なのは、直前の総仕上げに自分が何をすべきか明確になっているかどうかです。できるだけ早い段階で直前期のイメージをし、焦らずに自分の苦手分野や覚え残したことに集中できる状態を作ることで、大事な時期を迷いなく過ごすことができるようになるでしょう。
4-3.社会人でも勉強時間を確保するコツ
社労士試験の合格者は約8割が社会人です。難関資格にもかかわらず、忙しいなかでも合格を掴んでいる受験生が毎年大勢いることになります。
ただし社労士試験に合格するための勉強時間を作るためには、少なからず工夫と意識が必要です。ここでは社会人合格者である筆者が実践した工夫を紹介しますので、参考にしてみてください。
4-3-1.スキマ時間の活用とながら勉強
会社と自宅の往復の通勤時間、昼休みなど、働いていてもある程度まとまった時間がとれるタイミングはあるはずです。また、お風呂に入りながら、移動しながら、料理をしながら…など、何かしているもののそこまで頭を使っていない時間は1日のなかに数十分はあるのではないでしょうか。
机に向かってテキストや問題集を開くことまではできなくても、スキマ時間やながら勉強用に単語帳を利用したり「5分以上時間があったらここを読み返そう」というページに付箋をつけておく、壁に暗記事項を貼り付けておいて目に入るようにしておく…など自分の行動導線に沿った勉強素材をあらかじめ準備しておくとよいでしょう。
ポイントは、スキマ時間や「ながら勉強」用の勉強素材を常に準備して勉強をするハードルを下げておくことです。スキマ時間や「ながら勉強」で新しい知識のインプットは難しいので、すでに勉強したことの復習や暗記事項に絞った時間の使い方にするのがおすすめです。
4-3-2.周囲の理解を得る
社労士試験の勉強期間は通常数ヶ月〜1年ほど必要になります。その間は少しでも勉強時間を確保する必要があるため、会社の付き合いを断りたい時があったり、家族のサポートが必要になったりすることもあるでしょう。
しかし、周囲の人があなたが勉強していることを知らない状態だと、急に付き合いが悪くなったと不審に思われたり、自宅で勉強する環境作りに非協力的になるかもしれません。周囲の理解を得て応援してもらうことができれば、無用な誘いが少なくなったり、勉強しやすい環境作りに協力してもらえる可能性が高くなります。
4-3-3.生活リズムを一定に保つ
働きながら時間を捻出するためには、起床時間を早めるか、就寝時間を遅らせるという方法をとる人が多いはずです。
しかし生活リズムが一定に保てていないと、思うようにいきません。飲酒など前日の過ごし方により朝の寝覚めが悪く勉強に集中できなかったり、残業により就寝前の時間が減ってしまい勉強時間が確保できなかったり…ということがないよう、なるべく仕事や家事のリズムを一定に保つような工夫と努力をすることがより多くの勉強時間の確保には必要です。とはいえ仕事をしながらだと、予定通りにいかない日も出てくると思います。そんなときは過剰にストレスを感じず「過ぎた時間は仕方ないから明日からがんばろう」と切り替えるのも、生活リズムを乱さないために必要なことです。
4-3-4.週単位・月単位での計画、タスクの優先順位付け
これは最も重要なポイントといってもいいでしょう。
計画がない状態で勉強を進めるのは非常に危険です。例えば労基法は条文や判例が難解で、理解に時間がかかる科目といわれています。自分のペースで勉強を進めてしまうと、インプットに時間を取りすぎてしまい問題演習の時間が少なくなってしまったり、他の科目に割ける時間がなくなってしまうことがあり得ます。
まずは大枠で月単位、そこから逆算する形で週単位のスケジュールを立てて、なるべくそれに沿って勉強を進めるよう心掛けましょう。年間・週間のスケジュール管理ができるバーチカル手帳やアプリなどを活用する方法もおすすめです。受験指導校のカリキュラム通りに進めていれば心配は少ないですが、独学で勉強をする人は注意が必要です。
4-4.受験指導校を利用する
より短時間・短期間で社労士試験に合格したい方は、受験指導校の活用を検討してみるとよいでしょう。
専門の講師に分からない論点の質問ができたり、自分の状況に合った勉強方法やスケジュールの相談も可能です。勉強の効率が上がることで、より短期間で合格できる可能性が高くなります。また、スケジュール管理の面でもモデルのカリキュラムが組まれているので、カリキュラムに沿って受講をしていくだけで、効率的に勉強を進めることができます。
5.まとめ
最後に、今回の記事の要点をまとめます。
◉社労士試験の合格に必要といわれている勉強時間は、800〜1,000時間
◉社労士試験の短時間・短期間合格のカギは、効率的な勉強方法ができるかどうか
◉社会人でも勉強時間を捻出する方法や工夫はある!
◉より短時間、短期間で合格したい方は、受験指導校の活用を
社労士試験は難しい試験ではありますが、必ずしも長時間の勉強時間が必要というわけではありません。
受験指導校を活用することで無駄を省き、効率よく勉強を進めていけば、800時間より短い時間で合格できる可能性は十分にあります。
逆に、独学の場合は、頻繁に行われる法改正のチェックなどもあり時間がいくらあっても足りず、1,000時間以上かかってしまう可能性もあります。
どのように勉強するかで合格まで必要となる時間は大きく変わってきますので、短期合格を目指すなら受験指導校の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
司法試験合格者数No.1の受験指導校・伊藤塾では、皆様からのリクエストの声にお応えし、2025年合格目標 社労士試験合格講座を開講しました。
夢の実現に向けて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。
伊藤塾が、あなたの挑戦を全力でサポートいたします。

著者:伊藤塾 社労士試験科
伊藤塾 社労士試験科が運営する当コラムでは、社会保険労務士試験に関する情報を詳しくわかりやすくお伝えしています。